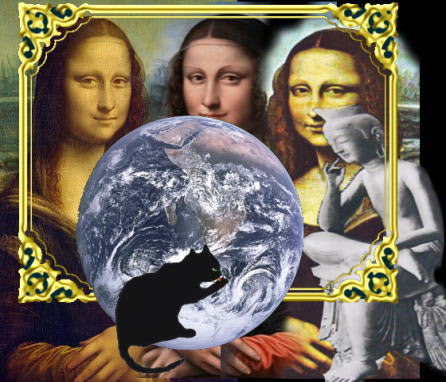帯=丗+冖+巾・・・丗(30・参拾)+ワ+ハバ・・・
廿+丨+冖+巾
巾(はば・はばへん・きんべん)
タイ
おび・belt
おびる
着物の上から腰に巻く細長い布
身につける
ひきいる・引き連れる
↓↑
帯広川
アイヌ語の
「オペㇾペㇾケㇷ゚(o-pere-perke-p)
(川尻・裂け・裂けている・もの
川尻が幾重にも裂けているもの)」
「オペリペリケプ・オベレベレフ・オベリベリ」
↓↑
黄道帯(コウドウタイ・Zodiac・ゾーディアック)
黄道の上下に9度の幅をとって空にできる帯
獣を象った星座を多く通ることから獣帯
↓↑
黒帯(black belt)・帯紐・・・組紐・紐育(NY)
一帯・映帯・温帯・夏帯・角帯・革帯・掛帯・冠帯・寒帯
滯==氵+帶・・・・・・燕
氵+廿+儿+冖+巾
滞=带
氵+帯
氵+丗+冖+巾
氵+卅+冖+巾
水・氵・氺(みず・さんずい・したみず)
タイ
とどこおる
物事が進まない・はかどらない
とどこおる・止まる・動かない
一箇所にとどまる
こる(凝)・こり固まる
渋滞・滞在
↓↑
![]()
燕=廿+北+口+灬
燕(つばめ・燕・玄鳥・乙鳥・ツバクラメ・ツバクロ・barn swallow)
燕≠or≒蔕(へた)・・・帶(帯)
火・灬(ひ・ひへん・れっか・れんが)
エン
くつろぐ
さかもり
つばめ
安んずる・安息する
さかもり・酒を飲む・酒を酌み交わす。
つばめ・ツバメ科の鳥。渡り鳥の一種。
古代中国の国名・戦国時代の七雄の一
古代中国の地名
奄→匽→燕
春秋時代以降、燕の士大夫層に
「韓(から・カン)・箕(みの・キ)」を氏とする者が多・・・蓑・笊
↓↑ ↓↑↓
秦末期
燕(紀元前209年~紀元前207年)
韓広が擁立されて名乗った
↓↑
三国時代
燕(236年~238年)
公孫淵が魏から自立
↓↑
五代十国時代
燕(756年~759年or763年)
燕 (安史の乱)
唐代に
平盧節度使
范陽節度使を兼ねた
安禄山
が
満州・内モンゴルの遊牧民の軍事力を背景に
安史の乱を起こして建てた
↓↑
五代十国時代
燕(911年~914年)
桀燕
劉仁恭(&息子の劉守光)が
河朔三鎮の勢力を背景に建てた
![]()
↓↑
「帯方郡(君+阝)=タイホウくむ=太奉訓」
「タイホウくむ」のドウオン異字(意字)・・・
↓↑
帯方郡=黄海道?=京城附近?
「倭国への万二千里の起点」
「従郡至倭」の行程の出発地点
漢江河口部の仁川付近・・・
帯(おび)の・・・帶(廿+儿+冖+巾)
方(かた)の
↓↑ ・・・方=亠+勹
╹ +一+ノ+𠃌
方(ほう・ほうへん・かたへん)
ホウ
かた
かく
ただしい
まさに
かた・むき・方位・方向・方角
行き先・向かう場所
いなか・地方・ある一定の地域
四角・四角形・方形
ただしい。正直である。また、きちんとしている。
ならべる。ならぶ。
くらべる。比較する。
やりかた。手段。技術。
同じ数を掛け合わせる。二乗。自乗。
「まさに」と読み
「ちょうど今・まさしく」などの意
「はじめて」と読み
「やっと・ようやく」などの意
さまよう・あてもなくぶらぶらと歩きまわる
彷・彷徨
かた=他人を呼ぶ敬称
かた=係・担当する人
↓↑ かた=ころ・夕方 朝方
郡(こおり)
・・・君+阝=尹+口+阝
邑=阝=おおざと・むら・くに
ーー↓↑ーー
![]()
楽浪郡
中国の前漢の
武帝が
朝鮮半島の
北西部に設置した
行政機関(地方自治体)
楽浪郡・・・波(なみ・ハ)を楽しむ
の他に
真番郡・・・真(まさに)番(つがえる)
臨屯郡・・・屯(駐屯)して臨(のぞむ)、
玄菟郡・・・玄菟(くろウサギ・黒兎)・・・半島の地形or月の兎の影
玄鳥(乙鳥・燕)
飛燕、濡燕、川燕 黒燕、群燕、諸燕、夕燕 燕来る、初燕、夏燕
![]()
「燕来る時になりぬと・・・燕=公孫氏?
雁がねは・・・・雁が音=雁金=雁・・・鴨?or鷹?
国思ひつつ・・・出雲?
雲隠り鳴く・・・大国主?
(大伴家持『万葉集』)・・・?
雁道(がんどう・かりのみち)
近世以前の日本人が
北方に存在する信じていた
架空の土地の名称・・・?
江戸時代には
「韓唐(からとう)」とも書かれ
中国においては
「月氐国(げつていこく)」と同一視された
の「漢四郡」
後漢のときに追加で
「帯方群」・・・帶方郡(君+阝)・・・帯(帶)を垂れる方向?
も置かれた
帶(廿+儿+冖+巾)=廿(20=念・弐拾)+儿(ノ+乚)+冖+巾
=ノ+廿(20=念・弐拾・二足)+乚(乙)+冖+巾
ーー↓↑ーー
朝鮮事情
衛氏朝鮮
紀元前195年?~紀元前108年
司馬遷の『史記』
便宜的に
楽浪郡朝鮮県(平壌)の名を用いた・・・
楽浪郡=朝鮮
朝鮮半島で「朝鮮」と称するのは
10世紀の高麗以降のこと・・・
燕の出自
亡命者
衛満が建国
『史記』、『漢書』には
名のみ「満」と記録
姓を「衛」と記すのは
2世紀頃に書かれた
王符の『潜夫論』以降・・・
↓↑
前漢・高祖
紀元前202年
燕王
臧荼が反乱し処刑され
盧綰が燕王に封じられたが
紀元前197年
盧綰が漢に背いて匈奴に亡命
劉建
を燕王に封じた
実態は遼東郡を含む燕の旧領を直轄化
その際、
燕人の
衛満は身なりを現地風にかえて
浿水(鴨緑江)を渡河
千人余りの徒党と朝鮮に亡命
衛満は、朝鮮を護ると
箕子朝鮮王の
準王にとりいり
朝鮮西部に植民
亡命中国(燕)人は数万人
さらに燕・斉・趙からの亡命者を誘い
亡命者の指導者となった
前漢が攻めてきたと詐称し
王都に乗り込み
準王は衛満に応戦したが
「勝負にならなかった(魏略)」と戦況を記録
衛満は
燕・斉の亡命者と原住民と連合し
王険城(平壌)を首都とし王位に就き
衛満朝鮮を建国
↓↑
『三国志・魏略・後漢書』によると
前漢建国当時の朝鮮は
箕子の子孫が代々朝鮮侯で
箕子(キシ)朝鮮
として
朝鮮王を僭称
箕準の代に
衛満
の手により王権を奪われ
箕準は
南方の・・・・「馬韓・弁韓・辰韓」の三国?
馬韓を攻略し
「(馬)韓王?」となった・・・「馬韓⇔百済」になった?
ーー↓↑ーー
しられたい・知られたい・・・自己顕示欲?顕示願望?
新羅例帯
しられたくない
新羅例拓無い
ーー↓↑ーー
新羅(シラギ・シンラ・シルラ)
斯蘆(シロ・サロ)
前57年~935年
古代の朝鮮半島南東部にあった国家
辰韓
(シンカン)
紀元前2世紀~356年
朝鮮半島南部にあった三韓の一
帯方郡の南
日本海に接し
後の新羅と重なる地域
↓↑
帯方郡(タイホウ-グン)
・・・「帯方」という名称は楽浪郡の属県?
204年~313年の
109年間
中国漢王朝によって
朝鮮半島の中西部に置かれた
軍事・政治・経済の地方拠点
↓↑
楽浪郡の南半を割いた数県
(晋代では7県・『晋書地理志』)
東の濊
南の韓
南端の倭(半島南端)・・・弁韓?
が属す
後漢から魏、西晋の時代にかけ
郡の経営や
羈縻支配を通じて
韓・倭という
東夷地域へ
中国の文化や技術を持ち込んだ
↓↑
魏朝以降には
華北の中国文化の窓口
郡の長が太守であり
配下の官吏と軍団の在する
郡役所が郡治
帯方郡治は
楽浪郡治(平壌)の南方にあった・・・ソウル?
↓↑
楽浪郡治の所在地
平壌の郊外、市街地とは
大同江・・・大(一の人)の
同(おなじ)の
江(川水の流れ、巧み)
を挟んだ対岸の
楽浪土城(平壌市楽浪区域土城洞)にあった
↓↑
公孫氏
後漢の末
中平六年(189年)
中国東北部の
遼東太守となった
公孫度は・・・公(おおやけ)=八(捌)+ム
孫(まご)
度(たび・旅・足袋・田尾)
・・・天孫降臨・・・?
後漢の放棄した
朝鮮半島へ進出
平壌付近から
漢城北方にかけてにあった
楽浪郡を支配下に置き
後を継いだ嫡子
公孫康・・・公孫康・・・康=广+隶・・・健康
广+肀+氺(水)
亠+丿+肀+氺(水)
╹+厂+肀+氺(水)
・・・厂(崖)の上の╹(灯火・あるじ)
・・・肀=熊手・柄杓
は
楽浪郡18城の南半
屯有県(黄海北道黄州)・・・駐屯の有る県
以南を割いて
帯方郡を分置
建安九年(204年)頃・・・
南方の土着勢力
韓・濊族を討ち
「是より後、倭・韓、遂に帯方に属す」
・・・倭は朝鮮半島の南部に存在していた
郡治=周囲の数十県(城)の
軍事・政治・経済を束ね
個々の県治よりもひときわ大きな城塞都市
公孫康は
魏の
曹操に恭順し
後漢の
献帝から
左将軍・襄平侯に任ぜられ
帯方郡は
後漢の郡とされた
↓↑
公孫康の死後
子の
公孫淵が幼いために
公孫康の実弟
公孫恭
が後を継ぎ
献帝から禅譲を受けた
魏朝の
文帝(曹操の子・曹丕)により
車騎将軍・襄平侯に封じられた
↓↑
太和二年(228年)・・・大和(やまと)
・・・太の和の
二のネン
年=𠂉+ヰ(wi・ゐ・井・韋)
韋(そむく・なめす・なめしがわ)
葦・偉・衛
228年
干支 : 戊申
神功皇后摂政二十八年・・・・・卑弥呼(?~242年~248年)
248-228=20
皇紀八八八・八百八拾八・888年
魏 : 太和二年
蜀 : 建興六年
呉 : 黄武七年
高句麗 : 東川王 二年
新羅 : 奈解王三十三年
百済 : 仇首王 十五年
↓↑
建興六年五月
泣いて馬謖を斬った(揮淚斬馬謖)年
「涙を揮(ふる)って馬謖を斬った」
↓↑
公孫淵
魏の
曹叡(明帝)からの承認され
揚烈将軍・遼東太守に任ぜられた
公孫淵は
魏朝の仇敵である
呉の
孫権との同盟を画策
魏から受けた
大司馬・楽浪公の地位を不足とし
景初元年(237年)
反旗を翻して独立を宣言
遼東の襄平城で
燕王を自称
帯方郡
楽浪郡
は燕に属した
↓↑
景初二年(238年)
魏の太尉
司馬懿
の率いる四万の兵によって
襄平城を囲まれ、長期の兵糧攻めで
公孫淵とその子
公孫脩は滅び
帯方郡は
「後漢─魏─燕」と
所属に変遷があったが
実質的は一貫して
公孫氏の領有下
韓や倭といった
東夷からの朝貢は
公孫氏が受け取っていた・・・
↓↑
卑弥呼(?~242年~248年)
238年 248-238=10
6月、邪馬台国の女王
卑弥呼が魏に使者を派遣
12月、明帝から「親魏倭王」の
金印・紫綬と銅鏡などを下賜
(魏志倭人伝)
干支 : 己未
神功皇后摂政三十九年
皇紀八九九・捌玖玖・899年
魏 : 景初三年
蜀 : 延熙二年
呉 : 赤烏二年
高句麗 : 東川王十三年
新羅 : 助賁王 十年
百済 : 古尓王 六年
↓↑
帯方郡は
魏の直轄経営
魏は
劉昕
と
鮮于嗣
をそれぞれ
帯方太守、楽浪太守に任じ
両者を密かに海路で
山東半島から黄海を越えて
朝鮮半島に派遣
帯方郡と楽浪郡の2郡を掌握させた
帯方郡は
魏の直轄地となる
太守
劉昕は
周辺の
東濊・韓族の首長に
邑君、邑長の印綬を賜与し
魏との冊封関係を改めて結び直した
邪馬台国・卑弥呼も
景初二年
(238年・『魏志倭人伝』の記述は誤りで
景初三年の説・・・?)
六月
帯方郡へ
朝貢使
難升米・・・難(むづかしい)
↓↑ 升(はかる・ます)⇔开の変形?
米(こめ)=丷+十+八
ベイ・マイ・メ
こめ・メートル
よね・稲の実
脱穀した穀物の実
メートル・長さの単位
亜米利加(アメリカ)の略
↓↑ アメリカ大陸
次使
都市牛利・・都(みやこ)=者+阝
市(いち)=亠+巾
牛(うし)=𠂉+十
利(とし)=禾+刂
刀・刂(かたな・りっとう)
リ
きく・するどい・よい・とし
よく切れる・都合がよい
役立つ
もうける
利息・利益
かしこい・さとい
役に立つ
きく・ものを言う・話をする
↓↑
を派遣した
太守は
劉夏で
郡の官吏を付けて
後漢の都
洛陽まで
難升米
の一行を送らせた
↓↑
正始元年(240年)
新太守
弓遵は
魏の詔書・金印紫綬を
配下の
梯儁
に持たせ
卑弥呼
のもとへ送った
↓↑
弓遵
正始六年(245年)
嶺東へ遠征し
東濊を討った後
帯方郡が所管していた
辰韓八国を
楽浪郡へ編入することになり
その決定を現地に伝えた際
通訳が誤訳をし
韓族を激怒させ
郡内の韓族が
帯方郡の
崎離営を襲った
弓遵と
楽浪太守の
劉茂
が討ち
魏軍は韓族を滅亡
弓遵も戦死
↓↑
正始八年(247年)
弓遵
から引き継いだ
太守
王頎は
倭の使者から
邪馬台国
と
狗奴国
との交戦の報告を受け
自ら上洛して官の決裁を仰ぐが
魏朝から
邪馬台国へ援軍が送られることはなく
魏の
少帝の
詔書
黄幢
を携えた
塞曹掾史
(外交官、軍使、軍司令副官など諸説)
の
張政が派遣された
↓↑
帯方郡の滅亡
泰始元年(265年)・・・泰=三+人+氺(水)
𡗗+氺(水)
始=女+台
魏の・・・・・・・・・・魏=委+鬼
禾+女+鬼
司馬炎(懿の孫、後の晋の武帝)
が魏の
曹奐(元帝)から禅譲を受け
晋朝(西晋)を興す
永康元年(300年)
八王の乱で混迷状態
帯方郡に属する県は
帯方・列口・南新・長岑・提奚・含資・海冥
七県(『晋書地理志』)
玄菟郡の遼東移動
前107年
衛氏朝鮮の跡地に
楽浪郡と共に置かれた
玄菟郡が
前75年
朝鮮半島から遼東(遼河東部地域)へと移動
111年
夫余が
玄菟郡、遼東郡、高句麗などを通り越し
楽浪郡を攻撃・・・?
122年
馬韓が帯方郡、楽浪郡、遼東郡を通り越し
高句麗主導で
濊貊と共に
遼東の
玄菟郡を攻撃したが
夫余によって撃退された・・・?
↓↑
建興元年(313年)
遼東へ進出した
高句麗が南下し
楽浪郡を占領
朝鮮半島南半に孤立した
帯方郡は
晋の手を離れ情報も途絶
帯方郡は
楽浪郡南部に残された
漢人の政権や都市は
東晋を奉じて5世紀初頭までの存続
5世紀前半
百済によって征服
5世紀後半
高句麗が
百済を駆逐して支配下へ置いた
↓↑
帯方郡の滅亡後
帯方の名は残ってい
広開土王碑文の
404年に
倭から
百済征伐の形で北侵
帯方界(旧帯方郡の境界)
に進入して
高句麗と戦った・・・
↓↑
帯方郡治の所在地
平壌の郊外
市街地とは
大同江を挟んだ対岸にある
楽浪土城(平壌市楽浪区域土城洞)にあった
帯方郡治の比定地
現代の38度線を挟んで諸説・・・?
↓↑
ソウル説と広州説
広州は最初の百済の都
3世紀の
馬韓の「伯済国」は広州にあった・・・
初期には
広州にあった帯方郡が
ソウルに遷り
その跡地に百済が興った・・・
↓↑
京畿道ソウル説
ソウルに帯方郡治があった・・・
『漢書地理志』に
前漢時代の
楽浪郡25県の1つとして
帯方県が記され
「帯水、西して帯方に至り海に入る」
この「帯水」とは
「大同江=列水」ではなく
中部を西流する大河の
漢江で
その河口部のソウルこそが
帯方郡治であった・・・「帯水=漢江」?
↓↑
京畿道広州説
ソウルの東南40kmの
広州を帯方郡治に比定・・・
漢江を河口から遡ると
ソウルを過ぎて北上する
北漢江と南東に向かう
南漢江に分かれる
「帯水、西して帯方に至り海に入る」
の
「帯水」を「北漢江」ではなく
「南漢江」
帯方郡治は広州・・・
↓↑
鳳山郡説と安岳郡説
↓↑
黄海北道鳳山郡説
平壌から南へ50km
黄海北道鳳山郡沙里院にある
唐土城
を帯方郡治に比定する説
楽浪郡址と同時代の
瓦・塼(煉瓦)・銭などが出土
付近の古墳群からは
「帯方太守 張撫夷塼」
と刻まれた塼槨墓が発見
↓↑
黄海南道安岳郡説
安岳郡に比定する説
「元康五年(295)」銘塼のある下雲洞古墳
「太康九年(288年)」銘塼出土の柳雲里北洞
楽浪墓制と同じく
漢人の塼槨墓
大同江河口の入江を扼する位置にあり
中国遼東半島、山東半島のどちらにも近い
↓↑
帯方郡の疆域
鳳山郡・安岳郡・信川郡など
載寧江流域の一帯には
他国からの流入者・亡命者などを含めた
中国人社会が形成されていた・・・
↓↑
北帯方
前漢が
楽浪郡・・・場所は遼東或いは遼西
↓↑ 遼東、遼西とは
遼東半島ではなく
遼河の東部或いは西部地域・・・?
「樂浪遂城縣有碣石山,長城所起」
「西連諸國至于安息,東過碣石以玄菟
樂浪為郡
卻匈奴萬里,更起營塞,制南海以為八郡」
「樂浪郡武帝置。雒陽東北五千里
…郭璞注山海經曰
列,水名。列水在遼東」
「浪郡,故朝鮮國也,在遼東」
「長岑縣,屬樂浪郡,其地在遼東」
「安帝永初五年(111年)
夫餘王始將歩騎七八千人寇鈔樂浪
殺傷吏民,後復歸附」
「楽浪郡の場所=遼東」
「乙支文徳・・・?
6世紀後半~7世紀初頭
石多(ソクダ)山の者・・・石多?
高句麗の将軍。大臣
隋の
宇文述
・・・宇(そら)文(ふみ)述(のべる)
于仲文
・・・于(まげる)仲(なか)文(ふみ)
は煬帝より
嬰陽王か
乙支文徳将軍の
捕縛を命じられていたが
隋の第二次高句麗遠征(612年)で
隋軍に追い討ちをかけ勝利」
元史(1369年)
「咸平府,古朝鮮地,箕子所封
↓↑ 漢屬樂浪郡,後高麗侵有其地」
と同時に
設置(紀元前108年)した郡
郡治は今の全羅南道羅州市にあった
漢四郡(楽浪・玄菟・臨屯・真番)は
漢五郡だった
紀元前八十二年?)
独立国を自称(帯方国)し
三十七年
高句麗に滅ぼされた・・・
↓↑
南帯方
魏(220年~265年)
全羅北道南原市に郡治が置かれた・・・
魏が遼東の公孫氏を滅ぼし
楽浪郡と帯方郡を接収した
238年以降のある時
魏は一時的にせよ
帯方郡を大きく南へ移動させた
魏が馬韓の反乱を鎮圧した
245/246年の出来事か・・・
↓↑
帯方郡=遼東
後漢書高句麗伝
「郡國志西安平、帶方縣 並屬 遼東郡」
魏志高句麗伝
「順(帝)、桓(帝)之間,復犯 遼東
寇 新安、居鄉
又 攻 西安平 于道上 殺 帶方令
略得 樂浪太守妻子」
晋書地理誌
「帶方郡 公孫度置。列口, 長岑, 含資」
長岑=遼東
含資県=遼西県属
↓↑
313年以降
平州
楽浪郡、玄菟郡、遼東郡、帯方郡、昌黎郡
から構成・・・
↓↑
「辰韓人などの亡命中国人(秦人)の遺構」
↓↑
韓は帯方郡の南、東西は海で尽き、南は倭と接する
楽浪郡の使いは大船に乗って
辰韓に入り、千人の仲間を奪還した
「万余の兵を船に乗せて攻撃する」
と辰韓を威嚇した
鉄が産出され
市場で中国が銭を用いるように鉄を用いる
韓、濊、倭や
楽浪、帯方にも
鉄を供給
↓↑
山海経
海内北経
「蓋国は・・・蓋=亠(トウ・ズ)=音の漢字の略字
蓋=艹+盍
艹+去+皿
艹+土(十一)+厶+皿・・・2月11日
艸・艹(くさ・くさかんむり・そうこう)
ガイ・コウ
ふた
おおい(覆い・蔽い・被い)
おおう
かさ
けだし
おおいかくす・かぶせる
とま
地をおおう天・空
「けだし=思うに・多分」
とま(苫)
むしろ(筵・莚・蓆)
かや(萱)
がま(蒲)
などを編んでつくったおおい(覆い)
「なんぞ・・・ざる」と読み
↓↑ 「どうして・・・しないのか」の意
鉅燕の南
倭の北にあり
倭は燕に属す」
陸続き・・・
燕は河北省北部(北京周辺)の国
蓋国=倭は燕に属す
遼東半島or朝鮮半島北部
漢書地理誌に
「樂浪海中有倭人」
楽浪海=遼東湾、西朝鮮湾、黄海・・・
魏志韓伝
「南は倭と接する」
「瀆盧国は倭と接する(與倭接界)」
倭が朝鮮半島にあった・・・
北史百済伝
百済=倭人
倭と百済は陸続き・・・
宋書倭国伝
倭王武=倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓
六国諸軍事、安東大将軍、倭王に叙爵
倭国が朝鮮半島に固執した理由
宋書倭国伝
倭の五王
「記紀」に記述が無い
旧唐書
「日本国は倭国の別種」
倭国と日本国は別の国・・・
三国史記新羅本紀
第四代国王
脱解(新羅王)=出身は多婆那国・倭国の東北一千里
脱解は倭人・・・
三国史記新羅本紀
倭国侵入記録
↓↑
馬韓、百済は遼東半島の国家
馬韓=百済初期の位置ではなく
遼東半島・・・
魏志韓伝
馬韓の西海上の大島に州胡があった
大島・・・
後漢書高句麗伝
建光元年(121年)
高句麗が
馬韓
濊貊
と共に
玄菟郡へ侵攻
夫余によって撃退された・・・
馬韓が朝鮮半島南西部とすると
高句麗が
楽浪郡の向こう側にあった
馬韓と共に
遼東にあった玄菟郡に侵攻・・・
馬韓=玄菟郡付近
宋書百済伝
百済国=高句麗とともに遼東の東、千余里に在った
朝鮮半島南西部は?
宋書百済伝
遼西を支配した
朝鮮半島南西部にあった百済が
遼河の西部を支配するのは不自然・・・
北史百済伝
「東は新羅、北は高句麗
西南は大海、小海の南に暮らす」
「小海」とはどこか?
北史
高句麗の南には「小海」がある
当時の高句麗は
遼東や遼西を支配していた
北史百済伝
百済の南
海行三カ月に
耽牟羅国(済州島)
朝鮮半島南西部から三ケ月?
南斉書
北魏が数十万騎で
百済を攻めた
渡海作戦を行ったような記述は無い
北魏と百済の間には高句麗が有り
高句麗の向こう側に数十万騎を送るのは不可能?
魏書勿吉伝
勿吉が百済と共謀して
水路から高句麗を攻撃する計画を立てた
北魏はこの計画を了承しなかった
百済が朝鮮半島南西部にあったとすると
不自然な計画?
史記夏本紀
「百済国西南
渤海中に大島十五有り
皆百済に属す」
百済は「渤海」に面していた・・・渤海は沿海州?
朝鮮半島南西部の
栄山江流域(羅州、光州、霊岩)
からは
前方後円墳、 超巨大甕棺墓、
九州式の横穴式石室などの倭人系の墳墓が多数出土
当時の朝鮮半島に存在した
百済系、新羅系、加耶系の文化とは全く異なっていた
倭人系勢力が長期間に渡り存在した
倭国の遺跡群・・・
馬韓や百済が朝鮮半島南西部にあったとすると
何故このような遺跡群が出てくるのか・・・
倭人系勢力の存在は
卑弥呼の時代から6世紀半ばまで確認
以降は百済式に変わった事が考古学的に確認
中国文献、朝鮮文献において
朝鮮半島における
倭国の記述が消える時期と一致・・・
倭の五王は
栄山江流域にいたのではないか・・・
百済が朝鮮半島南西部にあったのは
武寧王
聖明王
以降の最後の期間だけだった・・・
栄山江流域の
羅州市
永洞里の古墳から発見された
人骨をDNA型鑑定
百済や新羅の人骨とはいずれとも似ていなかった
現代日本人のDNAと非常によく似ていた
栄山江流域には
現代日本人と血縁関係が深く
独自の文化圏を維持した強力な
倭人系の国家が300年に渡って存在
↓↑
古朝鮮は
遼東国家
楽浪郡平壌説
衛氏朝鮮、箕子朝鮮、楽浪郡
なども朝鮮半島にあった・・・
遼東にあった・・・なら
後漢書光武帝紀
衛氏朝鮮の跡地に
楽浪郡を置き
その地は遼東にあった
衛氏朝鮮は遼東にあった・・・
史記朝鮮列伝
「朝鮮には濕水、洌水、汕水が有り
三水が合流して洌水となる」
後漢書郡國志
「列水は遼東にある」
朝鮮は遼東にあった・・・
史記蘇秦列伝
「燕東有朝鮮(潮仙二音,水名)
遼東、北有林胡、樓煩」
燕は
北京のあたりにあった国
記載順序によれば
朝鮮は遼東より西側にあった
「朝鮮」は川の名前・・・
朝鮮=遼河流域
魏志韓伝
衛氏朝鮮の宰相が
東の辰国に亡命・・・
史記朝鮮列伝
衛氏朝鮮王の
右渠を打つために
斉から渤海へ
楼船に5万の兵を載せて出発した
衛氏朝鮮は渤海に面していた・・・
晋書地理誌
「樂浪郡漢置。朝鮮県=周封箕子地。
遂城県=秦築長城之所起」
箕子朝鮮があった場所は
秦の始皇帝の築いた
長城の始まる所(碣石山)の近くにある・・・
箕子朝鮮は遼東か遼西あたりにあった・・・
隋書
「高麗之地,本孤竹國也。
周代以之封于箕子
漢世分為三郡,晉氏亦統遼東」
孤竹国は河北省にあった国
箕子朝鮮は遼西あたりにあった・・・
旧唐書
「遼東之地,周為箕子之國,漢家之玄菟郡」
箕子朝鮮は遼東にあった・・・
↓↑
遼史地理志
「東京遼陽府は、本の朝鮮の地なり」
箕子朝鮮は遼陽市のあたりにあった・・・
楽浪郡、玄菟郡
と同じく
衛氏朝鮮
箕子朝鮮
も朝鮮半島にあったという
記述は古代史書には存在せず
その場所は遼東か遼西・・・
「朝鮮」とは
漢書地理志で
「楽浪郡の25あった県の一つ」
後漢書郡国志で
「楽浪郡の17あった県の一つ」
「朝鮮」という地域は
朝鮮半島のような広大な地域を示す地名ではなく
川の名前・・・
その川とは
朝鮮半島ではなく
遼陽市を流れる
「太子河付近の河川」だった・・・
↓↑
衛氏朝鮮の跡地には
漢四郡が置かれたが
真番郡・臨屯郡はすぐに廃止され
実質的に設置されたのは
楽浪郡と玄菟郡の2郡だけ
朝鮮半島部分は
楽浪郡と後に設置する
帯方郡が担当
遼東半島部分は
遼東郡が担当
遼東部分は
楽浪郡を追い出した分を
玄菟郡が担当することになった・・・
これを否定すれば
楽浪郡と共に
衛氏朝鮮の跡地に置かれ
28年後に廃止されて
楽浪郡に統合された
臨屯郡
定説では
江原道の江陵市のあたりにあったはずの
臨屯郡の太守
章封泥が
遼西の遼寧省の葫芦島市で発見
臨屯郡の太守
章封泥が
遼西で発見されたのは不自然
↓↑
遼東郡の
文県
と
番汗県が離れすぎ
遼東郡の説明に
文県と
番汗県が
併記されている
「満潘汗」が朝鮮国との国境であり
「文」と「満」が同じ音であるため
「満潘汗」は
「文県と番汗県」を意味するものと推測される
朝鮮国を朝鮮半島に置いたことによって
番汗県は
清川江河口にある
博川付近に比定されることとなった
しかし
文県は遼寧省 営口市付近に比定
文県と番汗県が離れすぎている
古朝鮮を朝鮮半島に移動した結果
遼東郡を巨大化させために発生した
玄菟郡が設置後まもなく
遼東に移動されたのはあまりにも不自然
玄菟郡と楽浪郡は
朝鮮跡地の郡として同時に頻繁に現れ
玄菟郡は楽浪郡の近くにあった・・・
楽浪郡が
衛氏朝鮮の跡地に創設された事から
楽浪郡を遼東から朝鮮半島に移動させるためには
衛氏朝鮮を朝鮮半島に移動させる必要があった
玄菟郡=遼東に存在した郡
楽浪郡を平壌とするために
玄菟郡だけをすぐに遼東に戻し
楽浪郡や遼東郡が抜けた
遼東部分を全て玄菟郡に分担させた・・・
↓↑
戦国時代
燕が朝鮮に侵攻
障壁(燕長城、遼東長城)を築いた
燕人満は長城を出て東に向かい
朝鮮との国境である
浿水に向かった
国境があった
番汗県や浿水を清川江とすると
燕長城は朝鮮半島内にあったはずだが
長城はどこにも見つからなかった
浿水を鴨緑江や大同江などに比定してみても
長城はどこにも見つからなかった
広範囲に建築された
建造物であるにもかかわらず
跡形もなく消えてしまった・・・
↓↑
楽浪郡や古朝鮮を
朝鮮半島に移した事により
楽浪郡
遂城県の万里の長城の起点も
朝鮮半島に大移動される事になった
朝鮮半島に長城が存在しないとなると
衛氏朝鮮が
朝鮮半島に存在しないという事になり
即ち
楽浪郡平壌説が成立しない
万里の長城の起点は
碣石山と明記されている
「玄菟郡の遼東移動」と同様
中国側から朝鮮半島を攻撃するのは困難だが
朝鮮半島から中国側を攻撃するのも困難
豊臣秀吉の朝鮮出兵時
小西行長は
清川江を越えられなかった
朝鮮戦争においても
補給線が伸びきった
米軍は鴨緑江を越えてきた
人民義勇軍に敗走した
歴史上で
朝鮮半島から
千山山脈を越えて
中国に攻め込んだ国家は
大日本帝国だけ(百済の遼西侵攻は除く)
↓↑
明代に作られた
虎山長城などを根拠に朝鮮半島まで
燕の長城が建設されなかった
その虎山長城ですら中国側は
遼東半島を貫く明史の長城の一部であるとしているが
明史の記述は長城の建設というより
単に防衛線を記述しただけとも見られる上
虎山長城自体が実際には
高句麗が建設した
泊灼城とも言われている
↓↑
楽浪郡平壌説
歴史書で朝鮮や楽浪郡の場所を示す
浿水、列水、帯水などの川の古名を
遼河、東遼河、渾河、太子河などではなく
鴨緑江、清川江、大同江などに
比定する事によって成立
浿水、列水、帯水などの地理条件を示すだけで
定説破綻
漢帝国の版図拡大を無理に行ったため
楽浪郡(朝鮮半島)
遼東郡(遼東半島)
玄菟郡(遼東)
の3郡の位置関係にはほとんど自由度が無い
↓↑
後漢書列傳・祭遵從弟肜
「(烏桓の)東は玄菟郡、樂浪郡」
玄菟郡と樂浪郡は隣接し
樂浪郡の西側は
遼東郡でも黄海でもない事が示されているが
楽浪郡平壌説の破綻
漢書に
「碣石より東は玄菟郡、楽浪郡」
玄菟郡と樂浪郡は隣接し
樂浪郡の西側は
遼東郡でも黄海でもない
↓↑
「夫余の楽浪郡攻撃」
夫余にとって
楽浪郡は
攻撃できる範囲内の距離にあった
玄菟郡、遼東郡、高句麗などを通り越して
楽浪郡を攻撃するのは不可能・・・
「馬韓の玄菟郡攻撃」
馬韓にとって
玄菟郡は攻撃できる範囲内の距離
帶方郡、楽浪郡、遼東郡などを通り越して
玄菟郡を攻撃するのは不可能・・・
↓↑
楽浪郡平壌説は論理破綻
↓↑
遼西地域において
臨屯太守章の封泥が出土した・・・
話題にしない事にする・・・
↓↑
朝鮮跡地に
玄菟郡が設置された事は
目立たない
興味を持たせない・・・
まるで頻繁に移動される
奇妙な郡であるような印象を与え
「玄菟郡の遼東移動の怪」
に疑問を持たせない
↓↑
楽浪郡平壌説によって
倭国が半島から消去された
高句麗は巨大な国家となってしまった
対馬海峡の向こう側にいた
倭国が半島国家群を属国にして
その強大な
高句麗と朝鮮半島で覇権を争った・・・
歴史教科書は
朝鮮半島から倭国を消去
歴史書は
朝鮮半島の倭国を消すことができなかった
↓↑
見つからない邪馬台国
見つからない侏儒国
見つからない州胡
見つからない万里の長城
裸国
黒歯国
倭国半島
夫余の楽浪郡攻撃
玄菟郡の遼東移動
馬韓の玄菟郡攻撃
百済の遼西支配
北魏の百済攻撃
文県と番汗県
朝鮮半島南西部から
倭人系の墳墓が多数出土し
日本国は倭国の別種
倭の五王
高句麗との戦争が
記紀に記録されていない
謎
↓↑
添付部分はそのままのモノではありません
「原文」のスベテは
「・・・
http://lelang.sites-hosting.com/naklang/rakurou.html
・・・」で
「虚構の
楽浪郡平壌説
~帯方郡、玄菟郡、馬韓の場所と
禁断の高句麗史
~Seeking truth in a world of lies~
暁 美焔(Xiao Meiyan) 社会学研究家,
2019.4.19 祝2.5版完成!
本ウェブページ内容の複製、引用、リンク、
再配布は自由です・・・」
↓↑
・・・以上は「カンジモウソウ」の中での
検索で発見し、勝手に部分引用し添付させてもらったモノで
「帯方郡⇔たいほうぐん⇔替法組⇔他意法句務」の
語源はナンゾヤの検索派生で発見したモノで
歴史資料の「原文」を・・・「ゲンブン」?
直にヨムことの乏しい
ボクにとっては
面白かった・・・デス・・・
↓↑
平州(へいしゅう)は
中国にかつて存在した州
北魏から金代にかけて
現在の
河北省
秦皇島市
一帯に設置・・・
583年(開皇三年)
隋が郡制を廃止し
北平郡が廃止
平州に編入
平州は
盧龍県1県を管轄
607年(大業三年)
州が廃止、郡が置かれ
平州が
北平郡と改称
619年(武徳二年)
唐により
北平郡は
平州と改められ
臨渝・肥如の2県を管轄
742年(天宝元年)
平州は北平郡と改称
758年(乾元元年)
北平郡は平州と改称
923年(天賛二年)
契丹が
後唐の平州を攻め落とした
遼の平州は
南京道に属し
遼興軍が置かれた
平州は
盧龍・安喜・望都の3県を管轄
1123年(天輔七年)
金の
阿骨打が
遼の平州節度使の
立愛を降し
平州は南京と改められた
1126年(天輔七年)
南京が平州にもどされた
平州は中都路に属し
盧龍・撫寧・海山・遷安・昌黎の5県を管轄
1215年
モンゴル帝国の
史天倪が平州を奪い
金の経略使の
乞住を降した
この地に
興平府が置かれた
1300年(大徳四年)
元の成宗により
永平路と改められた
永平路は
中書省に属し、4県1州州領2県を管轄
1369年(洪武二年)
明の洪武帝により
平灤府と改められた
1371年(洪武四年)
永平府と改められた
永平府は1州5県を管轄
清のとき
永平府は
直隷省に属し、1州6県を管轄
ーーーーー
・・・だから・・・なに・・・
「楽浪郡は朝鮮半島にも遼東半島にもなかった」・・・?
じゃぁ「帯方郡」は・・・?
廿+丨+冖+巾
巾(はば・はばへん・きんべん)
タイ
おび・belt
おびる
着物の上から腰に巻く細長い布
身につける
ひきいる・引き連れる
↓↑
帯広川
アイヌ語の
「オペㇾペㇾケㇷ゚(o-pere-perke-p)
(川尻・裂け・裂けている・もの
川尻が幾重にも裂けているもの)」
「オペリペリケプ・オベレベレフ・オベリベリ」
↓↑
黄道帯(コウドウタイ・Zodiac・ゾーディアック)
黄道の上下に9度の幅をとって空にできる帯
獣を象った星座を多く通ることから獣帯
↓↑
黒帯(black belt)・帯紐・・・組紐・紐育(NY)
一帯・映帯・温帯・夏帯・角帯・革帯・掛帯・冠帯・寒帯
滯==氵+帶・・・・・・燕
氵+廿+儿+冖+巾
滞=带
氵+帯
氵+丗+冖+巾
氵+卅+冖+巾
水・氵・氺(みず・さんずい・したみず)
タイ
とどこおる
物事が進まない・はかどらない
とどこおる・止まる・動かない
一箇所にとどまる
こる(凝)・こり固まる
渋滞・滞在
↓↑

燕=廿+北+口+灬
燕(つばめ・燕・玄鳥・乙鳥・ツバクラメ・ツバクロ・barn swallow)
燕≠or≒蔕(へた)・・・帶(帯)
火・灬(ひ・ひへん・れっか・れんが)
エン
くつろぐ
さかもり
つばめ
安んずる・安息する
さかもり・酒を飲む・酒を酌み交わす。
つばめ・ツバメ科の鳥。渡り鳥の一種。
古代中国の国名・戦国時代の七雄の一
古代中国の地名
奄→匽→燕
春秋時代以降、燕の士大夫層に
「韓(から・カン)・箕(みの・キ)」を氏とする者が多・・・蓑・笊
↓↑ ↓↑↓
秦末期
燕(紀元前209年~紀元前207年)
韓広が擁立されて名乗った
↓↑
三国時代
燕(236年~238年)
公孫淵が魏から自立
↓↑
五代十国時代
燕(756年~759年or763年)
燕 (安史の乱)
唐代に
平盧節度使
范陽節度使を兼ねた
安禄山
が
満州・内モンゴルの遊牧民の軍事力を背景に
安史の乱を起こして建てた
↓↑
五代十国時代
燕(911年~914年)
桀燕
劉仁恭(&息子の劉守光)が
河朔三鎮の勢力を背景に建てた

↓↑
「帯方郡(君+阝)=タイホウくむ=太奉訓」
「タイホウくむ」のドウオン異字(意字)・・・
↓↑
帯方郡=黄海道?=京城附近?
「倭国への万二千里の起点」
「従郡至倭」の行程の出発地点
漢江河口部の仁川付近・・・
帯(おび)の・・・帶(廿+儿+冖+巾)
方(かた)の
↓↑ ・・・方=亠+勹
╹ +一+ノ+𠃌
方(ほう・ほうへん・かたへん)
ホウ
かた
かく
ただしい
まさに
かた・むき・方位・方向・方角
行き先・向かう場所
いなか・地方・ある一定の地域
四角・四角形・方形
ただしい。正直である。また、きちんとしている。
ならべる。ならぶ。
くらべる。比較する。
やりかた。手段。技術。
同じ数を掛け合わせる。二乗。自乗。
「まさに」と読み
「ちょうど今・まさしく」などの意
「はじめて」と読み
「やっと・ようやく」などの意
さまよう・あてもなくぶらぶらと歩きまわる
彷・彷徨
かた=他人を呼ぶ敬称
かた=係・担当する人
↓↑ かた=ころ・夕方 朝方
郡(こおり)
・・・君+阝=尹+口+阝
邑=阝=おおざと・むら・くに
ーー↓↑ーー

楽浪郡
中国の前漢の
武帝が
朝鮮半島の
北西部に設置した
行政機関(地方自治体)
楽浪郡・・・波(なみ・ハ)を楽しむ
の他に
真番郡・・・真(まさに)番(つがえる)
臨屯郡・・・屯(駐屯)して臨(のぞむ)、
玄菟郡・・・玄菟(くろウサギ・黒兎)・・・半島の地形or月の兎の影
玄鳥(乙鳥・燕)
飛燕、濡燕、川燕 黒燕、群燕、諸燕、夕燕 燕来る、初燕、夏燕

「燕来る時になりぬと・・・燕=公孫氏?
雁がねは・・・・雁が音=雁金=雁・・・鴨?or鷹?
国思ひつつ・・・出雲?
雲隠り鳴く・・・大国主?
(大伴家持『万葉集』)・・・?
雁道(がんどう・かりのみち)
近世以前の日本人が
北方に存在する信じていた
架空の土地の名称・・・?
江戸時代には
「韓唐(からとう)」とも書かれ
中国においては
「月氐国(げつていこく)」と同一視された
の「漢四郡」
後漢のときに追加で
「帯方群」・・・帶方郡(君+阝)・・・帯(帶)を垂れる方向?
も置かれた
帶(廿+儿+冖+巾)=廿(20=念・弐拾)+儿(ノ+乚)+冖+巾
=ノ+廿(20=念・弐拾・二足)+乚(乙)+冖+巾
ーー↓↑ーー
朝鮮事情
衛氏朝鮮
紀元前195年?~紀元前108年
司馬遷の『史記』
便宜的に
楽浪郡朝鮮県(平壌)の名を用いた・・・
楽浪郡=朝鮮
朝鮮半島で「朝鮮」と称するのは
10世紀の高麗以降のこと・・・
燕の出自
亡命者
衛満が建国
『史記』、『漢書』には
名のみ「満」と記録
姓を「衛」と記すのは
2世紀頃に書かれた
王符の『潜夫論』以降・・・
↓↑
前漢・高祖
紀元前202年
燕王
臧荼が反乱し処刑され
盧綰が燕王に封じられたが
紀元前197年
盧綰が漢に背いて匈奴に亡命
劉建
を燕王に封じた
実態は遼東郡を含む燕の旧領を直轄化
その際、
燕人の
衛満は身なりを現地風にかえて
浿水(鴨緑江)を渡河
千人余りの徒党と朝鮮に亡命
衛満は、朝鮮を護ると
箕子朝鮮王の
準王にとりいり
朝鮮西部に植民
亡命中国(燕)人は数万人
さらに燕・斉・趙からの亡命者を誘い
亡命者の指導者となった
前漢が攻めてきたと詐称し
王都に乗り込み
準王は衛満に応戦したが
「勝負にならなかった(魏略)」と戦況を記録
衛満は
燕・斉の亡命者と原住民と連合し
王険城(平壌)を首都とし王位に就き
衛満朝鮮を建国
↓↑
『三国志・魏略・後漢書』によると
前漢建国当時の朝鮮は
箕子の子孫が代々朝鮮侯で
箕子(キシ)朝鮮
として
朝鮮王を僭称
箕準の代に
衛満
の手により王権を奪われ
箕準は
南方の・・・・「馬韓・弁韓・辰韓」の三国?
馬韓を攻略し
「(馬)韓王?」となった・・・「馬韓⇔百済」になった?
ーー↓↑ーー
しられたい・知られたい・・・自己顕示欲?顕示願望?
新羅例帯
しられたくない
新羅例拓無い
ーー↓↑ーー
新羅(シラギ・シンラ・シルラ)
斯蘆(シロ・サロ)
前57年~935年
古代の朝鮮半島南東部にあった国家
辰韓
(シンカン)
紀元前2世紀~356年
朝鮮半島南部にあった三韓の一
帯方郡の南
日本海に接し
後の新羅と重なる地域
↓↑
帯方郡(タイホウ-グン)
・・・「帯方」という名称は楽浪郡の属県?
204年~313年の
109年間
中国漢王朝によって
朝鮮半島の中西部に置かれた
軍事・政治・経済の地方拠点
↓↑
楽浪郡の南半を割いた数県
(晋代では7県・『晋書地理志』)
東の濊
南の韓
南端の倭(半島南端)・・・弁韓?
が属す
後漢から魏、西晋の時代にかけ
郡の経営や
羈縻支配を通じて
韓・倭という
東夷地域へ
中国の文化や技術を持ち込んだ
↓↑
魏朝以降には
華北の中国文化の窓口
郡の長が太守であり
配下の官吏と軍団の在する
郡役所が郡治
帯方郡治は
楽浪郡治(平壌)の南方にあった・・・ソウル?
↓↑
楽浪郡治の所在地
平壌の郊外、市街地とは
大同江・・・大(一の人)の
同(おなじ)の
江(川水の流れ、巧み)
を挟んだ対岸の
楽浪土城(平壌市楽浪区域土城洞)にあった
↓↑
公孫氏
後漢の末
中平六年(189年)
中国東北部の
遼東太守となった
公孫度は・・・公(おおやけ)=八(捌)+ム
孫(まご)
度(たび・旅・足袋・田尾)
・・・天孫降臨・・・?
後漢の放棄した
朝鮮半島へ進出
平壌付近から
漢城北方にかけてにあった
楽浪郡を支配下に置き
後を継いだ嫡子
公孫康・・・公孫康・・・康=广+隶・・・健康
广+肀+氺(水)
亠+丿+肀+氺(水)
╹+厂+肀+氺(水)
・・・厂(崖)の上の╹(灯火・あるじ)
・・・肀=熊手・柄杓
は
楽浪郡18城の南半
屯有県(黄海北道黄州)・・・駐屯の有る県
以南を割いて
帯方郡を分置
建安九年(204年)頃・・・
南方の土着勢力
韓・濊族を討ち
「是より後、倭・韓、遂に帯方に属す」
・・・倭は朝鮮半島の南部に存在していた
郡治=周囲の数十県(城)の
軍事・政治・経済を束ね
個々の県治よりもひときわ大きな城塞都市
公孫康は
魏の
曹操に恭順し
後漢の
献帝から
左将軍・襄平侯に任ぜられ
帯方郡は
後漢の郡とされた
↓↑
公孫康の死後
子の
公孫淵が幼いために
公孫康の実弟
公孫恭
が後を継ぎ
献帝から禅譲を受けた
魏朝の
文帝(曹操の子・曹丕)により
車騎将軍・襄平侯に封じられた
↓↑
太和二年(228年)・・・大和(やまと)
・・・太の和の
二のネン
年=𠂉+ヰ(wi・ゐ・井・韋)
韋(そむく・なめす・なめしがわ)
葦・偉・衛
228年
干支 : 戊申
神功皇后摂政二十八年・・・・・卑弥呼(?~242年~248年)
248-228=20
皇紀八八八・八百八拾八・888年
魏 : 太和二年
蜀 : 建興六年
呉 : 黄武七年
高句麗 : 東川王 二年
新羅 : 奈解王三十三年
百済 : 仇首王 十五年
↓↑
建興六年五月
泣いて馬謖を斬った(揮淚斬馬謖)年
「涙を揮(ふる)って馬謖を斬った」
↓↑
公孫淵
魏の
曹叡(明帝)からの承認され
揚烈将軍・遼東太守に任ぜられた
公孫淵は
魏朝の仇敵である
呉の
孫権との同盟を画策
魏から受けた
大司馬・楽浪公の地位を不足とし
景初元年(237年)
反旗を翻して独立を宣言
遼東の襄平城で
燕王を自称
帯方郡
楽浪郡
は燕に属した
↓↑
景初二年(238年)
魏の太尉
司馬懿
の率いる四万の兵によって
襄平城を囲まれ、長期の兵糧攻めで
公孫淵とその子
公孫脩は滅び
帯方郡は
「後漢─魏─燕」と
所属に変遷があったが
実質的は一貫して
公孫氏の領有下
韓や倭といった
東夷からの朝貢は
公孫氏が受け取っていた・・・
↓↑
卑弥呼(?~242年~248年)
238年 248-238=10
6月、邪馬台国の女王
卑弥呼が魏に使者を派遣
12月、明帝から「親魏倭王」の
金印・紫綬と銅鏡などを下賜
(魏志倭人伝)
干支 : 己未
神功皇后摂政三十九年
皇紀八九九・捌玖玖・899年
魏 : 景初三年
蜀 : 延熙二年
呉 : 赤烏二年
高句麗 : 東川王十三年
新羅 : 助賁王 十年
百済 : 古尓王 六年
↓↑
帯方郡は
魏の直轄経営
魏は
劉昕
と
鮮于嗣
をそれぞれ
帯方太守、楽浪太守に任じ
両者を密かに海路で
山東半島から黄海を越えて
朝鮮半島に派遣
帯方郡と楽浪郡の2郡を掌握させた
帯方郡は
魏の直轄地となる
太守
劉昕は
周辺の
東濊・韓族の首長に
邑君、邑長の印綬を賜与し
魏との冊封関係を改めて結び直した
邪馬台国・卑弥呼も
景初二年
(238年・『魏志倭人伝』の記述は誤りで
景初三年の説・・・?)
六月
帯方郡へ
朝貢使
難升米・・・難(むづかしい)
↓↑ 升(はかる・ます)⇔开の変形?
米(こめ)=丷+十+八
ベイ・マイ・メ
こめ・メートル
よね・稲の実
脱穀した穀物の実
メートル・長さの単位
亜米利加(アメリカ)の略
↓↑ アメリカ大陸
次使
都市牛利・・都(みやこ)=者+阝
市(いち)=亠+巾
牛(うし)=𠂉+十
利(とし)=禾+刂
刀・刂(かたな・りっとう)
リ
きく・するどい・よい・とし
よく切れる・都合がよい
役立つ
もうける
利息・利益
かしこい・さとい
役に立つ
きく・ものを言う・話をする
↓↑
を派遣した
太守は
劉夏で
郡の官吏を付けて
後漢の都
洛陽まで
難升米
の一行を送らせた
↓↑
正始元年(240年)
新太守
弓遵は
魏の詔書・金印紫綬を
配下の
梯儁
に持たせ
卑弥呼
のもとへ送った
↓↑
弓遵
正始六年(245年)
嶺東へ遠征し
東濊を討った後
帯方郡が所管していた
辰韓八国を
楽浪郡へ編入することになり
その決定を現地に伝えた際
通訳が誤訳をし
韓族を激怒させ
郡内の韓族が
帯方郡の
崎離営を襲った
弓遵と
楽浪太守の
劉茂
が討ち
魏軍は韓族を滅亡
弓遵も戦死
↓↑
正始八年(247年)
弓遵
から引き継いだ
太守
王頎は
倭の使者から
邪馬台国
と
狗奴国
との交戦の報告を受け
自ら上洛して官の決裁を仰ぐが
魏朝から
邪馬台国へ援軍が送られることはなく
魏の
少帝の
詔書
黄幢
を携えた
塞曹掾史
(外交官、軍使、軍司令副官など諸説)
の
張政が派遣された
↓↑
帯方郡の滅亡
泰始元年(265年)・・・泰=三+人+氺(水)
𡗗+氺(水)
始=女+台
魏の・・・・・・・・・・魏=委+鬼
禾+女+鬼
司馬炎(懿の孫、後の晋の武帝)
が魏の
曹奐(元帝)から禅譲を受け
晋朝(西晋)を興す
永康元年(300年)
八王の乱で混迷状態
帯方郡に属する県は
帯方・列口・南新・長岑・提奚・含資・海冥
七県(『晋書地理志』)
玄菟郡の遼東移動
前107年
衛氏朝鮮の跡地に
楽浪郡と共に置かれた
玄菟郡が
前75年
朝鮮半島から遼東(遼河東部地域)へと移動
111年
夫余が
玄菟郡、遼東郡、高句麗などを通り越し
楽浪郡を攻撃・・・?
122年
馬韓が帯方郡、楽浪郡、遼東郡を通り越し
高句麗主導で
濊貊と共に
遼東の
玄菟郡を攻撃したが
夫余によって撃退された・・・?
↓↑
建興元年(313年)
遼東へ進出した
高句麗が南下し
楽浪郡を占領
朝鮮半島南半に孤立した
帯方郡は
晋の手を離れ情報も途絶
帯方郡は
楽浪郡南部に残された
漢人の政権や都市は
東晋を奉じて5世紀初頭までの存続
5世紀前半
百済によって征服
5世紀後半
高句麗が
百済を駆逐して支配下へ置いた
↓↑
帯方郡の滅亡後
帯方の名は残ってい
広開土王碑文の
404年に
倭から
百済征伐の形で北侵
帯方界(旧帯方郡の境界)
に進入して
高句麗と戦った・・・
↓↑
帯方郡治の所在地
平壌の郊外
市街地とは
大同江を挟んだ対岸にある
楽浪土城(平壌市楽浪区域土城洞)にあった
帯方郡治の比定地
現代の38度線を挟んで諸説・・・?
↓↑
ソウル説と広州説
広州は最初の百済の都
3世紀の
馬韓の「伯済国」は広州にあった・・・
初期には
広州にあった帯方郡が
ソウルに遷り
その跡地に百済が興った・・・
↓↑
京畿道ソウル説
ソウルに帯方郡治があった・・・
『漢書地理志』に
前漢時代の
楽浪郡25県の1つとして
帯方県が記され
「帯水、西して帯方に至り海に入る」
この「帯水」とは
「大同江=列水」ではなく
中部を西流する大河の
漢江で
その河口部のソウルこそが
帯方郡治であった・・・「帯水=漢江」?
↓↑
京畿道広州説
ソウルの東南40kmの
広州を帯方郡治に比定・・・
漢江を河口から遡ると
ソウルを過ぎて北上する
北漢江と南東に向かう
南漢江に分かれる
「帯水、西して帯方に至り海に入る」
の
「帯水」を「北漢江」ではなく
「南漢江」
帯方郡治は広州・・・
↓↑
鳳山郡説と安岳郡説
↓↑
黄海北道鳳山郡説
平壌から南へ50km
黄海北道鳳山郡沙里院にある
唐土城
を帯方郡治に比定する説
楽浪郡址と同時代の
瓦・塼(煉瓦)・銭などが出土
付近の古墳群からは
「帯方太守 張撫夷塼」
と刻まれた塼槨墓が発見
↓↑
黄海南道安岳郡説
安岳郡に比定する説
「元康五年(295)」銘塼のある下雲洞古墳
「太康九年(288年)」銘塼出土の柳雲里北洞
楽浪墓制と同じく
漢人の塼槨墓
大同江河口の入江を扼する位置にあり
中国遼東半島、山東半島のどちらにも近い
↓↑
帯方郡の疆域
鳳山郡・安岳郡・信川郡など
載寧江流域の一帯には
他国からの流入者・亡命者などを含めた
中国人社会が形成されていた・・・
↓↑
北帯方
前漢が
楽浪郡・・・場所は遼東或いは遼西
↓↑ 遼東、遼西とは
遼東半島ではなく
遼河の東部或いは西部地域・・・?
「樂浪遂城縣有碣石山,長城所起」
「西連諸國至于安息,東過碣石以玄菟
樂浪為郡
卻匈奴萬里,更起營塞,制南海以為八郡」
「樂浪郡武帝置。雒陽東北五千里
…郭璞注山海經曰
列,水名。列水在遼東」
「浪郡,故朝鮮國也,在遼東」
「長岑縣,屬樂浪郡,其地在遼東」
「安帝永初五年(111年)
夫餘王始將歩騎七八千人寇鈔樂浪
殺傷吏民,後復歸附」
「楽浪郡の場所=遼東」
「乙支文徳・・・?
6世紀後半~7世紀初頭
石多(ソクダ)山の者・・・石多?
高句麗の将軍。大臣
隋の
宇文述
・・・宇(そら)文(ふみ)述(のべる)
于仲文
・・・于(まげる)仲(なか)文(ふみ)
は煬帝より
嬰陽王か
乙支文徳将軍の
捕縛を命じられていたが
隋の第二次高句麗遠征(612年)で
隋軍に追い討ちをかけ勝利」
元史(1369年)
「咸平府,古朝鮮地,箕子所封
↓↑ 漢屬樂浪郡,後高麗侵有其地」
と同時に
設置(紀元前108年)した郡
郡治は今の全羅南道羅州市にあった
漢四郡(楽浪・玄菟・臨屯・真番)は
漢五郡だった
紀元前八十二年?)
独立国を自称(帯方国)し
三十七年
高句麗に滅ぼされた・・・
↓↑
南帯方
魏(220年~265年)
全羅北道南原市に郡治が置かれた・・・
魏が遼東の公孫氏を滅ぼし
楽浪郡と帯方郡を接収した
238年以降のある時
魏は一時的にせよ
帯方郡を大きく南へ移動させた
魏が馬韓の反乱を鎮圧した
245/246年の出来事か・・・
↓↑
帯方郡=遼東
後漢書高句麗伝
「郡國志西安平、帶方縣 並屬 遼東郡」
魏志高句麗伝
「順(帝)、桓(帝)之間,復犯 遼東
寇 新安、居鄉
又 攻 西安平 于道上 殺 帶方令
略得 樂浪太守妻子」
晋書地理誌
「帶方郡 公孫度置。列口, 長岑, 含資」
長岑=遼東
含資県=遼西県属
↓↑
313年以降
平州
楽浪郡、玄菟郡、遼東郡、帯方郡、昌黎郡
から構成・・・
↓↑
「辰韓人などの亡命中国人(秦人)の遺構」
↓↑
韓は帯方郡の南、東西は海で尽き、南は倭と接する
楽浪郡の使いは大船に乗って
辰韓に入り、千人の仲間を奪還した
「万余の兵を船に乗せて攻撃する」
と辰韓を威嚇した
鉄が産出され
市場で中国が銭を用いるように鉄を用いる
韓、濊、倭や
楽浪、帯方にも
鉄を供給
↓↑
山海経
海内北経
「蓋国は・・・蓋=亠(トウ・ズ)=音の漢字の略字
蓋=艹+盍
艹+去+皿
艹+土(十一)+厶+皿・・・2月11日
艸・艹(くさ・くさかんむり・そうこう)
ガイ・コウ
ふた
おおい(覆い・蔽い・被い)
おおう
かさ
けだし
おおいかくす・かぶせる
とま
地をおおう天・空
「けだし=思うに・多分」
とま(苫)
むしろ(筵・莚・蓆)
かや(萱)
がま(蒲)
などを編んでつくったおおい(覆い)
「なんぞ・・・ざる」と読み
↓↑ 「どうして・・・しないのか」の意
鉅燕の南
倭の北にあり
倭は燕に属す」
陸続き・・・
燕は河北省北部(北京周辺)の国
蓋国=倭は燕に属す
遼東半島or朝鮮半島北部
漢書地理誌に
「樂浪海中有倭人」
楽浪海=遼東湾、西朝鮮湾、黄海・・・
魏志韓伝
「南は倭と接する」
「瀆盧国は倭と接する(與倭接界)」
倭が朝鮮半島にあった・・・
北史百済伝
百済=倭人
倭と百済は陸続き・・・
宋書倭国伝
倭王武=倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓
六国諸軍事、安東大将軍、倭王に叙爵
倭国が朝鮮半島に固執した理由
宋書倭国伝
倭の五王
「記紀」に記述が無い
旧唐書
「日本国は倭国の別種」
倭国と日本国は別の国・・・
三国史記新羅本紀
第四代国王
脱解(新羅王)=出身は多婆那国・倭国の東北一千里
脱解は倭人・・・
三国史記新羅本紀
倭国侵入記録
↓↑
馬韓、百済は遼東半島の国家
馬韓=百済初期の位置ではなく
遼東半島・・・
魏志韓伝
馬韓の西海上の大島に州胡があった
大島・・・
後漢書高句麗伝
建光元年(121年)
高句麗が
馬韓
濊貊
と共に
玄菟郡へ侵攻
夫余によって撃退された・・・
馬韓が朝鮮半島南西部とすると
高句麗が
楽浪郡の向こう側にあった
馬韓と共に
遼東にあった玄菟郡に侵攻・・・
馬韓=玄菟郡付近
宋書百済伝
百済国=高句麗とともに遼東の東、千余里に在った
朝鮮半島南西部は?
宋書百済伝
遼西を支配した
朝鮮半島南西部にあった百済が
遼河の西部を支配するのは不自然・・・
北史百済伝
「東は新羅、北は高句麗
西南は大海、小海の南に暮らす」
「小海」とはどこか?
北史
高句麗の南には「小海」がある
当時の高句麗は
遼東や遼西を支配していた
北史百済伝
百済の南
海行三カ月に
耽牟羅国(済州島)
朝鮮半島南西部から三ケ月?
南斉書
北魏が数十万騎で
百済を攻めた
渡海作戦を行ったような記述は無い
北魏と百済の間には高句麗が有り
高句麗の向こう側に数十万騎を送るのは不可能?
魏書勿吉伝
勿吉が百済と共謀して
水路から高句麗を攻撃する計画を立てた
北魏はこの計画を了承しなかった
百済が朝鮮半島南西部にあったとすると
不自然な計画?
史記夏本紀
「百済国西南
渤海中に大島十五有り
皆百済に属す」
百済は「渤海」に面していた・・・渤海は沿海州?
朝鮮半島南西部の
栄山江流域(羅州、光州、霊岩)
からは
前方後円墳、 超巨大甕棺墓、
九州式の横穴式石室などの倭人系の墳墓が多数出土
当時の朝鮮半島に存在した
百済系、新羅系、加耶系の文化とは全く異なっていた
倭人系勢力が長期間に渡り存在した
倭国の遺跡群・・・
馬韓や百済が朝鮮半島南西部にあったとすると
何故このような遺跡群が出てくるのか・・・
倭人系勢力の存在は
卑弥呼の時代から6世紀半ばまで確認
以降は百済式に変わった事が考古学的に確認
中国文献、朝鮮文献において
朝鮮半島における
倭国の記述が消える時期と一致・・・
倭の五王は
栄山江流域にいたのではないか・・・
百済が朝鮮半島南西部にあったのは
武寧王
聖明王
以降の最後の期間だけだった・・・
栄山江流域の
羅州市
永洞里の古墳から発見された
人骨をDNA型鑑定
百済や新羅の人骨とはいずれとも似ていなかった
現代日本人のDNAと非常によく似ていた
栄山江流域には
現代日本人と血縁関係が深く
独自の文化圏を維持した強力な
倭人系の国家が300年に渡って存在
↓↑
古朝鮮は
遼東国家
楽浪郡平壌説
衛氏朝鮮、箕子朝鮮、楽浪郡
なども朝鮮半島にあった・・・
遼東にあった・・・なら
後漢書光武帝紀
衛氏朝鮮の跡地に
楽浪郡を置き
その地は遼東にあった
衛氏朝鮮は遼東にあった・・・
史記朝鮮列伝
「朝鮮には濕水、洌水、汕水が有り
三水が合流して洌水となる」
後漢書郡國志
「列水は遼東にある」
朝鮮は遼東にあった・・・
史記蘇秦列伝
「燕東有朝鮮(潮仙二音,水名)
遼東、北有林胡、樓煩」
燕は
北京のあたりにあった国
記載順序によれば
朝鮮は遼東より西側にあった
「朝鮮」は川の名前・・・
朝鮮=遼河流域
魏志韓伝
衛氏朝鮮の宰相が
東の辰国に亡命・・・
史記朝鮮列伝
衛氏朝鮮王の
右渠を打つために
斉から渤海へ
楼船に5万の兵を載せて出発した
衛氏朝鮮は渤海に面していた・・・
晋書地理誌
「樂浪郡漢置。朝鮮県=周封箕子地。
遂城県=秦築長城之所起」
箕子朝鮮があった場所は
秦の始皇帝の築いた
長城の始まる所(碣石山)の近くにある・・・
箕子朝鮮は遼東か遼西あたりにあった・・・
隋書
「高麗之地,本孤竹國也。
周代以之封于箕子
漢世分為三郡,晉氏亦統遼東」
孤竹国は河北省にあった国
箕子朝鮮は遼西あたりにあった・・・
旧唐書
「遼東之地,周為箕子之國,漢家之玄菟郡」
箕子朝鮮は遼東にあった・・・
↓↑
遼史地理志
「東京遼陽府は、本の朝鮮の地なり」
箕子朝鮮は遼陽市のあたりにあった・・・
楽浪郡、玄菟郡
と同じく
衛氏朝鮮
箕子朝鮮
も朝鮮半島にあったという
記述は古代史書には存在せず
その場所は遼東か遼西・・・
「朝鮮」とは
漢書地理志で
「楽浪郡の25あった県の一つ」
後漢書郡国志で
「楽浪郡の17あった県の一つ」
「朝鮮」という地域は
朝鮮半島のような広大な地域を示す地名ではなく
川の名前・・・
その川とは
朝鮮半島ではなく
遼陽市を流れる
「太子河付近の河川」だった・・・
↓↑
衛氏朝鮮の跡地には
漢四郡が置かれたが
真番郡・臨屯郡はすぐに廃止され
実質的に設置されたのは
楽浪郡と玄菟郡の2郡だけ
朝鮮半島部分は
楽浪郡と後に設置する
帯方郡が担当
遼東半島部分は
遼東郡が担当
遼東部分は
楽浪郡を追い出した分を
玄菟郡が担当することになった・・・
これを否定すれば
楽浪郡と共に
衛氏朝鮮の跡地に置かれ
28年後に廃止されて
楽浪郡に統合された
臨屯郡
定説では
江原道の江陵市のあたりにあったはずの
臨屯郡の太守
章封泥が
遼西の遼寧省の葫芦島市で発見
臨屯郡の太守
章封泥が
遼西で発見されたのは不自然
↓↑
遼東郡の
文県
と
番汗県が離れすぎ
遼東郡の説明に
文県と
番汗県が
併記されている
「満潘汗」が朝鮮国との国境であり
「文」と「満」が同じ音であるため
「満潘汗」は
「文県と番汗県」を意味するものと推測される
朝鮮国を朝鮮半島に置いたことによって
番汗県は
清川江河口にある
博川付近に比定されることとなった
しかし
文県は遼寧省 営口市付近に比定
文県と番汗県が離れすぎている
古朝鮮を朝鮮半島に移動した結果
遼東郡を巨大化させために発生した
玄菟郡が設置後まもなく
遼東に移動されたのはあまりにも不自然
玄菟郡と楽浪郡は
朝鮮跡地の郡として同時に頻繁に現れ
玄菟郡は楽浪郡の近くにあった・・・
楽浪郡が
衛氏朝鮮の跡地に創設された事から
楽浪郡を遼東から朝鮮半島に移動させるためには
衛氏朝鮮を朝鮮半島に移動させる必要があった
玄菟郡=遼東に存在した郡
楽浪郡を平壌とするために
玄菟郡だけをすぐに遼東に戻し
楽浪郡や遼東郡が抜けた
遼東部分を全て玄菟郡に分担させた・・・
↓↑
戦国時代
燕が朝鮮に侵攻
障壁(燕長城、遼東長城)を築いた
燕人満は長城を出て東に向かい
朝鮮との国境である
浿水に向かった
国境があった
番汗県や浿水を清川江とすると
燕長城は朝鮮半島内にあったはずだが
長城はどこにも見つからなかった
浿水を鴨緑江や大同江などに比定してみても
長城はどこにも見つからなかった
広範囲に建築された
建造物であるにもかかわらず
跡形もなく消えてしまった・・・
↓↑
楽浪郡や古朝鮮を
朝鮮半島に移した事により
楽浪郡
遂城県の万里の長城の起点も
朝鮮半島に大移動される事になった
朝鮮半島に長城が存在しないとなると
衛氏朝鮮が
朝鮮半島に存在しないという事になり
即ち
楽浪郡平壌説が成立しない
万里の長城の起点は
碣石山と明記されている
「玄菟郡の遼東移動」と同様
中国側から朝鮮半島を攻撃するのは困難だが
朝鮮半島から中国側を攻撃するのも困難
豊臣秀吉の朝鮮出兵時
小西行長は
清川江を越えられなかった
朝鮮戦争においても
補給線が伸びきった
米軍は鴨緑江を越えてきた
人民義勇軍に敗走した
歴史上で
朝鮮半島から
千山山脈を越えて
中国に攻め込んだ国家は
大日本帝国だけ(百済の遼西侵攻は除く)
↓↑
明代に作られた
虎山長城などを根拠に朝鮮半島まで
燕の長城が建設されなかった
その虎山長城ですら中国側は
遼東半島を貫く明史の長城の一部であるとしているが
明史の記述は長城の建設というより
単に防衛線を記述しただけとも見られる上
虎山長城自体が実際には
高句麗が建設した
泊灼城とも言われている
↓↑
楽浪郡平壌説
歴史書で朝鮮や楽浪郡の場所を示す
浿水、列水、帯水などの川の古名を
遼河、東遼河、渾河、太子河などではなく
鴨緑江、清川江、大同江などに
比定する事によって成立
浿水、列水、帯水などの地理条件を示すだけで
定説破綻
漢帝国の版図拡大を無理に行ったため
楽浪郡(朝鮮半島)
遼東郡(遼東半島)
玄菟郡(遼東)
の3郡の位置関係にはほとんど自由度が無い
↓↑
後漢書列傳・祭遵從弟肜
「(烏桓の)東は玄菟郡、樂浪郡」
玄菟郡と樂浪郡は隣接し
樂浪郡の西側は
遼東郡でも黄海でもない事が示されているが
楽浪郡平壌説の破綻
漢書に
「碣石より東は玄菟郡、楽浪郡」
玄菟郡と樂浪郡は隣接し
樂浪郡の西側は
遼東郡でも黄海でもない
↓↑
「夫余の楽浪郡攻撃」
夫余にとって
楽浪郡は
攻撃できる範囲内の距離にあった
玄菟郡、遼東郡、高句麗などを通り越して
楽浪郡を攻撃するのは不可能・・・
「馬韓の玄菟郡攻撃」
馬韓にとって
玄菟郡は攻撃できる範囲内の距離
帶方郡、楽浪郡、遼東郡などを通り越して
玄菟郡を攻撃するのは不可能・・・
↓↑
楽浪郡平壌説は論理破綻
↓↑
遼西地域において
臨屯太守章の封泥が出土した・・・
話題にしない事にする・・・
↓↑
朝鮮跡地に
玄菟郡が設置された事は
目立たない
興味を持たせない・・・
まるで頻繁に移動される
奇妙な郡であるような印象を与え
「玄菟郡の遼東移動の怪」
に疑問を持たせない
↓↑
楽浪郡平壌説によって
倭国が半島から消去された
高句麗は巨大な国家となってしまった
対馬海峡の向こう側にいた
倭国が半島国家群を属国にして
その強大な
高句麗と朝鮮半島で覇権を争った・・・
歴史教科書は
朝鮮半島から倭国を消去
歴史書は
朝鮮半島の倭国を消すことができなかった
↓↑
見つからない邪馬台国
見つからない侏儒国
見つからない州胡
見つからない万里の長城
裸国
黒歯国
倭国半島
夫余の楽浪郡攻撃
玄菟郡の遼東移動
馬韓の玄菟郡攻撃
百済の遼西支配
北魏の百済攻撃
文県と番汗県
朝鮮半島南西部から
倭人系の墳墓が多数出土し
日本国は倭国の別種
倭の五王
高句麗との戦争が
記紀に記録されていない
謎
↓↑
添付部分はそのままのモノではありません
「原文」のスベテは
「・・・
http://lelang.sites-hosting.com/naklang/rakurou.html
・・・」で
「虚構の
楽浪郡平壌説
~帯方郡、玄菟郡、馬韓の場所と
禁断の高句麗史
~Seeking truth in a world of lies~
暁 美焔(Xiao Meiyan) 社会学研究家,
2019.4.19 祝2.5版完成!
本ウェブページ内容の複製、引用、リンク、
再配布は自由です・・・」
↓↑
・・・以上は「カンジモウソウ」の中での
検索で発見し、勝手に部分引用し添付させてもらったモノで
「帯方郡⇔たいほうぐん⇔替法組⇔他意法句務」の
語源はナンゾヤの検索派生で発見したモノで
歴史資料の「原文」を・・・「ゲンブン」?
直にヨムことの乏しい
ボクにとっては
面白かった・・・デス・・・
↓↑
平州(へいしゅう)は
中国にかつて存在した州
北魏から金代にかけて
現在の
河北省
秦皇島市
一帯に設置・・・
583年(開皇三年)
隋が郡制を廃止し
北平郡が廃止
平州に編入
平州は
盧龍県1県を管轄
607年(大業三年)
州が廃止、郡が置かれ
平州が
北平郡と改称
619年(武徳二年)
唐により
北平郡は
平州と改められ
臨渝・肥如の2県を管轄
742年(天宝元年)
平州は北平郡と改称
758年(乾元元年)
北平郡は平州と改称
923年(天賛二年)
契丹が
後唐の平州を攻め落とした
遼の平州は
南京道に属し
遼興軍が置かれた
平州は
盧龍・安喜・望都の3県を管轄
1123年(天輔七年)
金の
阿骨打が
遼の平州節度使の
立愛を降し
平州は南京と改められた
1126年(天輔七年)
南京が平州にもどされた
平州は中都路に属し
盧龍・撫寧・海山・遷安・昌黎の5県を管轄
1215年
モンゴル帝国の
史天倪が平州を奪い
金の経略使の
乞住を降した
この地に
興平府が置かれた
1300年(大徳四年)
元の成宗により
永平路と改められた
永平路は
中書省に属し、4県1州州領2県を管轄
1369年(洪武二年)
明の洪武帝により
平灤府と改められた
1371年(洪武四年)
永平府と改められた
永平府は1州5県を管轄
清のとき
永平府は
直隷省に属し、1州6県を管轄
ーーーーー
・・・だから・・・なに・・・
「楽浪郡は朝鮮半島にも遼東半島にもなかった」・・・?
じゃぁ「帯方郡」は・・・?