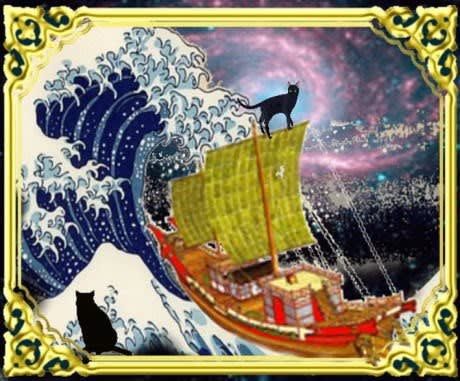聞雁(ブンガン)・・・目を細めてサイコウ・・・違う? ↓↑ 「靴=くつ=沓」の効用・・・
↓↑
長距離ランナー(走者)の靴(沓・舄)・・・
軍靴(グンカ)の伝令の情報・・・
草鞋(わらじ)の飛脚の手紙・・・
草履(ぞうり)
下駄(げた)
雪駄(雪踏・せった)
襪(シタウズ)は足指の股のあいていないもの
革足袋(かわたび)
小人革(こびとがわ)は中国(唐)渡来の革足袋
東北で産し薄く滑らかな上質の鹿革
小人は面(おもて)を革(あらた)む
「君子豹変、小人革面。 易経」
革命=命を鞣(なめす)す
皮革(ヒカク)=鞣した動物の皮
木綿足袋=長崎足袋
足袋(たび)は和装の際に足に直接履く
叉割れ靴下の一種
地下足袋(じかたび)は
「弋職=鳶職(とびしょく)・曳き屋、遣り方)」
が足に直接履くモノ
↓↑
遠走・遠足
安政遠足(あんせいとおあし)
1855年(安政二年)
安中藩主(群馬県安中市)
板倉勝明が
藩士96人に
安中城門から
「碓氷峠(うすいとうげ・・・小碓命
群馬県安中市松井田町坂本
と
長野県北佐久郡軽井沢町との境
信濃川水系
と
利根川水系
とを分ける
中央分水嶺)」
の
熊野権現神社まで
走らせた徒歩競走
1955年(昭和30年)
「碓氷峠(うすいとうげ)」・・小碓命?
タイヒョウ・・・・・他意豹?
の茶屋で発見された
『安中御城内御諸士御遠足着帳』
に記録
↓↑
「マラトンの戦い
(希語 Μάχη του Μαραθώνα・Battle of Marathōn)」
紀元前490年9月12日 or 11月2日
ギリシアのアッティカ半島東部
マラトン(Marathon)で
アテナイ・プラタイア連合軍(1万1000)
VS
アケメネス朝ペルシア(約2万5000)
↓↑
第2回ペルシア戦争
ペルシア帝国
ダレイオス1世の派遣遠征軍を
アテネ連合軍の
ミルチアデスの指揮下
重装歩兵1万 (ホプリタイ)
ボエオチア地方の
プラタイアイの援軍1000
が迎え撃ち
勝利した戦い・・・
↓↑
「エウアンゲリオン(良い知らせ)」
福音 (英語Gospel)
エウアンゲリオンEvangelion
ギリシャ語 εὐαγγέλιον, euangelion
「良い(euエウ-=good)
知らせ(-angelion アンゲリオン=message)」
good news
↓↑
「兵士
フィディピディス(Philippides)・・・ヘロドトス
or
エウクレス(Eukles)・・・プルタルコス
が勝利の知らせを
アテネに伝える伝令の役を命じられ
約三十六キロの道のりを駆け
アテネに帰り着き
「わが軍、勝てり」
と叫び、倒れて息絶えた」
↓↑
「韋駄天」も息切れ・・・
・・・聴癌(疒+品+山)の
呻(口+申)き・・・
カワヤ(化話也)で・・・
↓↑
韋 応物(イ オウブツ)
・・・これが
この時代の
和銅五年(712年)・古事記
養老四年(720年)・日本書紀
(712年~770年)
の名前???
↓↑ ↓↑
770年
干支 庚戌年
日本 神護景雲四年、宝亀元年
皇紀1430年
中国 唐 大暦五年
↓↑ ↓↑
770年
8月 弓削道鏡が失脚し、下野に配流
9月 和気清麻呂らを召還
10月23日
(神護景雲四年十月一日)瑞亀献上改元
(宝亀 元年十月一日)白壁王即位
第四十九代光仁天皇
誕生
菅原清公
ミカエル2世・・・観返る似与?
東ローマ帝国
アモリア王朝・・・安杜阿・蛙摸理倦?
初代皇帝
↓↑ ↓↑
死去
8月28日(神護景雲四年八月四日)
孝謙天皇・第46・48代天皇(718年~770年)
10月31日 (宝亀元年十月九日)
↓↑ ↓↑
文室浄三(ふんや の きよみ)
初名 智努王・知努王・珍努王・茅野王(ちぬおう)
天武天皇の孫
長親王の子
↓↑ ↓↑
阿倍仲麻呂(698年~770年)
李白、王維ら唐代の文人多数と交際
↓↑ ↓↑
岑参 (715年~770年)
(シンシン・・759年(乾元二年)虢州刺史
762年(宝応元年)太子中允・殿中侍御史
765年(永泰元年)嘉州の刺史)
↓↑ ↓↑
杜甫(712年~770年)・・・杜の鍛冶屋の補?
(トホ・712年(先天元年)~770年(大暦五年))
・・・徒歩?
杜審言の子の
杜閑が奉天の県令
その子が
杜甫
字 子美
号 少陵野老
老杜・大杜
別号 杜陵野老・杜陵布衣
杜少陵・杜工部(検校工部員外郎)
杜拾遺(左拾遺)
720年(開元九年)初めて「大字」を習う?
742年(天宝元年)姑母の「万年県君」
が洛陽で死亡
杜甫は多彩な要素を
対句表現によって構成する詩人
↓↑ ↓↑ ↓↑
韋 応物(イ オウブツ)
「豬 負 武通」
・・・伊吹山の「建」?
736年~791年?
中唐の詩人
京兆府
杜陵県 出身
玄祖父 韋沖(イチュウ)
高祖父 韋挺(イテイ)
曾祖父は
則天武后の時代の宰相
韋待価(イタイカ)
祖父 韋令儀(イレイギ)
父 韋鑾(イラン)・・・親鸞(シンラン)
鸞=䜌+鳥
戀=䜌+心=恋=亦+心
䜌 = 亦
戀愛・戀情
・・・ 鑾=糸+言+糸+金
ラン・すず
天子の馬車などにつける鈴
天子の馬車・天子
鑾駕(ランガ)・鳴鑾(メイラン)
786年
蘇州刺史・・・蘇(我)襲 刺史(志士・嗣子・猪)?
↓↑
聞雁(ブンガン)・・・雁(ガン・かり・鴈)
文借 カモ目カモ科ガン亜科の
文癌 水鳥一群の総称
文願 「枕」詞は「遠つ人」
↓↑
故園眇何處 故園(コヱン)
眇(ビョウ)として
何処(いずくぞ)
↓↑
歸思方悠哉 帰思(キシ)
方(まさ)に
悠なる哉(カナ)
謬悠之説(ビュウユウのセツ)=荒唐無稽
別府 結う 窃?
↓↑
淮南秋雨夜 淮南(ワイナン)・・・倭委名務?
秋雨の夜(ヨ)・・・・安芸得の世?
↓↑
高斎聞雁来 高斎(コウサイ)・・・北斉(550年~577年)
南北朝時代
高氏によって建国
雁(ガン・かり)の
来(きた)る
を聞く
ーー↓↑ーー
牛=𠂉+十
牝=牛+匕
牟=ム+牛
むさぼる(貪る)
眸=目+牟(ム牛)=瞳
𤘱=牛+𠂔
異体字「𤙂・㸬・𤘱・𤙍」
牡=牛+土(十一)
牴=牛+氐(氏一)
おひつじ・雄の羊・羝
およそ・おおよそ・ふれる・あたる・さわる
牢=宀+牛(𠂉十)・牢屋・牢獄
物=牛+勿(なかれ・フツ)・「物資・物質」
「物部・物語」
物体=形而下⇔物部
観念=形而上⇔物語
牧=牛+攵(𠂉乂)・牧場
牲=牛+生(𠂉土・𠂉十一)・犠牲
特=牛+寺(土寸)・特権
牽=亠+丷+冂+牛
牾=牛+吾(五口)
![]()
![]()
犀=尸+=丨=+牛
異体字「犀・𡱝・𡳚・𡥷」
「尾+牛」=「𡱕+牛」
犀(サイ・セイ) ・犀利(サイリ)
木犀・木樨(モクセイ)
遲=遅 (チ・おそい)・遅刻
稚=穉 (チ・わかい)・稚拙
犇=牛+𤘧
犂=牛+禾+勹+丿
犒=牛+高(ねぎらう・コウ)
犖=𤇾+牛=炏+冖+牛
ラク
まだらうし
すぐれる・卓犖
毛色がまだらの牛
あきらか・はっきりした
犠=牛+義
犢=牛+
トク
こうし・牛の子・犢車
舐犢(シトク)
犢鼻褌(ふんどし)
犧=牛+羲(羊禾丂戈)
女媧(人類創造の女神・姓は風、伏羲の妻妹)
犏=牛+扁
雄の赤牛と雌のヤクを交配した雑種牛
赤牛より力が強く乳量が多く
ヤクよりおとなしい)
牦牛(ヤク)との一代交配種
旄牛(ボウ牛・モウギュウ)
ーー↓↑ーー
仮名⇔相象類似の漢字
↓↑
阿ア・伊イ・宇ウ・江エ・於オ
了 ィ 宀 工 才
↓↑
加カ・機キ・久ク・介ケ・己コ
力 ‡ 勹 亇个 コ
↓↑
散サ・之シ・須ス・世セ・曽ソ
廾 氵 一人 乜 冫
丷
↓↑
多タ・千チ・川ツ・天テ・止ト
夕 干 爪 亍 ト
⺌ 梳
↓↑
奈ナ・仁ニ・奴ヌ・祢ネ・乃ノ
ナ 二 又 丶不 丿
㔫=𠂇+匕
𡯃=左=𠂇+工
右=𠂇+口
↓↑
八ハ・比ヒ・不フ・部ヘ・保ホ
八 七𠤎匕 𠃌 𠆢 𣎳・𣎵
𣏕・𤝂・㳈・𤘱
梳(とく)
↓↑
末マ・三ミ・牟ム・女メ・毛モ
マ 彡 ム 乂 乇=睫毛
矛 私 乄
罓・网=目を瞑る
↓↑
也ヤ・・由ユ・・譽ヨ
乜 ユ ヨ・⺕
夬 彐
↓↑
良ラ・利リ・流ル・礼レ・呂ロ
ラ 刂 儿 𠄌 口
乚 囗
↓↑
和ワ・井ヰ・・恵ヱ・乎ヲ
冖 韋 工 刁
倭 偉
輪 緯
〇 違
〇〇〇=三輪山に
居・為=爲
ーー↓↑ーー↓↑ーー
韋=ヰ=ゐ(wi)
=為(ゐ・なす・なせ)呉音、漢音
爲=爫+尸+¬+勹+灬
爪+尸+¬+勹+灬
「爪(手のツメ)」+「象」
で「象」を手なずける・・・?
僞=イ+爲=似せる・虚偽
葦=蘆=芦=あし=足・脚・肢・葭・疋・趺=尼子
↓↑ ↓↑
韋=ヰ=ゐ(wi)
ゐ(wi)=居・為・井・率・座
猪・位・藍・謂・坐
藺
「韋」字=「違」の本字
背きあうことを意
字形は
背いた足の象形「舛(ます)」
「以鼠為璞(イソイハク)」
五十五葉句?
委蘇磐俱?
取るにたらない物を
高価なものとして扱うこと
「璞(ハク)」は宝石の原石
鄭の国では原石を「璞(ハク)」
周の国では鼠の生肉を「朴(ハク)」
と言っていた
鄭の国の商人が
周の国の人に
「ハク」を買わないかと言われたが
「璞=宝石の原石」ではなく
「朴=鼠」だった・・・「ねずみ=移鼠=イエス」?
「鼠を以て璞と為す」・・・「鼠」を守って「王の」
『戦国策(秦)』
璞=王+菐・・・「菐は煩猥で、瀆菐は煩雑」
「丵=掘鑿に使う道具・刺青の針」
「男子皆黥面文身」の「針」
「丵=掘削などに用いる器・削岩機
大なるものが業で撲伐の器
両手に持つ形が菐
両手に持って叩くのが撲
相対して土壁を撲(う)ち堅めるのが
対(對)
材木を切り出して樸
玉を切り出して璞
丵=叢生する艸(くさ)」
「僕=下僕・使用人・君僕=you & me」
「撲耕=小作農・貝菐=土地の貸借関係」
「業=稼業・職業・産業」
王+业+䒑+夫
王+业+䒑+二+人
王+业+丷+一+夫
王+业+丷+一+二+人
王+业+䒑+一+一+人
王+业+丷+一+一+一+人
↓↑
石韋(ひとつば)=一葉・・・樋口一葉?
薬用植物一
獅子ひとつ葉
ウラボシ(裏星)科
多年生
シダ(羊歯・歯朶)植物
革質の葉が根茎から
一枚ずつ直立
生薬名 セキイ(石韋)
↓↑
画韋=えがわ=絵革
獅子(しし)
牡丹(ぼたん)
不動尊などの
文様の彫り型を当て
藍や赤で染めた革
『延喜内蔵寮
(えんぎくらりょう)式』に
「画革二十張」
武具・調度品の覆い
袋物、韋緒(かわお)などに利用
中世以降は
甲冑(かっちゅう)の
金具廻(かなぐまわり)の
包韋や弦走(つるばしり)
として用いた
染法は染型による
踏込染(ふんごみぞめ)が行われた
獅子牡丹(ししぼたん)文
風神雷神
竜文
倶利加羅(くりから)文
不動三尊像
などが用いられ
牡丹が形式化して
藻のようになった
藻獅子文(もじしもん)が
南北朝・室町時代に流行
江戸時代には
肥後(熊本県)の
八代韋(やつしろがわ)
甲冑の
「革」は硬質の主に牛馬の皮
「韋」は柔らかな鹿の押し韋
もみ韋の事
↓↑
韋編(イヘン)
韋=なめしがわので綴(と)じた本の革ひも
本・書物
↓↑
韋編三絶(イヘンサンゼツ)
イヘン
⇔「異変・異篇」
サン
「纂・簒・篹
撰・讃」
ゼツ
「説・洩・拙・窃」
孔子が晩年「易経」を読み
綴じた革ひもが何度も切れた
「史記孔子世家」の故事
繰り返し読むこと・熟読
韋編三たび絶つ
↓↑
韋駄天走(イダテンはしり
ヰダ・テンソウ)
イダ 伝奏・転送
「彙拿・異拿・意拿」
テン
「典・点・店・展・転・添」
ソウ
「叢・奏・相・双・総・送」
奏⇔秦⇔泰⇔奉
韋駄天(Skanda)
サカンダ・・・左官拿?
塞建陀天
私建陀天
建駄天
・・・
建(たける・武
倭男具那・童子・小碓命)
駄(馬+太)
天(二+人)
天部に属する神=韋陀・韋天将軍
八将の一神
小児の病魔を除く神
足の速い人
の例え
帝釈天が
仏の
荼毘(ダビ)処・・・焼身・焚焼
死体を焼いて弔う
火葬場
に至って
二牙を拾得したが
二捷疾羅刹=夜叉
=薬叉
(ヤクシャ)
訳者・譯者・役者
翻訳者 演技者
役人・厄人
約人
屋久人
のために
一牙を奪われた
ーーー↓↑ーー
屋久(やく)島
↓↑
『隋書』
大業三年(607年)
煬帝の代
「夷邪久国」
の記述が初見
「夷邪久」=屋久島
と
「夷邪久」=南島全般
(種子島・屋久島より南方)
を指す説・・・
↓↑
『日本書紀』
推古天皇二十四年(616年)
「掖久・夜勾・掖玖」
の人三十人が日本に永住した記事
舒明天皇元年(629年)
大和朝廷から掖玖に使が派遣された記録
天武天皇十一年(682年)
「多禰人・掖玖人・阿麻彌人(奄美人)
それぞれ禄を賜った」
という記載・・・
↓↑
『続日本紀』
文武三年(699年)
「多褹・掖玖・菴美・度感」
から朝廷に来貢
位階を授けた
記録
↓↑
種子島と多禰国との記述
大宝二年(702年)八月一日条
「薩摩と多褹が化を隔てて命に逆らう
是に於いて兵を発して征討し
戸を校して吏を置けり」
薩摩国
多禰国
が成立
以後、
令制国として一国に準ずる
「多禰国」に国司を派遣
南島(南西諸島・奄美・沖縄方面)
との交流
隼人の平定
遣唐使の派遣のため
「格」は中国として扱われていた・・・?
↓↑
天平勝宝五年(753年)十二月十二日
鑑真
大伴古麻呂
吉備真備
らを乗せた遣唐使船
第二船
第三船
が屋久島に帰国
第二船は
十二月十八日
大宰府に向け出港
二十日
秋目
二十六日
大宰府に到着
734年
753年
の二度
遣唐使が
多禰国
に帰国
↓↑
天長元年(824年)十月一日
「多禰島国司を廃止
能満郡・熊毛郡・馭謨郡・益救郡
の四郡を
熊毛郡・馭謨郡
の二郡に再編」し
「大隅国」に編入
↓↑
1203年
鎌倉幕府から
種子島氏に
種子島、南西諸島が与えられ
屋久島も支配下に置かれた
↓↑
1542年
大隅の
禰寝氏が
種子島氏の悪政を正すとの名目で
屋久島に襲来、島を占拠
宮之浦に
城ケ平城を築城
↓↑
1544年
種子島氏は
屋久島の奪還で城を攻める
禰寝氏は敗退
再び島は種子島氏の支配下
火縄銃が初めて使用された・・・
↓↑
1595年
種子島久時のとき
太閤検地に伴う所替えで
薩摩国
知覧に移され
屋久島は
島津家の直轄地となる
京都方広寺の
大仏殿建立用材調達で
島津家は
屋久杉を切り出した
↓↑
泊如竹
島津光久に招かれ薩摩藩に使えた僧侶
屋久島の
「安房」
の生まれ
↓↑
1708年
ジョヴァンニ・バッティスタ
シドッティ
Giovanni Battista Sidotti(Sidoti)
屋久島に上陸
↓↑
1891年(明治二十四年)
地租改正
島の山林が国有地に編入
国有林監視所が設置
↓↑
1921年(大正十年)
屋久島の国有林を
島民一般のためにのみ使用する
「屋久島国有林経営の大綱」を定めた
↓↑
1922年(大正十一年)
インフラ整備開始
ー↓↑ーー
韋弦之佩(イゲンのハイ)
異言 の葉意?
中国
戦国時代
「西門豹」は短気な性格を直そうと
「ゆったりとしたなめし皮」を身に着け
春秋時代
「董安干」は厳格な性格に改めるために
「かたい弓のつる」を身につけた
韓非子「観行篇」
↓↑
藜杖韋帯(レイジョウイタイ)
例 条 異体
飾り気が無く、慎ましいこと
「藜杖」は「あかざの杖」
「韋帯」は「なめし皮の帯」
『陳書(宣帝紀)』・・・「宣綴記」
本居宣長の綴記?
↓↑
布衣韋帯(フイイタイ)
不意異体
不異衣袋
不委異碓
官職についていない、普通の人
身分の低い人
『漢書』「賈山伝」
↓↑
佩韋佩弦(ハイイハイゲン)
↓↑
「韋」の「ことわざ」
韋編三度絶つ(いへんみたびたつ)
韋駄天走り(いだてんばしり)
↓↑
「韋」を含む人名
秋月韋軒(あきづき いけん)
韋天祖昶(いてん そちょう)
韋那磐鍬(いなの いわすき)
韋那部真根(いなべの まね)
韋駄天(イダテン)
↓↑
同部首「韋」の漢字
韓・・・韓国
韜・・・六韜三略
韋・・・ヰ・ゐ
ーー↓↑ーー↓↑ーー
姊=女+𠂔
通仮字「秭」
異体字「𡛷・姉」
𠂔=市=丶+帀
巿=十+冂・・・巿≠市(亠+巾)
一+巾
=前掛け・膝掛け・割烹着
=袚=衣+犮
芾(ハイ・フツ・ヒ・フチ)
草木が盛んに生い茂るさま
祭礼に用いる膝掛け
蔽芾(ヘイヒ)=小さいさま
杮(こけら)落し=欠片落とし
新築開館
開演
初演
「こけ=蘚・苔・鱗・虚仮」等
杮=十+八+巿(十+冂)=木+𠂔
芾=艹+巿
通仮字「紼」
異体字「市・𦬝」
𠂔=シ=丂+丨+丿=𠂔
止める
上に伸びようとする草木に
「ノ」を加えて
「伸びを止める」の意
同「𠥽」
ーーーーー
・・・???・・・
ペトロ(ヘブライ語 Šimʿon bar-Yonā
古典ギリシア語 Petros
古典ラテン語 Petrus)
↓↑
パウロ(ギリシア語 Παῦλος)
ヘブライ語 サウロ(Šāʼul)
パウロス(ギリシャ語パヴロス)
↓↑
「パウロ」=「小さい」
ラテン語
「パウルス」が転訛したギリシア語
「パウロス」の「ス」が落ちた形?
↓↑
「サウロ」・・・査雨露(烏鷺・迂路・洞・虚)?
が
「パウロ」・・・葉雨露(烏鷺・迂路・洞・虚・空)?
と名乗る
使徒言行録(使徒行伝・13章)
第一回伝道旅行
アンティオキア・・・案綴於記蛙?・・・蛙=かえる
教会から
宣教師として派遣
バルナバ・・・・・・場留名葉?
サウロ
キプロス島・・・・・記附呂諏当(問う)?
地方総督
セルギウス・パウルス・・・施留義得諏(碓・臼・宇受)?
パウルスが信仰に入った時、
サウロに・・・・・・・・・・佐宇盧?
「パウロ(パウルス)」
・・・・・葉鵜呂・葉得留諏?
という自分の名前を薦めた・・・?
↓↑
ラテン語の名前
「サウロ(サウルス)」
「サウロ」
古代
イスラエル王国最初の王
サウルに由来
ヘブライ語
「シャーウール」
ベニヤミン族
↓↑
「サウロ」は
「サウル」のギリシア語形
「サウロス」から
「ス」を省いた語
「サウル」=「主が求めた・求められた」
という意
↓↑
「パウロ」=「小さい」
小さい
ちいさい
ちさい
ちっさい
小
しょう
ちっちゃい
ちっぽけ
ちんまり
↓↑
英語
little
リトル
リトゥゥ
small
スモール
スモーウ
スモーゥ
tiny
タイニ
↓↑
ラテン語
minor
ミノル
parvum
パルウム・・小さいチャン=少彦名命
parvus
パルウゥス・小さいチャン=少彦名命
少名毘古那神
(すくなびこなのかみ)
須久奈比古命
別名
少彦名命
宿奈毘古那命
須久那美迦微
須久奈比古
少日子根命
小比古尼命
小彦命
小日子命
小名牟遅神
久斯神
少名彦命
↓↑ ↓↑
国造りの神
農業神
薬神
禁厭(呪術)の神
温泉の神
穀物
知識
酒造(醗・醸・醸造)
石の神
↓↑ ↓↑
親
神産巣日神
高皇産霊尊
天湯河桁命
↓↑ ↓↑
配偶者
伊豆目比売命
↓↑ ↓↑
子
菅根彦命
↓↑ ↓↑
神社
大洗磯前神社等
氏族
梶井氏(金丸村主)
鳥取連
伊豆国造
葛城国造
宇佐国造
忌部氏
服部氏
玉祖氏
↓↑ ↓↑
アイスランド語
litill=リーティトル
smar=スマウル
↓↑
イタリア語
piccolo
ピッコロ
piccola
ピッコラ
↓↑
カタロニア語(カタルーニャ語)
petit
パティト
petita
パティタ
↓↑
古代ギリシャ語
μικρον
ミクロン
mikros
ミークロス
↓↑
代ギリシャ語
μικρός
mikros
ミクロス
↓↑
ロシア語
малый
マールイ・・・丸井・円井
маленький
malen'kij
マーリニキー
マーリニキイ
マーリニキィ
マーリンキィー
↓↑
ウクライナ語
малий
malyj
マルィー
↓↑
ポーランド語
mały
マウィ
↓↑
チェコ語
maly
マリー
↓↑
マケドニア語
мал
mal
マル
↓↑
ブルガリア語
малък
malăk
マラク
↓↑
クロアチア語
mali
マーリ
sitan
シタン
↓↑
リトアニア語
mažas
マージャス
↓↑
ペルシア語
kuchek
クーチェキ
↓↑
ウルドゥー語
choṭā
チョーター
↓↑
ヒンディー語
cʰoṭā
チョーター
↓↑
ベンガル語
chhoto
チョト・・・一寸
↓↑
ネパール語
sāno
サーノ
↓↑
現代ヘブライ語
katan
カタン
↓↑
中国語
小
xiǎo
シァォ
シィアオ
シャオ
シアオ
↓↑
広東語
細
サイ
ーーーーー
石
英語
カブル=cobble
ストーン=stone
カブルストーン=cobblestone
ロック=rock
ボウルダ=boulder
↓↑
ドイツ語
シュタイン=Stein
フェルス=Fels
フェルゼン=Felsen
↓↑
フランス語
ピエール=pierre
ロック=roc
ロシェ=rocher
ロッシュ=roche
↓↑
イタリア語
ピエトラ=ピエートラ=pietra
ロッチア=ロッチャ=roccia
↓↑
「石」=「岩・磐」=カブル=cobble
「岩石」=rock・stone・ボウルダ=boulder
石蓴(あおさ)
石決明(あわび)
石蚕(いさごむし)
石が流れて木(こ)の葉が沈む
石に裃(かみしも)
石に灸(キュウ)
石に漱(くちすす)ぎ流れに枕(まくら)す・・・夏目漱石
石に立つ矢
石の上にも三年
石を抱(いだ)きて淵(ふち)に入(い)る
石臼を箸に刺す
石城・石槨(いしき)
石工(いしク)
石塊(いしころ)
石灯籠(いしドウロウ)
石子・石投(いしなご)
石橋を叩いて渡る
石部金吉鉄兜
(いしべきんきちかなかぶと)
石首魚・石持(いしもち)
石持草(いしもちソウ)
石綿(いしわた)
石茸(いわたけ)
石見(いわみ)
石斑魚(うぐい)
石陰子(かせ)
石高(コクだか)
石持(コクもち)
石伏魚(ごり)
石榴(ざくろ)
石神(シャクジ)
石南花・石楠花(シャクナゲ)
石花(せ)
石英(セキエイ)
石絨(セキジュウ)
石筍(セキジュン)
石菖(セキショウ)
石鏃(セキゾク)
石炭(セキタン)
石竹(セキチク)
石庭(セキテイ)
石磴(セキトウ)
石破天驚(セキハテンキョウ)
石盤・石板(セキバン)
石碑(セキヒ)
石斧(セキフ)
石油(セキユ)
石漆(せしめうるし)
石火(セッカ)
石灰(セッカイ)
石鹼(セッケン)
石膏(セッコウ)
石斛(セッコク)
石蕗(つわぶき)
石花菜(てんぐさ)
石竜子(とかげ)
石松(ひかげのかずら)
石蒜(ひがんばな)
ーーーーー
・・・???・・・
↓↑
長距離ランナー(走者)の靴(沓・舄)・・・
軍靴(グンカ)の伝令の情報・・・
草鞋(わらじ)の飛脚の手紙・・・
草履(ぞうり)
下駄(げた)
雪駄(雪踏・せった)
襪(シタウズ)は足指の股のあいていないもの
革足袋(かわたび)
小人革(こびとがわ)は中国(唐)渡来の革足袋
東北で産し薄く滑らかな上質の鹿革
小人は面(おもて)を革(あらた)む
「君子豹変、小人革面。 易経」
革命=命を鞣(なめす)す
皮革(ヒカク)=鞣した動物の皮
木綿足袋=長崎足袋
足袋(たび)は和装の際に足に直接履く
叉割れ靴下の一種
地下足袋(じかたび)は
「弋職=鳶職(とびしょく)・曳き屋、遣り方)」
が足に直接履くモノ
↓↑
遠走・遠足
安政遠足(あんせいとおあし)
1855年(安政二年)
安中藩主(群馬県安中市)
板倉勝明が
藩士96人に
安中城門から
「碓氷峠(うすいとうげ・・・小碓命
群馬県安中市松井田町坂本
と
長野県北佐久郡軽井沢町との境
信濃川水系
と
利根川水系
とを分ける
中央分水嶺)」
の
熊野権現神社まで
走らせた徒歩競走
1955年(昭和30年)
「碓氷峠(うすいとうげ)」・・小碓命?
タイヒョウ・・・・・他意豹?
の茶屋で発見された
『安中御城内御諸士御遠足着帳』
に記録
↓↑
「マラトンの戦い
(希語 Μάχη του Μαραθώνα・Battle of Marathōn)」
紀元前490年9月12日 or 11月2日
ギリシアのアッティカ半島東部
マラトン(Marathon)で
アテナイ・プラタイア連合軍(1万1000)
VS
アケメネス朝ペルシア(約2万5000)
↓↑
第2回ペルシア戦争
ペルシア帝国
ダレイオス1世の派遣遠征軍を
アテネ連合軍の
ミルチアデスの指揮下
重装歩兵1万 (ホプリタイ)
ボエオチア地方の
プラタイアイの援軍1000
が迎え撃ち
勝利した戦い・・・
↓↑
「エウアンゲリオン(良い知らせ)」
福音 (英語Gospel)
エウアンゲリオンEvangelion
ギリシャ語 εὐαγγέλιον, euangelion
「良い(euエウ-=good)
知らせ(-angelion アンゲリオン=message)」
good news
↓↑
「兵士
フィディピディス(Philippides)・・・ヘロドトス
or
エウクレス(Eukles)・・・プルタルコス
が勝利の知らせを
アテネに伝える伝令の役を命じられ
約三十六キロの道のりを駆け
アテネに帰り着き
「わが軍、勝てり」
と叫び、倒れて息絶えた」
↓↑
「韋駄天」も息切れ・・・
・・・聴癌(疒+品+山)の
呻(口+申)き・・・
カワヤ(化話也)で・・・
↓↑
韋 応物(イ オウブツ)
・・・これが
この時代の
和銅五年(712年)・古事記
養老四年(720年)・日本書紀
(712年~770年)
の名前???
↓↑ ↓↑
770年
干支 庚戌年
日本 神護景雲四年、宝亀元年
皇紀1430年
中国 唐 大暦五年
↓↑ ↓↑
770年
8月 弓削道鏡が失脚し、下野に配流
9月 和気清麻呂らを召還
10月23日
(神護景雲四年十月一日)瑞亀献上改元
(宝亀 元年十月一日)白壁王即位
第四十九代光仁天皇
誕生
菅原清公
ミカエル2世・・・観返る似与?
東ローマ帝国
アモリア王朝・・・安杜阿・蛙摸理倦?
初代皇帝
↓↑ ↓↑
死去
8月28日(神護景雲四年八月四日)
孝謙天皇・第46・48代天皇(718年~770年)
10月31日 (宝亀元年十月九日)
↓↑ ↓↑
文室浄三(ふんや の きよみ)
初名 智努王・知努王・珍努王・茅野王(ちぬおう)
天武天皇の孫
長親王の子
↓↑ ↓↑
阿倍仲麻呂(698年~770年)
李白、王維ら唐代の文人多数と交際
↓↑ ↓↑
岑参 (715年~770年)
(シンシン・・759年(乾元二年)虢州刺史
762年(宝応元年)太子中允・殿中侍御史
765年(永泰元年)嘉州の刺史)
↓↑ ↓↑
杜甫(712年~770年)・・・杜の鍛冶屋の補?
(トホ・712年(先天元年)~770年(大暦五年))
・・・徒歩?
杜審言の子の
杜閑が奉天の県令
その子が
杜甫
字 子美
号 少陵野老
老杜・大杜
別号 杜陵野老・杜陵布衣
杜少陵・杜工部(検校工部員外郎)
杜拾遺(左拾遺)
720年(開元九年)初めて「大字」を習う?
742年(天宝元年)姑母の「万年県君」
が洛陽で死亡
杜甫は多彩な要素を
対句表現によって構成する詩人
↓↑ ↓↑ ↓↑
韋 応物(イ オウブツ)
「豬 負 武通」
・・・伊吹山の「建」?
736年~791年?
中唐の詩人
京兆府
杜陵県 出身
玄祖父 韋沖(イチュウ)
高祖父 韋挺(イテイ)
曾祖父は
則天武后の時代の宰相
韋待価(イタイカ)
祖父 韋令儀(イレイギ)
父 韋鑾(イラン)・・・親鸞(シンラン)
鸞=䜌+鳥
戀=䜌+心=恋=亦+心
䜌 = 亦
戀愛・戀情
・・・ 鑾=糸+言+糸+金
ラン・すず
天子の馬車などにつける鈴
天子の馬車・天子
鑾駕(ランガ)・鳴鑾(メイラン)
786年
蘇州刺史・・・蘇(我)襲 刺史(志士・嗣子・猪)?
↓↑
聞雁(ブンガン)・・・雁(ガン・かり・鴈)
文借 カモ目カモ科ガン亜科の
文癌 水鳥一群の総称
文願 「枕」詞は「遠つ人」
↓↑
故園眇何處 故園(コヱン)
眇(ビョウ)として
何処(いずくぞ)
↓↑
歸思方悠哉 帰思(キシ)
方(まさ)に
悠なる哉(カナ)
謬悠之説(ビュウユウのセツ)=荒唐無稽
別府 結う 窃?
↓↑
淮南秋雨夜 淮南(ワイナン)・・・倭委名務?
秋雨の夜(ヨ)・・・・安芸得の世?
↓↑
高斎聞雁来 高斎(コウサイ)・・・北斉(550年~577年)
南北朝時代
高氏によって建国
雁(ガン・かり)の
来(きた)る
を聞く
ーー↓↑ーー
牛=𠂉+十
牝=牛+匕
牟=ム+牛
むさぼる(貪る)
眸=目+牟(ム牛)=瞳
𤘱=牛+𠂔
異体字「𤙂・㸬・𤘱・𤙍」
牡=牛+土(十一)
牴=牛+氐(氏一)
おひつじ・雄の羊・羝
およそ・おおよそ・ふれる・あたる・さわる
牢=宀+牛(𠂉十)・牢屋・牢獄
物=牛+勿(なかれ・フツ)・「物資・物質」
「物部・物語」
物体=形而下⇔物部
観念=形而上⇔物語
牧=牛+攵(𠂉乂)・牧場
牲=牛+生(𠂉土・𠂉十一)・犠牲
特=牛+寺(土寸)・特権
牽=亠+丷+冂+牛
牾=牛+吾(五口)


犀=尸+=丨=+牛
異体字「犀・𡱝・𡳚・𡥷」
「尾+牛」=「𡱕+牛」
犀(サイ・セイ) ・犀利(サイリ)
木犀・木樨(モクセイ)
遲=遅 (チ・おそい)・遅刻
稚=穉 (チ・わかい)・稚拙
犇=牛+𤘧
犂=牛+禾+勹+丿
犒=牛+高(ねぎらう・コウ)
犖=𤇾+牛=炏+冖+牛
ラク
まだらうし
すぐれる・卓犖
毛色がまだらの牛
あきらか・はっきりした
犠=牛+義
犢=牛+
トク
こうし・牛の子・犢車
舐犢(シトク)
犢鼻褌(ふんどし)
犧=牛+羲(羊禾丂戈)
女媧(人類創造の女神・姓は風、伏羲の妻妹)
犏=牛+扁
雄の赤牛と雌のヤクを交配した雑種牛
赤牛より力が強く乳量が多く
ヤクよりおとなしい)
牦牛(ヤク)との一代交配種
旄牛(ボウ牛・モウギュウ)
ーー↓↑ーー
仮名⇔相象類似の漢字
↓↑
阿ア・伊イ・宇ウ・江エ・於オ
了 ィ 宀 工 才
↓↑
加カ・機キ・久ク・介ケ・己コ
力 ‡ 勹 亇个 コ
↓↑
散サ・之シ・須ス・世セ・曽ソ
廾 氵 一人 乜 冫
丷
↓↑
多タ・千チ・川ツ・天テ・止ト
夕 干 爪 亍 ト
⺌ 梳
↓↑
奈ナ・仁ニ・奴ヌ・祢ネ・乃ノ
ナ 二 又 丶不 丿
㔫=𠂇+匕
𡯃=左=𠂇+工
右=𠂇+口
↓↑
八ハ・比ヒ・不フ・部ヘ・保ホ
八 七𠤎匕 𠃌 𠆢 𣎳・𣎵
𣏕・𤝂・㳈・𤘱
梳(とく)
↓↑
末マ・三ミ・牟ム・女メ・毛モ
マ 彡 ム 乂 乇=睫毛
矛 私 乄
罓・网=目を瞑る
↓↑
也ヤ・・由ユ・・譽ヨ
乜 ユ ヨ・⺕
夬 彐
↓↑
良ラ・利リ・流ル・礼レ・呂ロ
ラ 刂 儿 𠄌 口
乚 囗
↓↑
和ワ・井ヰ・・恵ヱ・乎ヲ
冖 韋 工 刁
倭 偉
輪 緯
〇 違
〇〇〇=三輪山に
居・為=爲
ーー↓↑ーー↓↑ーー
韋=ヰ=ゐ(wi)
=為(ゐ・なす・なせ)呉音、漢音
爲=爫+尸+¬+勹+灬
爪+尸+¬+勹+灬
「爪(手のツメ)」+「象」
で「象」を手なずける・・・?
僞=イ+爲=似せる・虚偽
葦=蘆=芦=あし=足・脚・肢・葭・疋・趺=尼子
↓↑ ↓↑
韋=ヰ=ゐ(wi)
ゐ(wi)=居・為・井・率・座
猪・位・藍・謂・坐
藺
「韋」字=「違」の本字
背きあうことを意
字形は
背いた足の象形「舛(ます)」
「以鼠為璞(イソイハク)」
五十五葉句?
委蘇磐俱?
取るにたらない物を
高価なものとして扱うこと
「璞(ハク)」は宝石の原石
鄭の国では原石を「璞(ハク)」
周の国では鼠の生肉を「朴(ハク)」
と言っていた
鄭の国の商人が
周の国の人に
「ハク」を買わないかと言われたが
「璞=宝石の原石」ではなく
「朴=鼠」だった・・・「ねずみ=移鼠=イエス」?
「鼠を以て璞と為す」・・・「鼠」を守って「王の」
『戦国策(秦)』
璞=王+菐・・・「菐は煩猥で、瀆菐は煩雑」
「丵=掘鑿に使う道具・刺青の針」
「男子皆黥面文身」の「針」
「丵=掘削などに用いる器・削岩機
大なるものが業で撲伐の器
両手に持つ形が菐
両手に持って叩くのが撲
相対して土壁を撲(う)ち堅めるのが
対(對)
材木を切り出して樸
玉を切り出して璞
丵=叢生する艸(くさ)」
「僕=下僕・使用人・君僕=you & me」
「撲耕=小作農・貝菐=土地の貸借関係」
「業=稼業・職業・産業」
王+业+䒑+夫
王+业+䒑+二+人
王+业+丷+一+夫
王+业+丷+一+二+人
王+业+䒑+一+一+人
王+业+丷+一+一+一+人
↓↑
石韋(ひとつば)=一葉・・・樋口一葉?
薬用植物一
獅子ひとつ葉
ウラボシ(裏星)科
多年生
シダ(羊歯・歯朶)植物
革質の葉が根茎から
一枚ずつ直立
生薬名 セキイ(石韋)
↓↑
画韋=えがわ=絵革
獅子(しし)
牡丹(ぼたん)
不動尊などの
文様の彫り型を当て
藍や赤で染めた革
『延喜内蔵寮
(えんぎくらりょう)式』に
「画革二十張」
武具・調度品の覆い
袋物、韋緒(かわお)などに利用
中世以降は
甲冑(かっちゅう)の
金具廻(かなぐまわり)の
包韋や弦走(つるばしり)
として用いた
染法は染型による
踏込染(ふんごみぞめ)が行われた
獅子牡丹(ししぼたん)文
風神雷神
竜文
倶利加羅(くりから)文
不動三尊像
などが用いられ
牡丹が形式化して
藻のようになった
藻獅子文(もじしもん)が
南北朝・室町時代に流行
江戸時代には
肥後(熊本県)の
八代韋(やつしろがわ)
甲冑の
「革」は硬質の主に牛馬の皮
「韋」は柔らかな鹿の押し韋
もみ韋の事
↓↑
韋編(イヘン)
韋=なめしがわので綴(と)じた本の革ひも
本・書物
↓↑
韋編三絶(イヘンサンゼツ)
イヘン
⇔「異変・異篇」
サン
「纂・簒・篹
撰・讃」
ゼツ
「説・洩・拙・窃」
孔子が晩年「易経」を読み
綴じた革ひもが何度も切れた
「史記孔子世家」の故事
繰り返し読むこと・熟読
韋編三たび絶つ
↓↑
韋駄天走(イダテンはしり
ヰダ・テンソウ)
イダ 伝奏・転送
「彙拿・異拿・意拿」
テン
「典・点・店・展・転・添」
ソウ
「叢・奏・相・双・総・送」
奏⇔秦⇔泰⇔奉
韋駄天(Skanda)
サカンダ・・・左官拿?
塞建陀天
私建陀天
建駄天
・・・
建(たける・武
倭男具那・童子・小碓命)
駄(馬+太)
天(二+人)
天部に属する神=韋陀・韋天将軍
八将の一神
小児の病魔を除く神
足の速い人
の例え
帝釈天が
仏の
荼毘(ダビ)処・・・焼身・焚焼
死体を焼いて弔う
火葬場
に至って
二牙を拾得したが
二捷疾羅刹=夜叉
=薬叉
(ヤクシャ)
訳者・譯者・役者
翻訳者 演技者
役人・厄人
約人
屋久人
のために
一牙を奪われた
ーーー↓↑ーー
屋久(やく)島
↓↑
『隋書』
大業三年(607年)
煬帝の代
「夷邪久国」
の記述が初見
「夷邪久」=屋久島
と
「夷邪久」=南島全般
(種子島・屋久島より南方)
を指す説・・・
↓↑
『日本書紀』
推古天皇二十四年(616年)
「掖久・夜勾・掖玖」
の人三十人が日本に永住した記事
舒明天皇元年(629年)
大和朝廷から掖玖に使が派遣された記録
天武天皇十一年(682年)
「多禰人・掖玖人・阿麻彌人(奄美人)
それぞれ禄を賜った」
という記載・・・
↓↑
『続日本紀』
文武三年(699年)
「多褹・掖玖・菴美・度感」
から朝廷に来貢
位階を授けた
記録
↓↑
種子島と多禰国との記述
大宝二年(702年)八月一日条
「薩摩と多褹が化を隔てて命に逆らう
是に於いて兵を発して征討し
戸を校して吏を置けり」
薩摩国
多禰国
が成立
以後、
令制国として一国に準ずる
「多禰国」に国司を派遣
南島(南西諸島・奄美・沖縄方面)
との交流
隼人の平定
遣唐使の派遣のため
「格」は中国として扱われていた・・・?
↓↑
天平勝宝五年(753年)十二月十二日
鑑真
大伴古麻呂
吉備真備
らを乗せた遣唐使船
第二船
第三船
が屋久島に帰国
第二船は
十二月十八日
大宰府に向け出港
二十日
秋目
二十六日
大宰府に到着
734年
753年
の二度
遣唐使が
多禰国
に帰国
↓↑
天長元年(824年)十月一日
「多禰島国司を廃止
能満郡・熊毛郡・馭謨郡・益救郡
の四郡を
熊毛郡・馭謨郡
の二郡に再編」し
「大隅国」に編入
↓↑
1203年
鎌倉幕府から
種子島氏に
種子島、南西諸島が与えられ
屋久島も支配下に置かれた
↓↑
1542年
大隅の
禰寝氏が
種子島氏の悪政を正すとの名目で
屋久島に襲来、島を占拠
宮之浦に
城ケ平城を築城
↓↑
1544年
種子島氏は
屋久島の奪還で城を攻める
禰寝氏は敗退
再び島は種子島氏の支配下
火縄銃が初めて使用された・・・
↓↑
1595年
種子島久時のとき
太閤検地に伴う所替えで
薩摩国
知覧に移され
屋久島は
島津家の直轄地となる
京都方広寺の
大仏殿建立用材調達で
島津家は
屋久杉を切り出した
↓↑
泊如竹
島津光久に招かれ薩摩藩に使えた僧侶
屋久島の
「安房」
の生まれ
↓↑
1708年
ジョヴァンニ・バッティスタ
シドッティ
Giovanni Battista Sidotti(Sidoti)
屋久島に上陸
↓↑
1891年(明治二十四年)
地租改正
島の山林が国有地に編入
国有林監視所が設置
↓↑
1921年(大正十年)
屋久島の国有林を
島民一般のためにのみ使用する
「屋久島国有林経営の大綱」を定めた
↓↑
1922年(大正十一年)
インフラ整備開始
ー↓↑ーー
韋弦之佩(イゲンのハイ)
異言 の葉意?
中国
戦国時代
「西門豹」は短気な性格を直そうと
「ゆったりとしたなめし皮」を身に着け
春秋時代
「董安干」は厳格な性格に改めるために
「かたい弓のつる」を身につけた
韓非子「観行篇」
↓↑
藜杖韋帯(レイジョウイタイ)
例 条 異体
飾り気が無く、慎ましいこと
「藜杖」は「あかざの杖」
「韋帯」は「なめし皮の帯」
『陳書(宣帝紀)』・・・「宣綴記」
本居宣長の綴記?
↓↑
布衣韋帯(フイイタイ)
不意異体
不異衣袋
不委異碓
官職についていない、普通の人
身分の低い人
『漢書』「賈山伝」
↓↑
佩韋佩弦(ハイイハイゲン)
↓↑
「韋」の「ことわざ」
韋編三度絶つ(いへんみたびたつ)
韋駄天走り(いだてんばしり)
↓↑
「韋」を含む人名
秋月韋軒(あきづき いけん)
韋天祖昶(いてん そちょう)
韋那磐鍬(いなの いわすき)
韋那部真根(いなべの まね)
韋駄天(イダテン)
↓↑
同部首「韋」の漢字
韓・・・韓国
韜・・・六韜三略
韋・・・ヰ・ゐ
ーー↓↑ーー↓↑ーー
姊=女+𠂔
通仮字「秭」
異体字「𡛷・姉」
𠂔=市=丶+帀
巿=十+冂・・・巿≠市(亠+巾)
一+巾
=前掛け・膝掛け・割烹着
=袚=衣+犮
芾(ハイ・フツ・ヒ・フチ)
草木が盛んに生い茂るさま
祭礼に用いる膝掛け
蔽芾(ヘイヒ)=小さいさま
杮(こけら)落し=欠片落とし
新築開館
開演
初演
「こけ=蘚・苔・鱗・虚仮」等
杮=十+八+巿(十+冂)=木+𠂔
芾=艹+巿
通仮字「紼」
異体字「市・𦬝」
𠂔=シ=丂+丨+丿=𠂔
止める
上に伸びようとする草木に
「ノ」を加えて
「伸びを止める」の意
同「𠥽」
ーーーーー
・・・???・・・
ペトロ(ヘブライ語 Šimʿon bar-Yonā
古典ギリシア語 Petros
古典ラテン語 Petrus)
↓↑
パウロ(ギリシア語 Παῦλος)
ヘブライ語 サウロ(Šāʼul)
パウロス(ギリシャ語パヴロス)
↓↑
「パウロ」=「小さい」
ラテン語
「パウルス」が転訛したギリシア語
「パウロス」の「ス」が落ちた形?
↓↑
「サウロ」・・・査雨露(烏鷺・迂路・洞・虚)?
が
「パウロ」・・・葉雨露(烏鷺・迂路・洞・虚・空)?
と名乗る
使徒言行録(使徒行伝・13章)
第一回伝道旅行
アンティオキア・・・案綴於記蛙?・・・蛙=かえる
教会から
宣教師として派遣
バルナバ・・・・・・場留名葉?
サウロ
キプロス島・・・・・記附呂諏当(問う)?
地方総督
セルギウス・パウルス・・・施留義得諏(碓・臼・宇受)?
パウルスが信仰に入った時、
サウロに・・・・・・・・・・佐宇盧?
「パウロ(パウルス)」
・・・・・葉鵜呂・葉得留諏?
という自分の名前を薦めた・・・?
↓↑
ラテン語の名前
「サウロ(サウルス)」
「サウロ」
古代
イスラエル王国最初の王
サウルに由来
ヘブライ語
「シャーウール」
ベニヤミン族
↓↑
「サウロ」は
「サウル」のギリシア語形
「サウロス」から
「ス」を省いた語
「サウル」=「主が求めた・求められた」
という意
↓↑
「パウロ」=「小さい」
小さい
ちいさい
ちさい
ちっさい
小
しょう
ちっちゃい
ちっぽけ
ちんまり
↓↑
英語
little
リトル
リトゥゥ
small
スモール
スモーウ
スモーゥ
tiny
タイニ
↓↑
ラテン語
minor
ミノル
parvum
パルウム・・小さいチャン=少彦名命
parvus
パルウゥス・小さいチャン=少彦名命
少名毘古那神
(すくなびこなのかみ)
須久奈比古命
別名
少彦名命
宿奈毘古那命
須久那美迦微
須久奈比古
少日子根命
小比古尼命
小彦命
小日子命
小名牟遅神
久斯神
少名彦命
↓↑ ↓↑
国造りの神
農業神
薬神
禁厭(呪術)の神
温泉の神
穀物
知識
酒造(醗・醸・醸造)
石の神
↓↑ ↓↑
親
神産巣日神
高皇産霊尊
天湯河桁命
↓↑ ↓↑
配偶者
伊豆目比売命
↓↑ ↓↑
子
菅根彦命
↓↑ ↓↑
神社
大洗磯前神社等
氏族
梶井氏(金丸村主)
鳥取連
伊豆国造
葛城国造
宇佐国造
忌部氏
服部氏
玉祖氏
↓↑ ↓↑
アイスランド語
litill=リーティトル
smar=スマウル
↓↑
イタリア語
piccolo
ピッコロ
piccola
ピッコラ
↓↑
カタロニア語(カタルーニャ語)
petit
パティト
petita
パティタ
↓↑
古代ギリシャ語
μικρον
ミクロン
mikros
ミークロス
↓↑
代ギリシャ語
μικρός
mikros
ミクロス
↓↑
ロシア語
малый
マールイ・・・丸井・円井
маленький
malen'kij
マーリニキー
マーリニキイ
マーリニキィ
マーリンキィー
↓↑
ウクライナ語
малий
malyj
マルィー
↓↑
ポーランド語
mały
マウィ
↓↑
チェコ語
maly
マリー
↓↑
マケドニア語
мал
mal
マル
↓↑
ブルガリア語
малък
malăk
マラク
↓↑
クロアチア語
mali
マーリ
sitan
シタン
↓↑
リトアニア語
mažas
マージャス
↓↑
ペルシア語
kuchek
クーチェキ
↓↑
ウルドゥー語
choṭā
チョーター
↓↑
ヒンディー語
cʰoṭā
チョーター
↓↑
ベンガル語
chhoto
チョト・・・一寸
↓↑
ネパール語
sāno
サーノ
↓↑
現代ヘブライ語
katan
カタン
↓↑
中国語
小
xiǎo
シァォ
シィアオ
シャオ
シアオ
↓↑
広東語
細
サイ
ーーーーー
石
英語
カブル=cobble
ストーン=stone
カブルストーン=cobblestone
ロック=rock
ボウルダ=boulder
↓↑
ドイツ語
シュタイン=Stein
フェルス=Fels
フェルゼン=Felsen
↓↑
フランス語
ピエール=pierre
ロック=roc
ロシェ=rocher
ロッシュ=roche
↓↑
イタリア語
ピエトラ=ピエートラ=pietra
ロッチア=ロッチャ=roccia
↓↑
「石」=「岩・磐」=カブル=cobble
「岩石」=rock・stone・ボウルダ=boulder
石蓴(あおさ)
石決明(あわび)
石蚕(いさごむし)
石が流れて木(こ)の葉が沈む
石に裃(かみしも)
石に灸(キュウ)
石に漱(くちすす)ぎ流れに枕(まくら)す・・・夏目漱石
石に立つ矢
石の上にも三年
石を抱(いだ)きて淵(ふち)に入(い)る
石臼を箸に刺す
石城・石槨(いしき)
石工(いしク)
石塊(いしころ)
石灯籠(いしドウロウ)
石子・石投(いしなご)
石橋を叩いて渡る
石部金吉鉄兜
(いしべきんきちかなかぶと)
石首魚・石持(いしもち)
石持草(いしもちソウ)
石綿(いしわた)
石茸(いわたけ)
石見(いわみ)
石斑魚(うぐい)
石陰子(かせ)
石高(コクだか)
石持(コクもち)
石伏魚(ごり)
石榴(ざくろ)
石神(シャクジ)
石南花・石楠花(シャクナゲ)
石花(せ)
石英(セキエイ)
石絨(セキジュウ)
石筍(セキジュン)
石菖(セキショウ)
石鏃(セキゾク)
石炭(セキタン)
石竹(セキチク)
石庭(セキテイ)
石磴(セキトウ)
石破天驚(セキハテンキョウ)
石盤・石板(セキバン)
石碑(セキヒ)
石斧(セキフ)
石油(セキユ)
石漆(せしめうるし)
石火(セッカ)
石灰(セッカイ)
石鹼(セッケン)
石膏(セッコウ)
石斛(セッコク)
石蕗(つわぶき)
石花菜(てんぐさ)
石竜子(とかげ)
石松(ひかげのかずら)
石蒜(ひがんばな)
ーーーーー
・・・???・・・