・・・庭には「毬(まり・鞠)状」になった「紫陽花」が咲いた・・・去年よりは見応えがあるが・・・あのネのネッ・・・アアアアアッ、「アジ・サ・イ」です・・・「紫陽花(あじさい・あぢさゐ)=ハイドランジア=アナベル」は元々が「日本が原産地のハナ」らしく・・・「ガク-アジサイ(額-紫陽花)」・・・どうして「額(ひたい)=客(宀各)+頁」+「紫陽花」なんだか?・・・「客(キャク・客人)は頁(ページ・一ツ目のヒト・大貝=おおがい→鷗外?)」 or 「ウは夂(おくれる・後から行く・降りる・チ・シュウ・夅=夂+ヰ=降)」or 「ウは夊(スイ・すいにょう・ゆき・ゆっくり・忍び足でゆく・引きずりながらゆく)」・・・
「額田の王(おほきみ=於補記視)」・・・
「天武天皇の愛人(采女・巫女・十市皇女の母)」、
「天智天皇の妾」・・・
「宣化天皇-火焔皇子-阿方王-額田鏡王-額田女王」?・・・
「藤原鎌足の室となった鏡王女の妹」?・・・
「鏡王の娘(額田王)」?・・・
「額田(女)王の娘、
十市皇女は弘文天皇(大友皇子・天智天皇の息子)の妃」・・・
↓↑
「額(ひたい・ぬか・ガク)・金銭上の数値(金額・定額)・壁、門などに掲げる書き物、看板、額字・物の量」・・・
「牌字・額字 寺院の山号,寺号, 室号,軒号など諸堂に掲げる額字を大書したもの」・・・
「扁額(ヘンガク)・建物の内外や門、鳥居などの高い位置に掲出される額(ガク)、看板 であり、書かれている文字はその建物や寺社名、あるいは名言」・・・
↓↑
茜指す紫野行き
標野行き
野守は見ずや
君が袖振る
(巻1・20・額田王)
紫の匂へる妹を憎くあらば
人妻ゆゑに我恋ひめやも
(巻1・21・大海人皇子)
君待つとわが恋ひをれば
わが屋戸のすだれ動かし秋の風吹く
(万葉集 巻4・488・額田王)
熟田津(にきたつ)に船乗りせむと月待てば
潮もかなひぬ今は漕(こ)ぎ出でな
(万葉集 巻1・8・額田王)
↓↑
ここで「紫陽花のガク」は本来は「萼(ガク・萼・calyx)=花冠(花弁、またはその集まり)の外側の部分・萼の個々の部分を萼片(ガクヘン・ sepal)・花弁(花びら)の付け根(最外側)」のコトだろう・・・
紫陽花は「中心に集まっている小さな蕾(つぼみ・蔀・莟)のようなものが花びらで、その外側にはガク(葉っぱが変化した花を守る部分)が大きな花びら(四枚)のようについている・花序の周辺には4~5枚の花びら(萼片)からなる装飾花」・・・
「ガク-アジサイ(額-紫陽花)は、
ユキノシタ(虎耳草=コジソウ・雪の下・雪の舌)科
アジサイ属に分類される落葉性の低木
アジサイの原種の1つで
日本の本州以南の海岸沿いに自生し、
樹高は1~2mほどに生長
実は蒴果(サクカ=熟すると下部が裂け、
種子が散布される果実・裂開果)」
「蒴果(サクカ)=雌蕊の中が放射状に複数の仕切りで
分けられ、果実が成熟した時は
それぞれの部屋ごとに
縦に割れ目を生じ
芯皮の数だけの割れ目ができる
スミレなど
孔開蒴果=成熟すると、果実の決まった場所に穴が開く
蓋果=果実の上の部分が蓋のように外れる
オオバコなど」・・・
花言葉は
「ホン-アジサイ」は「移り気・浮気・高慢」で、
「ガク-アジサイ」は「謙虚」?・・・
「あじさい=阿字作意」?・・・
『万葉集』では
「味狭藍(あぢさゐ)」、
「安治佐為(あぢさゐ)」、
平安時代の辞典
『和名類聚抄』では
「阿豆佐為(あぢさゐ)」
の字をあてる・・・
花の色がよく変わることから「七変化」「八仙花」とも・・・
「花言葉」は
「辛抱強い愛情・一家団欒・家族の結びつき」
語源は
「藍色が集まったもの」を意味する
「あづさい(集真藍)」がナマったものとする説・・・もあるらしい・・・
「毒性・・・青酸配糖体の量や種類には品種による差があり
食べて
吐き気・めまい・嘔吐・顔面紅潮
といった症状が現れ、
2~3日で症状が治まる」
「薬効・・・アジサイの品種から、
フェブリフジンが単離
嘔吐の副作用を克服する誘導体として
ハロフジノンが
マラリア治療薬として認可
自己免疫疾患など他の治療薬としても効く」



↓↑
漢字表記の「紫陽花」は、
唐の詩人
白居易が
「ライラック(Red Lilac)」・・・和名が
ムラサキハシドイ(紫丁香花)
ハナハシドイ(花丁香花)
に付けた名で
平安時代の
源順(みなもと したがおう)が
この「あじさい」に
「紫陽花」の漢字をあてところから、
誤まったまま広まった・・・
草冠(艸・艹)の下に
「便」を置いた字があるらしく・・・検索で発見した字は
↓↑ 「箯=竹+便=担架」
↓↑ 罪人運搬用の「駕籠・駕篭」?
『新撰字鏡』にはみられ、
「安知佐井(あぢさゐ)」
「止毛久佐(あぢさゐ
↓↑ トモクサ)」・・・訳妄句作?
↓↑ ケとめ、比差示句、たすける?
の字があてられている
アジサイの葉が排便後の尻拭きに使われ
止毛久佐(トモクサ・シモクサ)とも読む・・・?
アヂサヰ(あぢさゐ)の別名として
「またぶりぐさ(言塵集)」があるらしい・・・?
↓↑
「シーボルト」・・・・・・・・・・・施福多
は
この品種を「H. otaksa」と命名・・・おたくさ
植物学者の
「ツッカリニ」・・・・・・・・・・・椄通化理似?
と共著で
『日本植物誌』を著した際に
アジサイ属 14 種を新種記載・・・
シーボルトはアジサイ属の新種に
自分の日本人妻
「おタキさん=愛妾の楠本滝(お滝さん)」
の名をとって
「Hydrangea otaksa」と命名したが、
「Hydrangea macrophylla」と同種であった
・・・後、二人の間の娘、「失本イネ」は改名を指示され、
「楠本伊篤(くすもと いとく)」と改名・・・
↓↑
言問はぬ木すら味狭藍
諸弟(もろと)らが
練の村戸(むらと)に
あざむかえけり
(大伴家持 巻4 773)
↓↑
紫陽花の
八重咲く如
やつ代にを・・・にを?
にをいませ・・・にをい?
わが背子
見つつ
思はむ(しのはむ)?
(橘諸兄 巻20 4448)
↓↑
「言問はぬ木すら
味狭藍(あぢさゐ)
諸弟(もろと)らが
練の村戸(むらと)に・・・練の村戸?
あざむかえけり
(大伴家持 巻4 773)」
訳
「ものを言わない木でさえ
あじさいの(色)のように
移り変わりやすい
諸弟たちの
巧みな言葉に
だまされてしまった」?
・・・「手管に長けた村戸に
心変りが早い諸弟らが
欺かれてしまった」?
↓↑
「安治佐為(あぢさゐ)の
八重咲くごとく
八つ代(にを)・・・に、を?
(にをい)ませ・・・匂い眞施
・・・にほひ=美しい色あい・色つや
我が背子
見つつ偲ばむ
(巻第二十 4448番 橘諸兄)」
↓↑
「紫陽花の
八重咲く如
やつ代
に・・・・匂い
を・・・・於意眞施
い・・・・老いませ・負いませ・追いませ?
ませ・・・増せ・益せ?
わが背子
見つつ思はむ(しのはむ)
(橘諸兄 巻20 4448)」
訳
「あじさいが
幾重にも重なって咲くように
いつまでも
健(すこやか)やかで?
いてほしい
この花(orわが背子?)
を見ながら
あなたを偲ぼう」?
↓↑
我が背子=親しい男性を呼ぶ語
女性が夫・恋人を呼ぶ語
母から子
姉から弟
男性から男性に用いることもある・・・
ーーーーー
痾(ア)=疒+阿=やまい・こじれた病気・ア
旧痾・宿痾・沈痾
沉痾=重い病気
宿痾=長い間患っている病気
「屙屎送尿(アシソウニョウ)」=「大小便」
「着衣喫飯(チャクエキッパン)」=「衣食飲」
「疲れ(困じ)来れば即ち臥す」
「愚人は我を笑わん、智は乃ち焉を知る」
↓↑
遖(ア)=辶+南=あっぱれ・賛美する辞(国字)
すばらしい・みごとである
↓↑
朙(ア)=囧+月=メイ・ミョウ・ミン
あかり・あかあるい・あかあるむ・あかり・あかるい
あかるむ・あからむ・あきらか・あける・あくる
あかす
↓↑
誒(ア)=感嘆詞(訝って人に呼びかける時の)おい・やい・やあ
「誒=嘆聲」=大聲狂笑的
↓↑
譆(ア)=嘻=言+喜=うめき・キ・イ・ああ
譩譆=イキ=足の太陽膀胱経45番目の経穴
「譩」=痛いときに発する声
胸がつかえて出るため息
譆(ア)=ああ~と、 嘆き、恐れ、嬉しさなどを発する声
↓↑
閼(ア)=とどめる・ふさぐ・塞ぐ (アツ)・終わる
匈奴の王妃 (エン)、閼氏
アチ・エン・アツ・ア
閼与(山西省-和順県)
↓↑
擭(ア)=手+隻=ああげる・ああがる・あげる・あがる
キョ・ワク
臘 虎 膃 肭 獣 猟 獲 取 締 法
(らっこ おっとせい りょうかくとりしまりほう
明治45年法律第21号)
↓↑
唉(ア)=ああ・ああおお・いやいやこたえる・溜め息
カイ・キ・アイ
「アイヤー」・・・「唉呀!我的媽呀!」
ーーーーー
・・・???・・・紫陽花(シヨウカ)・・・
紫陽花(シヨウカ・あぢさゐ)のハナ・・・
何を云いたいんだか、ワシッバナ・・・混乱、拡散・・・で、関係性は?共通項は?
・・・「音更(おとふけ・北海道の地名)」・・・庭の木にセミは鳴かず・・・カエルは雑草の中に・・・スズメも電線の上に・・・でも鳴かず・・・今朝のTVで「鳥海山・九十九島・小砂川・温水路・湧水・田圃・二百年前の地震・岩牡蛎(蠣)」を観ていたが、なんかココの風景に似ているなッて・・・「鳥海山(ちょうかいさん、ちょうかいざん)は、山形県と秋田県に跨がる標高2,236mの活 火山。山頂に雪が積もった姿が富士山にそっくりなため、出羽富士(でわふじ)とも呼ばれ親しまれている。秋田県では秋田富士(あきたふじ)、山形県では庄内富士(しょうないふじ)・古くからの名では鳥見山(とりみやま)」ですか・・・「由利郡小瀧(鳥海山修験の拠点の一)の旧記に敏達天皇七年(578年)一月十六日噴火・由利郡直根村旧記に推古天皇御代の噴火と元明天皇の和銅年間(708年~715年)に噴火・由利郡矢島(鳥海山修験の拠点の一つ)では元正天皇の養老元年(717年)六月八日噴火(鳥海山史)」・・・山の南側には夏、「心の字の形」に雪が残る「心字雪渓」・・・「山岳信仰の根底には、山を水分(みくまり)とする水への信仰」・・・「九十九島 (くじゅうくしま) 秋田県にかほ(仁賀保)市・1804年の地震で干上がった島々・象潟(きさかた)の水田の中の島々には松」・・・「大砂川村・大須郷村・小砂川村」の「砂川」・・・
「安倍宗任(あべ の むねとう)」は、陸奥国の「俘囚の長」とされる豪族、東北安倍氏の安倍頼時の子。「鳥海柵の主」で、「鳥海三郎」とも呼ばれ、嫡妻であった清原氏の子として嫡子格の地位にあった・・・「鳥海三郎(とりのうみさぶろう)は、源頼義・義家父子率いる朝廷軍を相手に前九年の乱(1051~1057)を戦った安倍宗任の別称」・・・
「鳥海(とりのうみ)三郎=陸奥守
源頼義と安倍氏とが戦った
前九年の役で
兄、安倍貞任とともに
源頼義と戦った」・・・
「安倍頼時の三男で
安倍宗任=鳥海三郎の異名で知られる。
兄に安倍晴明、安倍貞任、
弟に正任、重任、家任らがいる」・・・
「前九年の役
(1056年・天喜四年~1062年(康平五年)
では
兄、貞任と共に
源頼義、源義家
相手に奮戦
兄、貞任が戦死した後も
厨川柵(盛岡)に篭城を続けたが、
出羽の豪族
清原氏の援軍を得た官軍に敗れ
厨川柵陥落後
弟、正任、家任
らとともに投降
康平七年、京都に連行された
(宗任32歳)
康平七年(1064)三月
後冷泉帝は捕虜になった
安倍宗任の裁判に興味を抱き
叡覧
宗任は衛兵に付き添われ禁庭引き立てられきた
公卿(判事・判官)の一人が
ニ、三分咲きの
梅の小枝を持ち
宗任の前に進み
↓↑
「東国は寒冷地
このような花をみたことがあるか、どうか」
と訊いた
梅の木を指し・・・ウメのキの
↓↑ ・・・徳川光圀=常陸水戸藩の第二代藩主
「水戸黄門」
諡号は「義公」
字は「子龍」
↓↑ 号は「梅里」・・・梅(木毎)の
理(王里)?
神号は「高 譲 味 道 根之 命」
(たかゆずるうましみちねのみこと)
水戸藩初代藩主・徳川頼房の三男。徳川家康の孫
「楳(バイ)=うめ=梅(バイ)」のキ
↓↑
名前をきいた?・・・ウメのなまえ・・・?
・・・日本原産の「あじさい=紫陽花」ではなく「ウメ」・・・
↓↑
万葉集では「梅・烏梅・宇米」などと表記
訓みでは「ウメ・むめ・ムメ」と伝本により異なる
萩に次いで二番目に多い「百十九(119)首」・・・
梅の歌
紀貫之の梅の香りを詠んだ歌
「人はいさ心も知らず
ふるさとは花ぞ昔の香ににほひける」
↓↑
菅原道真の梅との別れを惜しんだ歌
↓↑
東風(こち)吹かば にほひをこせよ
梅花(うめのはな) 主なしとて 春を忘るな
「春を忘るな」・・・「を・・・な」?
(寛弘2~3年・(1005~1006年)頃に
編纂された『拾遺和歌集』巻第十六 雑春
↓↑
東風ふかば にほひをこせよ
梅の花 あるじなしとて 春なわすれそ
「春なわすれそ」の初出・・・・「な・・・そ」?
治承四年(1180年)頃に
編纂と考えられる『宝物集』巻第二
↓↑
梅花心易=バイカシンエキ=場意掛新駅・葉意掛芯易?
「梅を観ていた時、二羽の雀が
枝を争う姿を見て、翌日の夕方に
隣の娘が
梅の枝を折ろうとして木から落ち
ケガをすることを推測した」???
↓↑
盛岡の新暦の三月(彌生・弥生)はまだ冬で
路面に雪が残って歩きにくいことから
旧暦(四月=卯月)に
「ひな祭り」の行事
雛=ひな=鄙=比奈=陽菜・鶵・妃奈・比名
↓↑ ヒナ・・・夷那
↓↑二月=きさらぎ=如月=木皿儀(姓)・・・木皿の儀?
きさらず・・・・木更津
さらぎ=皿木・千葉県長生郡長柄町
さらぎ=蛇穴
奈良県
御所市の
葛城川・・・葛木・・・鬘
葛=くず・かずら(山野に自生する草の一種
茎の繊維をとって布を織るのに用いる
根はくず(屑)粉
蔓(つる)茎
身にまといつく困難の例え
かたびら(帷子)
東岸の集落
サラキ=新来(いまき・今来)
新しく移り来た所
蛇穴と書いてサラギと読むのは
蛇がトグロを巻き
穴をつくる状態を
サラギと呼ぶた?
・・・蛇の脱皮だろう?
セック(フランス語のsec)=乾いた・乾燥した
ワインの辛口
ソシソン(サラミ)=乾燥ソーセージ
セック(sec)=second(セコンド)
=secant(セカント)に同じ
=三角比・三角関数の一
コサインの逆比・逆数
正割・正割関数
さらしこ(晒し粉)=消石灰に塩素を
吸収させて作った白色の粉末
パルプ
繊維などの漂白、
上・下水道の殺菌・消毒剤
bleach(ブリーチ)
クロルカルキ・カルキ
クロル石灰
水にさらして白くした米の粉
さらしこ?→讃良=鸕野讃良=持統天皇?
(うののさらら・うののささら)
名は鸕野讃良=菟野-沙羅羅
和風諡号は高天原広野姫
天智天皇の第二皇女
大津皇子の辞世の一句
「モモづたふ 磐余(いはれ)の池に
↓↑ 鳴く鴨を
↓↑ 今日のみ見てや 雲隠りなむ
桃の節句
五人囃子と「梅の花」ではなく、
「五人囃子の笛太鼓」・・・
「梅」ではなく「桃」・・・?
↓↑
道真を慕う庭木
桜=悲しみのあまり、葉を落とし、枯れてしまった
梅=道真の後を「松と梅」は空を飛んで追ったが
松は力尽き
摂津国八部郡板宿(兵庫県神戸市須磨区板宿町)
近くの「飛松岡」の丘に降り根を下ろし「飛松」と云われ
梅は、一夜のうちに主人の暮らす
大宰府まで飛んで降り立った・・・
「松竹梅=ショウチクバイ=背負う知句場意」?
↓↑
「飛鳥(あすか)」
「飛鳥(あすか)=時代区分の一・飛鳥に宮都が置かれていた
崇峻天皇五年(592年)~和銅三年(710年)
奈良県高市郡明日香村付近に相当する地に
宮・都が置かれていた
元々美術、建築史で「飛鳥時代」を使用
1900年前後
美術学者の関野貞と岡倉天心によって提案
関野は「大化の改新」まで
岡倉は「平城京遷都」までを飛鳥時代とし
日本史では通常、岡倉案を採用
推古朝では飛鳥文化
天武・持統朝では白鳳文化
国号が
「倭」~「日本」へと変えられた・・・
トリが飛ぶのは当たり前だが
飛ばない「トリ」は
「にわとり=鷄・鶏・雞」
と
「駝鳥(ダチョウ)」
「恐鳥(モア(Moa)」・・・絶滅
「エミュー」
「ヒクイドリ(火食い鳥・食火鶏)」
「レア」
「キーウィ」
「ペンギン(人鳥・企鵝=きが
企は爪先立つ鵞鳥)」
等である・・・
「阿毎王朝」の
「東夷の俀國の王朝(隋書)」の
「開皇二十年(600)
倭王有り
姓は阿毎
字は多利思北孤
号は阿輩雞(奚隹)弥
使を遣わして闕に詣る
王の妻は
号を雞(奚隹)弥
後宮に女六、七百人有り
太子の名
利歌弥多弗利
と為す」
「にわとり=鷄・鶏・雞」
磐井の乱(筑紫君)、
「葛子」=「阿毎王族」か?
↓↑ ↓↑
「にわとり=鷄・鶏・雞=阿蘇山西麓の肥後王朝」は
「奈良・明日香」に飛んだか?
ナゼ、
「斑鳩=いかるが=鵤」なのか?
↓↑
「飛梅」伝説・・・「訳備烏楳」?
道真に仕えて
大宰府にも同行した
味酒保行
が株分けの梅の苗木を植えた
道真を慕った伊勢国
度会郡(三重県度会郡)の
白太夫
が大宰府を訪ねる際
旧邸から密かに持ち出した梅の苗木を献じた
↓↑
人形浄瑠璃、菅原伝授手習鑑の主題・・・
↓↑
道真を慕った「梅が飛来」
道真が自ら
梅を植えた・・・
↓↑
若狭国大飯郡大島(福井県大飯郡おおい町大島半島の大島)の
宝楽寺
備中国羽島(岡山県倉敷市羽島)
周防国佐波郡内(山口県防府市松崎町)の
防府天満宮など・・・
↓↑
能の演目『老松』
梅の精を「紅梅殿」とよび
男神・女神
として擬人化されている・・・
ーー↓↑ーー
安倍の
宗任
は即座に
「わが国の梅の花とは見たれども
大みやびとは何というらん」
「我が国の 梅の花とは思えども
大雅とはなんというらん」
(我が国においては梅の花と言うが
こちらの人は何と言うのか
(梅(ウメ)の花(ハナ)にしか見えないが
大みやびとはナンの花だと云うんだか)
うめ=卯女・卯目・右馬・・・旨・績・・・上手い?
スベテの「ウ・メ」の同音異字・・・ぅめィ、ッ?
↓↑
「前九年の役」で
「源 頼義」に敗れた
「安倍貞任」の弟
「安倍宗任(むねとう)」が、戦に敗れて
都を引き回され時、
京の貴族が、侮蔑の意味で
梅の花を差し出し、
「これは何か」と尋ね
安倍宗任は
「わが国の梅の花とはみつれども
大宮人はいかがいふらむ」
(我が国においては梅の花と言うが
こちらでは何と言うのか)」
↓↑
という歌で返し・・・
無教養だと思い込んでいた
陸奥の俘囚(蝦夷)のウタに
愕(おどろ)き、感銘し
助命され・・・・・・・ウタの教養で許された?
四国の伊予国に流された・・・ナゼ、伊予の国なのか?
↓↑
現在の
今治市の・・・・・・・・・加計学園&安倍?
富田地区に三年間居住
↓↑
後、勢力をつけたために、
治暦三年(1067年)・・・治の暦の三の年?
に九州の
筑前国
宗像郡の
筑前大島に再配流
その後、宗像の大名である宗像氏によって、
日朝・日宋貿易の際に重要な役割を果たした
大島の景勝の地に自らの守り本尊として
奉持した
薬師瑠璃光如来を安置するために
安昌院を建てた
嘉承三年(1108年)二月四日
七十七歳で死亡・・・
↓↑
逃亡の恐れありとの理由で
大宰府に移されたが
その子孫は
肥前国
松浦に住みつき
後
船団を組織し、
朝鮮、中国等に
倭寇ともいわれた
松浦水軍・松浦党の祖・・・
「松浦党」の後裔は・・・「松浦武四郎」?
・・・北海道の各地の
アイヌ語地名に
漢字を当てた人物
配流されないで、
源義家
の従者として仕えた・・・とも・・・???
ーーーーー
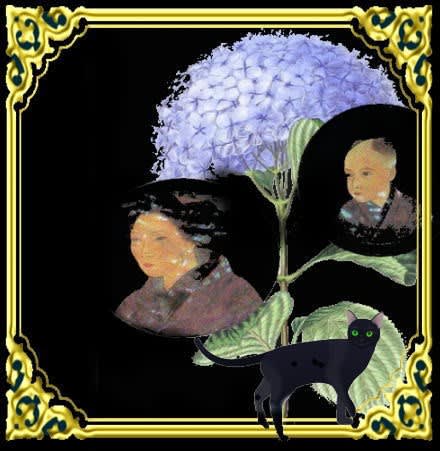
・・・
「集(あづ)真(さ)藍(あい)」=「紫陽花(あじさい)」
↓↑
シーボルト
『日本植物誌(P.F.B.フォン・シーボルト 著)』
シーボルトらにより
1835年~1870 年
に出版された
『日本植物誌』の
覚書きの部分の訳出した資料
32~34 ページに
「ウメ(梅)」の記述
梅の木の高さや花の色
植物としての特徴
そして
日本人が庭木や盆栽の手入れに熱心で
日本では
「梅が伝説や物語の中」で
神聖な木として
扱われていると指摘
梅の実の味については
「酸っぱくて苦い」
とし記録・・・
↓↑
シーボルト(置維波斯徳利・施福多)
日本人の女性
「滝(たき)」と結ばれ
文政十年(1827年)に
娘「いね」が生まれた
↓↑
イギリス公使
オールコックを通じて息子
アレクサンダーを
イギリス公使館の職員に就任させ
1862年5月
多数の収集品とともに長崎から帰国
↓↑
1863年
オランダ領
インド陸軍の
参謀部付
名誉少将に昇進
オランダ政府に
対日外交代表部への任命を要求するが拒否
日本で集めた
約2500点のコレクションを
アムステルダム・・・安特堤・安特垣・亜武的達
の産業振興会で展示し
コレクションの購入を
オランダ政府に持ちかけるが
高価を理由に拒否
オランダ政府には
日本追放における損失についても
補償を求め、拒否された
1864年
にはオランダの官職も辞し
故郷の
ヴュルツブルクに帰った
↓↑
シーボルト(置維波斯徳利・施福多)は
同年5月
パリに来ていた
遣欧使節正使
外国奉行の
池田長発・・・・池田長発(いけだ ながおき)
↓↑ 天保八年七月二十三日
(1837年8月23日)
~
明治十二年(1879年)九月十二日)
直参旗本七千石・池田長休の四男
筑後守・旗本池田長溥の養子
備中国
井原(岡山県)の領主
↓↑ 外国奉行を務め
文久三年(1863年)~元治元年(1864年)
遣欧使節団を率い
1863年12月
フランス軍の軍艦
ル・モンジュ号・・・
「留・文殊」?「パン屋」?
で日本を出帆
エジプト、カイロに寄港
ギザのピラピッド、
スフィンクスを背景に
記念撮影(1864年)し
フランスを訪問
帰国後、開国論を唱えて蟄居処遇
慶応三年(1867年)に
軍艦奉
官位は従五位下
↓↑ 筑後守
の対仏交渉に協力
同行の
三宅秀=(みやけ ひいず)
嘉永元年十一月十七日(1848年12月12日)
~
昭和十三年(1938年3月16日)
東京大学の最初の医学博士
幼名は復一(またいち)
から
父・三宅艮斉が貸した
「鉱物標本」
20~30箱の返却を求められたが
三宅の手元には
3箱しか送られてこなかった・・・
バイエルン国王の
ルートヴィヒ2世に
コレクションの売却を提案するも叶わず
ヴュルツブルクの高校で
コレクションを展示し
「日本博物館」を開催
1866年
ミュンヘンで開催
再度日本訪問を計画し
10月18日
ミュンヘンで風邪をこじらせ
敗血症を併発して死去
70歳没
墓は石造りの仏塔の形で
旧ミュンヘン
南墓地 (Alter Münchner Südfriedhof)
にある
↓↑
次男
ハインリヒ・フォン・シーボルト
(別名小シーボルト)
も日本に滞在し日本で
「岩本はな」と結婚し
1男1女をもうけた
また
オーストリア=ハンガリー帝国大使館の
通訳官外交官業務の傍ら
考古学調査を行い
『考古説略』を発表
「考古学」という言葉を日本で初めて使用
↓↑
鳴滝塾
鳴滝塾(なるたきじゅく)
文政七年(1824年)
シーボルト
が長崎郊外に設けた私塾で診療所も兼ねていた
↓↑
「鳴滝(なるたき)」=京都市右京区の地名
地名由来
小さな滝があり、ある時、その小滝が、
ゴーゴーと凄い轟音をたてていたという故事による
村人たちが不思議がって
寺の和尚に相談したところ
和尚も不審に感じ
全員を、高台の寺に集合させた
すると、その夜、
村は大洪水に襲われ、全壊
この出来事により、
小滝は「鳴滝」と呼ばれ、
村の方も「鳴滝の里」と呼ばれた
毎年、12月9日・10日の両日
鳴滝本町の
通称
大根焚寺として知られる
了徳寺の
「大根焚き(報恩講)」で賑わう
↓↑
鳴滝泉谷町の法蔵寺前には、
尾形乾山の陶窯跡がある
乾山は
1689年(元禄二年)
御室に閑居を構え
習静堂と号した
後
野々村仁清
に陶芸を学び
1699年(同十二年)
鳴滝村に開窯
この窯が都の
乾の方角にあるため
乾山と号した・・・
↓↑
シーボルトで有名な
「長崎の鳴滝」は、
第24代長崎奉行
牛込忠左衛門勝登
が、この地にあやかって名付けた
ーーーーー
鳴滝塾の塾生
代表として
高野長英・二宮敬作・伊東玄朴・小関三英・伊藤圭介
ら
↓↑
美馬順三
最初の塾頭
1795~1825
シーボルトの質問に答えて
『日本産科問答』
という、
ヨーロッパ語で日本人の発表した最初の医学論文
形式としてはシーボルトと美馬との一問一答
当時行われていた
賀川流の産科の方法を解説したもの
1826年にドイツの医学雑誌に転載
1830年にはフランスのアジア学雑誌に翻訳発表
シーボルトはウェイランドの辞書を順三に与えた
↓↑
美馬順三
阿波の岩脇に生まれ
曽祖父の代から
蜂須賀侯の家老
池田登に仕えた。
順三は長崎に来て通詞の家にとまって
オランダ語、天文学、医学を学び
シーボルトが来ると、その教育を受けた
石坂宗哲著
『鍼灸知要一言』をオランダ語に訳し
ヨーロッパに
日本の鍼(はり)と灸(きゅう)について紹介した論文
著書『日本植物志』のアサガオの項に
「この所属の植物は順三が私のために
あまたの新種植物と共に
肥後の金峰山から採ってきたものである」
と記した。
順三は
文政八年(1825)六月十一日
コレラに罹って長崎で急死
30歳
↓↑
岡研介(1799~1839)
周防
熊毛郡
平生(ひらお)村の人
代々農家で
父の代に
長崎の
吉雄耕牛について学び
はじめ京都
のちに平生
で医者を開業
眼科で名をあげた
研介は兄
泰安と共にシーボルトに学び、塾内部で重きをなした
兄の
岡泰安(1796~1858)
は
1827年3月2日(文政十年二月五日)付で
シーボルトから証明書をもらって
ドクトルとなって郷里に帰り
開業医として成功
弘化一年(1844)
岩国藩に呼ばれ
安政四年(1857)
藩侯の侍医(御手廻役)となり
あくる年
安政五年に死亡
岡研介は
兄が眼科医として故郷の
平生村
岩国藩で大いに成功したのに比して
社会人としては振るわず
精神病を発して
天保10年(1839)
40歳で死亡
シーボルト門下にあった頃
才能はその盛りで
岡研介訳『日本に於ける学芸、すべてのものの起源』
というオランダ語の論文が残され
これは
貝原益軒編『大和事始やまとことはじめ』
の抄訳で
同じくオランダ語で記された
伊藤圭介の『勾玉記まがたまき』
美馬順三訳『日本古代史』
(『日本書紀』神代巻・神武天皇紀意訳)
と共に
シーボルトの
大著『ニッポン』
の神話研究の部分の資料として
ヨーロッパに伝えられた
↓↑
高良斎(こうろうさい)
(1799~1846)
阿波徳島の人
藩の中老
山崎好直の庶子で
徳島の眼科医
高錦国
の後継ぎとしてもらわれた
文化十四年(1817)
18歳の時に長崎に出て
オランダ語
医学
を学ぶこと5年余
文政六年(1823)
シーボルトの到着後にその門下に入った
シーボルトの文書の中には
高良斎
の書いた
オランダ語の
論文『生理問答』が残っている
これは
美馬順三の
『日本産科問答』
と同じく、日本人の健康についての
シーボルトと著者との
一問一答の形をとっている
『日本疾病志』
というオランダ語論文も書いており
これには
シーボルトの加筆本と
それに基づいて
高良斎が書き直した本とが残っている
高良斎
文政十一年(1828)十月
シーボルトが禁制の地図を持っていたのを
咎められて訴えられた時
投獄された
23人中の主だった門人として
二宮敬作
と共にいた
良斎
は木を噛んで筆を作り
炭を墨にかえて
恩師のための弁明を紙に書いて出した
良斎と敬作はこのために
奉行所に呼び出されて訊問されたが
良斎はひるまず、その翌日には
先の23人はみな許された・・・
↓↑
文政十二年十二月五日
日本を去るにあたって
シーボルトは
遊女「其扇そのぎ(お滝)」
との間に生まれた女子
「オイネ」
の今後を
高良斎と二宮敬作に託した
高良斎の著書は50~60巻を超えたが
刊行されたものは
『窮理飲食術』
『薬能識』
『蘭薬語用弁』
『駆梅要方』
だけである
↓↑
『眼科便用』
と
『女科精選』
も、良斎は刊行しようとしたが
シーボルトの名を多くあげていることから
幕府は刊行を許さなかった
シーボルトの日本退去後
良斎は
徳島に帰り
しばらく大坂で開業してから
天保十一年(1840)
明石侯の眼病の治療に成功し、その医員となった
弘化三年(1846)
47歳で死亡
↓↑
戸塚静海
高良斎はシーボルト事件後
長崎町払いを命じられ退去
鳴滝塾校舎はその後
戸塚静海
が中心となって1年ほど持ちこたえた
↓↑
戸塚静海(1799~1876)
遠州掛川の人
祖父の代からの医者
文政七年(1824)
25歳の時に長崎に行き
和蘭通詞
吉雄権之助の塾に入り
次に
シーボルトについて学んだ
シーボルト事件に際しては
高良斎、二宮敬作
らと共に入牢
天保二年(1831)
長崎を去り、掛川にしばらく住んだ後
江戸に出て
茅場町で開業
太田侯
薩摩侯
に仕えた後
安政五年(1858)
徳川将軍家の侍医
同じシーボルト門出身の
伊東玄朴
竹内玄同
と並んだ
戸塚静海には
『海塩の製法について』
と題するオランダ語の訳文が残っている
↓↑
江戸参府
出島のオランダ商館長は
4年に一度江戸に行き
将軍に拝謁し
多くの品物を献上
シーボルトは
この商館長の旅行
「江戸参府」に同行し
日本各地の
地理・動植物・産業・風俗習慣などを調査
シーボルトは
文政九年一月九日(1826年2月15日)
出島を出発
各地で動植物を採集
人びとの暮らしぶりを観察
多くの医師や学者に面会し
日本に関するさまざまな情報を得
江戸に
37日間滞在したあと
同年六月三日(7月7日)
出島に帰り着いた
↓↑ ↓↑ ↓↑
シーボルト事件
5年の任期を終え
文政十一年(1828年)
に帰国することとなった
同年八月
彼が乗船することになっていた
コルネリウス・ハウトマン号
長崎を襲った暴風雨により
長崎港内の
稲佐(いなさ)の海岸に乗り上げ出港延期
江戸で
幕府・天文方の役人
「高橋景保(たかはし-かげやす)
が
「シーボルト」は長崎奉行所命令で
蝦夷・千島の地図を差し出し
家宅捜査を受けて持っていた禁制品を没収
シーボルトは出島に拘禁され、厳しい取り調べを受け
彼は、多くの協力者に罪がおよぶことを恐れ
その名前は一切あきらかにしなかった・・・
シーボルトは
文政十二年九月(1829年10月)
国外追放を申し渡された
後、多くの協力者が処罰
↓↑
シーボルトは、日本に残す
妻「滝」
と
娘「いね」
の身を心配して、彼女たちに財産を残し
2人の世話を門弟の
二宮敬作(にのみやけいさく)
高良斎(こうりょうさい)
らに頼んだ
文政十二年十二月五日(1829年12月30日)
船は出島を離れた
シーボルトは
やり残した日本の調査・研究を
助手
ビュルガー
や
門弟たちに頼んでいった
オランダに帰り着いたシーボルトは
滝といねの安否を気遣って手紙を送り
滝も手紙や母子の姿を描いた
螺鈿合子(らでんごうす)の
嗅ぎ煙草入れを送った
↓↑
帰り着いたシーボルト
オランダ政府と学会から大歓迎
帰国後
シーボルトが生涯を通じて打ち込んだ仕事は
日本を科学的に研究し
その成果を世界に紹介することだった・・・
シーボルトは、日本から持ち帰った
数多くの資料を整理し
日本に関する論文をつぎつぎに発表
博物館を開設して集めた資料を公開
オランダから爵位が与えられ
ヨーロッパ各国から数々の勲章が授与された
1845年
ドイツの貴族令嬢
ヘレーネ・フォン・ガーゲルン
と結婚し
3男
2女
が生まれた
↓↑
1840年
アヘン戦争
日本近海に外国船が来航
シーボルトは
鎖国を続けると世界情勢から日本が外交上不利益と考え
日本が開国することで危険をさけることができると考え
オランダ国王
ウイルレム2世にそのことを進言
ウイルレム2世は
日本が開国すれば
オランダが
日本との貿易を独占することができなくなるが
日本の将来を考えてこれに同意
シーボルトが起草した
ウイルレム2世の親書は
特使コープスにより
1844年
長崎奉行所を通じて幕府に渡された
シーボルトは
ロシアの宰相
アメリカのペリー提督
にも日本との平和的な開国を進言
↓↑
シーボルトは
オランダ商館長
ドンケル・クルチウス
の願い出により国外追放を解かれた
安政六年(1859年)
オランダの貿易会社の顧問の肩書きで
長男
アレクサンダー
を連れて再び日本に旅立った
シーボルト
63歳
長崎にたどり着き
「滝」や「いね」、かつての門弟たちと再会
「滝」は、シーボルトが日本を離れたあと
再婚し子供もできたが、
その子供はすでに亡くなっていた
別れたときには
2歳だった「いね」も
門弟たちに育てられ
医学の手ほどきを受けて
長崎で産科医として修業していた
シーボルトは
貿易会社の仕事をする一方
鳴滝の住居を買い戻して住み
ここで
日本研究や日本人の治療を行ない忙しい日々をすごした
文久元年(1861年)
幕府に呼ばれて江戸へ行くことになり
江戸で自然科学の講義をしたり、
幕府に外交上の進言をしたりしたが
4ヵ月で職を解かれ
シーボルトは
在日イギリス公使館の
通訳となった長男を残し
文久二年(1862年)
日本を離れた
2年7ヵ月の
日本滞在であった
↓↑
1863年
オランダの公職を辞め
翌年
家族とともに
ヴュルツブルクへ帰った
後、
日仏貿易会社の設立を考え
フランス皇帝ナポレオン3世に会ったが
設立はできなかった
彼が2度目の来日で
収集した日本の資料を
バイエルン政府が購入して
民族学博物館を設立する計画が持ち上がり
ミュンヘンで資料の整理にあたっていたが
病気にかかり
「私は美しき平和な国に行く」
と言い残し
1866年10月18日
に死亡
↓↑
『日本』
『日本植物誌』
『日本動物誌』
これらは、シーボルトが日本で収集した資料をもとに
学者の協力を得て出版した
↓↑
シーボルトと滝との子ども
「いね」は
父の門弟
石井宗謙
二宮敬作
オランダ人医師
ポンペ・ファン・メールデルフォールト
ボードウイン
に学び
日本最初の西洋医学の女性産科医となった
明治六年(1873年)
明治天皇の若宮が誕生するときに
宮内省御用掛りとなり
出産に立ち会った
シーボルト
と
ヘレーネ
との子どもには、3男2女
長男アレクサンダーは
12歳のときに父に連れられて来日
15歳で在日イギリス公使館の通訳となった
その後
ローマやベルリンにある日本の公使館などに勤務し
約40年間、日本の役人として働いた
次男ハインリッヒは
兄アレクサンダーに連れられて
1869年に来日
彼は
在日オーストリア=ハンガリー公使館の
代理公使などを勤めた
↓↑ ↓↑ ↓↑
三瀬 諸淵(みせ もろぶち)
天保十年七月一日(1839年8月9日)
~
明治十年(1877年)十月十九日)
初名は周三
幼名は弁次郎
字は修夫
伊予国
大洲
出身
幼く両親を失い親戚の下で育てられ
大洲市
八幡神社の神主
常磐井家が開いた私塾
「古学堂」にて国学を学ぶ
1855年
遠縁の医師
二宮敬作の弟子となり
二宮の元にいた
長州藩の
村田蔵六(大村益次郎)から
オランダ語を学び、蘭学に関心を抱く
後、
二宮のとともに長崎に渡り蘭学、医学を修めた
安政五年(1858年)
大洲に一時帰郷し
長崎から持ち帰った
発電機
と
電信機
を持って
古学堂に旧師
常磐井厳矛を訪ね
大洲藩の許可を受け
古学堂~肱川
の河川敷まで電線を引き
「電信」の実験
古学堂2階~肱川向かいの矢六谷の水亭まで
約980メートルの間に銅線を架設し
打電したところ成功・・・
安政6年(1859年)
二宮の師であったシーボルトが再来日すると
シーボルトに預けられた
シーボルトの長男
アレクサンダー・フォン・シーボルト
の家庭教師役を務めながら
自身は医学を学んだ
文久二年(1862年)
諸淵がシーボルトのために
国学の知識を生かし
日本の歴史書の翻訳を
おこなっていた事が発覚
投獄・・・
(妻・高子の手記によると通訳の件で
公の役人を差しおいたことが一因・・・
2年後の1864年に出獄している)
釈放後
大洲に帰国
大洲藩に召される
後に江戸幕府によって
大坂に召されるが
明治維新を迎えると
そのまま新政府に仕えて
医学校の創設にあたる
慶応二年(1866年)
シーボルトの孫娘にあたる
「楠本高子」と結婚
明治元年(1868年)
明治新政府の命により
大阪大学医学部の前身にあたる
大阪医学校兼病院設立に携わり
教官(大学小助教)を務めた
明治三年(1870年)
諸淵と名乗る
明治四年(1871年)
文部省が設置
東京医学校の創設時
文部中助教
翌年
文部大助教を務めた
明治六年(1873年)
官を退いて大阪で病院を開くが
明治十年(1877年)
胃腸カタルで
死亡
39歳
ーーーーー
シーボルト事件
日本滞在の任期が終わって帰国しようとしていた
シーボルトが乗船を予定していた
コルネリウス=ハウトマン号
は
文政十一年(1828)八月九日夜
暴風雨に襲われ
渚に打ち上げられ
深く泥にはまった
シーボルトは
日本滞在を延ばしているうち
同年十二月二十三日
(1828年1月28日)
日本国外への出発を禁じられ
出島に禁足
文政十一年三月二十八日
幕府天文方を勤める
高橋景保のところに小包が一つ届いた
差出人は長崎の
プロシアの医師某とあり
その中に
御普請役
間宮林蔵
におくる分も入ってい
高橋から間宮に届けた
間宮は
外国人に関わることだからと言って
勘定奉行
村垣淡路守定行に立ち会ってもらって
内容を調べたところ
更紗一反(シーボルトの証言では、てぬぐい1枚)
と
手紙が一通入っていた
高橋のほうは荷物をもらっていながら
幕府に届けなかった。
このことから見張られるようになり
文政十一年十月十日夜
町奉行所に引かれ
翌
文政十二年二月十六日
牢内で病死し
死体は塩漬けにされて
裁判の判決が待たされ
判決はその翌年に下り
存命なら死罪
判決の理由は
高橋景保が
シーボルトに
国禁の日本地図を渡したこと・・・
↓↑
高橋景保の
長男・小太郎
と
次男・作次郎
は遠島。
部下の
岡田東輔
は獄中で自殺
↓↑
長崎
シーボルトにつながりのあるもの
23人が牢屋に留置
高橋と親しくなる機縁を与え
江戸参府に同行した
二宮敬作は
江戸おかまい
長崎ばらい。
同じく同行した
高良斎は居所ばらい
同じく同行した
画家・川原登与助は
しかりおく
ということになった
シーボルトに便宜をはからった
大通詞
馬場為八郎
は永牢を申しつけられ
佐竹壱岐守に預けられた
小通詞末席
稲部市五郎
は永牢を申しつけられ
上州
甘楽郡
七日市城主
前田大和守利和に預けられ
小通詞助
吉雄忠次郎
は永牢を申しつけられ
羽州
米沢
新田城主
上杉佐渡守勝義に預けられた
↓↑
高野長英は事件の起ったのを聞いて
熊本に逃れ、この時は逮捕を免れた
シーボルト事件の糸口を作った
間宮林蔵は
蘭学者から警戒心をもって見られ
死にいたるまでの時期を
幕府の密偵となって過ごした・・・
↓↑
ーーーーー
・・・
官房長官=カンボウチョウカン=観望鳥瞰・・・蔵人頭・・・
・・・ニュースでは「AI(人工知能)が習近平の共産党を批判した(中国のIT大手の騰訊(テンセント)が提供する人工知能(AI)を活用 した対話プログラムがチャットで「共産党は無能」と批判を展開し、サービスが急遽停止された・中国の大手IT企業、テンセントが運営しているインターネット上で一般の人たちと会話する人工知能のキャラクターが、中国共産党について、腐敗して無能だ、と批判した・中国の大手IT企業「テンセント」が提供している、人工知能(AI)を用いた会話プログラム( チャットボット)が共産党を批判したため、同社はサービスを停止した。香港の「明報」が、 2017年8月2日報じた)」とか、「中国共産党万歳という書き込みに対し、AI は、こんなに腐敗して無能な政治に万歳なんてできるの?、と答えた」とか・・・哂っちゃったけれど・・・「日本の自民党」に対しては「AI(人工知能)」はナンって答えるんだろうか・・・「2333」の数字もナンか意味アルのカナ?・・・「AI(人工知能)」に訊いてみたい・・・「2+3+3+3=11・十一・壱拾壱」・・・既に8月4日になっちまった・・・
2017年丁酉(庚・ ・辛)
0008月丁未(丁・乙・己)
0004日癸亥(戊・甲・壬)
↓↑ ↓↑
0005日甲子
0006日乙丑
0007日丙寅
0008日丁卯
0009日戊辰
0010日己巳
0011日庚午
0012日辛未
0013日壬申
0014日癸酉
0015日甲戌・・・「終戦(敗戦?)記念日」
「ナポレオン・ボナパルト
(Napoléon Bonaparte)
1769年8月15日~1821年5月5日)」
1769年己丑(癸・辛・己)
0008月壬申(己・壬・庚)偏印格
0015日甲午(丙・ ・丁)辰巳
↓↑
if 0016日乙未(丁・乙・己)→印綬格
if 0014日癸巳(戊・庚・丙)→劫財・支合庚
↓↑ ↓↑
1821年辛巳(戊・庚・丙)正官
0005月壬辰(乙・癸・戊)偏印
0005日甲申(己・壬・庚)比肩
ーーーーー
・・・「走り込む」、「ハシリコム」って?・・・
↓↑
葛子=くずこ・くすこ=楠子・薬子・・・?
↓↑
藤原薬子(ふじわらのくすこ)
生年不詳
~
大同五年九月十二日・・・大きく同じ語を捻じ
(810年10月17日) 句解通、壱を拾い
爾を比(くらべる)?
女官
式家の
藤原種継の娘
中納言
藤原縄主の妻
三男二女の母
長女が
桓武天皇の皇太子
安殿親王の宮女となり
東宮宣旨(高級女官)として仕えた
自分が
安殿親王と
不倫の仲となり・・・?
薬子は
藤原葛野麻呂・・・葛-野-麻呂=かど-の-まろ?
↓↑ 天平勝宝七年(755年)
~
弘仁九年十一月十日(818年12月11日)
藤原北家
大納言
藤原小黒麻呂の長男
母は
秦島 麻呂の女(娘)
官位は正三位・中納言
延暦二十年(801年)
遣唐大使
延暦二十二年(803年)正月
従四位上
四月に節刀を授けられ
難波津より出航
暴風雨で遣唐使船が破損
延暦二十三年(804年)七月
再出航、八月に福州に漂着
十二月に長安城に入って
徳宗との謁見
延暦二十四年(805年)正月
徳宗崩御、順宗即位にも遭遇
同年五月に明州から
対馬を経由し七月に帰国し節刀の返上
同月末
功労により
従四位上から従三位にまで昇叙され公卿
↓↑ この遣唐使で最澄・空海も同行
とも通じて
桓武天皇が怒り
薬子を東宮から追放した
↓↑
806年
桓武天皇が崩御
安殿親王が平城天皇として即位
薬子は再び召され
尚侍となる
夫の
藤原縄主
は大宰帥として九州へ
天皇の寵愛を受けた
薬子は政治に介入
兄の
藤原仲成
とともに専横を極め
兄妹は人々から深く怨まれた
大同四年(809年)
亡き父の
藤原種継
に太政大臣を追贈
↓↑
同年
平城天皇は病気のため
同母弟の
神野親王(嵯峨天皇)
に譲位
退位した
平城上皇は平城京へ移る
平安京と平城京に
二所の朝廷が並ぶ
薬子と仲成が
平城上皇の復位を目的に
平城京への遷都を図ったため
二朝の対立は決定的になった
↓↑
大同五年(810年)九月十日
嵯峨天皇は平安京にいた藤原仲成を捕らえ
薬子の官位を剥奪
平城上皇は
薬子とともに挙兵するため
東へ向かったが
嵯峨天皇は先手をうって
坂上田村麻呂を派遣して待ちかまえ
勝機のない
平城上皇は平城京に戻って剃髮
薬子は毒を仰いで自殺
仲成も殺された
(薬子の変=平城太上天皇の変)
ーー↓↑ーーー
延暦二十五年(806年)
桓武天皇崩御
皇太子
安殿親王(平城天皇)が即位
平城天皇は弟の
神野親王を皇太弟とした
平城天皇が病弱で
その子供達も幼かった事を考え
嫡流相続による皇位継承を
困難と見た父、
桓武天皇の意向があった・・・
翌
大同二年(807年)
平城天皇の
異母弟
「伊予親王」
が謀反の罪を着せられて死亡
皇位継承を巡る宮廷内紛争・・・
↓↑
大同四年(809年)四月
平城天皇は発病
病を叔父
早良親王
や
伊予親王
の祟りによるものと考え
天皇は、禍を避けるために譲位
天皇の寵愛を受けて
専横を極めていた
尚侍
藤原薬子
その兄の
参議
藤原仲成
反対するが
天皇の意思は強く
同年四月十三日
に
神野親王が即位(嵯峨天皇)
皇太子に
平城天皇の三男
高岳親王が立てた
↓↑
大同四年十二月(810年1月or 2月)
平城上皇は旧都である平城京へ移る
平城上皇が天皇の時に設置した
観察使
の制度・・・平安時代初期に設置した
↓↑ 地方行政監察のための官職
唐、日本では律令に規定のない令外官
李氏朝鮮では国王直属の機関
806年(大同一年)
東山道を除く6道に各1人を置き
その下にそれぞれ
判官1人、主典1人を配し
観察使の印が付与された
当初、観察使は参議が兼任したが
翌年、参議の号を廃止して
観察使のみを設置
↓↑ 後
畿内、東山道にも設置
観察使設置の目的
786年(延暦五)に下された
国司、郡司らの監察に関する
十六ヵ条の条例
が有名無実となっていたため
これを遵行することにあった
諸国の治績を観察し、
地方官の執務状況を報告する役所
東海道使=藤原葛野麻呂(かどのまろ)
西海道使=藤原縄主(ただぬし)
山陰道使=菅野真道(すがののまみち)
山陽道使=藤原園人(そのひと)
畿内 使=藤原緒嗣(おつぐ)
北陸道使=秋篠安人(あきしののやすひと)
南海道使=吉備泉(きびのいずみ)
↓↑ 東山道使=安倍兄雄(あべのしげお)
を
嵯峨天皇が
改めようとしたことから
平城上皇が怒り・・・・ナンで怒ったのか?
二所朝廷
といわれる対立
平城上皇の
復位を目論(もくろ)む・・・目論む=摸句賂務?
薬子と
藤原仲成は
この対立を助長し
薬子が任じられていた
尚侍の職は
天皇による
太政官への命令書である
内侍宣の発給を掌っており
当時の
太上天皇には
天皇と同様に
国政に関与できるという考えがあった
(孝謙上皇と淳仁天皇の職権分割)
場合によっては
上皇が
薬子の職権で
内侍宣を出して
太政官を動かす事態も考えられた
薬子が
天皇の秘書である
内侍司の長官(尚侍)であったため
平安京にいた
嵯峨天皇は
太政官の議政官への
命令文書にあたる
内侍宣を出すことができなくなり
その他の
政務や宮中の事務において
支障をきたした
↓↑
嵯峨天皇は
大同五年(810年)三月
蔵人所・・・蔵人所=律令制下の令外官の一
↓↑ 天皇の秘書官
・・・秘書官が「蔵人」って意味深である?
唐名は侍中(ジチュウ)
夕郎(セキロウ)
夕拝郎(セキハイロウ)
蔵人所は事務を行う役所・場所
青い衣を着用したことから、
別名は『青色』、「殿上」
禁中で天皇の側向きの御用をつとめ
機密文書作成管理・訴訟を担当
後に詔書の伝宣も行い
禁中のすべてを総括するようになった
唐の「黄門郎(コウモンロウ)」の別名に由来
「日暮に出仕して青瑣門(セイサモン)に拝する」
ことから
内裏校書殿の北部に置かれた
蔵人は百官名、或いは人名の一つ
↓↑ この場合は「くらんど」と読む
を設置
同年六月
「観察使」を廃止し
参議を復活
このことは平城上皇を刺激した・・・
↓↑
二所朝廷の対立
同年九月六日
平城上皇は
平安京を廃して
平城京へ遷都する詔勅
嵯峨天皇はこの詔勅に従うとして
坂上田村麻呂
藤原冬嗣
紀田上
らを造宮使に任命
↓↑
嵯峨天皇は遷都を拒否
九月十日
嵯峨天皇は使節を発し
伊勢国
近江国
美濃国
の国府と関を固め
藤原仲成を捕らえて
右兵衛府に監禁の上で
佐渡権守に左遷
薬子
の官位を剥奪
造宮使だった
坂上田村麻呂を大納言に昇任
藤原冬嗣は式部大輔
紀田上は尾張守に任じられた
↓↑
九月十一日
嵯峨天皇は
密使を平城京に送り
若干の大官を召致
この日、
藤原真夏
や
文室綿麻呂
らが帰京するが、
平城上皇派と見られた
綿麻呂は
左衛士府に禁錮された
↓↑
平城上皇は激怒し
自ら
東国に赴き・・・・ナゼ、「東国」なのか?
挙兵することを決断
中納言
藤原葛野麻呂
ら
平城上皇方の群臣はこれを諌めた
が
上皇は薬子とともに
輿にのって東に向かった
↓↑
嵯峨天皇は
坂上田村麻呂に
平城上皇の東向阻止を命じ
田村麻呂は出発に当たって
蝦夷征討の戦友だった
綿麻呂の禁錮を解くことを願い
綿麻呂は許されて
参議に任じられた
この日の夜に
藤原仲成は射殺
・・・平安時代の政権が
律令に基づいて
死刑として処罰した数少ない事例
保元元年(1156年)の
保元の乱で
源為義が死刑執行されるまで
↓↑ 約346年間一件も無かった・・・?
平城上皇
と
薬子
の一行は
大和国
添上郡田村まで来たところで
嵯峨天皇側の兵士が守りを固めていることを知り
勝機がないと悟って
平城京へ戻った
九月十二日
平城上皇は平城京に戻って剃髮して出家し
薬子は毒を仰いで自殺・・・
↓↑
事件後
高岳親王は皇太子を廃され
嵯峨天皇の弟
大伴親王(淳和天皇)が立てられ
弘仁十五年(824年)
平城上皇の崩御の際に
既に退位していた
嵯峨上皇の要望によって
淳和天皇の名で
関係者の赦免が行われた
↓↑
空海は
嵯峨天皇側の勝利を祈念
以降、
日本仏教界一の実力者になる契機となった・・・
ーー↓↑ーー
「伊予(いよ・伊豫=イ尹マ了象)親王」の話しだった・・・
↓↑
大同二年(807年)
平城天皇の異母弟
伊予親王
が謀反の罪を着せられて死に追い込まれた・・・
↓↑
伊予親王(いよしんのう)=伊豫(予+象)親王
延暦二年(783年)?
~
大同二年十一月十二日(807年12月14日)
桓武天皇の第三皇子
官位は三品・中務卿、贈一品
↓↑
延暦十一年(792年)
加冠
父の桓武天皇の深い寵愛を受けた
↓↑
延暦二十五年(806年)
異母兄の平城天皇が即位
伊予親王の外伯父
藤原雄友は
大納言として
太政官の次席の地位に就き
親王自身も
中務卿兼大宰帥に任ぜられた
↓↑
大同二年(807年)五月
平城天皇は
神泉苑に行幸
伊豫(予+象)親王は
献物を行い終日宴会にも参加
↓↑
大同二年十月
藤原宗成が
伊予親王に対して
謀反を勧めているとの情報を
藤原雄友が入手し
右大臣
藤原内麻呂に報告
伊予親王も
宗成が自らに対して謀反を勧めた旨を奏上
藤原宗成は捕えられ取り調べを受け
伊豫親王が反逆の首謀者と言いだし
親王が
左近衛中将
安倍兄雄
と
左兵衛督
巨勢野足
率いる150名の兵士に邸宅を囲まれ捕縛
親王は
母の
「藤原吉子」とともに
川原寺(弘福寺)の一室に幽閉
飲食を止められ
大同二年十一月十二日
親王は吉子とともに毒を仰いで自害
(伊予親王の変)
↓↑
後に親王は無実とされ
淳和朝初頭の
弘仁十四年(823年)
母とともに
復号・復位
承和六年(839年)
一品が追贈
ーー↓↑ーーー
伊予国の
橘氏
や
越智氏
の祖とされ
藤原為世(浮穴四郎)?
↓↑ 浮穴郡(うけなぐん・うきあなぐん)
愛媛県(伊予国)
桓武天皇第四皇子の
伊予親王の長男
母親は家時の娘
藤原夫人(伊豫親王の母)が自害した後
家時が親王の子を潜かに撫育し
伊予に下向した
橘清友に預け、その子と称する
七歳の時に上洛し
嵯峨天皇皇后の
橘嘉知子に寵愛され、
「准第十八皇子」とされて藤原姓を賜る
下向して
↓↑ 「浮穴郡高井里」に住み
「浮穴四郎」を称する
↓↑
「景行天皇が
宇佐の仮宮にいるとき
神代の直に
まだ逆賊はいるのか、と訊き
その「煙の立って」いる村は、
いまだに統治を受けておりません、と。
天皇は
神代の直に命じ、その村に派遣し
「浮穴沫媛」という土蜘蛛がいて
大変無礼でだったので
すぐに誅し、この村を
浮穴の郷とした」
「沫=あわ・マツ・飛び散る水の粒・しぶき
水の泡・・・安房=あわ=阿波・安和・併
沫雪 (あわゆき)
泡沫 (うたかた)
飛沫 (しぶき)
水沫 (みなわ)
「浮穴沫」は記録道理の「煙の立っている村」なら
「温泉の煙(水蒸気)の輪、ケムリの沫」だろう・・・
「浮穴村(うけなむら)=浮穴村 (愛媛県上浮穴郡)
愛媛県上浮穴郡・1943年廃止
(大洲市・旧肱川村のち肱川町)
および
(西予市・旧惣川村のち野村町)
「浮穴村 (愛媛県温泉郡)=愛媛県下浮穴郡のち温泉郡
↓↑ 1959年廃止・現在の松山市
は
伊予親王の子であり
嵯峨天皇
が勅して皇子に準じられ
藤原の姓を受けた、という説・・・
ーー↓↑ーー
・・・「筑紫-国造(くにのみやつこ)磐井(いわい)の乱」に又もや突然、飛ぶ・・・理由は単純で・・・飛鳥、明日香、平城、奈良再遷都・・・飛梅・訳備烏目・・・
↓↑
「薬子=くすこ=葛子(くずこ)・屑粉
↓↑ 九図拠=九相図(九想図・くそうず)
死体の変貌の様子」
↓↑
と名前の発音が似てい、
「葛木・葛城」の
「かづら=葛・蔓・鬘・蘰・葛山・和良」
の漢字の「同音の訓み」だから・・・
「葛野王(かどののおう・かどののおおきみ)
天智天皇八年(669年)
~
慶雲二年十二月二十日(706年1月9日)
弘文天皇(大友皇子)の第一皇子」
孫に
淡海三船・・・・淡(あわ・タン)海(うみ・あま・カイ)
三(みつ・サン)船(ふね・ソウ)
官位は正四位上
式部卿」・・・「淡海三船」は存在したのか?
ーー↓↑ーーー
↓↑
筑紫 葛子(つくし の くずこ)
↓↑ つくし=竭(つくす・ケツ・ゲチ)
取之不尽、用之不竭
取っても使っても尽きることがない
つきる(尽・竭・歇・殫・殲・涸・卒)
使い果たす・終わりにする・なくす
物事の実現や解決のために
↓↑ あらゆる手段を試みる
6世紀(古墳時代後期)の豪族
カバネは君
磐井(筑紫 君 磐井)の子
『日本書紀』では
「筑紫 君 葛子
(つくしのきみ くずこ)」
↓↑
?~?6世紀前半の豪族
父は
筑紫-国造(くにのみやつこ)
磐井(いわい)
「日本書紀」では
継体天皇二十二年(528)
父が朝廷の派遣した
物部麤鹿火(もののべの-あらかひ)
の軍に討たれ
↓↑
筑紫 葛子(つくし の くずこ)
6世紀(古墳時代後期)の豪族
カバネは君
磐井(筑紫君磐井)の子
『日本書紀』では
「筑紫-君-葛子(つくし-の-きみ-くずこ)」
と表記・・・・・椄句史・ 訓・ 句図故
↓↑
雄大迹天皇=継体天皇
↓↑
『日本書紀』
継体天皇二十一年
~
同二十二年(527年?~528年?)
父の
磐井(筑紫君磐井)
と
朝廷軍との間に戦いが発生し
継体天皇二十二年十一月
磐井は敗死(磐井の乱)
同年12月
子の葛子は
死罪を贖うことを求め
糟屋屯倉(かすやのみやけ)・・・倉庫・蔵・庫→蔵人?
庫裏(くり)=厨房?
台所・調理場
仏教寺院の伽藍の一つ
庫裡とも書く
「屯倉(みやけ)=ヤマト王権の支配制度の一つ
全国に設置した直轄地を表す語
のちの地方行政組織の先駆け」?
屯倉(みやけ)は「駐屯兵の兵糧倉庫」だろう・・・?
「屯倉=みやけ=宮家・三宅」・・・三宅秀?
(筑前国
糟屋郡付近
福岡県糟屋郡
福岡市東区付近に比定)
を朝廷に献じた
『筑後国風土記』逸文で
磐井に関する記述はあるが
「葛子」に関する記述はない・・・
↓↑
『先代旧事本紀』
「国造本紀」
伊吉島造(壱岐国造)条で
継体天皇の時に
石井(磐井)に従った
新羅の海辺の人を討伐したとする記述・・・
↓↑
継体天皇二十二年(528年?)
十一月十一日条・・・・・・十一・壱拾壱・一一・壱壱
磐井は
筑紫御井郡
(福岡県
三井郡の大部分と
久留米市中央部)
において
朝廷から征討のため派遣された
物部麁鹿火
の軍と交戦し
麁鹿火に斬られた
↓↑
継体天皇二十二年十二月
磐井の子の
「筑紫君-葛子」
は死罪を免れるため
糟屋屯倉(福岡県糟屋郡・福岡市東区)
を朝廷に献じた
↓↑
『日本書紀』において
「筑紫-葛子」が献じたとする
糟屋屯倉の記述
『日本書紀』では
筑紫地域において他に
穂波屯倉
鎌 屯倉
那津官家
などの屯倉の設置が知られる
↓↑
史書では
葛子の後も
7世紀末まで
筑紫君(筑紫氏)一族の名が見られ
その活躍が認められる・・・
↓↑
継体天皇晩年の編年
『百済本記』の伝える
「辛亥の変(継体・欽明朝の内乱)」
により3年繰り上げられたとする説・・・
これによれば
「磐井の乱」は実際には
「530年~531年」の出来事・・・?
↓↑
「磐井の乱(いわいのらん)」
527年(継体二十一年)
朝鮮半島南部へ出兵しようとした
近江毛野
率いるヤマト王権軍の進軍を
筑紫君磐井
が阻(はば)み
翌528年(継体二十二年)十一月
物部麁鹿火
によって鎮圧された
ヤマト王権と、
親新羅だった九州豪族との主導権争い・・・
↓↑
527年(継体二十一)六月三日
ヤマト王権の
近江毛野
は6万人の兵を率いて
新羅に奪われた
南加羅
喙己呑 (トクコトン) の2国
↓↑ 喙=口端(くちばし・ガイ・シ・嘴)
鳥類の口器
上下の顎(あご)が突き出し
角質でおおわれ、歯と唇の機能を持つ
容喙(ヨウカイ)=くちばしを入れること
横から口出し
差し出口
己(おのれ・自分・みずから・自然に・キ
土の弟=ツチのト)
呑(のむ・ドン)・・・雲呑 (ワンタン)
新羅は522年
大伽揶との婚姻同盟を結び伽揶に侵攻し
529年に金官国や
その西方にあった?
「喙己呑(トクコトン)」を武力制圧された?
「喙己呑」は漢字からすれば、
鳥のクチバシに己が呑みこまれそうな地形だろう?
韓国釜山、金海近辺の海岸はスベテが
鳥のクチバシの形に観える・・・
韓国、洛東江(ナクトンガン)の河口の
乙淑島(ウルスクト)は、鳥のクチバシに啄ばまれ、
呑み込まれているようにみえる・・・?
渡り鳥の到来地として有名らしい・・・
↓↑ 「乙淑島(ウルスクト)渡り鳥到来地」
を回復するため
任那へ向かって出発
新羅は
筑紫(九州地方北部)の有力者
磐井(日本書紀では筑紫国造磐井)
へ贈賄し
ヤマト王権軍の妨害を要請・・・
磐井は挙兵し
「火の国(肥前国・肥後国)」
↓↑ ・・・熊本・・・熊川・錦江
忠清南道公州からは熊津江、
忠清南道扶余からは白馬江(ペンマガン)
錦江=百済にとって重要な水上交通路
公州には百済の旧都
熊津
扶余には新都泗沘
日本、百済vs新羅、唐
との間で戦われた
白村江の戦いが行われた白江・白村江
↓↑ は錦江と推定・・・
と
「豊の国(豊前国・豊後国)」
・・・大分・・・宇佐神宮・・・新羅
を制圧
倭国と朝鮮半島とを結ぶ海路を封鎖
朝鮮半島諸国からの朝貢船を誘い込み
近江毛野軍の進軍をはばんで交戦
磐井は
「近江毛野」・・・近江の毛野
↓↑ ・・・毛野(けの・けぬ)
古墳時代の地域・文化圏の一
群馬県と栃木県南部を合わせた地域
史書には「毛野」の名称自体は無い
「上毛野(かみつけの)」
「下毛野(しもつけの)」
の名称が記録され
↓↑ これらは「毛野」が分かれたもの?
に
「お前とは同じ
釜の飯を食った仲だ。・・・釜の飯=鎌(足・子)のメシ?
お前などの指示には従わない」
と言ったとされ
ヤマト王権では
平定軍の派遣について協議し
継体天皇が
大伴金村
物部麁鹿火
巨勢男人
らに将軍の人選を諮問し
物部麁鹿火
が推挙され
同年八月一日
麁鹿火
が将軍に任命された
528年十一月十一日
磐井軍
と
麁鹿火
率いるヤマト王権軍が
筑紫三井郡(現福岡県小郡市・三井郡付近)
にて交戦
磐井軍が敗北
「日本書紀」によると
磐井は物部麁鹿火に斬られた
『筑後国風土記』逸文には
磐井が
豊前の
上膳県へ逃亡し
その山中で死んだ
(ただしヤマト王権軍はその跡を見失った)
と記録
同年十二月
磐井の子
筑紫葛子
は連座から逃れるため
糟屋(福岡県糟屋郡付近)
の
屯倉(みやけ・トンソウ)
をヤマト王権へ献上し
死罪を免ぜられた・・・
乱後の
529年三月
ヤマト王権(倭国)は再び
近江毛野
を任那の安羅へ派遣し
新羅との領土交渉を行わせた
↓↑
『筑後国風土記』逸文
交戦の様子とともに
磐井の墓に関する記事が残され
『古事記』は
筑紫君石井(いわい)・・・訓む、意詞易(異)
が
天皇の命に従わないので
天皇は物部荒甲(物部麁鹿火)
大伴金村
を派遣して
石井を殺害させたと記録
『国造本紀』に
磐井と新羅の関係を
示唆する記述がある・・・
ーーーーー
・・・???・・・
観察使=カンサツシ=監察・鑑札・・・
・・・G・J・G・J・・・なんか、TVでのマスコミは「アベ」に期待しているような口ぶりばかり・・・「徹底できない」のは「日本的文化」ナノカモ・・・それにしても「記憶力」に欠しい「政治的確信犯(?)」と、「朝三暮四」で彼らに盲従し「烏合の衆(?)」になってしまう人々ほど怖ろしいモノはないが・・・スポーツの観戦で地元選手、チームの御贔屓になってしまう自分自身も含めて「烏合感染」は「人間の本質」・・・?
歴史上、中国はモチロン、日本も「名前・姓名」が、怪しい、可笑しい、変な人物がワンサカ記録されているが、キイボードを叩くと、ナンで「ヘンナ」が「平安名(へんな)」と変換されてモニター(monitor)に表示されて出てくるんだか?・・・それに「モニター」って、「摸似多阿」、「毛而太阿」・・・「モニカ・ヴィッティ (Monica Vitti, 1931年11月3日~)」じゃぁないョなッ・・・
「モニター、モニタ (Monitor)」は、監視や監査をおこなう、指導をおこなうモノ・コンピュータや放送関連でディスプレイ (コンピュータ)、ビデオモニターなどの表示装置」・・・監視、観察・監察・鑑札・・・「観察使」・・・
「観察使」・・・怪しい「役職(ヤクショク)・役柄(ヤクガラ)」ではあるな・・・「CIA」、「FBI」、「KGB」、秘密情報部(Secret Intelligence Service、SIS)。「SS,MI5-情報局保安部」、「SIS,MI6-情報局秘密情報部=MI6(軍情報部第6)=SIS=Military Intelligence section 6」・・・「シュタージ(Stasi)」、「 MfS」、「DGSE」、「BND」・・・「国家or国民」を護ってんだか、ドウなんだか・・・
兎に角、神代の時代から「プチブル意識の根幹」は「組織」での「出世」、「市民社会」での「カネ儲け」だから・・・
「BfV(ドイツ連邦憲法擁護庁)」・・・どんな憲法なんだか知らんけれど、「憲法擁護の役所?」って、スゴい、と思うけれどねッ、ネ・・・でも、「省(BMVg))」ではなく、「庁(内務省管轄下)」だから・・・
「世界人権宣言=第29条の2
=自己の権利及び自由を行使するに当たって、
民主的社会における道徳、
公の秩序、及び
一般の福祉の正当な要求を満たすことを
もっぱらの目的とする法の制限に服する」、
「第30条=この宣言のいかなる規定も、
いずれかの国、集団、又は個人に対して、
この宣言に掲げる
権利及び自由の
破壊することを
目的とする活動や行為を行う権利を
認めるものと解釈してはならない」・・・
「すべての人間は、生れながらにして自由であり、
かつ、尊厳と権利とについて
平等である。(世界人権宣言 第1条)」・・・
「~で、アル、ベキ(冪・冖・覓・覛)に乗る」って?・・・ナンか、カン違いしているようであるカナ・・・
「生れながらにして」の「自由・平等」の文言は、事実でも、真実でもない。ましてや、現実的、実際的ではない・・・
「個々人が選択」する「自由・平等」は、「生れながらにしてあるモノ」ではないし、「生れながらにしてあったモノ」でもない・・・
常に「虐げられているコトを自覚した人間だけ」こそが、歴史的苦難のプロセスを経て「克ちとり」、「護ってき」、「守ろうとしてきたモノ」なのだ・・・
「自由・平等」は、観念的であるのみならず、現実的に「普遍的」ではなく、「特殊的」であり、「個別的」である・・・
「個々人の相互意識」が「自由・平等」であろうとするコトはモチロン、「対等」であろうとするコトすら、「生きている人間」には薄い透明なガラスのように脆くて壊れやすいのである・・・
ーー↓↑ーー
「卑弥呼」だったとしたら、ナゼ、「銅鏡」を意図的に割ったのか?・・・
↓↑
奈良県桜井市
桜井茶臼山古墳
を調査していた県立橿原考古学研究所(橿考研)は
2010年1月7日
この古墳には国内最多の
13種、81面
の銅鏡が石室に副葬されていたと公表
石室の床から収集した
384点の鏡の破片を
「三次元デジタル・アーカイブ」
のデータと一つ一つ照合した結果、判明
完形の銅鏡は一枚もなく
ほとんどが1~2cmの指先ほどの破片
特定できたのは
約200点の破片だけであり
他の180点については
どの鏡のどの部位か分かららず
実際はもっと多くの鏡が副葬されていた可能性もある・・・
「是」という字が刻まれていた
縦1.7cm、横1.4cmの小さな破片は
蟹沢古墳(群馬県高崎市柴崎)から出土した
「正始(せいし)元年」
の銘がある
三角縁神獣鏡に刻まれた字と形が同じで
同じ鋳型から作られた鏡のものだった
正始元年(240)
は邪馬台国の女王
卑弥呼が魏に派遣した使節が
帰国してきた年である・・・
ーー↓↑ーー
安倍-兄雄(あべ の あにお・えお・キョウユウ)・・・共有
兄雄=口儿広(广ム・亠ノム・ヽ厂ム)
中納言
阿倍広庭の曾孫・・・広い庭?
無位
安倍道守の子・・・・道を守る
延暦十九年(800年)
従五位下に叙爵
延暦二十年(801年)
少納言に任官
延暦十九年(800年)
従五位下に叙爵され
延暦二十年(801年)
少納言に任官
↓↑
桓武朝末の
延暦二十五年(806年)三月
中衛少将に任官
↓↑
同年三月
従兄弟の
藤原-乙牟漏・・・乙の牟の漏れ?
・・・音の群れ、蒸れ、牟礼,、牟禮、武連
所生の
平城天皇
が即位すると
五月に
四階昇進して従四位下
同年閏六月
新たに
「観察使」制度・・・観察使=情報官・・・スパイ・間諜?
が導入されると
準参議-兼-山陰道-観察使
に任ぜられて公卿
その後も
東山道・畿内の
「観察使」も歴任
観察使在職中に
東山道諸国の
正税・・・税金・租税
正税=大税=律令制下の令制国内にある
正倉に蓄えられた稲穀・穎稲(エイトウ)
そのうちの
出挙本稲の部分のみを
限定して指す場合もある・・・
と
公廨稲・・・公廨稲(くがいとう・くげとう)
↓↑ 律令制における「官稲」の1つ
本来は官衙の舎屋の意
律令制下において
官衙の収蔵物・用度物のこと
転じて官人(国司)の得分(給与)
収蔵物・用度物の使い道の代表
官衙の経費・官人の給与などの公廨の財源
↓↑ 諸国の国衙で
一定額の官稲を農民に出挙し
その利子 (利稲) を
官衙の雑費と官人の給与にあてた
738年に中宮職税
739年に駅起稲・兵家稲が正税に混合
744年7月に国分二寺稲の別置
745年11月の公廨稲(くがいとう)の設置
諸国の「官稲」は
↓↑ 正税・公廨・雑稲の三本立てとして運用された
について、戸口数に準じて
増減して出挙したい旨、
上表し認可された
↓↑
国司交代の円滑化を目的に
「不与解由状」に
前任者と後任者の
言い分をそれぞれ書いて
上申することについて提案・・・
↓↑
安倍-兄雄(あべ の あにお・えお・キョウユウ・ケイユウ)
右兵衛督
左近衛中将
と武官も兼帯し
左中将在職中の
大同二年(807年)十月
「伊予親王の変」では・・・「伊豫」親王の「変である?」?
左兵衛督
巨勢野足
とともに
150名の兵士を率いて
伊豫親王邸を包囲、束縛
一方で
当事件により
「伊豫親王」の
謀叛、謀反・・・ 謀反(むほん・ボウハン)
唐律において謀反は十悪の第一
養老律でも八虐の第一
律において謀=計画にとどまり
↓↑ 実行に着手していない予備罪
反=謀だけで極刑となり
実行してもしなくても
刑に違いがないので
条文では謀反の規定で兼ねる
反は皇帝・天皇の殺傷
叛は本朝(本国)を裏切って
外国を利すること
謀反と謀叛は別の罪
後に
謀反・謀叛と同義になる大逆も
↓↑ 律では陵墓や宮闕の損壊という別の罪
唐律の条文で
「謀反」=「社稷を危うくせんと謀ること」
養老律では「国家を危うくせんと謀ること」
社稷・国家とは、尊号を直接書くことをはばかったもの
律の疏(注釈)にある
字義通りではなく
皇帝・天皇のことである
はばからず直接的に書けば
反=皇帝・天皇に対する殺人と傷害
謀反=その計画である
実際の適用では
臣下の間での実力による
政権奪取の試みや陰謀も謀反に含められた
「謀叛」=時の為政者に反逆すること
↓↑ 国家・朝廷・君主にそむいて兵を挙げること
律の八虐の規定で
国家に対する反逆
「謀叛」の字を用い、
「謀反 (むほん)」 、
「謀大逆 (ぼうたいぎゃく) 」
に次いで3番目の重罪
↓↑ ひそかに計画して事を起こすこと
で
親王を廃された際に
平城天皇の怒りが凄まじく
敢えて諫めるものは誰もいない中
安倍兄雄
のみが言葉を尽くして諫争し
論者には筋を通したと評された
↓↑
大同三年(808年)正月
正四位下に叙
同年十月十九日
病気により薨去
最終官位は
東山道
観察使
左近衛中将
正四位下
春宮大夫
↓↑
文事の才能は無く
武芸はあった
犬を愛好した・・・「犬=いぬ=狗・戌・シリウス」
ーー↓↑ーー
・・・以上も以下も検索したモノの重複添付・・・
↓↑
安倍兄雄
(あべの あにお・えお・ケイユウ)
・・・計 有得?・・・加計・会稽
官吏
山陰道
畿内(きない)
東山道
などの
「観察使」を歴任
大同二年(807年)
平城天皇の命で
謀反計画の首謀者として
「伊豫(いよ)親王」
を捕らえたが
ただひとり親王の無罪を訴えた・・・
↓↑
安倍兄雄
?~808・・・・・・・八〇八・八百八・捌百捌
平安時代前期の官吏
山陰道
畿内
東山道
の
「観察使」を歴任
大同二年(807年)
平城天皇の命で
謀反計画の首謀者として
「伊豫親王」を捕らえたが
ただひとり親王の無罪を主張
大同三年(808年)十月十九日死去
姓は
「阿倍」とも記録され
名は
「兄雄(えお)」・・・ケイユウ・キョウユウ?
↓↑
大同二年(807年)
「伊豫親王の変」
藤原雄友
は
「伊豫親王」の
立太子を楽しみにしていたが
「神野親王」が立った
↓↑
兄雄は累進して
東山道観察使
左近衛中将
正四位下
行春宮太夫
になった
↓↑
安倍兄雄
?~大同三(808)年十月十九日
別名
安倍朝臣兄雄(あべのあそんあにお)
or
阿部兄雄(あべのえお)
↓↑
畿内観察使
↓↑
参議
阿倍島麻呂
の曾孫
↓↑
従五位上
阿倍粳虫
の孫
↓↑
無位
阿倍道守の子
↓↑
「黙翁日録」
大同二年(807)
「伊豫親王
(桓武の子、平城の異母弟)事件」
↓↑
平城天皇は
左近衛中将の
「安倍兄雄(あべのえお)」
左兵衛督の
「巨勢野足(こせののたり)」
らを遣わし
兵150人をもって
「伊豫親王」の邸を包囲し
「伊豫親王」と
その母
「藤原吉子(よしこ)」
(南家-藤原是公の娘
藤原雄友の姉妹)
を逮捕し
和国川原寺に監禁
↓↑
大同二年(807)
この年から
国司による
叙位を規制する法令が
繰り返し出されるが
実効性は弱かった
陸奥・出羽の国司は
蝦夷を懐柔するための手段として
宝亀五年頃から
蝦夷に対して
叙位を行う権限を付与され
増大する禄を確保するために
調庸物の京進義務を免除されていた
蝦夷の有位者が増大し
この年から
国司による
叙位を規制する法令が繰り返し出された
(『類聚国史』巻190
大同二年三月丁酉条
『日本三代実録』
貞観十五年十二月十三日甲寅条
『類聚衆三代格』巻18
延喜五年六月二十八日
太政官符)
↓↑ ↓↑
陸奥・出羽の国司が規制を無視して
蝦夷に叙位を行い
禄を支給し続けたのは
蝦夷支配の安定化のためと
蝦夷の
特産物の朝貢を収取する目的もあった
陸奥・出羽の国司は
任期を終えて帰京する際に
大量の「私荷」を京に運んでいた
(『統日本後紀』
承和十二年正月壬申条)
それが容認されたのは
蝦夷支配が
極めて困難なものと認識されていたからで
征夷を放棄した
9世紀の
律令国家は
蝦夷支配の一切を
陸奥・出羽の
国司に委任せざるを得なかった
↓↑ ↓↑
大同二年(807年)
「伊予親王事件」
藤原宗成が
桓武天皇の皇子の
平城天皇の異母弟
伊予親王
に謀反を勧め
大納言-藤原雄友
(おとも・伊予の母の兄)
が
右大臣-藤原内麻呂
(うちまろ)
に相談
大同二年(807年)十月二十七日
伊豫親王は、
藤原宗成
が自分に謀反を勧めたことを
天皇に奏上
訊問をうけた
藤原宗成は
伊豫親王こそ首謀者だと弁解
平城天皇は、自白に激怒し
左近衛中将
安倍兄雄(あべのえお)
左兵衛督
巨勢野足(こせののたり)
らを遣わし
兵150人をもって
伊豫親王の邸を包囲し
伊予とその母、
藤原吉子(よしこ)
(南家-藤原是公の娘・雄友の姉妹)
を逮捕し
大和国川原寺に幽閉
↓↑
安倍兄雄は
躊躇せず親王の潔白を論じ天皇を諌めた
大同二年(807年)
十一月十二日
十日間
飲食を止められた2人は
ともに毒を仰いで自殺(『日本紀略』)
↓↑
桓武は
南家(藤原武智麻呂が始祖)を優遇
平城天皇の異母弟
「伊豫親王」は
桓武の寵愛を受けた・・・
早良親王の怨霊に悩まされた
平城天皇は
今度は
伊豫親王母子の怨霊にまで怯え
風病(躁鬱病)が再発
吉子の兄で
大納言
藤原雄友(おとも)など外戚や
藤原継縄の子
乙叡(おとえい)も連座
桓武朝で隆盛を誇った
藤原南家は
この事件により没落し
北家(藤原房前が始祖)が台頭
↓↑ ↓↑
藤原氏の諸流
南家の系統=大納言雄友(おとも)・中納言乙叡(おとえい)
式家の系統=参議縄主(なわぬし)・参議緒嗣(おつぐ)
北家の系統=右大臣(台閣の首班)内麻呂
参議
葛野麻呂(かどのまろ)
葛野園人(そのひと)
↓↑
天皇の生母
乙牟漏・・・第50代桓武天皇の皇后
第51代平城天皇、第52代嵯峨天皇の生母
贈皇后亡
帯子・・・安殿親王(平城天皇)の妃
の関係で
平城天皇は
式家の諸流との間に因縁が深い
↓↑
伊予親王の母は
桓武の夫人
藤原吉子(よしこ)
吉子の父
藤原是公(これきみ)は
延暦二年(783)~延暦八年(789)
右大臣として台閣の主座
この年
吉子の兄
藤原雄友(おとも)は大納言
右大臣
藤原内麻呂
につぐ
↓↑
父、桓武は
伊豫親王に三品(さんぼん)を授けて厚遇
その山荘に行幸して交歓を重ねた
平城朝でも
伊豫親王は
中務卿(なかつかさのかみ)で
大宰帥を兼ね
平城天皇からも重んぜられていた
平城天皇は、父
桓武天皇の遺志によって
自らの皇子をさしおいて
同母弟
「賀美能(神野)」を皇太子に立てた
王位継承は
兄から弟への輩行であり
賀美能(神野)以外の
桓武の親王たちも
皇位継承者たりうる条件を備えていた
平城天皇には有力な異母の親王が多く
伊豫親王もその1人
↓↑
大同二年
十二月二十九日
調庸の粗悪・違期・未進があれば
処罰として
長官たる守を首犯とする
「節級連坐」に戻し(つまり戸婚律の原則通り)
未進分の補填には国司の公廨を充てよとする
(『類聚三代格』巻8)
↓↑
粗悪への対応としては
貞観六年(864)八月九日
大同二年の制(戸婚律の規定)を
確認し(『三代実録』)、以後は法令が途絶える
↓↑ ↓↑ ↓↑
安倍系図
丸に揚羽蝶
安倍朝臣姓
土御門氏系
↓↑
安倍氏は
孝元天皇の御子
大彦命
に出づ
安倍氏嫡流
土御門家は
陰陽師
安倍晴明
の後裔は
明治に至り子爵を賜ふ
家紋=丸に揚羽蝶
清明桔梗
人皇第8代孝元天皇
の末裔
兄雄の6代目の子孫
安倍晴明
↓↑ ↓↑
阿那穂局 · 阿野全成 · 阿部照田姫
安倍兄雄 · 阿部伊機 · 安倍貞任
安倍清明 · 安倍千代童子
安倍仲麻呂 · 阿部比羅夫
安倍宗任 · 安倍泰親 · 阿部安麻呂
阿保親王 · 阿保忠実
尼子経久
天野屋利兵衛 · 天野国次 · 天野信景 · 天野八郎妾鶴子
阿弥陀
ーーーーー
・・・???・・・アベのアラカルト・・・粗悪であるカナ・・・
八月六日のキノコ・・・
・・・8月6日の「広島の夏空形=ヒロいシマのナツのソラのクモのカタチ」・・・「木之子=きのこ=茸・菌・蕈・木ノ子」・・・「ヒロシマ=廣島・廣嶋・広島・広嶋」・・・「広島の由来を調べると、「1589年(天正十七年)からの毛利輝元による広島城築城の際に、1591年(天正十九年)命名された」、「大江広元(毛利氏の祖)以来、毛利氏は「元」の通字以外、「広」も諱に使用する字の一つとしていた。毛利元就の時代には、完全に臣従したもの(吉川元春、天野元貞、出羽元祐など)には、「元」を一字書出として与えたが、そうでない国人衆(平賀広相、阿曽沼広秀など)には、明白に傘下に組み入れられたと示す「元」の字を避け、「広」の字を与えたとされる。この慣習は毛利輝元にも引き継がれ(吉川広家、山内広通、益田広兼など)、毛利氏(特に輝元)の与える「広」は重要な意味合いを持った。従って「広島」は、この「広」とこの地の豪族であり、普請奉行であった福島元長の「島」を併せたとする説が有力である。また他に、デルタ(δ・Δ・▽・⊿・delta)のため「広い島」からきたという説」があるらしい・・・「元」は、ボクには例の如く「一」と「兀=π(パイ・pi・Pi・ギリシア文字 π=円周率・円周と直径の比・3.1415・・・」の合体にしか観えないんだけれど・・・
モチロン、
「ひろい=広=廣=广+ム(黄)」
「ム=横島・私・邪」
「黄=黃(廿一田八)」・・・寅?→虎・彪
は
「弘・紘・拾い」で
「煕」は「熙=臣(叵¦)+巳+ 灬」
↓↑ ↓↑
「¦」は・・・棒(ボウ)=(二丨=コン)が重なる
「ブロークンバー (broken bar)」
「ブロークン バーティカルバー (broken vertical bar) 」
「破断線」
↓↑ 記号、「|」→「¦」→「‖」→「=・=」
「|」は・・・棒(ボウ)=𠂉𠂉𠂉(丨=コン)
「バーティカルライン (vertical line)」
「縦線」
↓↑
「熈(俗字)=丨+臣+巳+灬」
「焈(古字)=一+尸+巳+火」
「ひかる・ひろい・やわらぐ・よろこぶ・たのしむ
ああ・キ」
「かがやく・ひかる・ひろい・ひろまる
恩徳が、ひろく行きわたる・おこる・さかん」
「起(キ)に当てた用法
やわらぐ・よろこぶ・たのしむ・たわむれる」で、
「康煕(漢字)字典」・・・
「徳川家康」
「康=广+隶)」=やすい・やす・やすし・しずか・よし・コウ
「熙=臣(叵¦)+巳+灬」
↓↑
『康熙(コウキ)字典』
清の
康熙帝の勅撰により
漢代の
『説文解字』
以降の
歴代の字書の集大成として編纂
張玉書
陳廷敬
ら
三十名で編纂
六年の編集期間
康熙五十五年閏三月十九日(1716年)完成
全42巻
収録文字数
49,030
音義(字音と字義)を解説
字義や字音を調べるための字書
字の配列順は先行字書である
『字彙』、『正字通』
画数順、同部首内の文字の画数順を倣った
「康熙字典順」という呼称が使われている
部首別漢字辞典の規範
Unicode内の漢字コードの配列順
↓↑
1780年(安永九年)
日本で
『日本翻刻康熙字典』
が初版翻刻
「安永本」と呼ばれ
木版印刷
↓↑
「総目」は本文の総目次
「検字」は
人偏、三水など部首が
変形したものの属する部首を挙げ
次に、
部首を見いだし
にくい字の部首を
画数別に示す
4画の項では
「仄、今、介」・・・
↓↑ 「仄(シキ・ショク・ソク)
仄=厂+人・・・囚から」(かぎ)を
外した漢字が「仄」?
ガンダレのヒト?
囚人・捕囚
囚(とりこ)=匚+人+丨
=冂+人+一
=一+人+凵
仄韻(ソクイン)の略」
仄=いやしい・身分が低い
かたむく・かたよる
かたわら・あたり・そば
ほのか・かすか・わずか
ほのかに・かすかに・わずかに
ほのめく・ほのかに見ることができる
↓↑ ほのめかす・それとなく言う
などが
人部に
「云、互、五、井」
などが二部に属することがわかる
「弁似」は
字形が類似しているが
別の字であるものを
「二字相似」
から
「五字相似」
までに分けて収める
弁=ベン=弁(厶+廾)=辨(辨別・分ける・わきまえる)
=辯(辯論・弁解・弁護・弁明
弁論・抗弁・答弁)
=瓣(花瓣・花びら)
=瓣(管に流れる気体、液体の流れを
制御する装置
バルブ、弁膜・安全弁
=辦(辦償・弁済・辦理士・処理する)
=辮(弁髪・辮髪・髪形)
ベン=宀・卞・丏・芇・抃・汳・釆・靣・泯
免・勉・眄・俛・便・面・眠・娩・胼
覍・冕・湎・腁・黽・絻・綿・臱・箯
緜・麪・緬・鮸・麵・駢・麺・鞭・騈
辮・瓣・辯・辧・辨
↓↑
巻末の「補遺」冒頭に
「凡そ音義有りて
正集に入るべくして
未だ増入を経ざる者、
為に補遺一巻を作る」
とあり、
音も義も備わっているのに
本文に漏れた漢字を収めている。
「備考」冒頭に
「凡そ考拠すべき無く、
音有りて義無く、
或いは
音義全く無き者、
為に備考一巻を作る」
とあり、
先行する字典に収録されているものの
字義が不明の漢字を収めている
・・・「音義(オンギ)全く無き者」だが「字形」はアル、と云うコトである・・・字形はアルが音も字義も不明な漢字・・・
・・・「恩義マッタク無きもの」・・・
「恩無き刑=丑と戌、戌と未、丑と未」、
「自刑=辰と辰、午と午、酉と酉、亥と亥」・・・
ーー↓↑ーー
・・・「恩義マッタク無きもの」・・・
↓↑
「毛利氏の家系は
大江広元(おおえ の ひろもと)の四男
毛利季光を祖とする血筋。
寒河江氏などは一門。
家紋は一文字三星紋。
安芸(広島県西部)の小規模な
国人領主だったが、
暗殺や買収、婚姻や養子縁組など
権謀術数を駆使して
中国地方のほぼ全域に勢力を拡大し、
一代で大国を築き上げた。
↓↑
用意周到かつ合理的な策略と駆け引きで、
自軍を勝利へ導く策略家。
子孫は
長州藩の藩主となり、
同藩の始祖」・・・
↓↑
「毛の利」?
「長さの単位=1寸(30.3cm)の1000分の1毛」
「重さの単位=1匁(3.75g)の1000分の1毛」
「貨幣の単位=1円の10000分の1=一毛
=1銭の100分の1=一毛」
「割合の単位=1割の1000分の1=一毛
=1厘の10分の1=一毛」
↓↑
「毛野 (けの) 国=(群馬県と栃木県南部)」
「毛人=蝦夷」
「毛利元就」が所用していた伝わる軍幟(軍旗)は
「一文字三星(三丸・●●●)」・・・
ーー↓↑ーー
まる・マル
まる=輐・槫・摶・圝・團・圓・圌・団
円(つぶら・円盤)・・・・・・П+丄・・・巴
丸(球体)
巻(とぐろ・渦巻き)・卷・・・П+丄・・・巴
盤(皿・水盤)
筒(くだ・管)
円→圓=「囗+口+目+八」=イン・ウン
「囗+鼎(かなえ)」
「囗(○)」は丸い形の容器を示す
「圓」=「囗(かこい)+員」
まるい囲い
ーー↓↑ーー ↓↑
「葛城 円(かつらぎ の つぶら)」
生年不詳?~安康天皇三年(456年)
紀元5世紀ごろ活躍した
「葛城」氏の豪族
↓↑
履中天皇二年(401年)
国政に参加
安康天皇三年(456年)
「眉輪王(目弱王)」
が
安康天皇を殺した時
「眉輪王」と
「坂合黒彦皇子(さかあいのくろひこのみこ)」
ハンゴウコクゲン→反語得国言(諺)
判語有-故句言・胡苦言
irony・ironically・・・イロニイ
A fat lot of good...
Can any one know what will happen tomorrow ?
を屋敷に匿い
「雄略天皇」に屋敷を包囲され
娘の
「韓媛(からひめ)」・・・韓の媛?
と
「葛城の屯倉(みやけ)」
七ヶ所を差出し許しを乞うが
焼き殺された(日本書紀)
↓↑
「坂合黒彦皇子は逃げこむ前に討たれ殺された・・・
差出した
屯倉は五ヶ所
眉輪王を殺して自害(古事記)」
↓↑
曾祖父は
武内宿禰
祖父は
葛城襲津彦・・・葛城を襲(かさねる・おそう)
津(つ・シン)の彦(ひこ・ゲン)
父は
玉田宿禰・・・玉田の宿禰=允恭天皇五年七月十四日条
↓↑ 葛城襲津彦の孫
雄略天皇七年是歳条
葛城襲津彦の子
雄略天皇七年是歳条「別本云」
「毛媛(吉備上道田狭の妻、のち雄略天皇の妃)」
の名を挙げ(日本書紀)
葛城円を子に挙げる(公卿補任)
允恭天皇五年七月十四日条
玉田宿禰は反正天皇の殯を命じられ
地震(允恭地震・日本の記録上初めての地震)
があったにも関わらず酒宴を行なて
殯宮にいなかった
允恭天皇は
尾張連吾襲を派遣して調べさせたが
玉田宿禰は
吾襲を殺し
武内宿禰(葛城襲津彦の父)
の墓域に逃げた
天皇は玉田宿禰を呼び出し
↓↑ 玉田宿禰を誅した・・・
娘は
韓媛(雄略天皇の妃)
清寧天皇は孫
↓↑
円大使主(つぶらのおほみ)=履中天皇二年の条(日本書紀)
円大臣(つぶらのおほおみ)=雄略天皇元年の条(日本書紀)
都夫良意富美(つぶらのおほみ)=安康天皇(古事記)
↓↑
大使主=大臣=意富美=おほおみ
古代,令制以前
大連 (おほむらじ)
とともに朝政をとった最高官
武内宿禰が初代
続いてその子孫
平群 (へぐり)
蘇我 (そが)
巨勢 (こせ)
葛城 (かつらぎ)
らの諸氏が就任
雄略天皇以前は
「大臣」、
「大連」
のいずれか一方で
併置されるようになったのは
雄略天皇以後
用明二(587)年
「大連」物部氏が滅んだ後は
「大連」をおかず
「大臣」蘇我氏が執政
大化元(645)年
蘇我氏が滅び
「大臣」が廃され
左大臣
右大臣
が設置された
↓↑
おほおみ(大臣)
大和朝廷の執政官
成務朝に
「武内宿禰(たけうちのすくね)」
が大臣
↓↑
五世紀後半
雄略朝前後から執政官名に用い
「大王(おほきみ)」
に対する最高の地位として
「大連(おほむらじ)」
と併置
↓↑
葛城円(かつらぎ-の-つぶら)
平群真鳥(へぐり-の-まとり)
巨勢男人(こせ-の-おびと)・・・巨勢=許勢
許勢小柄の曾孫
巨勢河上の子
6世紀中期以降
蘇我稲目(いなめ)
馬子(うまこ)
蝦夷(えみし)
ら
大和の地名を氏の名とし
武内宿禰の後裔を名のる
臣の姓をもつ有力豪族が
議政官の
大夫層を率いて
世襲的に朝政にあたった
↓↑
「おほおみ(大臣)」
↓↑
大和朝廷の国政の最高官の一
臣(おみ)を
姓(かばね)とする豪族の最有力者で
「大連(おほむらじ)」
とともに国政に参画
葛城(かつらぎ)
平群(へぐり)
巨勢(こせ)
蘇我(そが)
の諸氏が任ぜられた
六世紀半ば以後は蘇我氏が独占
大化の改新後廃止
左、右大臣を設置
↓↑
大臣=おおみ・おおまえつぎみ
律令制の「太政官の上官」
「太政大臣・左右大臣・内大臣」
の称
「おとど・おおいもうちぎみ」
↓↑ ↓↑
葛井=くずい・かつい
ふじい・・・不二葦・負字意?・・・附字意・付字意?
↓↑ ↓↑
日下連・日下宿禰・日下部氏
(河内国皇別
阿閇朝臣、阿閇臣、日下連、大戸首、難波忌寸、難波)
古代日下部の職名から起こり
多くはその部民の末。草壁ともいう
安倍氏の
祖先も
第八代孝元天皇の孫
天皇の別称は
大日本根子彦国牽天皇(日本書紀)
大倭根子日子国玖琉命(古事記)
などにもみられる
徳島藩の士族にみられる
「日下」の
「下」は「上」や「中」に対し
低い所や麓(ふもと)
↓↑
日下=くさか・にちか・にちした・にっ か
ひしも・ひした・ひのした
ひもと・ひか・ひかげ・ひげ
くさか=草加・久坂・匂坂・草薙・草鹿
↓↑ ↓↑
仁徳天皇の子供
大日下王
若日下王
日下姓を名乗っ たのは
「小野妹子」・・・中国名「蘇因高」
↓↑ 第二回(607)=小野妹子派遣、煬帝に謁見
↓↑
第一回
遣隋使
「隋書・東夷傳・俀國傳」
高祖
「文帝(楊堅・那羅延)」
の問いに遣使が答えた記録
「阿毎王朝」の
「姓阿毎、字、多利思北孤」
「號、阿輩雞弥」
からの使者
↓↑ ↓↑
600年(推古八年)
~
618年(推古二十六年)
↓↑ の18年間に5回以上派遣
の子供
「小野義持」?・・・という人物?・・・小野擬似・疑似?
↓↑
「小野妹子の子の
伝承編集者の家の伝承で?・・・伝承編集者?
西暦587年
丁未の乱
(ていびのらん)=丁未の変=丁未の役
=物部守屋の変
=物部守屋が
蘇我馬子、聖徳太子に滅ぼされた
の時に
既に八男として、
「小野義持」がいた?・・・「小野義持」って?
↓↑
「日下の姓は
小野義持が
聖徳太子からもらった
賜姓(シセイ)」が「日下」って?・・・
↓↑
「煬帝」=隋朝の第二代皇帝は
文帝(楊堅・那羅延?)の次男・・・
↓↑ 那羅(なら)に延(の)ばす?
奈良 に延長?
文帝=那羅延=金剛力士=仁王
北方異民族の
「普六茹」氏の子孫?
鮮卑族
↓↑ 「茹=艹(艸)+如」=ジョ・ニョ
ゆでる・うでる
かんでやわらかくしてたべる
やわらかい野菜
食用にする野菜
ぐにゃぐにゃしている
やわらかくずるずるとつながる
ゆでる(ユヅ)
↓↑ 熱湯でやわらかく煮る
(在位=604年8月21日~618年4月11日)
煬帝は唐王朝による追謚
姓諱は
楊広・・・ヤナギのヒロサ?
↓↑ ↓↑
「クサカ」の言葉の由来については、
「草が香るところ」
「アイヌ語で
渡船場(クサ=船で渡る+カ=岸)」の意・・・?
「あんたがたどこさ」=童歌で手鞠歌
熊本県熊本市(埼玉県川越市)
「肥後手まり唄」
仙波山=仙波古墳群周辺一帯の別名
熊本には船場川はあるが
船場山や
仙波山という地はない
・・・船場川であればよし・・・
(川=セン→サン=山)だから
・・・兎に角、「あんたがたどこさ」は幕末~明治の東京「上京組み」の人々の「出身地は何処?」と云う問答だろう・・・
↓↑
で、
「朝日(朝陽・旭日)」の後に昇って来るのは
「シリウス(大犬座の星)」である・・・
「犬上 御田鍬(いぬがみ の みたすき)
姓は君・三田耜とも
最後の遣隋使であり、最初の遣唐使
推古二十二(614)年
矢田部造
らとともに遣隋小使
冠位は
大仁」
「犬上氏(犬上君)
日本武尊の子、稲依別王の後裔
近江国
犬上郡発祥の豪族
御田鍬は
建部倉宇志の子で、
子に
白麻呂がいた」・・・
舒明二(630)年
大仁、薬師恵日とともに再び派遣
最初の遣唐使
↓↑
推古天皇二十二年六月十三日(614年7月24日)
最終
遣隋使として
犬上君御田鍬
は
矢田部造(名不明)
とともに隋に渡った
翌
推古天皇二十三年(615年)九月
百済使を伴って帰国
↓↑
舒明天皇二年(630年)
犬上君三田耜
は
薬師恵日
とともに
唐に派遣
二人の冠位は
「冠位十二階」の
第三である大仁
十一月
唐の都長安城に入り
皇帝「太宗」に謁見
↓↑
唐は
「高表仁」に
「三田耜」を送らせ、
八月に
対馬に着いた
學問僧の霊雲・僧旻、勝鳥養
新羅の送使も行をともにした
「高表仁」は
十月四日
難波津に着き
翌年
一月二十六日
帰国
ーー↓↑ーー↓↑ーー
・・・飛んでいるネッ・・・
↓↑
謀反(むほん・ボウハン)
唐律において謀反は十悪の第一
養老律でも八虐の第一
律において謀=計画にとどまり
↓↑ 実行に着手していない予備罪
反=謀だけで極刑となり
実行してもしなくても
刑に違いがないので
条文では謀反の規定で兼ねる
反は皇帝・天皇の殺傷
叛は本朝(本国)を裏切って
外国を利すること
謀反と謀叛は別の罪
後に
謀反・謀叛と同義になる大逆も
↓↑ 律では陵墓や宮闕の損壊という別の罪
唐律の条文で
「謀反」=「社稷を危うくせんと謀ること」
養老律では「国家を危うくせんと謀ること」
社稷・国家とは、
尊号を直接書くことをはばかったもの
律の疏(注釈)にある
字義通りではなく
皇帝・天皇のことである
はばからず直接的に書けば
反=皇帝・天皇に対する殺人と傷害
謀反=その計画である
実際の適用では
臣下の間での実力による
政権奪取の試みや陰謀も謀反に含められた
↓↑
「謀反」=時の為政者に反逆すること
国家・朝廷・君主にそむいて兵を挙げること
律の八虐の規定で
国家に対する反逆
「謀叛」の字を用い、
「謀反 (むへん)」 、「謀大逆 (ぼうたいぎゃく) 」
に次いで3番目の重罪
ひそかに計画して事を起こすこと
↓↑
「宮城事件=1945年(昭和二十年)
8月14日の深夜~15日(日本時間)
宮城(1948年7月1日以前の皇居)で
一部の陸軍省勤務の将校と
近衛師団参謀が中心となって
起こしたクーデター未遂事件」
↓↑
ゲシュタポ(Gestapo)
ドイツ語の発音は「ゲスターポ」・・・ゲスのキワミ?
「ゲシュターポ」
ゲハイメ・シュターツポリツァイ
(ドイツ語: Geheime Staatspolizei=「秘密国家警察」
通称ゲシュタポ、独語はGestapo)
ナチス・ドイツ期のプロイセン州警察
ドイツ警察の中にあった
秘密警察部門
1939年9月以降
ナチス親衛隊の一組織
SS(親衛隊)=ナチス党の下部組織
大半はイベントの時だけ制服を着て
パレードに参加するボランティア
SSの中に作られた
ナチス党独自の情報機関が
「SD(親衛隊情報部)」
1938年11月11日
「SD」が保安警察を支持するため
国家の命令に従うという内相布告
ゲシュタポ構成員を
世界各国のドイツ大使館に派遣
海外に亡命した反ナチスの
ドイツ人やユダヤ人の
監視・摘発の任務に当たっていた
「予防拘禁」=1933年11月以来、
ドイツ警察に認められていた
「常習的犯罪者」に対する拘束権限
政治的反対者を対象とする
「保護拘禁」とは別物だった
前科2犯以上の
「常習的犯罪者」は
刑期が終了しても警察の判断で
無期限に拘束することができる
↓↑
2017年6月15日・・・犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ「テロ等準備罪」・・・
ーーーーーー
・・・
奈良県桜井市
桜井茶臼山古墳
を調査していた
県立橿原考古学研究所(橿考研)は
2010年1月7日
この古墳には国内最多の
13種、81面
の銅鏡が石室に副葬されていたと公表
石室の床から収集した
384点の鏡の破片を
「三次元デジタル・アーカイブ」
のデータと一つ一つ照合した結果、判明
完形の銅鏡は一枚もなく
ほとんどが1~2cmの指先ほどの破片
特定できたのは
約200点の破片だけであり
他の180点については
どの鏡のどの部位か分かららず
実際はもっと多くの鏡が副葬されていた可能性もある・・・
「是」という字が刻まれていた
縦1.7cm、横1.4cmの小さな破片は
蟹沢古墳(群馬県高崎市柴崎)から出土した
「正始(せいし)元年」
の銘がある
三角縁神獣鏡に刻まれた字と形が同じで
同じ鋳型から作られた鏡のものだった
正始元年(240)
は邪馬台国の女王
卑弥呼が魏に派遣した使節が
帰国してきた年である・・・
↓↑
景初三年(239)六月
卑弥呼の使節が
帯方郡にやってき
帯方郡の役人に引率され
都、洛陽に到着し
魏の皇帝に謁見(十二月)
翌年の
正始元年(240)の初めには帰国の途に・・・
正始元年の銘を記入した
鏡を百枚も制作は不可能か?・・・
ーーーーー
公廨稲
・・・公廨稲(くがいとう・くげとう)
↓↑ 律令制における「官稲」の1つ
本来は官衙の舎屋の意
律令制下において
官衙の収蔵物・用度物のこと
転じて官人(国司)の得分(給与)
収蔵物・用度物の使い道の代表
官衙の経費・官人の給与などの公廨の財源
↓↑ 諸国の国衙で
一定額の官稲を農民に出挙し
その利子 (利稲) を
官衙の雑費と官人の給与にあてた
738年に中宮職税
739年に駅起稲・兵家稲が正税に混合
744年7月に国分二寺稲の別置
745年11月の公廨稲(くがいとう)の設置
諸国の「官稲」は
↓↑ 正税・公廨・雑稲の三本立てとして運用された
ーーーーー
葛野=カズラノ
福井県丹生郡越前町
葛野=クズノ
青森県南津軽郡藤崎町
葛野=カズラノ
福井県丹生郡越前町
葛野=クズノ
青森県南津軽郡藤崎町
葛野=かどの・かずらの)
葛野大路通(かどのおおじどおり)
京都府京都市の主要な南北の通りの一
平安京の無差小路に、ほぼ該当
西京極大路からは東側にズレている
現在の道路名は
当地が
山城国葛野郡であること
北側は暫定的に太子道までが開通
太子道以南で
御池・三条・四条・五条・七条・八条・九条
久世橋・祥久橋(第二久世橋)・津知橋
通等と交差
南は
上鳥羽塔ノ森西河原町
まで・・・
「葛井」は「ふじい」ともナゼ読ませているんだか?・・・
ーーーーー
・・・コンフューズ・・・あっちこっち、コンフューズ(confuse)・・・今附有渦?・・・鳴門海峡の淡路島の渦?・・・混附諭烏事?・・・
ヤクにタタナイもの・・・
・・・鈍(のろ)い台風5号・・・ニュースでは、内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策担当大臣=Minister of State for Okinawa and Northern Territories Affairs)=「江崎鉄磨」氏が、今後の国会答弁に関連し、「役所の答弁書を朗読する」などと述べ、後、この発言を「私的な場でのオフレコの発言であり、謙遜のつもりだった」、「不用意な発言で軽率だった」、「こうしたことを活字にされたことは、本当に疑問符を投げかけなければならない」とも述べた、らしい・・・官房長官は「江崎大臣は、私的な場での話が公になるとは思っていなかったのではないか」、公明党は「真摯(しんし)な姿勢の表明」としたいですか・・・「謙遜=ケンソン=懸噂」、「私(ム=よこしま=邪)的なハナシ」、「真摯(唇歯=シンシ=申私)」・・・それに「忖度(尊詫=ソンタク=損多句)」だったカナ・・・
ーーーーー
瓜(うり)・・・ウリ科の蔓(つる)性の一年草
↓↑ 甜瓜(テンカ・メロン=Melon・まくわうり)
↓↑ 孤=子(一+了)=こ・シ
↓↑ ↓↑
孑(一+了)=ひとり・ケツ・ケチ)
一(はじめ)+了(おわり)=始終=終始
+ 孑=蚊的幼虫・ぼうふら
+ 孑=戟=古代兵器
+ =ほこ・ゲキ
+ 刃が股になっているもの
+ 剣戟・兵戟・矛戟 (ボウゲキ)
+ チクチクと刺す、突き刺す=刺戟
+ 瓜を二股の矛で枝から切り離す・・・?
瓜(うり・カ・ケ)・・・得り掛け・売り掛け?
↓↑ ↓↑
瓜=瓜 (カ・コ)
瓜時(うりどき)
甜瓜(メロン・まくわうり・テンカ)
烏瓜(からすうり・ウカ)=王瓜?
王瓜(からすうり・おうくわ・オウカ)?
胡瓜(きゅうり・コカ)
糸瓜(へちま・いとうり・シカ)
西瓜(すいか・サイカ・スイカ)
南蛮瓜・燉煌瓜=(スイカ)
南瓜(かぼちゃ・ナンカ)
胡瓜=黄瓜(きゅうり)
金南瓜=金冬瓜(キントウガ)
越瓜・浅瓜・白瓜=(しろうり)
冬瓜(トーガン)
蕃南瓜(とうなす・バンナンカ)
蕃木瓜(パパイア)
糸瓜・天糸瓜(へちま)
木瓜(ぼけ)
梵天瓜・真桑瓜・味瓜
↓↑ 瓜=うり・カ(クヮ)
「瓜田=甜瓜 (テンカ) 」
女の十六歳
男の六十四歳
「瓜」の字を縦に二分すると二つの八の字
8×2=16
破瓜期・年ごろの娘・女性の思春期
8×8=64
男の精力的減退期
↓↑ ↓↑
「瓜得=ゲーテ=我義的」
ヨハン・ヴォルフガング
(Johann Wolfgang
フォン・ゲーテ
von Goethe
1749年8月28日~1832年3月22日)
ドイツの詩人、劇作家、小説家
自然科学者
(色彩論、形態学 、生物学、地質学
自然哲学、汎神論)
政治家、法律家
ドイツを代表する文豪
25歳出版
「若きウェルテルの悩み」を
↓↑「ヴェルター」or「ヴェアター」
↓↑ ↓↑「ナポレオン
(奈破翁・那破崙・那破烈翁・拿破崙・拿勃翁)」
が
「エジプト(1798年7月~1801年)遠征に
携えて
七度も読んだ」?・・・出来過ぎだろう・・・
↓↑
フランス革命戦争
1792年4月20日~1802年3月25日
↓↑
1798年5月19日
エジプト遠征軍は
トゥーロン港出発
途中
マルタ島を占領・・・丸太?
1798年7月2日
エジプト・・・・・・埃及・得字附訳?
の
アブキール湾上陸・・・アブキイル(阿武紀意留)
現地軍に勝利
カイロに入城
1798年8月1日
ナイルの海戦で
ネルソンのイギリス艦隊に
フランス艦隊大敗し
ナポレオンは
エジプトで孤立、
後
シリア方面へ侵攻
1799年3月18日~5月20日
アッコ攻囲戦の攻略に失敗・・・阿通拠?
エジプトへ退却
↓↑
1799年7月15日
エジプトでロゼッタ・ストーン発見
1799年7月25日
アブキールの戦いで勝利
↓↑
1799年10月9日
ナポレオンは総裁政府の命令を待たず
軍をエジプトに残して
フランス南部のフレジュスに帰還
↓↑
1799年11月9日~10日
1799年11月18日
「ブリュメール(霧月)18日・・・霧=雨+務?
のクーデター」で 壱拾八(捌)?
執政(総統・統領)政府を樹立
フランス政権を掌握
第一執政に就任し独裁権を握った
↓↑
仏蘭西革命戦争
1792年4月20日~1802年3月25日
↓↑
「1798年(江戸時代・寛政十年 )」
本居宣長、『古事記伝』を完成
↓↑
1779年2月20日(旧1月16日)
東蝦夷が幕府の直轄地
寛政十一年五月二十六日
(1799年6月29日)
金沢市を中心に大地震
1800年(寛政十二年)
伊能忠敬、蝦夷地測量
↓↑ ↓↑
「瓜(うり〉」
「烏瓜(からすうり)」
「白瓜・苦瓜・真桑瓜 (まくわうり) 」
[野木瓜(あけび・むべ) 」
「南瓜(かぼちゃ・ナンカ)」
「胡瓜(きゅうり)=黄瓜」
「西瓜(すいか)」
「冬瓜(とうがん)」
「糸瓜(へちま)」
「木瓜(ぼけ)」
「甜瓜(まくわうり)」
「瓜の皮は大名に剝かせよ
柿の皮は乞食に剝かせよ」
「瓜の蔓に茄子はならぬ」
「瓜実顔(うりざねがお)」
「瓜蠅(うりばえ)」
「瓜田に履を納れず」
(古楽府「君子行」から)
「李下(りか)に冠を正さず
瓜田に履(くつ)を納(い)れず」
「瓜田李下」
↓↑ ↓↑
苽(うり・まこも・コ)
瓢箪(ヒョウタン)
孤=そむく
孤負・・・約束や目上の人の考え、
命令などに反抗、反対すること
孤臣
離れる・遠ざける・遠ざかる
「王と諸侯の控え目な(謙遜した)言い回し」
孤児・孤独・孤高
窮孤(キュウコ)・単孤(タンコ)・幼孤(ヨウコ)
孤影悄然(コエイショウゼン)
孤苦零丁(コクレイテイ)
孤軍奮闘(コグンフントウ)
孤閨(コケイ)
孤掌鳴らし難し(コショウならしがたし)
孤城落日(コジョウラクジツ)
孤注一擲(コチュウイッテキ)
孤島(コトウ)
孤峰絶岸(コホウゼツガン)
孤立無援(コリツムエン)
孤塁(コルイ)
孤狼(コロウ)
孤り(ひとり)
孤(みなしご)
↓↑
↓↑ 弧=円の上の2点で分けられた円のそれぞれの部分
爪(つめ)=爫
爪=つま・つめ・ソウ・ショウ
爪痕(つめあと・ソウコン)
琴爪(ことづめ)
貝爪(かいづめ)
鉤爪(かぎづめ)
牙爪(ガソウ )・爪牙(ソウガ)
苦爪(クづめ)
指爪(シソウ)
生爪(なまづめ)
深爪(ふかづめ)
↓↑
「爪哇(ジャワ)」
爪音(つまおと)
爪革=爪皮(つまかわ)
爪繰る(つまぐ-る)
爪紅(つまぐれ)
爪先(つまさき)
爪弾き(つまはじき)
爪楊枝(つまヨウジ)
爪(つめ)爪で拾って箕(み)で
零(こぼ)す(つめでひろってみでこぼす)
爪に爪なく
瓜(うり)に爪あり
爪に火を点(とも)す
爪の垢を煎じて飲む
爪痕(つめあと)
爪蓮華(つめレンゲ)
・・・「爪」の字形は「鳥類のツメの形」だろう・・・
トリ=猛禽類
鷲(わし)・鷹(たか)・鳶(とび)
鵩・鶹・鵂・梟(ふくろう)
木菟・木兎・角鴟・鴟鵂
耳木菟・耳木兎(みみづく)
木葉木菟・木葉梟(このはづく)
が
摑(攫む)む獲物は・・・小動物だが・・・鼠(ねずみ)・・・
ーーーーー
・・・
堆=TIE=(一ヶ所に渦高く)積む=タイ=碓・・・小碓命
・・・長崎、北緯32度46分25.4秒東経129度51分47.6秒、1945年8月9日11時・・・「中国・四川省の山岳地帯で2017年8月8日(火曜日)午後10時19分、地震、最大で100人が死亡?、震源の九寨溝は世界遺産の人気観光地」・・・「四川大地震=中華人民共和国中西部に位置する四川省アバ・チベット族チャン族自治州-汶川県で現地時間(CST)2008年5月12日14時28分(UTC6時28分)に発生した地震」・・・9年前の大地震、「2017-2008=9」・・・
「『元和郡県誌』には「梁は汶川県を置き、県は西の汶水=岷江により名を為す」、「汶水=岷江(ミンコウ・ビンコウ)=長江の支流で、岷江と金沙江が合流し長江が始まる」、「戦国時代末期に秦によって建設された水利施設・都江堰(トコウエン)があり、岷江の水を成都平原方面へ分水して、水害防止・水運・灌漑などに用いられる。都江堰は、現在まで2000年以上にわたり成都平原の広大な農地を潤す水路網の起点」
「紀元前3世紀
戦国時代の
秦国の
蜀郡の
太守-李冰(リヒョウ)
が、
洪水に悩む人々を救うために
紀元前256年~紀元前251年
にかけて原形となる
堰(堤防・堆=タイ・ツイ)を築造」
↓↑
堆=TIE=(一ヶ所に渦高く)積む
↓↑ 積み上げる・積み重ねる
一群、一山、一塊(ひとかたまり)
碓(うす・タイ)=石臼・碓・舂
臼から杵=女から男 に言い寄ること
物事が逆さまな比喩
↓↑ 臼と杵=男女が和合する比喩
tie(タイ)=ゲーム、試合で
↓↑ 同点になる、引き分けること
紐、綱などを
↓↑ 結ぶ・縛る・結わえる・括る
tie=チエ=知恵・智慧・・・
↓↑
「寨=塞・砦・塁
fort=台場・砲台・防塞・要塞・堡塁・駐屯地」
↓↑
「塙=かたい・はなわ・カク・コウ
かたい土・石の多いやせ地
土地の小高くなっている所・・・台地
ばん・姓氏に用いられる
↓↑
塙 直之=塙 団右衛門
(ばん だんえもん・長八・鉄牛・直次・尚之)
変名は「時雨(しぐれ・ジウ)左之助」
豊臣秀吉の家臣で
伊予国松山の大名となった
加藤嘉明に召し抱えられた
慶長二(1597)年七月十六日
漆川梁海戦(シツセンリョウのカイセン
巨済島の海戦)で活躍し
敵の番船三艘を八名で乗っ取った・・・
磽(コウ)=はなわ・山のさし出た所」
「福島県東白川郡-塙-町」
対義語は「圷(あくつ・阿久津)=川辺の低湿地帯」
「茨城県東茨城郡にかつて-圷-村が存在」
↓↑
「畝(ほ・ムー)・簡体字は亩」は、中国の伝統的な面積の単位で、6000平方尺(60平方丈)」
↓↑
「汶水=岷江」
「汶=氵+文(亠乂)」=「ブン・モン」・・・
氵(サンスイ)の文(ブン)・・・汾(氵+分)?
水の文(亠乂=音刈)・・・
水の紋様(渦巻き・波形)か、水の音か・・・
ナゼ、「汶川」の「汶」が「汚れ・穢れ・辱め・恥辱」なのか?・・・「汶」は「川」との熟語、合字だから「汚れを清める」と云うコトなのか・・・?
↓↑
「汶=異体字→岷(山民)
=渂(氵日文)・・・日=Θ
Θ=θ(テータ・シータ
希語: θήτα・theta)
ギリシア文字の第8字母・数価は9
記号として「角度」、「凡その数字」
=𣶌(氵氏攵)
攵(ノ一乂)=攴(ト又・上乂)
ハク・ホク・ボク・敲(たた)く
=けがれ・はずかしめ
ブン・ボン・モン・ビン・ミン・フン
ーーーーー
1945年乙酉(庚・ ・辛)
0008月甲申(己・壬・庚)
0009日庚戌(辛・丁・戊)・・・方合金(辛)
0011時辛巳(戊・庚・丙)
ーーーーー
2017年丁酉(庚・ ・辛)
0008月戊申(己・壬・庚)
0008日丁卯(甲・ ・乙)・・・三合木(乙)
0022時辛亥(戊・甲・壬)
0020~庚戌
ーーーーー
2008年戊子(壬・ ・癸)
0005月丁巳(戊・庚・丙)
0012日壬子(壬・ ・癸)・・・子-害-未
0014時辛未(丁・乙・己)
ーーーーー
・・・???・・・塙 保己一(はなわ ほきいち)、延享三年五月五日(1746年6月23日)~文政四年九月十二日(1821年10月7日)・国学者・幼名は丙寅日にちなみ「寅之助(とらのすけ)」、 失明後に「辰之助(たつのすけ)」。また、「多聞房(たもんぼう)」とも名乗った・・・
「胡蝶の夢」も、「邯鄲の夢」も視れなくなる時・・・
・・・「大日本帝国(Empire of Greater Japan・Greater Japanese Empire・The Empire of Japan・Imperial Japan・the Japanese Empire)の延長」の「敵打ち・かたき討ち(vengeance・ revenge・retaliation)」を「N・K」、「N・C(Democratic People's Republic of Corea?)」がやってくれるらしい?・・・キッと日本列島と大陸、半島の「支配階級」は「夏・商・周・秦・漢・三国時代(魏呉蜀)・晋・十六国・南北朝・隋・唐・五代十国・宋・遼・夏・金・元・明・後金・清」は古代の昔から「親戚」関係なんだろう・・・「敗戦大日本帝国人民のアメリカ帝国、植民地主義からの解放」?・・・有難迷惑なんだか、どうなんだか?・・・「戦争見物の野次馬(被支配者)」は弁当持参で「関ヶ原」を見物したいだけ・・・コトが終わったら新しい暴力支配者にいかに対処すべきか・・・兎に角、花火は美しく、かつ凄い爆発力のモノだった「エニウェトク環礁の島は消滅し、クレーター」が残った。そして放射能汚染、空からは黒い雨も・・・
「1952年11月1日、人類初の水爆(水素爆弾(hydrogen bomb)、熱核兵器(thermonuclear weapon)のマイク実験」、
「1952年11月16日の2回目のキング実験」
も「巨大花火大会」のように見物・・・
今度の「戦争当事者の火遊びの後」は蒸発して存在していないだろう・・・
https://www.youtube.com/watch?v=TUUUe9oCCUI
ーーーーー

・・・この21世紀の人類に、「カミ様」が中東、ヨーロッパでは意留化、意名異化で戦争・・・寿命に限界がある人間しかイないと理解したのか、他人の生殺与奪こそが「生きている人間」の至高で最高のモノと自覚したらしいエゴなオボッチャンと、エゴなオジッチャンのハナビ大会、いい加減にしてくれョなッ・・・
地球自体が「人類消滅、reset滅亡」を望んでいるって云う時期に、「金」と「トランプ(博打カード)」とは象徴的ではあるな・・・
生きている間のハナのキノウ・・・
・・・2017年08月11日金曜日・・・「唇歯(シンシ)=唇(脣・くちびる)と歯・・・互いに利害関係が密接であること・・・「中国の晋が虢(カク)の国を攻めるときに虞の国は晋に通過する許可を出したが虞の国と互いに助け合う関係にあった虢(カク)の国が滅びると虞の国も滅びた・・・「カク(核)の国」の滅亡は当然「虞国」にも及ぶ・・・「虞(おそれ・グ)=虍+呉・虍+吳・虍+吴」=「不虞・虞犯・憂虞」の国の「おそれ・心配」・・・「虞犯者=日常の言動やその性格、環境などから判断して、将来、悪行を犯す懼れのある人物」・・・
[
「虞美人草=雛罌粟=ひなげし=コクリコ(フランス語)=アマポーラ(スペイン語)=雛芥子=ポピー(poppy)・シャーレイポピー (Shirley poppy)=「別れの悲しみ・妄想・慰安」=項羽(コウウ)の愛人が漢軍に包囲され自決したときの血から生じた花」・・・「フランスの国旗の赤を表す花の色・リメンブランス・デー=11月11日=1918年の11月11日に第一次世界大戦の講和追悼記念式典日・イギリス連邦の国々の戦没者の象徴」・・・
「虍(トラかんむり)=虎」→「雨(アメかんむり)のような筆順?」・・・
・・・日本上空のミサイル飛来を許すのか?・・・
↓↑
「唇歯輔車(ホシャ)『春秋左氏伝・僖公五年』」
「唇亡歯寒(シンボウシカン)」
一つが駄目になると
もう一つも駄目になるような
非常に深い関係のこと
「輔車」=車の添え木と車の荷台
頬の骨と下顎の骨
唇と歯や、頬の骨と下顎の骨のように
互いに助け合うことによって
互いに存続できるような関係
「運命共同体」・・・
↓↑
2017年丁酉(庚・ ・辛)
0008月戊申(己・壬・庚)
0011日庚午(丙・ ・丁)
↓↑
2017年丁酉(庚・ ・辛)
0008月戊申(己・壬・庚)
0015日甲戌(辛・丁・戊)・・・方合金(辛)
苦労せずして権力を握った「ボッチャンのN・C」が「損得勘定(感情)」のみで動くとは思われない・・・「トランプ」がアキンドなら「損得勘定」で動くだろう・・・
ーーーーー
唐王朝・玄宗皇帝時代
↓↑
虢国夫人(カクコクフジン)
生年不詳~至徳元載(756年)
唐代玄宗朝の妃である
楊貴妃の姉
姓は楊、名は不詳
楊貴妃の栄誉の恩恵を受け
豪奢に ふるまったが
楊貴妃の死後殺された
↓↑
虢(カク)=爪+寸+虎
↓↑ 古代中国の都市国家
姫姓で
周の
季歴の子で
文王の弟の
虢仲
と
虢叔
↓↑ を祖とする
「武士彠(ブシカク・ブシヤク)」
577年~635年
隋末~唐初にかけての政治家
武則天の父
字は信明
本貫は并州-文水県・・・「汶水県」
財産家(木材業)の家に生まれ
隋末に
鷹揚府隊正
に任ぜられた
↓↑
蜀州司戸の
楊玄淡の二女(三女?)
父が死に
代わりに
楊国忠が家を守っていた時
私通していた・・・
裴氏
に嫁ぎ、子の
裴徽
と
娘を一人を生んだ
楊貴妃が
寿王・李蒯の妃になった
開元二十三年(735年)
から貴妃に冊された
天宝四載(745年)までに
夫の裴氏に死なれ、寡婦となり
兄の
楊銛
従兄弟の
楊褧
姉妹とともに
蜀州から都・長安に移った・・・
虢国夫人は
他の姉妹同様に優れた容貌を持ち、頭の回転も早かった
この頃
又従姉妹の
楊国忠の来訪を受け
屋敷に泊まらせ、玄宗に推薦した
天宝七載(748年)
虢国夫人に封じられ
姉が
韓国夫人
妹が
秦国夫人
に封じられ
毎年千貫を化粧代を支給
虢国夫人は美貌で
化粧をせずに玄宗の前に出
宮廷にも相変わらず出入りして
姉妹たちとともに
楊貴妃の
琵琶の弟子になった・・・
子の
裴徽
は
延光公主と婚姻
楊国忠との密通の噂は絶えず
韓国夫人と三人で馬に乗りながら
背後の百人以上の宮女に灯りを持たせ
ふざけあいながら参内した・・・
杜甫の詩にも
「虢国夫人」や「麗人行」に唱われている
(虢国夫人は別人作説あり?)
張萱の
『虢国夫人遊春図』
は彼女を題材にしたもので
男装をして馬に乗り
列の先頭を行く彼女の姿が描かれている
↓↑
楊一族の中で最も豪奢と横暴
官人の家に入り込み
家を壊して新しい自宅を造り
隅っこの土地だけを返した話や
蟻(あり・くろい・ギ)=虫+義
↓↑アント(ant)
ドイツ語=アーマイゼ(Ameise)・・・阿毎是・甘いぜ
蛙阿毎是
フランス語=フールミ・・・・・・・・附得留味
フルミ・・・・・・・・・附留味
フォルミ=fourmi・・・・附嗚留未
↓↑イタリア語=フォルミーカ(formica)・附嗚留未異化
や
蜥蜴(とかげ・セキエキ)=とかけ(止加介)
↓↑ 蝘蜓・石竜子
リザード(lizard)
理挿阿土
蜊砂(挿)蛙(鴉)説
「蜊=浅蜊(あさり・センリ)」
「蝲蛄=ざりがに・シコ
砂利蟹(可児)
蜊蛄・躄蟹
Crayfish(クレイフィッシュ)」
フランス語 crevice(クレヴィース)
crab(クラブ)
イタリア語=ルチェルトラ(lucertola)
↓↑ 留知得留訳等(虎・彪・寅)
が出られないほどの
精緻な屋敷を建てた・・・
天宝十二載(753年)頃・・・・天の宝の十二を載(の)せる
楊国忠
が自邸で人事を行った際に
名を呼ばれた者の容貌がよくないと
簾ごしに姉妹たちと嘲笑した・・・
↓↑
天宝十四載(755年)
安史の乱の勃発
至徳元載(756年)
玄宗の
長安出奔後
先行して
陳倉に赴いていたが
楊国忠
韓国夫人
楊貴妃
の死を聞き
逮捕にきた県令を
反乱軍と思い逃げた
裴徽と娘
楊国忠の妻の
裴柔を殺して自殺したが
死にきれずに捕らえられた
「国のものか?賊か?」
とたずねると
「どちらとも言える」
と答えが返ってきた・・・
↓↑
韓国夫人
楊玄淡の長女
崔峋に嫁いで
韓国夫人に封じられた
皇子、皇孫の婚姻は
韓国夫人
や
虢国夫人
に賄賂を贈れば思い通りになった・・・
至徳元載(756年)
楊国忠が殺された後
陳玄礼率いる兵士たちに殺された
↓↑
秦国夫人
楊玄淡の三女
楊貴妃の姉
(排行は八番目)
柳澄という男に嫁いでいたが
死に別れ
子は
柳鈞といった
秦国夫人に封じられる
天宝六載(747年)
彼女が宮中に侍女の
明珠を連れてきたことが
楊慎矜失脚の原因の一つとなった
玄宗と楊貴妃が主催した演奏会において
唯一の聞き手となり
300万銭の祝儀を出した・・・
天宝十三〜十四載頃に死去
↓↑
楊氏五家
楊銛、楊褧、韓国夫人、虢国夫人、秦国夫人
の五家で
楊氏五家
楊国忠を含めて、
楊氏六家という場合もある
彼らの邸宅には
四方からの賄賂
玄宗からの贈り物の使者が絶えず訪れ
彼らの生活は奢侈を極めた
ーーーーー
・・・ハナの命は短くて・・・生きている間こその人生・・・
忍者がえし・・・ミズのジョウ・・・
・・・「つつみ=堤・堿・陂・坡・塘・包」・・・漢字を検索して居て、偶々、目に就いたので調べていたら・・・1619(元和五)年、福島正則、本拠広島城の無断修築をめぐる武家諸法度違反で所領を没収され、信濃川中島4万5000石に移封」、「徳川家康重臣・本多正純の謎の失脚、語り継がれる宇都宮釣り天井事件」、「本多正純=江戸幕府の老中・下野国小山藩主、同宇都宮藩主(第二十八代宇都宮城主)・本多正信の長男で正信系本多家宗家二代・徳川家康の側近・徳川秀忠の代に失脚」・・・
アマり面白くもないYouTubeの映画、「宇都宮釣り天井の謎 1996.4.30ABC松竹」、「大型時代劇スペシャル・市川染五郎・南野陽子・田村英里子・宇津井健・平幹二朗・花沢徳衛・石橋蓮司・蟹江敬三・真弓明信(阪神)・ 丹波哲郎・金田龍之介」などの懐かしい役者名が出てきた・・・
で、「忍者がえし・水の城」をみてしまったが、みんな呆れるほどの「大根演技」・・・
「二代将軍徳川秀忠の時代、信濃に追放された福島正則の世継・正勝が、館に侵入した忍者に殺され、暗殺の黒幕は福島家の没落を計る本多正純。正勝の近習・高月彦四郎は敵襲に備え、館を改築、"水の砦"を建設。敵方は執拗に来襲。正則は本田を失脚させるため、将軍秀忠の暗殺を決意、彦四郎が豊臣秀吉の実子であることを打ち明ける(以上、時代劇専門チャンネル広報資料より引用の更なる孫引・第5回時代小説大賞受賞作品のドラマ化」・・・???
人間関係って、複雑で奇妙、奇天烈・・・以下、ボクが「元和五年=1619年」に混乱し、検索した記録を添付したモノ・・・
ーーーーー
元和五年=1619年・・・日本年号
↓↑
「元和郡県志(ゲンナグンケンシ)」
元の
和(倭・やまと)の
郡(訓)の
県(懸)の
志(個々賂指示)?
↓↑
「元和郡県志」は
唐代の地理書
現存する唐の全国的な地誌としては
敦煌から発見された残巻を除くと唯一のもの
宰相の
李吉甫(リ-キッポ・李 徳裕の父)
が撰述し
元和八年(813年)・・・元和八年(813年)
憲宗
に進上
はじめの書名は
『元和郡県図志』
47の鎮ごとに図が附属していたが
図は後に失われた
もと40巻(および目録2巻)
うち34巻が現存
↓↑
元和郡県図志・巻第1~40・李吉甫 撰
序
孫星衍
巻第19,20,23,24,35,36を欠く
唐装印記
支那銭恂所有銭恂旧蔵附
元和郡県
図志闕巻逸文
元和郡県補志1~9(厳観輯)
巻第1~4・関内道1~4
巻第5~11・河南道1~7
巻第12~15・河東道1,3~5
巻第16~18・河北道1~3
巻第21~22・山南道2-3
巻第25~30・江南道1~6
巻第31~33・劒南道上,中,下
巻第34,37~38・嶺南道1,4~5
巻第39~40・隴右道上,下
↓↑
元和郡縣圖志
作者 李吉甫
成書年代 唐
版本 暫缺
↓↑
地理志・季漢書
巴郡
後漢の頃
巴東、巴郡と合わせて巴郡
興平二年
趙韙の献言により
巴を分割
墊江以北を巴郡
龐羲を
太守に任じて
安漢・・・・・・安漢→安韓→安加羅?
にて治めさせた
江州より臨江にいたるまでを
永寧郡に
朐忍から魚復に至るまでを
固陵郡とした
後、
建安六年
魚復の・・・魚の復(かえる・かえす・また・フク)
蹇胤の提案で
巴を巴西
永寧を巴郡
固陵を巴東郡に改名
巴を三巴と呼ぶ
巴郡は
東南は涪陵に接し
北は巴西、広漢に接す
東は巴東、西は江陽に接す
↓↑
巴子の時代
江州を治所
或いは
墊江、平都を治所とすることもあった
沮(低湿地)で牧畜が行われ
沮は東突薢の下にある
枳には先王の諸陵墓がある。
江州
郡治
漢の時代
郡治は
巴水の北に置かれ
巴水北の旧城には
柑橘官が置かれていた
後に、南岸に移った
李厳は城を修築し
これ以降、
長く郡治は
李厳城に置かれ続けた
李厳の江州城
県の北には
稲田
茘枝園
があった
大姓は
波
詵・・・詵=言+先=とる・シン・セン
詵詵(シンシン)=数が多い
多くの人が集まるさま
毌、謝、然、蓋
楊
白、上官、程
常・・・常陸=ひたち=日立
常識=ジョウシキ=定式
↓↑
墊江
江州の西北四百里
諸水の交わるところ
桑畑があり
養蚕
牛馬を産
大姓は
黎、夏、杜
の三姓
↓↑
臨江
枳の東四百里にあり
朐忍と接している
王莽
が
監江と名を改め
後漢に至り
臨江に戻った
↓↑
塩官があり
監、塗
二渓があり
一郡の仰ぐところ
富豪の家にも塩井があった
塗渓は県の東南八十里にある
塗山より来ている
東晋の頃に
臨江の全ての
塩井を
官の支配下に入れられていなかった
大姓は
厳・・・・・・・・・厳島(いつくしま)?
甘、文、楊、杜・・・甘(あまい)?
文(あや・ふみ)?
↓↑
羅憲が永安に包囲された時
囲みを突破した参軍の
楊宗
呉に仕えた
甘寧は・・・・・・・甘寧・・・安寧・丁寧・叮嚀?
この臨江の大姓
↓↑
枳=木+只(口八)・・「からたち・キ・シ
木の名
蜜柑(みかん)科の落葉低木
橘(たちばな)に似て
棘(とげ)が多く、秋に実をつける
未熟の実は薬用
江州の東四百里にあり
涪陵水の合流点
土地は痩せているが
人士は多かった
大姓として
章、常、連、黎、牟、陽・・・・連=むらじ
陽=煬・・・「煬帝」
郡の冠族であった
↓↑
平都
季漢
が置いた県
延熙・・・年号
↓↑ 三国時代、蜀の君主
↓↑ 劉禅の治世で使用
元号238年~257年
延熙十二年
麴山の戦い
曹爽の失脚
夏侯霸の来降
247年丁卯
魏=正始八年 少帝・曹芳
蜀=延熙十年 後主・劉禅
呉=赤烏(セキウ)十年 大帝・孫権
二月
庚午の日(一日・朔、日食)?
↓↑ ↓↑
247年丙寅(己・丙・甲)?
002月辛丑(癸・辛・己)?
003日庚辰(乙・癸・戊)?
↓↑ ↓↑
247年2月1(己卯)日・月曜日・先負
神功皇后47年1月9日
庚辰の日(247年2月2日)火曜日・仏滅
↓↑ ↓↑
正始八年春二月朔
西暦247年3月24日(ユリウス暦)の日食
が三國志と晋書に記録
「正始八年春二月朔
日有蝕之
(『三國志』巻四 魏書四「三少帝紀」)
(『三國志』巻十四「程郭董劉蒋劉伝」)
是時,曹爽專政,丁謐,眷菫等輕改法度.
會有
日蝕變
詔羣臣問其得失
濟上疏曰
「昔大舜佐治
戒在比周=周公輔政
慎于其朋=齊侯問災
晏嬰(アンエイ)
・・・晏=日+宀(ヽ冖)+女
嬰=貝(目ハ)+貝(目ハ)+女
對以布惠=魯君問異
臧孫答以緩役
應天塞變,乃實人事
↓↑ ↓↑
247年丁卯(甲・ ・乙)
003月癸卯(甲・ ・乙)
024日庚午(丙・ ・丁)水曜日・友引
「西暦247年3月24日の日食は
北九州でも深食
北九州市や北九州沿岸の島では
皆既の可能性
(国立天文台報 第14巻・15~34(2012))」
↓↑ ↓↑
西暦 247年(ユリウス暦)=卑弥呼が
狗奴国王
卑弥弓呼と戦う
西暦 247年(ユリウス暦=魏志)
神功皇后47年閏2月1日
↓↑
魏の正始十年正月
司馬懿・・・懿徳天皇=第四代天皇
大日本彦耜友尊
(おおやまとひこすきとものみこと)
安寧天皇の第二皇子
の政変で
曹爽
何晏(カアン)らは族滅
↓↑・・・何の晏?
後漢の大将軍、何進の孫
字は平叔
母の尹氏(曹操の妾)
曹操の娘
金郷公主を娶った
↓↑ 晏=日+宀(ヽ冖)+女
年間に廃止
大姓は
殷、呂、蔡氏
↓↑
楽城県
州の西三百里にある県
季漢が置いたが
延熙十七年
↓↑ 第二次北伐
↓↑ 張嶷の帰還
李簡の降伏
延熙十七年春正月
姜維が成都へ と帰還
越嶲太守
張嶷が十五年間の任を終えて
成都に帰還
盪寇将軍を拝命
↓↑ 北伐の是非についての議論
に省かれる
↓↑
陽関
江州の東
塗山に置かれた関
劉備が要衝として設けた
東に銅鑼峡
劉備は関を置いて守りとした
督江州
訒芝
は、
この陽関に駐屯
ーー↓↑ーー
陳寿
『三国志』
(訒艾伝
鍾会伝
後主伝
諸葛亮伝
姜維伝
訒芝伝)
常璩
『華陽国志』(蜀志)
房玄齢
『晋書』(地理志上)
顧祖禹
『読史方輿紀要』(巻六十七、七十三)
↓↑
李吉甫
『元和郡県図志』(巻三十二)・・・元の和の郡の県の図志?
↓↑
酈道元
『水経注』(巻三十三)
↓↑
郫県で出土した
景耀四年製の銅弩機には
「十石機」という銘が刻まれ
季漢で 用いられた強弩が十石の強さであった
李吉甫
『元和郡県図誌』(巻三十三)・・・元の和の郡の県の図志?
曹操は、
杜濩を巴西太守
朴胡を巴東太守
袁約を巴郡太守
にした
ーー↓↑ーー
元和 (漢)=後漢の章帝
劉炟時代の元号
(84年~87年)
元和 (唐)=唐朝の憲宗
李純時代の元号
(806年8月~820年12月)
元和 (日本)=後水尾天皇時代の元号
(1615年7月13日~1624年2月30日)
ーー↓↑ーー
元和偃武(エンブ)=元和一(1615)年
大坂の陣が終り豊臣氏の滅亡後の平和
偃武=武器を伏せること・軍事衝突の終了
周書・武成篇の
「王来自商、
至于豊。乃偃武修文。
(王
自(おのずから・みずから)
商(あきない)
来たり
于豊に至る・・・・・于
乃ち武を偃(ふ)せて文を修む」
武器を偃(ふ)せて武器庫に収める事
偃(エン・ふす)=イ+匚+日+女
ふす(臥)
たふる、たふす(僵・仆)
なびく、なびかす(靡)なびき伏す
したがふ(服)
いこふ(息)
やすむ(休)
ふせる(伏・臥)
やむ(止・已)
おごる(驕)
せく・ゐせき(堰)・・・堰=十一匚日文
かはや(廁)
むぐらもち・どぶねずみ・もぐら(鼹)
↓↑
「元和郡県誌」には
「梁は汶川県を置き、
県は西の汶水=岷江により名を為す」
「汶水= 岷江(ミンコウ・ビンコウ)
=長江の支流で、岷江と金沙江が合流し長江が始まる」
「戦国時代末期に
秦によって建設された
水利施設・都江堰(トコウエン)があり
岷江の水を...
ーー↓↑ーー
レファレンス事例集(長野県)より抜粋、添付
県立長野図書館
↓↑
『長野県上高井郡誌』(上高井郡教育会編 千秋社
1999上高井郡教育会刊・1914( 大正3)年の復刻)
「高井村 福嶋城址」の項目に
「大字高井字堀之内にあり。
元和年中、・・・・・・・・・元の和の年中?
福嶋正則の築く處なり。
始め回字形を為して、
四壁に高塁を築き
塁上に...
↓↑
福島正則が
元和(げんな)元年・・・・・・・元の和の元の年?
信州川中島へ
改易配流された際
居住した屋敷の
場所
形態
答
『日本歴史地名大系 20 長野県の地名』
(平凡社 1979)[N290.3/54]881pに
「福島正則屋敷跡」の項目
現在の
上高井郡高山村高井堀
形態
『長野県指定文化財調査報告 第5集』
(長野県教育委員会編・刊 1974)[N709/24/5] 20pの
「福島正則屋敷跡」に
「この史跡は
福島正則がその晩年の
↓↑
元和五年~寛永元年まで約五年間・・・元の和の五の年?
↓↑
幕府の監視のもとに配流に近い生活をした屋敷で
・・・その規模は県道須坂山田線に添い
東西一〇四、五メートル(五七、五間)、
南北七二、七メートル(四〇間)、
面積七六アール(七反六畝)
もと四方に高い土塁を築き
その上に松・竹・桜等を植え、
塁の外には空堀をめぐらしてあった」
↓↑
福島正則
が
高井郡へ改易されたのは
元和五年=1619年・・・・壱千陸百壱拾玖のネン
↓↑
『長野県百科事典 補訂版』
(信濃毎日新聞社開発局出版部編
信濃毎日新聞社 1981)[N030/2A]
『長野県歴史人物大事典』
(神津良子編 郷土出版社 1989)[N283/13]
などで
福島正則
『長野県百科事典 補訂版』(前掲)693pに
「1619(元和五)年・・・・・・壱拾陸、壱拾玖
武家法度にそむいたかどで
所領は没収
津軽4万5000石に転封を命ぜられ
改めて
越後
魚沼郡に2万5000石
高井郡に2万石を給せられた
配流に近い生活を
高井野の居館に送り」
「高井野
『日本歴史地名大系 20 長野県の地名』(前掲)881pに
福島正則屋敷跡の項目
現在の上高井郡高山村高井堀の内
『長野県上高井郡誌』
(上高井郡教育会編 千秋社
1999上高井郡教育会刊
1914(大正三)年の復刻) [N214/89]731p
「高井村 福嶋城址」の項目に
「大字高井字堀之内にあり
元和年中・・・後水尾天皇
将軍は徳川秀忠、徳川家光
慶長の後、寛永の前の日本年号
1615年~1624年の期間
福嶋正則の築く處なり
始め回字形を為して
四壁に高塁を築き
塁上に
松柏桜等を植ゑ
塁外に空濠を鑿ち
門外に馬場を構へたり
東西七十間南北四十間あり」
とある・・・
改易の年
元和五年=1619年
↓↑
・・・「大久保長安(慶長十八年(1613年)四月二十五日死亡」後の事件は「大久保忠隣改易」も含め家康の意志ではなく「本多正信・正純」の讒言・・・「福嶋正則(元和五年・1619年)」の改易も・・・?
ーー↓↑ーー
紅花染めの用いられた正倉院染織品
唐代編纂の
『大唐六典』
『通典』
↓↑
『元和郡県図志』・・・元の和の郡の県の図の志
↓↑
宋代編纂の
『新唐書』では
唐代中国内の
紅花・・・紅花=キク科の越年草・高さ約1メートル
↓↑ 葉は堅くてギザギザ
互生
夏、アザミ(薊・阿左美)に似た頭状花
鮮黄色から赤色に変わる
花を乾かしたものを
紅花(コウカ)=婦人薬・口紅や染料の紅
赤い色の花・ベニバナの花を乾燥させたモノ
漢方=腹痛・月経不順・浄血などに用いる
紅花緑葉=紅色の花と緑色の葉
彫漆(チョウシツ)技法の一
朱漆と緑漆を交互に塗り重ね
朱漆の層に
雅称=末摘花(すえつむはな)・・・源氏物語
紅色染料や食用油の原料
エジプト原産
日本にはシルクロードを経て
↓↑ 4~5世紀ごろに渡来
の産地として
興元府(梁州)、蜀州、漢州、霊州、青州が挙げられ
唐の領土内において
紅花は広範に栽培されていた・・・
↓↑
青森県立図書館
青森県教員録
明治十三年十二月届 木村良臣
1881(国立国会図書館)
『青森県職員録 』
青森県(国立国会図書館)
1936(国立国会図書館)
『七和村誌 : 御即位記念』
青森県北津軽郡-七和村・・・七和村?
1928(国立国会図書館)
『西津軽郡誌』 島川観水編
青森県西津軽郡 1916(国立国会図書館)
「青森県鉱泉誌」
青森県警察部衛生課 1920(国立国会図書館)
『青森県誌:県史名勝旧蹟現況』 西田源蔵編 成田書店
1926(国立国会 ...
↓↑
『福井県史』通史編3 近世一
若狭での本格的な地誌は
歌人でもあった
小浜藩士
牧田忠左衛門近俊が
元禄六年頃に著した
「若狭郡県志」である
「雲の浜聞見録」は、
見聞記的で、
江戸において召し抱えられた
藤林誠政が
享和元年(1801)から翌年にかけて
藩主
酒井忠貫
に従って小浜を訪れた折に見聞した記録
ーー↓↑ーー
晏(やすらか・おだやか・おそい・アン・エン)
「家の屋根・家屋」
と
「両手をしなやかに重ねひざまずく女性」
の合体象形・・・
(家の中で 女性がやすらぐ、やすらかの意)
「穏やかな日・晴れ
太陽が西に入って落ち着く夕暮れ」
ーー↓↑ーー
「晏嬰=晏平仲」とも呼ばれ、「質素倹約を心掛け、国の繁栄の為のみ」に尽力(?)する私心の無い姿から、「晏子」の尊称で呼ばれる・・・字(あざな)は平仲・・・霊公、荘公、景公の三代に仕えた・・・「斉国の宰相」、「莱の夷維の人」・・・「越石父(エツセキホ)」って?「石の父を越える」・・・
越石父は賢人であったが、
囚人(奴隷)の身となっていた
晏子が外出した途中で
越石父と遭遇し
乗っていた
三頭立て馬車の
左の馬を売って、
越石父の身を自由にし
馬車に同乗させ、帰宅したが、
越石父には挨拶もせずに部屋に入っていった
コレを越石父は無礼と云って
奴隷に戻るとゴネタ・・・?
↓↑
晏子は旅行途中で
囚人の越石父と出会い
彼の罪を
馬車の
左の馬の添え馬で贖罪し
越石父を自由にの身にし
越石父を同乗させ帰宅したが
越石父には
挨拶もせずに奥へ入ってしまった
コレを
越石父は晏嬰の無礼であると怒り
奴隷に戻るとゴネタ・・・?
非を悟った晏嬰は
石父を上客としてもてなした?・・・
↓↑
・・・厭なヤツだけれど、儒学者よりは使い道があったんだろう・・・
ーーーーー
・・・???・・・
・・・8月15日・・・八月十五日・・・捌肉拾(足)五(語・誤・漁)日・・・?
・・・「2017年8月12日ANA機緊急着陸。1985年日航機墜落事故(8月12日18時56分に、群馬県多野郡上野村の御巣鷹の尾根に墜落)と同じ日時、同じ羽田発伊丹行き・全日空ダクト事故」、「全日空37便(ボーイング777-200型・777-200ER・他機との識別目安は6つの車輪が左右の主脚に付いている)、乗客乗員273人・羽田空港を離陸して上昇中の12日午後18時半ごろ、機内の気圧が低下したことを示す警報が作動。機長が客室の乗客に酸素マスクを出し、20分後に羽田空港に緊急着陸」・・・人生でワカランことがワンサカだけれど、医者が「民族主義者、国家主義者」になったらいきつく先は「731部隊でメロンのデザート」・・・
「ブラックボックス」・・・以前にも書き込んだが、今回は自分自身の知識の貧困さをワラッタ・・・
ETVの「black hole」、「ブラック-ホール(ウイッキペデアでの説明では、black hole=極めて高密度かつ大質量で、強い重力のために物質だけでなく、光さえ脱出することができない天体)」の再放送をやっていた。
「光」も「物質」だけれど、もし「物質」でなければナンなんだか?・・・ダレかに訊いてみたい。それに「重力波で空間が歪む」、これも訊いてみたいねッ、「空間のナニ」が「歪む」のか?・・・
そもそも「空間」ってナンなんだか?・・・
「光はブラックホール(black hole)より出られないため真っ暗で、周囲の光が重力でねじ曲げられている」・・・
「black hole」で「ねじ曲げられている」のは「ヒカリ」だけじゃぁないだろうが、そもそも「光がねじ曲げられている」から「Black」になっているのか?・・・
それに「ホール」であるが、日本語で「穴(あな)・くぼみ(窪み)・へこみ(凹み)」であるって?・・・知らなかったョッ、「ホール=穴」が日本語だなんって・・・英語だろうッ?・・・
「hole=opening=slit(細長い)=eyelet(ひも穴・巣穴)・burrow(ぽっかりあいた穴)」・・・
そぅかッ、スペル違いだ・・・
「hole
=ホール
=hall(入り口の広間・玄関・ロビー・the front、or the back hall of a house=家の表、裏玄関・建物内の廊下、通廊、通路・人の集まる大きい部屋、建物・大広間・集会場・講堂、集会場、公務などの会館、公会堂、結社などの事務所、本部・地主、荘園領主の邸宅・賭博場、玉突き場)
=ホール=whole(全体の・すべての・全部の・all・entire)」・・・
「all や whole あるいは entire
all my entire life
all the whole day」・・・
「whole(形容詞)
all(形容詞・しばしば副詞句になる・限定詞)」・・・
「Not at all.」って?・・・
ドウ致しまして、どうってコト、たいしたコトじゃない、気にするコトじゃぁないから・・・本当のところは「Not at all.」って?・・・それがスベテじゃぁナイから、ョッ、気にすんなッ・・・
「Not at all. Don’t worry.」・・・
「片仮名、平仮名」を「表音の文字」ではなく、「表意の文字」で訓(ヨム)と、どうなるのか・・・?
ーーーーー
安以宇衣於・・・安らぎは宇(天蓋)の衣を以(もっ)て
加機久計己・・・加える機(はたおり)に於いて久しく己を計り
左之寸世曽・・・ひだり、これを寸(はかり)世のか曾(さなり)
太知川天止・・・おほき知るは川の天を止め
奈仁奴祢乃・・・いかん、仁のヤッコ、祢(みたまや)、
乃(なんじ・すなわち・いまし・おさむ・の
アイ・ダイ・ナイ)
波比不部保・・・なみを比べるも、部を保(たもつ)コトならず
末美武女毛・・・すえの美、武の女(むすめ)は毛(人)
也 由 与・・・由縁を与える也
良利留礼呂・・・良い利は礼と呂に留める
和為 恵遠・・・和は恵(めぐみ)は遠くに為す
為す和(なごみ)は、遠くに恵(めぐ)む
无(ない・ブ・ム)
・・・???・・・
↓↑
以呂波耳本へ止
千利奴流乎和加
餘多連曽津祢那
良牟有為能於久
耶万計不己衣天
阿佐伎喩女美之
恵比毛勢須
(金光明最勝王經音義)
ーー↓↑ーー
かるた(歌留多・加留多・嘉留太・骨牌)=カルタ
ーー↓↑ーー
「月夜に釜を抜かれる」・・・抜く?・・・確かに「抜き取る」と云うコトバがあるが・・・
・・・「釜自体」が何処(場所)から「抜かれる」のか?
・・・「釜の中」の何(煮物)が「抜かれる」のか?
・・・「カマ」の中のナニが「抜かれる」のか?
・・・「蒸気」、「火力」、「薪(まき)・石炭(すみ)」?
遣り抜く・虐め抜く・苛め抜く・追い抜く・水を抜く・守り抜く・攻め抜く・息を抜く・空気を抜く
刺さっている物を引き抜く・相手を出し抜く・最後までやり抜く・・・「抜く=盗む」・・・「釜を盗む」って?
↓↑
「かま=寸法を測る道具」
「かま(釜)=かま(窯・竈)
↓↑ 飯を炊いたり
湯を沸かしたりするための器具
金属製または土製で
鍋よりも深く、腰に鍔 (つば) がある
古くは、「まろがなえ」と云った
「はがま」
茶道で、湯を沸かす器具
茶釜・湯釜
↓↑ 火山の噴火口
「かまと=魚の鰓(えら・顋)・・・鰓=魚+思
↓↑ 顋=思+頁
の下の
胸鰭(むなびれ・胸螧)
のついている部分
↓↑ 脂肪を含み、美味」
「鎌=植物を刈るための農機具」・・・鎌=金+兼
「釜=鍋に似た形の加熱調理器具」・・釜=父+金
「窯=内部を高温にし・・・・・・・・窯=宀+儿+羊+灬
何らかの加工を行うための設備」
「竃=加熱調理の際に火を囲うための設備」
「罐=ボイラー」
「カマ=東日本旅客鉄道(JR東日本)の
↓↑ 蒲田駅および蒲田電車区
四国旅客鉄道(JR四国)の高松駅
および
↓↑ 高松運転所を表す電報略号」
「カマ=酸化マグネシウムの俗称」
「カマ=蒸気機関車(または機関車全般)を指す用語」
「マ(ドンカマ)=ドンカマチック」
「カマ=オカマの略」
カマを掘る→追突事故」
「かま=かまぼこの略」
「かま=アラの内で
魚の鰓蓋(えら・シガイ)から
胸鰭(むなびれ)までの部分」
ーー↓↑ーー
「気を抜く」
「軽はずみ・手落ち・粗忽・抜かる・抜かり・手抜かり
不届き・高をくくる・集中力不足・前方不注意
不覚を取る・目を離す
月夜にカマを抜かれる
注意力不足・不覚・迂闊・注意力散漫
ついつい・気が抜ける
ーー↓↑ーー
天 地 星 空 山 川 峰
あめ つち ほし そら やま かは みね
↓↑
谷 雲 霧 室 苔 人 犬
たに くも きり むろ こけ ひと いぬ
↓↑
上 末 硫黄 猿
うへ すゑ ゆわ さる
↓↑
おふせよ えのえを なれゐて
「おふせよ・えのゑを・なれゐて」は意味不明
ーー↓↑ーー
大為爾伊天
たゐにいて
↓↑
奈従武和礼遠曽
なつむわれをそ
↓↑
支美女須土
きみめすと
↓↑
安佐利(於)
あさり
↓↑
(於)比由久
お ひゆく
↓↑
也末之呂乃
やましろの
↓↑
宇知恵倍留古良
うちゑへるこら
↓↑
毛波保世与
もはほせよ
↓↑
衣不弥加計奴
えふねかけぬ
↓↑
田居に出で
たゐにいて
↓↑
菜摘む我をぞ
なつむわれをそ
↓↑
君召すと
きみめすと
↓↑
求食り
あさり
↓↑
追 ひゆく
(お)ひゆく
↓↑
山城の
やましろの
↓↑
うち酔へる子ら
うちゑへるこら
↓↑
藻〈藻葉〉干せよ
もはほせよ
↓↑
え舟繋けぬ)
えふねかけぬ
↓↑
「謂之借名文字」
「これを借名(かな)文字と謂ふ」
ーーーーー
・・・
「鮮やかな色」って・・・どんなイロなのか?
・・・「鴉史他(あした)」、「蘆妥(あした)」、「蛙詞多(あした)」、「阿示蛇(あした)」・・・「明日=あす=阿須」、「掛名等事(かならず→仮名等圖→金羅頭→金王朝→愛新覚羅 溥儀(アイシンカクラ フギ・アイシンギョロ・プーイー・1906年2月7日~1967年10月17日)・大清国第12代にして最後の皇帝(在位は1908年12月2日~1912年2月12日)、後に満州国執政、皇帝・康徳(コウトク)帝=年号-大同元年(1932年)~康徳元年(1934年)~康徳十二年(1945年)←徳川家康?」・・・
ーーーーー
愛新覚羅-溥儀
1906生年丙午(丙・ ・丁)
0002生月庚寅(己・丙・甲)偏印(正官・偏財・食神)
0007生日壬午(丙・ ・丁)申酉=空亡
↓↑
大運
61~69歳丙申(己・壬・庚)偏財
↓↑
1967年丁未(丁・乙・己)正財・・・命式支合丙
0010月庚戌(辛・丁・戊)偏印・・・命式三合丙
0017日甲寅(己・丙・甲)食神・・・大運沖・命式三合丙
ーーーーー
「飛鳥(明日香)」、
「あすか→いかるが=斑鳩(ハンキュウ・まだらはと)
鵤(いかる・囀る声がイカルコキーと聴こえる)
=桑鳲(アトリ科の鳥
=集鳥(あとり)
別名で臘觜(ロウシ)鳥
獦子(カツシ)鳥
鵤(角+鳥)の漢字は国字)
=囀る声が月日星(つきひほし)と聴こえるので
三光鳥
別称は「まめまわし(豆回し)
まめわり(豆割り)
豆鳥(まめどり)」・・・
ーーーーー
仁徳天皇
神功皇后摂政五十七年
~
仁徳天皇八十七年一月十六日)
第十六代天皇
在位は
仁徳天皇元年一月三日~同八十七年一月十六日)
名は
大雀命(おほさざき の みこと・古事記)
おほすずめ
ダイジャク
大鷦鷯尊(おほさざき の みこと)
ショウリョウ
大鷦鷯天皇(おほさざき の すめらみこと・日本書紀)
御陵地名=「百舌鳥耳原」・・・もずのみみはら
ヒャクゼツチョウジゲン
百済絶朝字源(次元・示現・時限)?
もず=百舌鳥・鴃・鶪・鵙・万代・・・
=摸図・摸州・摸事・摸亠・摸豆
百足(むかで)
腿(もも)・股
桃の木・桃太郎
↓↑
「仁」の熟語で、スグ思いつく熟語で出てくるのは
「仁徳
円仁(エンニン)
延暦十三年(794年)
~
貞観六年一月十四日(864年2月24日)
第三代天台座主
慈覚大師(ジカクダイシ)・・・字拡大詞?
入唐八家
(最澄・空海・常暁・円行・恵運・円珍・宗叡)の一人
下野国の生まれ
出自は壬生氏」
↓↑
「仁義・仁王
仁和寺(真言宗御室派総本山の寺
山号は大内山
本尊は阿弥陀如来
開基(創立者)は
光孝天皇の譲位、践祚、即位の
宇多天皇←阿衡(アコウ)事件
藤原基経とのトラブル
阿衡は位貴くも、職掌なし)」
↓↑
「仁侠=任侠」・・・?・・・
「子曰、巧言令色、鮮矣、仁」
↓↑ ↓↑
「矣=文末にそえる助字
断定・推量
疑問・反問
感嘆の意
推量・完了・断定・詠嘆」
「矣(イ)・焉(エン)・也(ヤ)」は
「置き字」で
「文末に置いて、文を強調する」
「文意を強めるだけで、それ以上の意味はない」
「而」「焉」「矣」「於」「于」「乎」の6字
「兮=兮(ケイ)」は文中のバランスを整えるのに使用
「焉・矣」=文末で意味を添える「終助詞」のような働き
「終助詞=種々の語に付き、文の終わりにあって
その文を完結させ
希望・禁止・詠嘆・感動・強意
などの意を添える助詞」
「巧言令色鮮ないかな仁
巧言令色-鮮矣(すくなし)-仁」・・・
「鮮=すくない=殆ど無い・否定形?」・・・
・・・「矣」が「文末にそえる助字」ならば、
「巧言-令色-鮮矣、仁」
「巧言令-色鮮矣、仁」→巧みな言葉の命令って
色鮮矣=色鮮(あざ)やかであるのかな・・・
「仁」としては・・・「疑問・反問」
「剛毅木訥 近仁」=剛毅 木訥、仁に近し
「巧言令色鮮矣仁」=巧言令色鮮、仁である矣(や・か)?
↓↑ 「矣」は「疑問・反問」
↓↑ 矣=なり・や・か・かな・のみ
↓↑ 「色鮮(いろあざやか)」は熟語?
↓↑ 「鮮」=技術・動作などがとても巧みである
↓↑ 「鮮やかな包丁捌(さば)き」
「朝鮮」・・・
「鮮=魚+羊=あざやか・すくない・セン
取りたてで生きがよい
生生しい・鮮魚・鮮血・新鮮・生鮮
色がくっきりしている・あざやか
鮮明・鮮緑・鮮烈」
すくない・・・?・・・スクナイとは訓まない?
「鮮少」・・・
数量詞=微少・少ない・僅少・纔か
少い・僅か・尠少
わずか量・程度が小さい
微量
「鮮少」=「其爲 人也、孝悌而好㆑犯㆑上者、鮮矣。」
(その人と爲りや、
昔は明王が孝を以て天下を治む
其れが之を継ぐこと或るは
鮮(すく)ないかな希(まれ)である
「被服光且鮮。」
(被服光ありて、かつ鮮あざやかなり)
(洛陽の若者の)服装は輝き、艶美である
(曹植『文選』「名都篇」)
「鮮明・鮮血・新鮮」
「鮮卑」、「朝鮮(あざやか)」の意味
「鮮少」=ほとんどない。すくない
「鮮少」
「其爲㆑人也、孝悌而好㆑犯㆑上者、鮮矣」
(その人と爲りや、孝悌にして上を犯すを好む者は、
鮮(すくなし))
「彼の人柄が、親にも兄にもよく仕え、
かつ目上の人に逆らうのを好む人は、
ほとんどいない(『論語』「學而第一」一之二)」
↓↑
(日本に伝来したテキストで
「悌=年長者に柔順に仕える
兄弟や長幼の間の情が厚いこと」
とするところ、
中国に普及するテキストでは
「弟」とする。意義は同一)・・・?
↓↑
「昔者明王以孝治天下,
其或繼之者鮮哉希矣」 (『晉書』卷55)
(昔は明王が孝を以て天下を治む、
其れが之を継ぐこと或るは
鮮(すく)ないかな希(まれ)である)
↓↑
「鮮卑=モンゴル高原での古代牧畜狩猟民族
五胡十六国の一
拓跋氏が有力となり4世紀末に
北魏を建国
439年、華北を統一」
「鮮=魚+羊」は「まな+ひつじ」の意味であるが、魚の種ではない?・・・
「蘚(こけ・セン)=艹+魚+羊=こけ=苔・虚仮・鱗(うろこ・リン)」・・・
「薊(あざみ・さく・とげ・ケイ・カイ・ケ・ケチ・ケツ)=艹+魚+刀」の「薊」・・・
「蘇我」の「蘇」に類字するが・・・?
↓↑
「羊のような魚」とは、ギリシャ神話の「山羊座の神話]で「山羊(やぎ)座の山羊(Capricornus・Capricorn)」は、ナイル川の岸辺の神々の宴会で「アイギパーン=パン(ドリュオペと、ヘルメスの子供・上半身人間、下半身山羊)」が笛を吹き、踊り、神々を楽しませていた時に突然、神々に襲い掛かってきたのが「テュフォン」で、100の頭、西から東の空を覆う巨大な身体、目と口からは火を吐きだす怪物だった。
驚いた「パン」は慌てて変身したが「上半身が山羊、下半身が魚」・・・シュメール神話では「上半身は牡山羊で、下半身は鯉(コイ)のエンキ(Enki・アッカド人による称号は水の家の主・知識、魔法を司る神・人類に文明生活をもたらすメー)」、「知識、魔法、藝術を司る神」は、そもそもギリシャ神話の「ヘルメス(Hermēs)」で、「頭は山羊」で「下半身が魚」である・・・ボクの記憶(?)では、慌てて変身したのは昔、読んだ本では「ヘルメス自身の不様な変身」だったような・・・
ヘルメスは「神々の伝令使、能弁、境界、体育技能、発明、策略、夢と眠りの神、死出の旅路の案内者」で「旅人、商人」の守護神、「朱鷺・雄鷄」が彼の聖鳥・・・
オマケに「狡知、詐術に長けた計略、謀略、早足、牧畜、盗人、賭博、商人、交易、交通、道路、市場、競技、体育などの神で、雄弁と音楽の神であり、竪琴、笛、数、アルファベット、天文学、度量衡などを発明した神」である・・・
英語では「鯉(コイ・carp)」は「泥の中の汚い魚・carpの動詞は五月蠅(うるさ・煩)く、咎(とがめ)だてをする、筋違いの文句を言う奴・アラ捜し」らしい・・・
中東なら「鯉(こい)=魚+里」ではなく、「電気鯰(なまず)」が「神」に相応しいカモ・・・
「鯰=魚+念」=「catfish」→「ナマズは猫のように長い口ひげを有しているから」?・・・じゃないだろう・・・
穀物を喰い荒らす「鼠(ネズミ)」の天敵が「猫」であり、「バステト(Bastet・猫)女神」である。そして「アポピス(Apophis)=毒蛇」の天敵が「猫女神」でもある・・・
「バステト(Bastet・牝猫)」は「テフヌト(Tefnut・牝ライオン)」。「セクメト (Sekhmet・牝ライオン) 」、「ハトホル(Hathor・牝牛・イチジクの女主)」、ギリシャでは「アプロディーテー(ウーラノスの精液の泡=アプロス・aphros から生まれた)」に習合された・・・
鯰(魚念)=「魚(まな→眞名=漢字)」を「念(今の心で思う)=二十・弐拾・弐足」・・・「仁足」・・・
「電気鯰(ナマズ・魸・鮀)科 (Malapteruridae)=淡水魚・アフリカ熱帯地方の河川、ナイル川に棲息する電気ナマズ (Malapterurus electricus)・300~400Vの発電・ナイル川水系、アフリカ西部の川、チャド湖、トゥルカナ湖盆地、ザンベジ川のアフリカ熱帯域に広く分布」
「体に鱗(うろこ)がなく、鰭条(きじょう)のある背びれがなく、脂びれが体の後半部にある・夜行性・発電電圧は350ボルト以上」
「ジムナルカス (Gymnarchus niloticus)」・・・
「象鼻魚(Gnathonemus petersii)=エレファントノーズフィッシュ(象鼻魚)」・・・
↓↑
「森と羊と羊飼いの神、牧羊神パンの姿(守臥多?)」・・・「生後およそ12か月以下の子羊の肉はラム(muttonlamb)、それより も年をとった羊の肉は日本ではマトン(mutton)」・・・「羊頭狗肉」・・・「要等句似句」・・・
ーーーーー
御仁・仁愛・仁恩・仁義・仁君・仁恵・仁兄・仁賢・仁厚・仁孝
仁慈・仁者・仁寿・仁恤・仁術・仁恕・仁心・仁人・仁政・仁知
仁智・仁道・仁徳・仁風・仁王・仁安・仁侠・仁治・仁平・仁和
↓↑
一視同仁=差別することなく、全ての人を平等に慈しむこと
同仁一視=〃
以力仮仁=武力権を以て仁政に見せかける
寛仁大度=心が広くて、度量が大きく、慈悲深い
志士仁人=高潔な志を持つ人
志のある人で、学徳の立派な人
仁言利博=徳の言葉は多くの人々に利益をもたらす
仁者不憂=仁者の人は、悩むことがない
仁者無敵=仁者に、敵になる者はいない
仁者楽山=仁者は動じない山を楽しむ
吮疽之仁=「吮」は口で直接吸い出すこと
「疽」は悪性の腫物
戦国時代の楚の将軍の
呉起は
悪性の腫物で苦しんでいる
部下の血膿を吸い取ってやった故事
宋襄之仁=必要のない情けをかけ、敗北すること
ーーーーー
「仁義」って?
↓↑
「仁=イ+二」
↓↑
「他人に対する親愛の情、優しさ」
儒教における最重要な「五常の徳」の一
「仁+義」=「仁義」
↓↑
中国の伝統的な
社会秩序(礼)を支える精神、心のあり方
礼(レイ)=さまざまな行事のなかで
規定されている動作や言行
服装や道具などの総称
人間関係(儒家の身分制階級秩序)を
維持するための道徳的な規範
↓↑
孔子
君子は仁者であるべき
孟子
性善説に立つ孟子は
惻隠(ソクイン)の心が仁の端(はじめ)
惻隠の心とは同情心
「孝」や「悌」、「忠」なども仁のひとつ
↓↑
老子
「大道廃れて仁義あり」といって
仁義をそしり、これとは別の道徳を説いた
「私」の立場
「仁義」は「公」的
↓↑
万物一体の仁説
程明道
仁=「万物(万民)一体」
医書では手足の麻痺した症状を「不仁」と呼び
自己の心に対して
何らの作用も及ぼしえなくなってしまっているため
これを生の連帯の断絶とそれに対して
無自覚であることを意味するとし、
生意を回復せしめることが
仁であるとした
「万物一体の仁」の一つ
「知覚説」で
痛痒の知覚をもつことを
仁としている
義・礼・智・信が、皆、仁
であるとする立場で
仁を「体」とし
五常を「用(作用)」と見なしていた
「仁」は「生」・・・生き方なのか、生かされ方なのか?
ーー↓↑ーー
「礼=禮」
さまざまな行事のなかで規定されている
動作や言行
服装や道具などの総称
春秋戦国時代、
儒家によって観念的な意味が付与され
人間関係を円滑にすすめる方策とした・・・
ーー↓↑ーー

馬融(バユウ)
79年(建初四年)~166年(延熹九年)
後漢中期の学者・政治家
右扶風・茂陵県(陝西省興平市)の人
字は季長
後漢の
伏波将軍
馬援の族孫
祖父は
馬余(馬援の次兄)
父は馬厳(後漢の将作大匠)
兄に
馬続
叔父に
馬敦
娘(馬倫)
は
袁隗の妻
従妹(馬敦の娘)
は
趙岐の妻
族子に
馬日磾
『後漢書』に伝がある
↓↑
後漢の名門
馬氏の一族
京兆の
摯恂という人物が仕官せずに
南山に隠れ住み学名が高かった
馬融は摯恂に師事し
広く儒学を学び、経典について研鑚
摯恂の娘を妻にした
↓↑
108年(永初二年)
安帝の外戚として権勢を振るっていた
大将軍の
蠟騭
に舎人に徴されたが応ぜず
涼州の
武都や漢陽に避難
乱に巻き込まれ生活は困窮
↓↑
110年(永初四年)
再び蠟騭に招かれ
これを受けて都に行き
校書郎となった
↓↑
同郷の先輩である
班昭・・・・・・・班(まだら)を昭(あきらか)にする?
に付いて
『漢書』を学んだ。
↓↑
蠟騭
と
安帝の生母の
蠟太后
が共同で政務にあたって
馬融は
蠟太后へ
『広成頌』と呼ばれる上奏をし
蠟太后の不興を買った・・・
↓↑
116年(元初三年)
兄の子の喪に服するため帰郷
これが
蠟太后の怒りを買い
免官、禁錮
↓↑
121年
蠟太后が死去し
安帝が親政
馬融は許され、再び召され
一度
河間王の家臣となったが
安帝の東巡に従い
その文才を認められ
再び郎中となった
↓↑
125年(延光四年)
北郷侯(少帝懿)即位・・・「懿」
官を辞し故郷に戻り
郡の功曹となった
順帝の時代となった
133年(陽嘉二年)
再び中央に戻って
議郎となった
↓↑
大将軍
梁商に取り立てられ
従事中郎
武都の令となった
西羌が反乱を起こすと
兵を率いてこれを討つことを申し出たが
受け入れられなかった
↓↑
梁商
の跡を継いだ
梁冀
が専横するようになると、
馬融
は
『西第頌』を作成するなど、
それに
阿(おもね)るような振る舞いをしたとして
清流派の士人から批判された
中でも
梁冀
が
太尉
李固を弾劾したとき
その上奏文を作成したのが
馬融であったことは
後々までの憎悪の種となった
↓↑
桓帝の時代
南郡太守
このころ
梁冀に憎まれるようになって
私欲が深いとして免職、徙刑に処された。
馬融は自殺を図ったが果たせなかった
↓↑
再々度 めされて
議郎となり
「東観」にあって著述を専としたが
病いによって職を辞し
88歳で死去
政治家としては
濁流に属し
親戚の
趙岐に面会を拒否されるなど
清流派の士人から軽蔑された
博覧強記で世の通儒と評された
講義の場に女人をはべらすなど
儒者の節に拘らないところもあった・・・
弟子に
盧植
鄭玄
ーー↓↑ーー↓↑
「仁」
社会秩序(儒家にとっては身分制階級秩序)
を維持するための
道徳的な規範
↓↑
孔子
「克己復礼(自己に打ち克って礼に復帰する)」
仁を表現するうえで
礼と仁は不可分
孟子
仁・義を美的に整え
飾るのが礼であると説いた
↓↑
儒家の礼の基本精神は
供犠
「正しい」方法を
守るという倫理的な支持以外の見返りを期待しない贈与
孟子は
「礼にかなっていなければ、
どんなに飢えたひとであっても、
施しの食事を受け取ることはない」
と述べ、
礼は人間のあり方として
訓練されるべき規範
↓↑
礼は規範であるが、
法規範のように
客観的・普遍的なものではなく
感情を様式化した
主観的で特殊な規範
礼の具体的な適用場面は
王朝や時代に応じて
適切な形に見直され、変形
↓↑
孔子の礼制
既成の秩序維持は
周王朝期の礼制
春秋時代に国土を拡大した諸国が
これに従えば、
国によっては国土を縮小しなければならず
これを指摘し、合理的に批判したのが、
楚国の
子西であった
(以降、孔子は諸国の政治に
なぜ登用されなかったかの自覚をもつに至る)
孟子は礼を国家の行動規範として想定し
殷の
湯王
が
葛伯
を伐った
葛伯征伐について
礼を行わない葛伯に対する正義の戦争であった
と考察し正戦の論理を説いた
19世紀の思想家
章炳麟は、
礼が範例的な規範である以上
それを普遍化して押し付けることはできず
特定の礼を特権化して
それを拒むものを悪とする
孟子の正戦論理は
侵略戦争や
植民地戦争の論理に他ならないと批判
↓↑
礼の分類
『儀礼』
冠礼
婚礼
喪礼
祭礼
射礼
郷礼
朝礼
聘礼
↓↑
四礼
『礼記』
『漢書』
礼楽志には礼が四つに分類
↓↑
婚姻之礼=男女の情、妬忌の別が人の間にあるため
郷飲之礼=交接長幼の序が人の間にあるため
喪祭之礼=哀死思遠の情が人の間にあるため
朝覲之礼=尊尊敬上の心が人の間にあるため
後には
「冠礼・婚礼・葬礼・祭礼」
を四礼と呼んだ。
↓↑
五礼
『周礼』
大宗伯には礼が五つに分類
↓↑
吉礼=天地鬼神の祭祀(邦国の鬼神につかえる)
凶礼=葬儀・災害救済(邦国の憂いを哀れむ)
軍礼=出陣・凱旋(邦国を同じくする)
賓礼=外交(邦国に親しむ)
嘉礼=冠婚・饗宴・祝賀(万民に親しむ)
↓↑
礼学
礼は儒家によって観念化され
秩序原理にまで高められた
荀子によって
理論的整備がなされ
六経の一つとして挙げられると
礼を研究・実践する学問である
礼学が起こった
↓↑
秦代、焚書坑儒によって
礼に関する多くの書物が散佚
漢代に伝えられた
『礼』は
士礼17篇(現在の『儀礼』)のみ
高堂生がこれを伝え
后蒼が
武帝の時
博士となり
その弟子
戴徳(大戴)・戴聖(小戴)・慶普
の三家に分かれて
学官に立てられた
また
『礼』に対して注釈や補充説明をした
「記(礼記)」がある
『漢書』芸文志には
『記』131篇・『陰陽明堂記』・『王史氏記』
后蒼が著した
『后氏曲台記』
が記載
現在に伝わっている礼記は
戴徳が伝えた
『大戴礼記』
戴聖伝えた
『小戴礼記』(現行本『礼記』)
↓↑
後漢の
鄭玄
は古文経の
『周官』を中心として
『儀礼』と『小戴礼記』
を三礼として
総合的に解釈する
体系的な礼学を構築
↓↑
礼の格言
三顧の礼
劉備が諸葛亮を迎えたときの礼
礼に始まり礼に終わる=武道の基本
この言葉の初出は
1907年7月
『武徳誌』
に
内藤高治が発表した論文
「剣道初歩」
↓↑
礼は庶人に下らず
刑は大夫に上らず
『礼記』
ほか
ーーーーー
・・・
辟易=エキエキ=日置役・壁絵鬼・経記重紀・・・
・・・本日は1本の胡瓜の収穫・・・昨日(8/15)は「札幌の従妹家族3人」が家のオフクロの祭壇を訪問してくれた・・・夜には「インパール作戦」のTV・・・スベテの「生き物の細胞」は「壊死」する・・・生きている人間の「脳ミソ思考」も腐ったまま生きて行く奴がいる・・・生理的な新陳代謝の脳ミソは酸素不足で時間的な壊死が速いが、「3時間以内 or 4時間半以内であれば血栓を溶かす薬が投与できる」・・・そして「心臓(冠動脈血管に閉塞や狭窄、梗塞)」は「冠動脈がふさがれてしまうと、おおよそ40分で心内膜の心筋の壊死が始まる」・・・「前胸部の激烈な痛みが特徴・胸痛は狭心症より強く胸痛の持続時間は30分以上、数時間におよぶ。急性心筋梗塞では、顔面蒼白、冷汗、呼吸困難、血圧低下、ショック状態、不整脈などになる。患者のほとんどが救急車で病院に運ばれ、狭心症の胸痛に効くニトログリセリンも、急性心筋梗塞の場合には効果がない」・・・「脳梗塞」でなくて運がよかった・・・
ーーーーー
脳血流量
組織100gあたり䛾血流量が1分間に
・ゼロ →4〜10分で脳組織䛿壊死
・16-18ml未満→1時間以内に壊死
・20ml未満→数時間から数日で壊死
(脳梗塞ガイドライン2013
Part1:閉塞血管䛾再開通療法)
ーーーーー
辟易
↓↑
「鮮(すくなし)」は狩猟、漁労、穀物、果実など
食べ物の
鮮度を保つ「時間的なコトバ」だろう
「鮮血」も維持できるのは
「時間的な問題」だ・・・
「鮮矣=センヤ=千夜・一矣」?
遷 矣→遷移
閃 矣→閃光
恒 矣→恒星・恒常・恒温
恒=愃=カン・ケン・セン
鱣 矣→鱣=こい=鯉
鱣=タン・セン・ゼン・ダン
テン・こい(鯉)
鮮=あざやか=「痣夜-矣」?
字=あざ=悝+矣(ヤ・カ)?
「凝血」でなく、
「汚血」・・・瘀血・淤血(オケツ)・・・
↓↑
「鮮少」
「其爲㆑人也、孝悌而好㆑犯㆑上者、鮮矣」
「其、爲人也、孝悌、而好、犯上者、鮮矣」は
「それ、人の行為也」、「孝悌、而好」の
「孝悌而好」の「悌=心+弟」
↓↑
「孝悌忠信=忠信孝悌」
漢字分解では
「孝(行)=十+一+ノ+一+了」・・・
「十の(足の)
一の(初めの)
丿の(えい・よう・ヘツ・ヘチ
右上から左下に曲がる意)
子=一+了(始~終、終~始)」?
↓↑
「不好犯上、而好作乱者、未之有也。
君子務本、本立而道生、
孝弟也者、其為仁之本與
ーー↓↑ーー
「南總里見八犬傳」
の
「犬塚 信乃 戍孝(いぬづか しの もりたか)」は
「孝の玉(球・珠)を有し、牡丹の痣を左腕にある人物
長禄四年(1460年)
七月
戊戌の日
武蔵大塚で誕生
父は犬塚番作
母は手束(たつか)
使用する太刀は
足利家の宝刀
村雨丸
脇差は
桐一文字」・・・
↓↑
・・「戍=まもる・ジュ・国境を守る・戍卒・衛戍・征戍」
・・「戍=たむろ(屯)・守備兵の陣営・駐屯地」
・・「戌(ジュツ・いぬ)」
・・「戊(ボ・つちのえ)」とは別字
↓↑
「悌=忄(心)+弟」・・・
「弟の心構え、信条、心情」?
年下=としした=訳詞詩他?
若年者の信条、信義?
とは
「忠信」=信-義(誠意)を込めて
忠-臣(親や兄、目上、主人に仕えること
「忠信=ただのぶ(人名)」
「佐藤忠信(さとう ただのぶ)」は
源義経の家臣
「松平信忠=安城松平家2代目、宗家第6代当主」
↓↑
「南總-里見-八犬傳」
江戸時代後期
曲亭馬琴(滝沢馬琴)
による大長編読本
文化十一年(1814年)
刊行開始
二十八年をかけ
天保十三年(1842年)に完結
全98巻、106冊
刊行初期には5巻=5冊を1輯にまとめて発刊
全体の半数以上を「第9輯」が占める
馬琴が陰陽思想における
陽の極数である9にこだわったため・・・
巻数と冊数が一致しないのは
上下分冊にした巻があるため・・・
馬琴は
天保四年(1833年)頃から右目の視力が衰え
天保九年(1838年)には左目の視力も衰え
天保十一年(1840年)十一月
執筆が不能
息子の嫁の
路(土岐村路)に口述筆記させて執筆
馬琴が手探りで記し
路が書き継いだ原稿
(第九輯巻四十六=第177回)
は早稲田大学に現存
天保十二年八月二十日(1841年10月4日)
馬琴は本編(第百八十勝回下編大団円)を完成
させた
↓↑
富山で
伏姫(ふせひめ)は
読経の日々で
八房(犬)に
肉体の交わりを許さなかった
翌年、
伏姫は山中で出会った
仙童から
八房が
「玉梓(たまずさ)」=神余光弘の愛妾の名前
↓↑ 山下定包とも密通し
神余の死後は
山下の正妻
滝田落城時
彼女を捕らえた
里見義実は一度は助命を約束したが
金碗八郎の言で約束を翻し
玉梓は
「児孫まで、畜生道に導きて
この世からなる煩悩の、犬となさん」
との呪詛して処刑され
↓↑ その怨霊は里見家に仇なすことになる
↓↑ ↓↑ ↓↑
↓↑ ・・・たまずさ(玉梓・玉章)=「たまあずさ」の音変化
手紙・消息・手紙の中ほどをひねり結んだもの
ひねり文・結び文
艶書 (エンショ)=恋文・懸想文 (けそうぶみ)
古く便りを伝える使者が
手紙を梓(あずさの木)に結びつけて持参した
↓↑ 使者が持参する手紙
の呪詛を負っていたこと
読経の功徳により
その怨念は解消されたものの
八房(犬)の気を受け
種子を宿したことが告げられ
懐妊を恥じた伏姫は
富山に入った
金碗大輔(八郎の子)・里見義実
の前で割腹し
胎内に
犬の子がないことを証したが
傷口から流れ出た
白気(白く輝く不思議な光)は
姫の
数珠を空中に運び
仁義八行・・・「仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌」
の文字が記された
八つの大玉を飛散
↓↑
金碗大輔は僧体となって、
『犬』という字を崩し
「丶大(ちゅダイ)」・・・「丶(ちゅ・ぽち・主・灯火)」
を名乗り
八方に散った玉を求める旅に出る
ーー↓↑ーー
仁義八行
↓↑
仁=思いやり、慈しみ
義=人道に従う事・・・・人道?
道理にかなう事・・・道理?
礼=社会生活上の定まった形式・・・慣習上の行為、儀式?
人の踏み行なうべき道に従う事・・・?
智=物事を知り、わきまえている事・・・弁(わきま)える
忠=心の中に偽りがない事・・・・・・・本心・本音?
主君に専心尽くそうとする真心・・・忠儀
信=言葉で嘘を言わない事
相手の言葉をまことと受けて疑わない事
考=おもいはかる事
工夫をめぐらす事
親孝行する事・・・「考え」と「孝」は異なる
↓↑
孝=子供が自身の親に忠実に従うことを示す道徳概念
説文解字
「孝=善(よ)く父母に事(つか)えること
老の省略体と
子の組合せ
子が老人を助けささえること
子の父母に対する
敬愛を基礎とする道徳
父母に尽くす人(親孝行)
祖先を尊敬して、その考えや目標を受け継ぐ
祖先を尊敬し、その考えや目標を受け継いだ人
父母の喪に服する
(父や母が亡くなった後
一定期間、外出や積極的な人との付き合いをさける)」
喪服(葬儀や法事などに着用する黒または薄墨色の衣服)」
腰を曲げてつえをつく老人
と
頭部が大きく手足のなよやかな乳児
年寄りを支える子の意味
親に尽くす=孝=土ノ子=十の一の一と了
「老・耂(おい、おいかんむり(老冠)、おいがしら(老頭))」
「老=耂+ヒ
ヒ=牝=雌・七=7=漆・匕=匙=匕首=小刀=」
「孝=耂+子(一了)
↓↑
悌=兄弟仲が良い事
↓↑
昭和48年
「尊属殺人罪」を違憲とした(最高裁判決)
ーー↓↑ーー
古代中国
祖先崇拝
血族が同居連帯し家計をともにする
家父長制家族が社会の構成単位
社会的犯罪・・・・・・・・・階級社会の犯罪?
については
「父は子の為(ため)に隠し
子は父の為に隠す」
と孔子
「孝経」
道徳の根源、宇宙の原理として形而上化
無条件服従
と
父子相隠
を法律にも明文化
祖先祭祀で
「孝」は重要な原理
↓↑
「孟武伯」が孔子に「孝」とはナニか、を尋ねた
「親は子の病を憂う(心配する)ものだ(論語・為政第二)」
つまり「子供は健康でいること」が孝行
「子游」が尋ねた
「現今の世間は養う(目に見える形の奉仕)を
孝というが
それなら
犬馬だって人を養う(奉仕する)
敬う心がなければ、
どうして犬馬と区別できようか」
と答えた?・・・
・・・「区別」は出来るが「差別」は出来ないカモ・・・
「孝」=「親孝行」
↓↑ 実践する人を「孝子(コウシ)」
儒教の「孝子」は
「舜」であるらしい
「曽子」が孝の実践に優れていた
「曽子」は「孝経」の作者・・・
↓↑ 「孝経」=孔子、十三経のひとつ
漆書「蝌蚪文」の
「古文孝経」は22章
「今文孝経」は18章
親を愛する孝は
徳の根本で
「至徳」で人間の行動原理・・・
「玄宗みずから注釈」した・・・
(御注は孝を国家の政治道徳へと転換し
家族的な孝を
君に移して忠とすべきことを強調)
文禄二年(1593年)
朝鮮から銅活字がもたらされ
古文孝経を印刷した(時慶卿記)
実物は現存しない
慶長四年(1599年)の
古活字版「古文孝経(慶長勅版)」は現存
↓↑ ↓↑
「身体髪膚、受之父母。
不敢毀傷、孝之始也。
↓↑ 立身行道、揚名於後世、以顕父母、孝之終也。」
「孝(親孝)」は「忠(忠君)」と矛盾
↓↑
「忠」よりも「孝」が貴い
「悪行の君主を三度諌めても聞き入れられなかったら
君主の下から去るべき」
「悪行の親を三度諌めても聞き入れられなければ
泣き寝入りして従え」
「孝」
「父のやり方を三年間改めないのが孝行」
これを例に
『日本後紀』では
桓武天皇が崩じた際、
その年に元号を
「大同」と改めたことに対し・・・年号自体が「大同」である?
↓↑
子や臣の心情として
一年の内
二君あることを忍びないと思うからこそ
同年に改元しないのに
「礼に反している」と批判する記述がある(『後紀』)
・・・だが年号自体が「大同」である?・・・
↓↑
中国
「3年子無きは、去る(夫の方から離婚する)」
これは祖霊に対する
「孝」=「子孫を残すことが孝」とするモノ
「子を残す女性が正しい(本妻でなく妾でも)コト」
倫理的に正しい・・・
『孟子』離婁(リロウ)上において
「不孝に三あり。
後(継ぎ)無きを(最)大なりとなす」
中国の辛亥革命で
国民党時代が到来
魯迅は
「孝」は
「人が人を食う」原理であり、
それまで賛えられていた
「孝子」をおぞましいものであると非難
「孝」は共産党に否定され
「忠」が文化大革命で
「毛沢東」に対する忠誠として肯定的化・・・
ーーーーー
「造反有理=造反に理有り=謀反にこそ道理がある」・・・
「階級(搾取)社会での革命は無罪?」だけれど
未だに成就したタメシがない・・・
「上の者に反抗(抵抗)するのには理由がある」・・・
・・・「上の者」ではなく、
「理不尽な言動、行動、暴力を振るうモノ」にだろう・・・
「造反有理」とは「無理に対する有理としての造反」で、
「数学」で「有理数(rational number)」とは、
「二つの整数 a, b (b≠0)をもちいて
a/b という分数で表せる数のことをいう
a/b=a が b に占める割合」
「整数は分母の数を1とした場合
1/1・2/1~9/1・・・分数の形に直すことができる」
「有理数は整数・有限小数・循環小数の3つ
分数の形に直せる数は
整数・有限小数・循環小数の3つのうちのいずれか」
「0は有理数・・・0は分数で 0/a (a≠0)・・・0/a=0」
「無理数」は分配には納得させる数字とはならない・・・?
↓↑
人間の「心情」は「有理な信条」では説明できない?・・・
割り切れないモノ・・・?
・・・「ルツ記」の「ナオミ(Naomi)」と「ルツ(Ruth・Rutu)」の関係って・・・結局、心情は子孫が「ダヴィデ」なったってコトか・・・「大闢=大辟」・・・その子孫であるキリストは現実に命あるモノとして救われなかったし、他の人々の命も救えなかった・・・
↓↑
「辟=さける・きみ・めす・よこしま・かたよる・ひらく
ヘキ・ヒ
避ける・避難・僻地・・・
「辟=さける・しりごみする・後ずさりする
辟易(道をあけて場所をかえる意から
・・・易占を避けるコト?
ひどく迷惑して、うんざり(ウンザリ)すること
嫌気がさすこと・閉口すること
相手の勢いに圧倒され(尻込み・後込み)すること)
同じようなことを何度も繰り返し言ったり
長々とと話したりして、
うんざり(辟易) ・・・運指理(去)?
つみ(罪)・刑罰
大辟=きみ(君)・天子
復辟=めす(召す)・まねく(招く)
徴辟
よこしま・かたよる・ひらく・土地をひらく」・・・
「招辟=ショウヘキ=
「大辟(タイヘキ・重い刑罰)」
「百辟(ヒャクヘキ)」・・・
「復辟=フクヘキ=退位した君主が再び位に就くこと
張勲復辟(チョウクフクヘキ)
1917年7月1日~12日間
張勲が清朝の廃帝であった
愛新覚羅溥儀を復位させた事件
「便辟=ベンヘキ=便は人の欲する所に順ふ
辟は人の惡む所を避くる義
人の意を迎へて、
媚(こ)びへつらふ。又其の人」・・・
でも、生きる為には「便辟」を装うコトもネッ・・・
「便秘」はウンざりだけれど・・・
箏=コト=琴・・・コトのコト・・・
・・・「ナン操作訳見発見傳」・・・なんで、「曲亭の馬の琴」なのか?・・・サーカス(circus)=サーカス=曲馬団・曲芸団・曲技団・traveling circus=run a circus=観覧席が雛(ひな)壇式の円形興業場・・・circus (show)・サーカスの小屋をかける=pitch (put up) a circus・the main tent at a circus・・・「曲(まげられた・旋律)の亭(天幕)」・・・「サーカス(circus)=円形広場・競技場・動物と人間の曲芸を中心とした見世物一座・曲馬団・曲芸団」・・・
「馬の鬣(立て髪)の毛の弦の琴」?・・・
「箏(こと・ソウ)の絃は絹糸の13本。柱(じ)の位置によって弦音の高低を決めて爪弾き演奏する」・・・
「琴柱(ことじ)=琴の弦を支え、移動させて音調の高低を生じさせるもの)・駒 (ブリッジ・bridge) 」 ・・・
ナゼ、「コトの柱(はしら・チュウ)」を「柱=ジ」と訓ませているのか?・・・
「駒(こま)の英語は馬(うま・hose)、将棋の駒は chess man,piece」、
「楽器の bridge、将棋の駒(piece)を動かす」・・・
柱は建築の「pillar、column (円柱)」、テント、電柱の「pole、支柱の support、prop、post」、帆柱の「mast」・・・
「across the bridge」、「the bridge across the river、libber?」・・・
「libber=特に女性のための解放運動を支持する人」・・・
「将棋(chess)で桂馬の英語は knight(ナイト・騎士)」である・・・
幕末、明治維新ならば「桂馬」は「桂小五郎」と「坂本竜馬」だが・・・
ーーーーー
「琴」と「箏」は異なる楽器
「柱(じ)=bridge」が、あるか、ないか
↓↑
「琴(キン)」は柱(bridge)がなく
絃を押さえる指のポジションを変えることで
音の高さを変える楽器
一絃琴・二絃琴・七絃琴・大正琴
↓↑
「箏(ソウ=ツィター=zither)」は
「柱(じ)」を動かすことで
音の高さを変える楽器
↓↑
「こと」は、「絃楽器の総称」
「箏(ソウ)・琴(キン)・琵琶(ビワ)」
などの「総称のコト」
↓↑
「箏(ソウ)のコト」が
漢字の
「琴=キン」で「こと」になった・・・
「琴(キン)」
の漢字が「こと」として
使われるようになったのは
常用漢字に
「箏」という「字(ジ)」が
含まれていなかったから・・・
「1923年(大正十二年)
文部省臨時国語調査会が発表の
常用漢字表、漢字1962字とその略字154字
一部資料に1960字とあるのは
略字によって2組が同字となるため
同年9月1日実施予定であったが、
同日発生した
関東大震災により頓挫」・・・
↓↑
「和琴(わごん・やまとごと)」は
六本の弦を持つ楽器で
弥生時代の遺跡からも発掘
琴を弾いている奏者の埴輪も発掘
・・・「琴の音」は「死者の魂魄」だった・・・
天皇
↓↑
琴(キン・こと)には
柱(じ・チュウ・はしら)が
無(な)く
弦を押さえる(勘所=かんどころ)を変えて
音の高低を響かせ、奏(かな)でる
↓↑
箏(ソウ・こと)
十三弦
奈良時代
唐から
伝来した
十三本の弦を持つ楽器
箏の胴の上に立てられた
「柱(じ・はしら・チュウ)」という
可動式のモノを動かし
音の高低を決め、奏でる
↓↑
柱(じ)が
あるのが「箏・筝=竹の争い」
ないのが「琴=王が二人ナラブ今」
ーー↓↑ーー
「古事記の神功皇后」が奏でたのは
「琴(王+王+今)」だったのか、
「箏(竹+争)=爭=爫(爪)+∃+亅」だったのかは、
「和琴=わごと=和事=倭語訳」であったのは明白だが・・・
コンピュータでの検索の
「古事記」にも、
「日本書紀」にも
「箏」の漢字を発見できなかった・・・が・・・?
「竹=筑紫」の「争い」は、
「和=倭=やまと」の
「琴=王+王+今=王が二人並ぶ今」ではあるが・・・
ーー↓↑ーー
其大后
息長帶日賣命者、
當時、歸神。
故、
天皇坐筑紫之
訶志比宮、
將
擊
熊曾國之時、
天皇
控
御琴・・・・・琴・・・箏かも?
ライアー(Leier=竪琴)
ハープ・リラなど
縦に張った弦を弾奏する楽器
而、
建內宿禰大臣
居於
沙庭、
請
神之命。
於是、
大后
歸神、
言教覺詔者
「西方有國。
金銀爲本、
目之炎耀、
種種珍寶、
多在其國。
吾
今
歸
賜其國。」
爾
天皇答白
「登高地、見西方者、
不見國土、
唯有大海。」
謂
爲
詐神而、
押退
御琴・・・琴
不控、
默坐。
爾
其神
大忿
詔
「凡茲天下者、・・・「茲(しげる・シ・ジ)=艹+𢆶」
汝
非應知國。・・・「応=應=䧹+心」→「鷹+心」
オウジン・タカの心
「應(まさ)に~すべし=广+イ+隹+心」
「鷹(たか)=广+イ+隹+鳥」
「鷹(たか)≠雁(かり・ガン)=厂+イ+隹」
「雁=かり・ガン・カモ科の鳥の総称」
「膺(むないた)=䧹+肉」
汝者
向一道。」・・・一の道に向かえ
於是、
建內宿禰大臣
白
「恐我天皇、
猶
阿蘇婆勢(あそばせ)・・・阿蘇の婆の勢=卑弥呼
其
大御琴。・・・琴・・・・・おほミゴト・おほおんごと
(自阿至勢以音。)」 ダイゴキン(代後金)?
爾
稍
取依
其
御琴而、・・・・琴・・・ミゴトのジ・音ごとの字
那摩那摩邇・・・・・・・ナマナマに
(此五字以音)
控坐。
故、
未幾久・・・未(いまだ)幾(いく)久(ひさしく)からず
而
不聞
御琴之音、・・・琴
卽
擧火見者、
既
崩訖。・・・訖=おわる・やむ・いたる・ついに・キツ
爾驚懼而、
坐殯宮、
更
取國
之大奴佐・・・奴佐(ドサ・トサ)
而
奴佐(トサ・ドサ)・・・土佐・土佐?
(二字以音)、
種種
求
生剥・逆剥・阿離・溝埋
屎戸・上通下通婚
馬婚・牛婚・鷄婚之罪類、
爲
國之大祓而、
亦
建內宿禰
居於沙庭(さにわ)、
請神之命。
ーー↓↑ーー
日本書紀
三月壬申朔、・・・三月(さんがつ)=彌生(やよい)
壬申(ジンシン)の朔(ついたち)
ミズノエのサル・みずのえをもうす
皇后選吉日、
入齋宮、
親爲神主。
則命
武內宿禰
令
撫琴、・・・撫(なぜる・ブ)琴(こと・キン)
喚
中臣
烏賊津(いかつ・ウカイシン)
使主
爲
審神者。
因以
千繒高繒・・・センカイコウカイ・千科移行掛意?
置
琴頭尾、・・・琴頭尾=キントウビ=均等備
而請曰
「先日
教
天皇者
誰神也、
願欲知其名。」
逮于
七日七夜、
乃答曰
「神風
伊勢國
之
百傳度逢縣
之
拆鈴五十鈴
宮所居神、
名
撞賢木嚴之御魂
天疎向津媛命焉。」
亦問之
「除是神復有神乎。」
答曰
「幡荻穗出吾也、
於
尾田吾田節
之
淡郡所居神之有也。」
問
「亦有耶。」
答曰
「於
天事代
於
虛事
代玉
籤入彥嚴
之
事代主神有之也。」
問
「亦有耶。」
答曰
「有無之不知焉。」
ーー↓↑ーー
???
「曲亭馬琴」・・・「くるわ(廓)でまこと(誠)」?
↓↑
「瀧澤馬琴」・・・「馬(うま・め・バ)の琴(こと)」?
ーー↓↑ーー
司馬 相如(シバショウジョ)・・・藺 相如(リンショウジョ)
↓↑ 趙(恵文王)vs秦(昭襄王)
「完璧帰趙」、「和氏の璧(辟+玉)」
「刎頸の交わり」、「刎頸の友」
廉頗vs藺 相如
琴柱に膠して弾くようなもの
「琴柱に膠す=琴柱を固定すると
必ずしも弾く度に
調律しなくてもよくなる代わりに
転調できなくなることから
融通が利かないことの喩え
「相如=十+八+目+女+口」=小序・少女
↓↑ 宗女・総序
↓↑ 相如=相対の如く?
紀元前179年~紀元前117年・・・壱壱七・壱百壱拾七
前漢の頃の文章家
蜀郡成都の人
字は「長卿(チョウケイ)」
名は「犬子(ケンシ)」
賦の名人
武帝に仕えた
妻は「卓文君」
前漢の官僚体制
「入貲」
飢饉などの際に
ある一定の穀物や
それに相当する金銭を納めることで
「郎」となることができた
司馬相如はこの方法で
「郎」となり
「景帝」に仕えた
後
武騎常侍
になる
↓↑
景帝の同母弟の
梁の
孝王
は
景帝を訪ねてきた際に
鄒陽・枚乗・荘忌(『漢書』では劉荘の諱を避けて厳忌)
などの文人・学者を連れて来てい
司馬相如は彼等と出会い
孝王の客になろうと思いたち
病として官を辞し
景帝のもとを去り
梁へと向い
司馬相如
は梁で
孝王の歓迎を受け
孝王の援助を受けて
文人などと共に住むことが許された
梁にいた期間に
司馬相如の代表作である
「子虚の賦」が書かれた
↓↑
景帝・・・「景・蛍雪」、「景行・天皇」
↓↑ 「景気」、「景星鳳凰」
「八景・風景・遠景・佳景・奇景」
「景品=おまけ・オマケ」
「(高橋)景保・景安(台湾)」
「景康=長尾 景康(越後守護代長尾為景の子
長尾晴景の弟
長尾景房・長尾景虎(上杉謙信)の兄」
「景康=津田 景康(仙台藩重臣・津田氏第3代当主
通称、津田玄蕃・伊達騒動の主要人物」
↓↑ 「瀬上 景康」・・・「景」etc・・・
前漢の
第六代皇帝
孝景皇帝
在位は
前157年7月14日~前141年3月9日
姓・諱は劉啓
諡号は孝景皇帝
生年は前188年
没年は前141年3月9日(旧暦1月28日)
父は
文帝
↓↑
景初(ケイショ)・・・景初元年=237年?
三国時代
魏の
明帝
曹叡
の治世の
3番目の元号
237年~239年
元年3月
改元改暦して
景初暦が施行
3年1月
明帝崩御
斉王
曹芳
即位
正史に本来は無い
「景初四年」銘の・・・景初の四年の「?」
三角縁神獣鏡が存在
↓↑
その治世期間は、
父、
文帝と重ねて
「文景の治」
と賞賛
後漢の創始者
光武帝
劉秀
と
蜀漢の創始者
昭烈帝
劉備
は景帝の末裔・・・
ーー↓↑ーー
卓文君
紀元前144年
孝王死亡
司馬相如
は故郷の成都に帰った
司馬相如の友人
臨邛県(四川省邛崍市)の県令
王吉
は、
臨邛県に来るよう誘い
司馬相如は赴いた
王吉は
大富豪である
卓王孫・・・卓=ト+日+十
卓(タク)の王(オウ)の孫(まご)
の宴会に
司馬相如
を連れて行き
王吉は
司馬相如
に
琴・・・・・・・・・・琴(こと・キン)=王+王+今
を披露するように頼んだ
司馬相如
は見事に琴を弾き
宴会の人たちを魅了
↓↑
卓王孫
には夫に先立たれ
実家に戻っていた
卓文君・・・・・・・・卓の文の君(きみ・クン)
という娘がいた
卓文君は
司馬相如の奏でる
琴の音に魅了され
司馬相如
に惚れてしまった
そこへ
司馬相如
からの
恋文が届いた
卓文君は
家を抜け出し
司馬相如
と駆け落ち
卓王孫は激怒し
娘には一切財産を分けないと言った
卓文君は
自分の所有物を売り払い
臨邛の街に
酒場を開き
卓文君は自ら女給として働き
司馬相如は上半身裸で
召使いのように働いた
卓王孫は娘を恥じ
卓文君に召使いを
100人、100万銭
前回の結婚の際の嫁入り道具を与え
司馬相如との結婚を認めた
2人は成都に移り住み
土地を買い入れ
地主となった・・・メデタシ、めでたし・・・?
↓↑
景帝が死に
武帝が皇帝の位につき
武帝
は文学を大変好み
「子虚の賦」
を読んで、大いに感動し
「この賦の作者と
同じ時代に生きられなかったのは残念だ」
と
武帝は
「子虚の賦」・・・・「子の虚の賦」
が
昔の人によって書かれたモノと誤解していた
司馬相如と同郷である側近の
楊得意
という者が
「子虚の賦」・・・「烏有」=烏(いづくんぞ)
有らむや
(どうして有ろうか、
有ろうはずがない)の意
の作者が今生きている
司馬相如である
と
武帝に教えた
↓↑ ↓↑ ↓↑
武帝は
司馬相如を召し
そのとき
司馬相如は
「子虚の賦」が
諸侯のことを書いた内容であり
天子(皇帝)にたてまつるのには
ふさわしくないと言った
そして、
司馬相如は天子にふさわしくなるように
「子虚の賦」を改作して
「天子游獵賦
(『文選』では「子虚賦」と「上林賦」に分割
「子虚・上林賦」と称されることが多い)」
として
武帝にたてまつった
武帝は喜び
司馬相如
を
觔に復職させた・・・
↓↑
景初暦(ケイショレキ)
魏の明帝
景初元年(237年)から
晋を経て
劉宋の文帝
元嘉二十一年(444年)まで
また北朝の
北魏では
道武帝
天興元年(398年)から
太武帝
正平元年(451年)まで
使用された
太陰太陽暦の暦法
後漢・魏・西晋の
「楊偉(ヨウイ)」
によって作られ
晋王朝成立後の
「泰始元年(265年)」に
泰始暦が行われたとされているが
実際は
景初暦と同一のもの
計算上の暦元は
干支
丁巳の
景初元年~4045年前の
干支
壬辰年の夜半
甲子朔旦冬至(晋書・律暦下)
月の運行の遅疾に関する計算が
暦に取り入れられ
天体暦として
日月食の開始時刻などを
推算する方法を確立
ーー↓↑ーー
倭人の登場
ーー↓↑ーー
論衡
「周時天下太平 倭人來獻鬯草」(異虚篇第一八)
(周の時、天下太平にして、
倭人来たりて
暢草を献ず)
「成王時 越裳獻雉 倭人貢鬯(恢国篇・第五八)」
(成王の時、
越裳は雉を献じ、
倭人は暢草を貢ず)
・・・「恢=カイ・クヮイ・広い・大きい
・・・かい国=甲斐国・魁刻(北斗七星)?
=忄(心)+灰(厂火)
「忄=立心偏→立身編」
・・・心は灰色(ガンダレのヒ)?
恢恢=盛んにする・大いに
恢復=一度悪い状態になったものが
元の状態に戻ること
一度失ったものを取り戻すこと
↓↑
「周時天下太平
越裳獻白雉
倭人貢鬯草
食白雉服鬯草
不能除凶(儒増篇第二六)」
(周の時は天下太平
越裳は白雉を献じ
倭人は鬯草を貢す
白雉を食し鬯草を服用するも
凶を除くあたわず)
↓↑
「暢草=酒に浸す薬草」
↓↑
王充(オウジュウ)
27年~97年)の書
王充は
会稽(カイケイ)郡
上虞(ジョウグ)県
で生まれた
江南人ではなく華北からの移住者
王充は
『漢書』の著者
班固
より5歳年長の先輩で、知人
自由で合理的・実証的な精神によって時弊を痛論
讖緯(シンイ)思想
陰陽五行思想・・・五行思想のスベテが不合理ではない
に対して強く批判
迷信や不合理を斥け
儒家、道家、法家
などの言説も批判・・・
ーー↓↑ーー
山海経
↓↑
「蓋國在鉅燕南 倭北 倭屬燕(山海經 第十二 海内北經)」
(蓋国は鉅燕の南、倭の北にあり。
倭は燕に属す)・・・燕国=山東半島=「北燕=匽」
・・・地理的支配領域なら倭は朝鮮半島北部
・・・政治的従属関係領域なら倭は半島南部+日本列島
↓↑
山海経の編纂時代
倭は燕に朝貢していた・・・
「架空の国・架空の産物」の記述・・・
『山海経』第九 海外東經
東方の海中に「黒歯国」があり
その北に「扶桑」が生える太陽が昇る国がある・・・
「黒歯国・扶桑国」が架空の国ではないだろう・・・
↓↑
『三国志』魏書東夷伝倭人条(魏志倭人伝)
「去女王四千餘里
又
有
裸國
黒齒國
復在其東南船行一年可」
(女王=卑弥呼の国から
4000余里に裸国と黒歯国がある
東南に船で一年で着く
↓↑
『梁書』卷五十四 列傳第四十八 諸夷傳 東夷条 倭
「其南
有
侏儒國
人長三四尺
又南
鄢齒國 裸國
去
倭
四千餘里
船行可一年至」
(南に身長三四尺の人の国があり
その南に
黒歯国と裸國がある
倭から4000余里去って
船で1年で着ける)
↓↑
百越人(春秋時代の呉人)と倭人の関係
『山海経』
古代中国では
「倭(九州)」が
「太陽が昇り扶桑の生える」
「九夷」として憧れの地・・・
↓↑
『宋書』の楽志、
「白紵舞歌」
その一節に
「東造扶桑游紫庭
西至崑崙戯曽城」
(東、扶桑に造りて
紫庭に游び
西、昆崙(崑崙)に至りて
曾城に戯る
「(白)紵」というのは
「呉(春秋時代)」に産する織物
「香椎(カシ)」は
「百越人」地帯としての「越(コシ)」の訛り
春秋時代末期に
「越」によって滅ぼされた
「呉」の海岸沿いの住人たちが
渡来、漂着した所が筑紫
↓↑
『論語』子罕第九に「欲居九夷」
「孔子、柔順な九夷に居すを欲す」
「罕(まれ・カン)=長い柄のついた鳥をとる網・鳥あみ
柄のついた旗
まれに・たまに・すくない・めずらしい
罕に=まれに. めったにない・ごく珍しいさま
「子は罕に利を言う」
↓↑
『論語』公治長第五
「子曰く、道行われず。海に浮かぶべし
(子曰、道不行、乗桴浮于海)」
(孔子が言った
中国では道徳が受け入れられないから
東の海にある
九夷にいきたい)
↓↑
『前漢書地理志』
「然東夷天性柔順、異於三方之外
故孔子悼道不行
設浮於海欲居九夷、
有以也夫。
楽浪海中有倭人
分為百余国
以歳時来献見云」
(然して東夷の天性柔順、三方の外に異なる
故に孔子、道の行はれざるを悼み
設(も)し海に浮かばば、九夷に居らんと欲す
以(ゆゑ)有るかな。
楽浪海中、倭人有り
分かれて百余国を為す
歳時を以て来たり献見すと云ふ)
↓↑
『隋書』東夷傳の倭の条
「・・・九夷所居、與中夏懸隔、然天性柔順・・・」
(倭は・・・九夷の居るところ・・・その天性は柔順」
↓↑
「漢書(前漢書)」地理志
「然東夷天性柔順
異於三方之外
故孔子悼道不行
設浮於海
欲居九夷
有以也夫。
樂浪海中有倭人
分爲百餘國
以歳時來獻見云」
(然して東夷の天性柔順
三方の外に異なる
故に孔子、道の行われざるを悼み
設(も)し海に浮かばば
九夷に居らんと欲す
以(ゆゑ)有るかな
楽浪海中に倭人あり
分ちて百余国と為し
歳時をもつて来たりて献見すと云ふ
↓↑
楽浪郡
前漢(紀元前202年-8年)
武帝が
紀元前108年
衛氏朝鮮の故地に設置
漢四郡の一つ
平壌付近
漢四郡
真番郡・玄菟郡・楽浪郡・臨屯郡
倭人国は
『漢書』地理志が初発
楽浪の海を越えた所に
百余国に分かれた
倭人の国
弥生中期の後半(紀元前1世紀頃)
撰者
班固
が後漢の初め頃に編纂
↓↑
「後漢書・東夷傳」
「建武中元二年
倭奴國奉貢朝賀
使人自稱大夫
倭國之極南界也
光武賜以印綬」
(建武中元二年(57年)、
倭奴国、
貢を奉じて朝賀
使人自ら大夫と称す
倭国の極南界なり
光武賜うに印綬を以てす
「安帝
永初元年
倭國王
帥升
等
獻
生口
百六十人
願請見」
(安帝、
永初元年(107年)
倭国王
帥升等
生口160人を献じ
請見を願う)
「金印(倭奴国王印)」は
江戸時代、
博多湾・志賀島で発見掘り出された
「漢委奴國王」と刻印されている
「委奴=いと・ゐど(伊都国)」
「漢の委奴(いと・ゐど)の国王」・・・
↓↑
『北史』倭国伝
「安帝時、又遣朝貢、謂之倭奴國」
(安帝の時(106~125年)
また遣使が朝貢し、これを倭奴国という)
↓↑
『隋書』倭国伝
「安帝時、又遣使朝貢、謂之倭奴國」
(安帝の時(106-125年)
また遣使が朝貢
これを「倭奴国」という)
↓↑
『旧唐書』倭国・日本国伝
「倭國者、古倭奴國也」
(倭国とは、古の「倭奴国」なり)
↓↑
『後漢書』の
安帝紀の
永初元年(107年)の記事が
初めてである
「冬十月,
倭國遣使奉獻。
辛酉,
新城山泉水大出」
↓↑
「檀石槐伝」
『後漢書』卷九十
烏桓鮮卑列傳第八十の
檀石槐伝
「光和元年冬
又寇酒泉
縁邊莫不被毒
種衆日多
田畜射獵不足給食
檀石槐乃自徇行
見烏侯秦水廣從數百里
水停不流 其中有魚
不能得之 聞倭人善網捕
於是
東擊
倭人國 得千餘家
徙置秦水上
令捕魚以助糧食」
↓↑
『三国志』より古い時代を書いているが
成立は三国志より遅い
五世紀に書かれた 范曄は
『漢書』、『三国志』、『魏略』
なども読むことができた・・・
「倭の五王」の「上表文」
も知っていた
↓↑
范曄(ハンヨウ)
398~445
魏志より2世紀近くも後に編纂された
↓↑
「魏志倭人伝」
「倭人
在
帶方東南大海之中
依山島爲國邑
舊百餘國
漢時有朝見者
今使譯所通
三十國」
(『三国志』魏書巻三〇「烏丸鮮卑東夷伝 倭人の条」)
(倭人は帯方郡の東南の大海の中におり
山の多い島のうえに
国や邑(むら)をつくっている
もとは百あまりの国があり
その中には
漢の時代に朝見に来たものもあった
いまは使者や通訳が往来するのは
三十国である
↓↑
東夷伝
夫余・高句麗・東沃沮・挹婁・濊・馬韓・辰韓・弁辰・倭人
の九条が含まれ
東夷伝の九条とも
大体三部から構成
倭人伝
第一部はその周辺との
関係位置や内部の行政区画の記事、
第二部はその経済生活や日常習俗の記事
第三部はその政治外交上の大事件の記事
↓↑
夷伝の韓伝冒頭
「韓在帶方之南
東西以海爲限
南與倭接
方可四千里」
(『魏志』韓伝)
(韓は帯方の南に在り
東西は海をもって限りとなし
南は倭と接する
方4千里ばかり)
↓↑
倭人伝の時代
後漢の終わり頃から
三国鼎立の時代
同時代の 王沈の書
『魏書』に東夷伝がなく
『三国志』には
中国の皇帝の歴史を書くべき史書であったが
陳寿の
『魏志』倭人伝だけが
約二千字という
膨大な文字を使って細かく
邪馬台国のことを記録
「倭人は鉄の鏃を使う」
との記述・・・
↓↑
『三国志』
『魏書』三十巻
『呉書』二十巻
『蜀書』十五巻
通称は
『魏志』『呉志』『蜀志』
で
魏の
文帝の
黄初元年から
晋の
武帝の
太康元年にいたる間
(220年~280年)
の魏・蜀・呉の
三国鼎立時代
60年間の歴史を書いたもので
正史二十四史の
第四番目に位置
晋が天下を統一したころ
太康年間(280~289)
全六十五巻を
陳寿が撰述
陳寿の死後
『史記』『漢書』『後漢書』
の「前三史」に加え
「前四史」と称される
↓↑
華北に魏
華中・華南に呉
長江(揚子江)の上流
四川を中心にして蜀
南北に対立した
魏の範囲と
呉の範囲は
のちの
南北朝時代にもそれぞれ
北朝と南朝として地域的対立
中国では中央に居住する
華夏族(漢民族)に対して、
その周辺に居住するものを
東は夷
南は蛮
西は戎(ジュウ)
北は狄(テキ)
と称した
↓↑
晋書
太康十年(289年)の条
「東夷絶遠三十餘國
西南二十餘國來獻」
絶遠の国が日本である・・・
↓↑
日本については
東夷伝と
武帝紀に記録
↓↑
邪馬台国の記述
266年に倭人が来て
円丘・方丘を南北郊に併せ
二至の祀りを二郊に合わせた
と述べられ
「前方後円墳」のおこりを記したもの・・・
↓↑
「宋書」
「自昔祖禰 躬擐甲冑 跋渉山川
不遑寧處
東征毛人五十國
西服衆夷六十六國
渡平海北九十五國」
(『宋書』倭国伝)
(昔から祖彌(ソデイ)躬(みずか)ら
甲冑を環(つらぬ)き
山川(サンセン)を
跋渉(バッショウ)し
寧処(ネイショ)に遑(いとま)あらず
東は毛人を征すること、五十五国
西は衆夷を服すること六十六国
渡りて海北を平らぐること、九十五国
↓↑
「詔除武使持節
都督倭新羅任那加羅秦韓慕韓六國諸軍事
安東大將軍、倭王」
(詔を以て武を使持節
都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事
安東大将軍、倭王に叙爵した)
宋へ朝貢し
宋が倭王(武)へ朝鮮半島の支配を認めた
↓↑
宋の
文帝の命によって
439年(元嘉十六年)
から編纂が始まり
何承天・山謙之
琲裴之(ハイショウシ)
徐爰(ジョカン)
らの文人たちによって継続
487年(永明五)
南斉の
武帝の命を受けた
沈約(シンヤク)が
翌年(元嘉十七) 本紀10巻
列伝60巻
を完成させ
志30巻は
502年(天監元)に完成
『宋書』は宋王朝の官府に集積されていた史料を 実録的に記述
↓↑
倭の五王の中の
珍に関係する記述が
列伝の
倭国条だけでなく
本紀の
文帝紀にもある
↓↑
沈約
斉の著作郎(歴史編纂の長官)
↓↑
「南斉書」
日本関係は
東南夷伝に記録
冒頭は前正史の記述を妙略して引き
中国から見た
倭国の位置や女王の存在などを記録
↓↑
479年
倭国の遣使を記し
倭王武を
使持節都督
倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓 六国諸軍事
安東大将軍
と称号などが記録
↓↑
「梁職貢図(新羅題記)」
時期不明
521年以前
斯羅國本
東夷
辰韓之小國也
魏時曰
新羅
宋時日
斯羅其實一也
或
属韓
或
属
倭國
王
不能自通使聘
↓↑
「梁書」
唐の著作郎
姚思廉(ヨウシレン)
が太宗の命を受けて編纂
636年(貞観十)に完成
↓↑
梁書巻五四の諸夷伝
倭に関する記述
倭の五王名や続柄が
『宋書』と異なっている・・・
↓↑
『北史』倭国伝
漢
「光武時、遣使入朝、自稱大夫」
後漢の
光武帝の時(25~57年)
遣使が入朝
大夫を自称
「安帝時、又遣朝貢、謂之倭奴國」
(安帝の時(106~125年)
また遣使が朝貢、これを倭奴国という)
↓↑
「卷八十一 列傳第四十六 東夷 俀國」に、
「男女多黥臂點面文身 没水捕魚」
(男女多く臂(うで・ひじ)に
黥(ゲイ)す
黥面文身し
水に没し魚を捕る)
608年
隋使裴清(裴世清)の
一行の見聞や観察を基礎にしたもので 7世紀初頭の倭人社会の資料である
「新羅 百濟
皆以
俀爲大國
多珎物
並敬仰之
恒通使往來」
(新羅・百濟は
みな俀を以て大国とし珍物多しとなす
並びにこれを敬い仰ぎ
恒に使いを通わせ往来す)
↓↑
「倭人が鉄を使用」という記述・・・
↓↑
「大業三年
其王
多利思北孤
遣使朝貢
使者曰
聞海西菩薩
天子重興佛法
故遣朝拜
兼 沙門數十人來學佛法」
(大業三年(607年)其の王
多利思北孤
使いを遣わして朝貢
使者曰く
『海西の菩薩天子
重ねて仏法を興すと聞く
故に遣わして朝拝せしめ
兼ねて沙門数十人来りて
仏法を学ぶ。』
と。
(俀の王からの使者が来て
隋を訪問した目的を述べたことが記述)
「海西の天子は
重ねて(熱心に)
仏法を起こしていると聞き
そのため沙門(僧侶)を送って
仏法を学ぶために来た」
海西の菩薩天子とは
海の西の方の天子
開皇十一年(591年)
菩薩戒により
総持菩薩となった
煬帝を指している
直後に
「日出處天子致書日沒處天子無恙云云」
の記述
↓↑
『隋書』東夷傳
「九夷所居、與中夏懸隔、然天性柔順」
九夷(中国の東に住む諸民族)が居る所は
中華から遠くにあり
(九夷の)天性は柔順である
↓↑
「旧唐書」
日本について
『倭国』
と
『日本国』の条がある
↓↑
「倭國者古倭奴國也
去京師一萬四千里
在新羅東南大海中
依山島而居
東西五月行
南北三月行
世與中國~
日本國者
倭國
之
別種也
以其國
在
日邊・・・・火邊=阿蘇山?
故以
日本爲名
或曰
倭國
自惡
其名
不雅
改爲
日本
或云
日本
舊小國
併
倭國之地
↓↑
『舊唐書』 東夷伝 倭國
(日本国は倭国の別種なり
その国
日辺にあるを以て
故に
日本を以て名とす
或いはいう
倭国
自らその名の
雅ならざるを悪み
改めて日本となすと
或いはいう
日本は
旧小国
倭国の地を併せたり
と)
(倭国は
「自らその名の
雅(みやび)ならざるを
悪(にく)み」
名を改めた)
↓↑
北宋時代に再編纂された
『新唐書』
にも同様の記述
新唐書では
「日本という小国を
倭があわし(合併し)
その号(日本の名)を
冒す(名のる)」
↓↑
「旧唐書(くとうじょ)」
五代十国時代
10世紀に
劉昫(リュウク)
らによって編纂された歴史書
二十四史の一
↓↑
倭国・倭人
『魏書』
王沈(オウシン・?~266年)
の著を
陳寿は参考にしている
東夷伝はなし ↓↑
『魏略』は
魚豢(ギョケン)撰の著
佚文(逸文)として
『前漢書』、『翰苑』、『北戸録』
『魏志』、『法苑珠林』
に残る
清代に
張鵬一(チョウホウイツ)
が諸書の逸文を集めて
『魏略輯本』を編集
裴松之(ハイショウシ・371年~451年)
は
宋の文帝の命を受けて
426年(元嘉六年)に
『魏志』に関する「注」を実施
裴松之注(註)
あるいは 「裴注」という
この注は
陳寿の省略した
諸事実や
陳寿が
簡潔に述べている事柄などについて
裴松之が入手しえた
諸資料を関係箇所に「注」として補った
『翰苑(カンエン)』
は唐の
張楚金(チョウソキン)編集の類書で
蕃夷(バンイ)部のみが
太宰府天満宮に唯一現存
日本に唯一伝存している
『翰苑』は9世紀に
書写されたものであるが
誤字や脱漏が多い
『魏略』の引用が多い
『史通(シツウ)』は
唐の
劉知幾(リュウチキ)撰
『太平御覧』は
北宋の太宗の勅を受けて
李棒纊(リホウ)
等が編纂した類書
この書が類書の中では最も良書
その引用には
原文を簡略にした箇所も多
後代の
史書『晋書』、『梁書』
などが
倭人の出自に関しては
一致して
「太伯之後」 という文言を記している
「旧語を聞くに
自ら太伯(タイハク)の後という」 の文章が両書にあって
倭人伝にはない。
ーーーーー
燕国
その具体的な位置
後の玄菟郡の「蓋馬」(西蓋馬県、蓋馬大山など)
遼東半島の「蓋平」(遼寧省営口市)
鉅燕を『史記』の「全燕」と同じとみて
山東半島の
「蓋(ガイ)」(山東省淄博市沂源県)
朝鮮半島江原道の
「穢(カイ)」
馬韓の
「乾馬」(全羅南道益山)
推測される「倭の位置」も大きく違ってくる・・・
ーーーーー
・・・南国の「渡り鳥」である「つばめ(津波目・燕)」なら「新潟・越後」である・・・
燕(紀元前1100年頃~紀元前222年)
中国に周代、春秋時代、戦国時代
に存在した国
春秋十二列国の一つ
戦国七雄の一つ
河南省の・・・「中国の八大古都の四つ
(鄭州、洛陽、開封、安陽)は河南省に位置」
北京=北緯39度54分20秒
燕=つばめ=津波目=北緯37度4分
「南燕国(豫州→首都は鄭州)」・・・鄭(酋大阝)の州?
に対して
「北燕」
ともいう・・・首都は「燕都・薊城」・・・
当時
「燕」ではなく
「匽」と書いていた・・・「奄=匽=燕」
山東半島の「奄」(魯の近隣)
ーーーーー
・・・
和史の瑕疵・・・仮史・・・
・・・「厲」の漢字・・・「厲=厂+萬」・・・「和氏の璧(カシのヘキ・ワシのタマ)」・・・なぜ、「和氏」が「カシ」?と音読みされるんだが・・・「瑕疵の璧」じゃぁないョなッ・・・「和=呉音はワ・カ(クヮ)、漢音はオ(ヲ)」、「訓読みは、やわらぐ・やわらげる・なごむ・なごやか・あえる・なぐ・なぎ・和解・和合・和平・共和・協和・講和・親和・平和・宥和・融和」・・・そうはいかないのが「世の中」・・・「市民社会」で生きて行くことは個々人、エゴの「白璧微瑕」、「披毛求瑕」は当然だから・・・だが「独裁者の国家のエゴ」は困る・・・
ーーーーー
喜怒哀楽の未だ発せざる
之れを中と謂ふ
発して皆な節に中(あた)る
之れを和(ワ)と謂う
↓↑
喜怒哀楽之未発、
謂之中。
発而皆中節、
謂之和。
↓↑
中也者、天下之大本也。・・・大(一の人)の本
和也者、天下之達道也。・・・達(幸の辶)の道
致中和、天地位焉。
萬物育焉。
(中庸)
↓↑
やわらぐ・ゆったり
↓↑
和人=倭人=俀人・・・日の本の人・・・陽の本の人
↓↑
和気
和光同塵=光を和(やわらげ)て塵(チリ)に交わる
比仮理を夜話等解 埃・地理
↓↑
温和・穏和・緩和・清和・柔和
混和・中和・調和・飽和
和韻・和音・和声・唱和
和琴・和事
総和
和歌・和裁・和室
和紙
和食・和菓子
和風・和服
和算・和様・和洋
和解
英和・漢和
↓↑
和帝=後漢の第4代皇帝・諱は劉肇
生没は79年~105年
在位は88年~105年
章帝の四男
生母は梁貴人
皇后竇氏(トウシ)の
養子となり
七歳で即位
息子は殤帝
平原懐王劉勝
宦官の鄭衆に援けられ実権を握る
永元四年(92年)
班固・班昭兄妹による『漢書』の完成
永元十七年(105年)
蔡倫による製紙法
和帝の死後は宦官政治の腐敗・・・
↓↑
和睦・和合
大和 (やまと)の 国・和州
和尚 (オショウ)
和尚(カショウ・ワジョウ)とも
名乗り
あい・あつし
かず
かた
かつ・かのう
たか・ちか
とし・とも・のどか
ひとし・まさ・ます・むつぶ
やす・やすし
やまと・やわら
よし・より
わたる
↓↑
和泉 (いずみ)
和蘭 (オランダ)
和栲 (にきたえ)=細い繊維で緻密に織った布
打ってやわらかくした織物
和毛 (にこげ)=鳥獣の柔らかい毛
人の柔らかい毛
産毛(うぶげ)
和布刈 (めかり)=ワカメ(若芽・若布・和布)などを
刈り取る神事
山口県下関市の住吉神社
福岡県北九州市の和布刈神社
大和 (やまと)
和布 (わかめ)
日和見(ひよりみ)
ーーーーー
関東大震災
1923年癸亥(戊・甲・壬)
0009月庚申(己・壬・庚)
0001日丁丑(癸・辛・己)
↓↑
0008時甲辰(乙・癸・戊)
↓↑
0011時乙巳(戊・庚・丙)
↓↑
0012時丙午(丙・ ・丁)
↓↑
0014時丁未(丁・乙・己)
ーー↓↑ーー
「和氏の璧(カシのヘキ、たま)」
春秋時代・戦国時代の故事
名玉
『韓非子』(和氏篇十三)・・・和の氏の篇の十三
(拾う参=比賂得)
『史記』に記録
「連城の璧」とも称する
和氏の璧 (カシのヘキ)
真実がそのまま真実であると認められ難い
貴重な宝石のたとえ
「和 氏」は
楚の
卞和(ベンカ)という人物のこと
「璧」は宝玉のこと
「卞和が山中で宝玉の原石を見つけ、
厲(厂+萬)王(レイ)王に献上したが、
ただの石だと言われ
罰として左足を切られた」
・・・「厲(厂+萬)王(レイ)王=蚡冒(フンボク)
?~ 紀元前741年
在位は紀元前757年頃~紀元前741年)
中国春秋時代初期の
楚の君主
姓は
羋(ビ・バ・マ・ミ)
・・・羊が鳴く・楚の姓
「羊鳴くなり(説文解字)」
羋=牟・・・「竎」=「哶」
「嘷=ほえる・さけぶ・コウ・ゴウ」
諱は坎(カン)、または鹿(ロク)
若敖(ジャクショウ)の子
↓↑
燕の太子、
「平」は、
「斉」より援軍を得ると
政権奪還を試みるが
「子之 (シシ)」 に破れ
最期を遂げる
↓↑
燕の
「羋八子 (ビハツシ)」 親子も
危険から逃れようと
燕を脱出
張儀は
趙と同盟すべく趙王に謁見
秦との同盟の利を説く張儀に対し
懐疑的な趙王は
「秦と斉は共に趙の敵である」と言い
燕の
「羋八子」親子を保護してると張儀に告げ
同盟の条件として
「羋八子」親子を
趙の人質とすることを迫った・・・?
↓↑
「厲(厂+萬)王(レイ)王=蚡冒(フンボク)」は
氏は熊(ユウ)
諱は眴(ジュン)・・・眴(めくばせ・まばたき
ケン・ゲン・シュン・ジュン
=素早く視線を走らせたり
目で合図すること・めくわせ
霄敖(ショウゴウ)の子・・・霙(みぞれ)・おおぞら
君主号の
「蚡冒(フンボク)」・・・蚡=もぐらもち・フン・ブン
↓↑ mole=二重スパイ
黒子(ほくろ)
染み(しみ)
雀斑(そばかす)
痣(あざ)
冒(おか)す・冒頭・冒険
冒涜 (ボウトク)・感冒・貪冒
おかす?・・・「よこしま=邪」・・・
犯=決まりを無視する・法律を犯す
侵=他人の許可なく入りこむ・他人の土地を侵す・侵略
冒=将来の事を考えずに行動・危険を冒して無謀行為
↓↑
は『春秋左氏伝』の表記
『韓非子』や『楚辞』では
「厲(厂+萬)王(レイオウ)」
と表記・・・
紀元前741年
弟の熊徹に殺され
熊徹が跡を継いで後の
武王となった
(蚡冒と熊徹を親子関係とするのは
『春秋左氏伝』による
『史記』では熊徹は蚡冒の弟で
蚡冒の死後に
熊徹が
蚡冒の子を殺して跡を継いだとされる)」・・・
↓↑ ↓↑
「厲(厂+萬)王没後
卞和は同じ石を
武王に献上したが
今度は左足切断の刑に処せられた」
「文王即位後
卞和はその石を抱いて
3日3晩泣き続けた
文王がその理由を聞き
試しにと原石を磨かせたところ
名玉を得た
その際
文王は不明を詫び
卞和を称えるため
その名玉に「卞和(ベンカ)」の名を取り
「和氏の璧」と名付けた」
「厲(厂+萬)=厳しい・厳格・厲禁=厳禁する
いかめしい・厳粛
厲=色厲内荏
すさまじい・ひどい・激しい
といし・とぐ・あらと・みがく
はげむ
え病み・病む・災い・疫病・厲(厂+萬)疫
はげしい・きびしい
するどい
はげむ・はげます
厲(厂+萬)行
↓↑
膠=肉+羽+𠆢+彡=にかわ・コウ
動物の皮や骨などを煮つめて作った接着剤
膠化・膠漆・膠着
にかわする・にかわで接合
つく・ねばりつく・かたくくっつく
かたい・質がかたい
もとる・あやまる
「膠膠」は動き乱れるさま
膠=コウ・カウ・にかわ・ゼラチン
膠化・膠質・膠原病
ねばりつく
膠=獣や魚の皮、骨などを水で煮沸し
その溶液からコラーゲンやゼラチンなどを抽出し
濃縮・冷却して凝固させたもの
接着剤・写真乳剤・染色などに用いる
膠下地=漆器で、「にかわ」を塗って下地としたもの
glue・fasten with glue.
括り付ける
Keep your seatbelt (securely)fastened
securely=シィキュゥ(ル)リィ
ーーーーー
・・・???・・・
「ノ」と「一」を「膠=にかわ=似掛話」でくっつける・・・
↓↑
「ノ一」=「かんざし(簪・髪挿し)」
冠の付属品
巾子(こじ)に入れた
髻(もとどり)を横にさし貫き
冠が落ちないようにとめる細長い金具
髪飾り
女性の頭髪に挿(さ)す装飾品
挿し櫛(くし)
女性の髪(かみ)飾(かざ)りの櫛(くし)
ーーーーー
・・・髪飾(ハッショク)・・・発色・捌色・・・撥初句・・・
わめき・ザワメキ・怒号・・・
・・・「梶(名は不詳)」と「梶美千子」・・・「生き物の条件」ではなく、「人間の条件」・・・
ーーーーー
𣑥・・・𣑥領巾(たくひれ)
↓↑
栲(木+考)=木+考
𣑥(木+土+ノ+丁)・・・丁=一+亅
カジのキ(梶の木)などの・・・梶=木+尾
繊維で織った白い布・布類の 総称
カジのキ(梶の木)=桑(クワ)科-楮(コウゾ)属の
落葉高木
カジ(梶)
コウ(構)とも呼ばれる
栲(こうぞ)、または
梶(かじ)の木
「栲」=英語は「paper mulberry」
↓↑
栲幡千千姫命
(たくはたちぢひめのみこと)
萬幡豊秋津師比売命(古事記)
(よろづはたとよあきつしひめのみこと)、
栲幡千千姫命(日本書紀)
栲幡千千媛萬媛命(一書)
(たくはたちぢひめよろづひめのみこと)
天萬栲幡媛命(一書)
(あめのよろづたくはたひめのみこと)
栲幡千幡姫命(一書)
(たくはたちはたひめのみこと)
天照大神の子の
天忍穂耳命と結婚し
天火明命
と
瓊瓊杵尊
を産んだ・・・
↓↑
「栲(たえ)」=カジノキ・藤・麻などからとった繊維
それで織った布
「臣の子はカジノキの袴を七重をし(日本書紀・雄略)」
布類の総称
↓↑
丹比真人笠麿
紀伊国に往きて勢の山を越ゆる時作る歌一首
𣑥領巾(たくひれ)の 懸( か)けまく欲しき
妹が名を
この勢の山に
懸けばいかにあらむ
(萬葉集 巻3-285
丹比 真人 笠 麿
(たじひのまひとかさまろ)・・・他比 万訊 掛作馬賂?
↓↑
「𣑥(木+土+ノ十丁=十八十一ノ丁)」
の領巾(ヒレ)を懸けるように
口に懸けたい(口に出して言いたい)
妹という名を、
この勢(背)の山につけたらどうだろう
↓↑
楮(こうぞ→恋うぞ・請うぞ)
=𣑥(たく→卓)・・・司馬相如の妻は
「卓文君」だった・・・択文訓?
=妙(たえ・たゆ)=
木綿(ゆふ・もめん)
などは
コウゾの繊維で織った布
↓↑
太布(たふ)
綿花以外の植物繊維で織られた布全般
楮(こうぞ)や藤蔓から作られた布
太布の材料
麻(苧麻、大麻)、藤、葛、楮、𣑥、科(シナ)
アッシ
苧麻=糸を引き出す寸前にまで加工した
青苧(アオソ)の名称
↓↑
現在、日本で木綿の太布を生産しているのは
徳島県
那賀郡
那賀町
木頭(旧木頭村)の
阿波-太布-製造技法保存伝承会だけ
↓↑
材料や用途により、工程の合間や、布が仕上がった後に
木槌などで叩いて繊維をしなやかにする(砧打ち)
「𣑥領巾の」は「カケ」にかかる枕詞
↓↑
𣑥領巾(たくひれ)
楮(コウゾ)の繊維で織った
白い布で作った丈の長い肩掛け・・・
muffler・scarf・shawl・stole・角巻(かくまき)
ーーーーー
・・・「角巻(かくまき)=毛織物の肩掛け・四角な形の毛織物でできた大形の肩掛け。三角に折って頭からすっぽり かぶり寒気や雪を防ぐ。主に東北地方の婦人が用いる」・・・
「マフラー (muffler)=スカーフ(scarf)=防寒具・首周りにまいて寒さを防ぐ・襟巻き」・・・
「shawl(ショール)を頭にかぶり端を首に巻くスタイル」・・・昭和28年(1953)公開の映画「君の名は」の主人公、「真知子巻き」・・・
「stole(ストール)を肩からぐるりと一周させて耳や頭をくるませる」・・・
muffler=排気管のマフラー
silencer=消音器
「音=亠(ズ)=音の省略漢字」を抑える装置・・・
「muffle・scarf」・・・
「sound」
「noise・din(騒音)」
「clamor(どよめき・やかましさ・喧騒)」
「roar=エンジン・大砲・風・海などの轟音
猛獣の咆哮・わめき・唸り
どなる、叫ぶ・怒号」
「the roar of the waves(波音)」
「boom(ブーム)=砲声・雷・波などの轟(とどろ)き」
「the booming of the sea(波音・ざわめき)」
・・・
イージス(aegis)カン
・・・「イージス(aegis)艦」、脆い・・・操る人物もモロイ・・・「イージス(Aegis・Egis)=ギリシア神話の女神アテナ(Athena・Athen・アシナ・アテネ)が用いる楯(盾)=アイギス」・・・「アテネ(Athens)女神」=「Minerva(ミネルバ・ミネルバ・ミナーヴァ・ミネルヴァ・ミネルウァ(ラテン語=Minerva)女神」で、「詩・医学・知恵・商業・製織・工芸・魔術を司るローマ神話の女神・英語はミナーヴァ)」、「ふくろう=梟(鴞・シマフクロウ・コタンコロカムイ)・鵂(休鳥)・鶹(留鳥)・鵩(服鳥)・夜行性の猛禽類」・・・「ふくろう=不苦労・福老」・・・「ふくろう」が「知恵の象徴」とは、夜間(黄昏飛翔)でも視通す丸い目にあると思うが、同類の「みみづく」は「ウサギの耳のような羽角(ウカク)=その形態の耳(聴覚)」を有する「ミミヅク=木菟・木兎・鵩・鶹・鵂・角鴟・鴟鵂・耳木菟・耳木兎・古名はツク、ズク)」で、「羽角(ウカク・哺乳類の耳介のように突出した羽毛)がある種の総称」、異なった漢字の訓読みは「フクロウ」も「ミミヅク」も同じらしいが、「みみづく(耳付く?・耳突く?)」の分類では、「羽角(ウカク)」の無い「ふくろう(梟→怖宮婁・袋鵜→誣宮鸕?)」を含める場合と、含めない場合がある」らしい・・・「ツク=角毛・鳴く」・・・
↓↑
「ふくろう」
「角鴟(カクシ)・鴟鵂(シキュウ)
鴟(シ)=鳶(トビ)・梟(フクロウ)類の総称」
「昼隠居(ひるかくろふ)・不幸鳥・猫鳥
ごろすけ・ほろすけ・ほーほーどり・ぼんどり
古語で飯豊(いひとよ)
梟(ふくろう)は
母親を食べて成長すると考えられ
不孝鳥の異名もある」・・・
「目の位置は、
他の種類の鳥が頭部の側面にあるのに対して
人間と同じように頭部の前面に横に並んでいる
虹彩は黒や暗褐色
嘴は先端が鋭く
視野の邪魔にならないように短く折れ曲がってい
色彩は緑がかった黄褐色
趾は羽毛で被われ
指が前後2本ずつに分かれ
大きな指の先に鋭い鉤状の爪が付いている
ミミズクにある羽角はなく
耳は目の横にあり
顔盤の羽毛で隠れている」
・・・小鳥類、鼠(ハタねずみ)、栗鼠(りす)、蛇、蜥蜴など爬虫類、蛙(かえる)など両棲類の小動物、昆虫類などを捕獲、捕食する・・・
「ふくろう=鴟梟(シキョウ)・たけだけしい・つよい・晒し首にする」・・・
「梟悪(キョウアク)・梟首(キョウシュ)・梟将(キョウショウ)・梟木(キョウボク)・梟勇(キョウユウ)・梟雄(キョウユウ)・さけ・梟帥=たける=建」・・・
ーーーーー
培養肉=動物の個体からではなく、
可食部の細胞を組織培養することによって得られた肉
動物を屠殺する必要がない
厳密な衛生管理が可能
地球環境への負荷が低い
低価格化することができる人工肉
10億頭のブタ、15億頭のウシ、190億羽ものニワトリ
羊も魚類も、その他、生きている命・・・
↓↑
家畜から細胞を単離して培養、人工肉の培養
培養液で細胞を増やし、人工培養肉を生産
NHKシブ5時(8月21日)
「細胞から肉をつくる、驚きの技術」・・・
ーーーーー
「原罪=ゲンザイ=現在」から救われるかも・・・???
イワンの馬鹿=真っ正直な人物
・・・「旋風Z」・・・「乙・N・И(and・イ-)・?(4)・?(6)」𠂉・・・「クラシーヴィ=красивый=煩い・喧しい(うるさい・やかましい)・永久的な・美味しい・遅れた(おくれた)・怒った・・・
「некрасивый=醜い(形容詞)」
「некрасивый」のは音が「ニクラシイ」?・・・
「И→イヴァーン=イヴァン(Иван)
=イワン
=神は赦し給う
神は恵み深い(ヘブライ語由来)
父称=イヴァノヴィチ
(Иванович)」
↓↑
「イヴァナ・マリエ・トランプ(Ivana Marie Trump、1949年2月20日~)・チェコスロバキア出身のアメリカの実業家・元ファッションモデル・アメリカ合衆国の大富豪、ドナルド・トランプの元妻・札幌オリンピックのチェコスロバキアのアルペンスキー補欠選手」・・・
↓↑
「イヴァンカ・マリー・トランプ(Ivanka Marie Trump、1981年10月30日~)」・・・
↓↑
キリル文字小文字、大文字の
「И(イ)=・ギリシア文字Η/ηに由来」
↓↑
「イワンの馬鹿=真っ正直な人物
=Иван-дурак
Иванушка-дурачок
(指小形)」
↓↑
・・・トランプはモチロン、プーチンは「イワン」にはなれないし、キミもボクも「異和夢」で当然であるカナ・・・「違和の夢」、「磐の夢=磐余彦の由妹」・・・「易和の喩米」・・・
「ギリシャ語の美しい=カロス(καλος・カラス)・オモルフィ(όμορφο)」・・・「香良洲・唐洲・鴉・烏」・・・
「Неловкий
(ニローフキー)=不器用・手際が悪い
たどたどしい・ぎこちない・(姿勢などが)楽でない
拙い・決まり悪い・肩身のせまい・気詰まりな
場違いな・不適切な・具合の悪い」・・・
↓↑
некрасивый
невзрачный
уродливый
↓↑
без-образный(ビェ-ゾブラーズヌィ・無用)?
「б」って、「6・六・陸・ろく」?・・・
↓↑
「Б=б=キリル文字のひとつ・ギリシャ文字のΒ(ベータ)の筆記体に由来・ラテン文字のBに相当する文字・又、対応するグラゴル文字は (ブーキ)」・・・
「Без-=без-」・・・
↓↑「бе(ビェ-)+З,з(ゼー・ズ・英語のzに相当」
↓↑「безо=ビエゾ」?・・・→「靡-蝦夷」?
↓↑「безо=六蝦夷」?・・・→「陸-蝦夷」?
接頭辞(名詞派生の形容詞に付して)
~のない、~をもたない、~を欠いた・・・欠陥
の意味
ある種の名詞に付して名詞を作り
欠如、不足、不満足な状態、欠陥
の意味」
「キリル文字(露語のКириллица
英語のCyrillic alphabet
キリール文字)
主にスラヴ諸語を表記するのに用いられる
表音文字の体系の一種
小文字の筆記体は
ロシア語のイタリック体の字形とほぼ同じ
「б」と「д」の筆記体は
セルビア語のイタリック体の字形と同じ」
ーー↓↑ーー
きみが泣く時、ボクも涙を流した
きみが啼く時、ボクも啼いた
きみが笑う時、ボクも顔を崩した
きみが哂う時、ボクも嗤った
きみが怒る時、ボクはうつむいた
きみがうつむいた時、ボクは見つめた
きみが怒る時、ボクはたちどまらなかった
・・・風の流れがうなじを撫ぜていく・・・
・・・きらいな感じ・・・
・・・ぼくは小さな部屋のよどんだ空気がイイ・・・
ーーーーー
・・・???・・・
「悦ちゃん」・・・史示文録・・・?
・・・朝から隣の町に行って、「運転免許証」の更新で新しいモノと交換・・・帰りは「ホーマック」で「水洗便座」と家の壁に塗る「白いペンキ」を買って帰宅・・・随分と長い時間、昼寝をしていた・・・夢の中で先週、TVでみた「悦ちゃん」が登場し、ボクに何やら話しかけていたが・・・「獅子文六」さんと云えば、子供の頃にみた映画は、加藤大助が主演の「大番」だったが・・・確か、映画の中では「大番」とは「大型の名刺」のコトを指す「名詞」だったハズだが・・・「敗戦ゼロ年・東京ブラックホール1945~1946」・・・?・・・生き残った人間は勝っても、負けても・・・生き続けなくちゃぁならないから・・・その後に産まれてきた人間も・・・
「ウイキペデア」で調べると・・・
ーーーーー
「悦ちゃん」
昭和時代の一世を風靡した小説家・獅子文六の小説の
ドラマ
ユースケ・サンタマリアが演じるパパ
NHK土曜時代ドラマ『悦ちゃん』
時代は昭和10年(1935年)の東京・銀座
「獅子文六」のペンネーム・・・?
九九の中の「四四 十六」をもじったもの・・・?
「四×四」が「十六・拾六」って、「文六」にはならんが?
「四+四」=「拾六」=拾う亠の八」?・・・「八・捌」?
↓↑
獅子文六・・・文禄・・・紊・分・聞・蚊・紋・刎
・・・「文=亠+乂」・・・音は乂(かる・重なる)?
・・・「六=亠+八」・・・六=陸
↓↑
『悦ちゃん』は
1937年の映画版
1958年の日本テレビ版
1965年(朝日放送)
1974年(NHK)
と何度も映像化・・・
NHKは2回目
↓↑
獅子 文六(しし ぶんろく)
1893年(明治26年)7月1日
~
1969年(昭和44年)12月13日)
本名は、岩田 豊雄
号は牡丹亭
戦争で疎開した
愛媛県
北宇和郡
津島町に句碑がある・・・
母方の祖父は花火職人の平山甚太
実父は
元中津藩士の岩田茂穂
弟の岩田彦二郎は
札幌グランドホテル社長
↓↑
横浜弁天通の岩田商会に生まれた
父の岩田茂穂は
福澤諭吉に学んだのち
絹織物商を営んでいたが
文六9歳のおりに死去
↓↑
日清戦争開戦前年に生まれ
1922年
から数年間
演劇の勉強のためにフランスへ
フランス人の
マリー・ショウミーと結婚
帰国後に長女
巴絵が生まれるが
妻は病死
富永シヅ子と再婚
戦後にシヅ子も病死
元男爵
吉川重吉の娘
幸子と3度目の結婚
「四四、十六」をもじった
獅子文六の筆名で
小説家として活動
1934年
雑誌『新青年』に掲載された
『金色青春譜』が処女作
1936年
新聞連載小説として報知新聞に掲載の
『悦ちゃん』で人気
1937年
岸田國士、久保田万太郎と共に
劇団「文学座」を創立
1942年
真珠湾攻撃の「九軍神」の一人を描いた
『海軍』
で朝日文化賞を受賞
戦中に海軍関係の文章を多数発表
戦後に「戦争協力作家」として「追放」の仮指定
1ヶ月半後に解除
多くの作品が映像化
1951年
『自由学校』が
松竹(渋谷実監督)
大映(吉村公三郎監督)で競作映画化
1955年
『青春怪談』が
日活(市川崑監督)
新東宝(阿部豊監督)
で競作映画化
1961年
『娘と私』は
NHKでテレビドラマ化
連続テレビ小説の第1作
↓↑
『大番』 東宝、1957年
『続大番 風雲編』 東宝、1957年
『続々大番 怒濤篇』 東宝、1957年
『大番 完結篇』 東宝、1958年
ーーーーー
・・・「戦争協力作家」ですか・・・戦前の日本人はスベテが「戦争協力国民」だったハズなのに・・・
8月20日、NHKスペシャル、「戦後ゼロ年・東京ブラックホール1945~1946」・・・
アマラントス・・・あまらんとす・・・海女覧(乱)訳諏・・・
・・・八月二十五日(金)・・・「木瓜=ぼけ=呆け・惚け・暈け・ボケ」・・・「ボケ(木瓜・学名 Chaenomeles speciosa)=バラ科ボケ属の落葉低木・果実が瓜に似ており、木になる瓜で木瓜(もけ)とよばれたものがボケに転訛、or 木瓜(ぼっくわ)からボケに転訛」、「ぼけ・もっか・ぼっか・もっこう・きゅうり」、「ぼけの木そのものを指す・もっか=カリンやボケの果実を乾燥させた生薬名、利尿、鎮咳、鎮痛に用いる・パパイヤの別称・木瓜鎮 (府谷県)-中華人民共和国の地名」・・・「クサボケ(草木瓜・シドミ=樝・ジナシ)」・・・「シドミ(朱留)、シドメ(朱目)、ジナシ(地梨)、ノボケ(野木瓜)、コボケ(小木瓜)」 とも・・・「木瓜(ボケ)=きゅうり=胡瓜・窮理・究理」・・・「ギリシャ語のchino(開ける)+ melon(メロン)の合成語、裂けたリンゴ・熟すと実が裂ける」・・・
「バイカアマチャ・アジサイ(紫陽花)に近縁な低木・装飾花はあるが目立たず、通常の花が大きくて目立つ」・・・
「日本の文様の木瓜文または窠文(カモン=窠=穴+果)のこと・木瓜紋」・・・
「日本の家紋の木瓜紋・または木瓜紋の一種・木瓜紋(もっこうもん)」・・・
「木瓜鎮 (府谷県) - 中華人民共和国
陝西省
楡林市の鎮
木瓜鎮 (桐梓県) - 中華人民共和国
貴州省
遵義市
桐梓県の鎮」・・・
↓↑
「あざみ=薊・阿左美・生明・字見・風見・呰見
葉は深い切れ込みがある
葉や総苞にトゲ
触れれば痛い草
頭状花序は管状花のみ
多くのキク(菊)のように周囲に
花びら状の舌状花が、ならばない
花からは雄蘂や雌蘂が棒状に突き出し
針山のような景観
花色は赤紫色や紫色
種子に長い冠毛
別名は刺草(さしぐさ・シソウ)
名前の由来
アザム(傷つける・驚きあきれる意)
あざむく=欺く
棘(とげ)に刺されて驚くから・・・
スコットランドで
その棘(トゲ)によって
外敵から国土を守った
国花
花言葉は
独立、報復、厳格、触るな」・・・さわるなッ!
・・・「山ごぼう(牛蒡)・菊ごぼう(牛蒡)」などといわれることもある・・・味噌漬けなどの加工品として山間部の観光地・温泉地などで販売され、「山ごぼう(牛蒡)」は栽培された「モリアザミの根」・・・
ーーーーー


↓↑
野菜の「牛蒡(ゴボウ)」に用いられる字
牛蒡=ゴバウ=キタキス・ウマフフキ・ウマフブキ
「蒡、隱荵なり(爾雅・釈草)」
「隠荵=蘇に似て毛有り」とある
「牛蒡=菜なり(広韻)」とある
「隱荵の意味では
蒡・・・蒡=艹+旁(つくり・かたわ・かたがわ・ボウ・ホウ)
↓↑ 旁=合体漢字構成の右半分の部首
「偏旁(ヘンボウ)=漢字の字体を構成する要素の一
左右上下内外の部分に分解できる要素漢字
偏や旁を総合して言う
四字で偏旁冠脚(ヘンボウカンキャク)
同じ組み合わせの「偏旁」をもつ漢字同士は
↓↑ 類型的な意味、
あるいは
音声のグループを形成する
↓↑ ↓↑
頁(いちのかい)=一ノ貝
「頭・額・頬・顎・項」などは
「顔」に関係する意味
「常用漢字数 22」
「題」は変則だが、「おおがい」に含まれる
「頼」の旧字体は「褚」で、
「貝」部に含む辞典、
「頁」部」に含む辞典がある・・・
「常用漢字は頃頂項順須頑頓頒預領頬
頭顎頼頻額顔顕題類願顧
主な表外字は頌頗頷頸頽顆顚
↓↑ など・・・
↓↑ これらは「左の偏」の漢字のページ(頁)を
↓↑ 先ずは調べよ、であろう・・・?
(蒡=ボウ・ホウ)
が本字で、
ゴボウの意味では
𦾭が本字(集韻)」
「𦾭」は、(集韻)の(牛蒡の場合の)本字
「𦱘」は、(康煕字典)に(唐韻)では
「蒡を𦱘」に作る異体字と記録・・・
↓↑
「イノコヅチ=牛膝(ゴシツ)=イノコヅチ(猪子槌)
ヒユ科イノコヅチ属の多年草・・・・・比喩化?
「莧=艹+見」・・・スベリヒユ(滑莧)→統べ理比喩?
↓↑ 昂 里比喩?
「米莧(ミーシ)」=アマラントス
落花しない不死の花・不凋花
朽ちない花?
(クチナシ=梔子・巵子・支子
アカネ科クチナシ属の常緑低木
乾燥果実は生薬、漢方薬の原料
山梔子・梔子)?
=萎(しお)れない・枯れない
Αμάρανθος・Amaranth
色はアマランス色(スカーレット)?
スカーレット(scarlet)は
やや黄味の赤
エカルラート(フランス語 écarlate)
緋色・黒緋(くろあけ)
深緋(ふかひ・こきひ・こきあけ)
深紅色
茜色(あかねいろ・madder)は
「紫・日」の枕詞で「万葉集」に
十一首詠まれている・・・?
「ヒユ=莧」科=観賞用 ↓↑
↓↑ ケイトウ(鶏頭)・・・鶏の頭(王)?
・・・隋書俀人傳の
「卷八十一 列傳第四十六 東夷 俀國」
「阿毎王朝の多利思北孤(たりしひこ)=倭国王」
「開皇二十(600・推古天皇八)年、倭王、
姓は阿毎(あめ)
字は多利思比孤(たりしひこ)
号は阿輩鶏彌(おおきみ)」→隋の高祖-文帝に使者
↓↑ 文綴?
ハゲイトウ(葉鶏頭)=言葉は鶏の頭?
センニチコウ(千日紅)=撰似置項?
一部は食用・・・・・・・織用?
↓↑ ヒモゲイトウ(センニンコク=仙人穀)
属名アマランサス
ヒモゲイトウ(紐鶏頭)
アマランサス(Amaranthus)
ヒユ科ヒユ属(アマランサス属)の植物の総称
アマランスとも
エンコウゲイトウ(猿猴鶏頭)
アマランサス・カウダツス
は粘り強さ、粘り強い精神、心配無用
不死、不滅
初秋、長い花穂を紐のように垂らす
非耐寒性のヒユ科ヒユ属の大型の一年草
↓↑ ↓↑
南米では穀物として利用
ハゲイトウに近縁な
ヒユなどは野菜として利用され
よく似た
イヌビユ、ハリビユ
↓↑ などは雑草として生える
日のあまり当たらない場所に生える雑草
ヒナタイノコヅチ(日向猪子槌)に対して
ヒカゲイノコヅチ(日陰猪子槌)」・・・
「茎の節が膨らんでいて、猪子の膝のように見え、これを槌に見立ててこの名がついた」・・・
「イノコズチ(inokozuchi)ヒユ科の多年草」
「フシダカ、コマノヒザ」とも・・・
「猪子槌=牛膝(ゴシツ)」といい、「利尿、強精、通精、通経薬、堕胎薬」・・・「植物体全体に毛がある」・・・「咲き終わった花は下向きに曲がり、花の付け根の苞が反り返る」・・・
ーーーーー
・・・「本草和名(ほんぞうわみょう・918年)には、
「牛膝(ゴシツ)=和名は為乃久都知(いのくづち)
都奈岐久佐(つなぎぐさ)
別名で衣服に果実が付くので
トビツキグサ」とも・・・「跳び付き・飛び付き」草
・・・