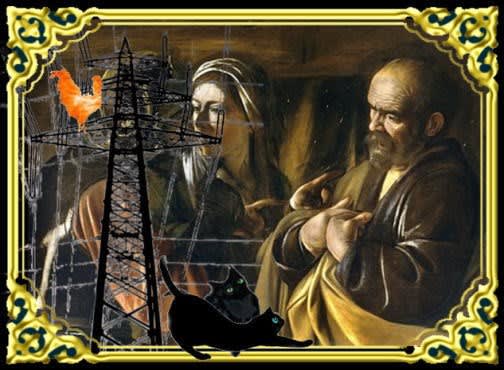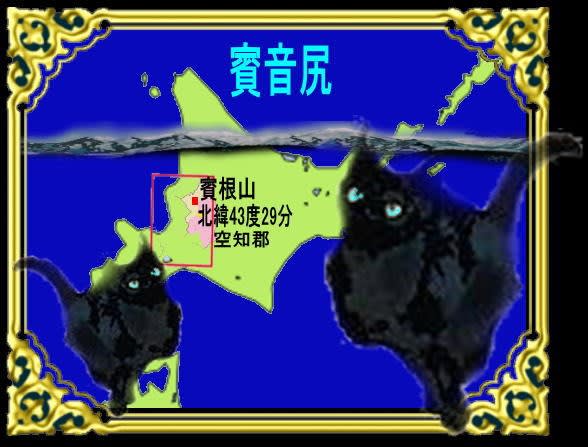November 25, 2017, 11:46 am
・・・「甲斐(かい)・甲府」⇔「会津(會津・あいづ・カイづ→蝦夷津)・若松(わかまつ・ジャクショウ)→若(もしか)しかしたら松(木公・十八八ム)⇔若(艹ナ口)いと云う字は苦(艹十口)しいと云う字に似てる(ワッ!・アン真理子 ・悲しみは駆け足でやってくる(1969年)」・・・「徳川義直は慶長八年(1603年)、徳川家康から甲斐国に封じられる」⇔「保科正之は会津、松平家初代藩主・信濃高遠藩主、出羽山形藩主を経て陸奥、会津藩初代藩主・江戸幕府初代将軍、徳川家康の孫・三代将軍、徳川家光の異母弟・家光と四代将軍家綱を輔佐」・・・そして「福島」・・・「カイ→アイヅわかまつ→尾張たかす→えぞ→・・・」の関連性はアルのか?・・![]()
![]()
會津若松・福島県
ーーーーー
地名
会津若松市(福島県の市)・旧市名は若松市
若松区(北九州市の区)・旧市名は若松市
若松(高崎市)・群馬県高崎市
若松 (船橋市)・千葉県船橋市
若松 (我孫子市)・千葉県我孫子市
ーーーーー
北九州市の若松区
↓↑
仲哀天皇と神功皇后が
熊襲を征伐したとき
洞の海に霊石を見つけ
これを神体としてまつり
神社の海辺に小松を植えた
武内宿弥が
「海原(うなばら・カイゲン)の
滄瞑(ソウメイ)たる
松の青々たる、我が心も若し」
が「若松」の地名由来
・・・滄=氵+倉
瞑=目+冖+日+六(亠八)
(目を)つぶる・くらい(暗)
メイ・ミョウ
滄瞑(わだのはら・大海)
瞑想(メイソウ)
若い松が多い所だったのでという説も・・・?
会津若松市(福島県)
↓↑
「福島県」の県名由来
明治九年
当時の
若松県
磐前(いわさき)県
福島県
が合併し「福島」の名称
1593(文禄二)年ごろ
木村吉清
によって
福島城に使われた
↓↑
信夫(しのぶ)郡は昔
見渡す限りの湖で
その真ん中に
信夫山があった
この山には
「吾妻 おろし」が吹きつけ
コレを
「吹島(ふくしま・ふきしま)」と呼んだ
「複揣摩・覆嶋・伏嶌・副縞・附句詞眞」?
湖が干上がり
陸地ができ
集落が生まれ
吹島は
風が吹きつける吹を福とし
福島と呼ぶようになった・・・
↓↑
福島の中心街一帯は
信夫(しのぶ)・・・・忍ぶ・偲ぶ・志信・耐・恕
の
里(さと・リ)
の
杉目(すぎのめ)郷・・・杉目(サンモク)=十八彡目
と呼ばれた
1413(応永二十)年頃
伊達盆地の支配者である
伊達持宗
がこの場所に
杉目城(大仏城=だいぶつじょう)を築いた
1590(天正十八)年
伊達政宗
の代に
豊臣秀吉よって領地を北に移され
蒲生氏郷(がもううじさと)
の領地となり
氏郷は、
会津黒川城
を本拠とし
伊達盆地の
杉目城を
その支城とし
黒川を若松・・・・・黒川=若松
杉目を福島・・・・・杉目=福島・・・岑越
に改名・・・
ーー↓↑ーー
古代、
「福島」の地名は元々が
「岑越(みねこし)=山+今+十一ト人戍(戌)」
越=走+戉(まさかり・エツ・オチ)⇔戍戌戎成
↓↑
信夫(しのぶ・シンプ)山(やま・サン)も
岑越山(みねこしやま)と呼ばれた
奈良時代の律令制
東山道の福島周辺の
駅名(馬宿)は
南から
安達(あだち・本宮)→
→湯日(ゆい・二本松市油井)
→岑越(みねこし)
→伊達(伊達郡桑折町)
→篤借(あつかし・宮城県白石市)
岑越は
松川(当時の流路は信夫山の南側)以北
摺上川以南で
松川以南は当時でも
杉妻(すぎのめ・杉目)であった
安土桃山時代
信夫郡・伊達郡が
蒲生氏郷支配になったとき
蒲生氏郷の下で
福島城主とされた
木村吉清が・・・木(十八)の
村(木寸)の
吉(士口)の
清(氵主月・氵亠十一冃・肉)
杉妻(杉目)を
福島と改名
ーー↓↑ーー
尾張は
慶長五年(1600年)九月
関ヶ原の戦い終結まで
清洲城主
福島正則・・・・・・・・「福の島の正の則」
が24万石で支配
戦功により
福島正則は
安芸広島藩に加増移封・・・
↓↑
そのあとに
徳川家康の九男
徳川義直(五郎太、義俊、義利)
が尾張徳川の家祖
↓↑
徳川義直は
慶長八年(1603年)
家康から
甲斐国
に封じられ
甲斐統治は
甲府城代
平岩親吉・・・・「平の岩の親の吉」
によって担われ
徳川義直(五郎太)自身は
在国せず
駿府城に在城
元服後
慶長十一年(1606年)
義直は
兄、
松平忠吉
の遺跡を継ぐ形で
尾張国
清須に移封
家臣団が編制され
尾張徳川家は
江戸時代を通じて
尾張藩を治めた
↓↑
徳川将軍家に
後継ぎがないときは
他の御三家とともに
後嗣を出す資格を有したが
七代将軍の
徳川家継
没後
紀州徳川家出身の
徳川吉宗
が
尾張家の
徳川継友
を制して
八代将軍に就任
その後
御三卿が創設され
尾張家からは
将軍は出なかった・・・
ーー↓↑ーー
梁川-松平家(大久保-松平家)
↓↑
梁川藩(やながわはん)
3万石
福島県
伊達郡
↓↑
1683年~1730年
四代目を継いだ
松平通春(宗春)
が
宗家断絶により
尾張藩主
徳川宗春
になったため
廃藩にした
↓↑↓↑
梁川藩(やながわはん)は
江戸時代の一時期
陸奥国
伊達郡
に存した藩
福島県
伊達市
梁川町
鶴ヶ岡
の
梁川城跡に陣屋を置いた
当初は
尾張藩徳川家の支藩(御連枝)
後には一時、
松前氏
が入封
↓↑↓↑
尾張徳川家連枝
幕府直轄領となった
梁川には、その後、
天和三年(1683年)
尾張藩二代藩主
徳川光友の三男の
松平義昌
が入封
3万石にて立藩
分家の理由
↓↑
尾張藩が
血脈の断絶を恐れ
同時期、同様の理由で
尾張藩は
四谷家
川田久保家
を分家させた
梁川の立藩は
有力な外様である
伊達氏への楔(くさび)であり
親藩を求める幕府の思惑とも一致
↓↑
享保十四年(1729年)五月
三代
尾張徳川義真が卒去
無嗣子のため廃絶
↓↑
同年九月
尾張藩三代藩主
徳川綱誠の十九男の
松平通春(徳川宗春)
に改めて
梁川3万石が与えられたが
享保十五年(1730年)
に世継を残さないまま
尾張藩主
徳川継友が死亡
通春が尾張藩を相続し
梁川を一時廃藩し
尾張宗家断絶を防止するという
役目を果たした
梁川藩を廃藩・・・
ーー↓↑ーー
藩祖、義直の遺命
「王命に依って催さるる事」
を秘伝の藩訓とした
勤皇家・・・?
戊辰戦争では官軍
↓↑
尾張徳川家の支系(御連枝)
美濃国
高須藩・・・「高(亠口冋・亠口冂口)
の
須(彡頁・一ノ目八)」
冋=冂=けいがまえ・まきがまえ・どうがまえ
えがまえ・えんがまえ・ケイ・キョウ
境界
を治めた
高須松平家(四谷松平家)
1799年
尾張徳川家
1801年
高須松平家で
義直の男系子孫は断絶
尾張徳川家は
養子相続を繰り返し
至っている
10代から13代まで
徳川吉宗の血統の養子が
藩主に押し付けられたが
これに反発した尾張派は
14代慶勝を
高須家から迎え
幕府からの干渉を弱めた
↓↑
明治維新
徳川慶勝が
佐幕から倒幕に転じ
官軍につき
侯爵を授けられ
第十六代
徳川義宜が
名古屋藩知事となった
秩禄処分後
約74万円という高額の
金禄公債証書を受領
資産のうち
約43万円を
第15国立銀行に出資し
配当金を再投資
士族授産のため
北海道
遊楽部原野の土地を開拓
八雲町を開拓
維新後
高い政治的・経済的地位を維持
↓↑
ーーーーー
「中山道(中仙道)」=「東山道」
↓↑
豊臣秀吉による奥州仕置
伊達政宗
の元の本領以外を没収
↓↑
会津には
蒲生氏郷が入る
翌年
葛西大崎一揆の戦後処理で
伊達政宗が
岩出山に移封
↓↑
蒲生氏郷が
福島県中通り以西のほとんどを領有
子の
蒲生秀行は
会津から
宇都宮に移され
代わって
越後国の
上杉景勝が
会津120万石を得
福島県の中通り以西と
山形県の置賜地方を領有
↓↑
葛西大崎一揆の原因を作ったとし
所領を奪われた
岩出山の旧領主の
木村吉清は
後に許されて
蒲生氏郷に仕えて
杉目城主となった
吉清は
杉目を
「福島」と改称・・・・福島
↓↑
関ヶ原の戦い
上杉景勝は
信夫郡、伊達郡を除く
福島県域の所領を失い
30万石となる
↓↑
会津に
蒲生秀行が再度入封
会津藩60万石が成立
2代目の
蒲生忠郷が早世し
伊予松山藩に移る
↓↑
1627年
加藤嘉明が
40万石で会津に入封
2代目
加藤明成が
会津騒動を起こし
領地を徳川幕府に返上
↓↑
1643年
松平氏
保科正之が
23万石で入封
以後
松平氏会津藩が
戊辰戦争まで続く
↓↑
信夫郡と伊達郡も
1664年
上杉氏
米沢藩から召し上げられ
会津藩以外の大藩はなくなり
会津と
浜通り夜ノ森以北(相馬氏領)を除く
県内のほとんどの地域で
小・中藩、天領が入り乱れて激しく変遷
この間
白河藩は
一時、徳川譜代となり
寛政の改革を主導した
松平定信など
城主が入った
↓↑
江戸時代
会津若松
と
日光街道
を結んだ重要な交通路
会津西街道(下野街道)の
大内宿には
幕末に置かれた
藩及び城郭
交代寄合陣屋
↓↑
会津藩支城の猪苗代城、
二本松藩、棚倉藩、中村藩、三春藩、
磐城平藩、福島藩、泉藩、湯長谷藩、下手渡藩、
水戸藩、支藩の守山藩、
幕末に
徳川幕府直轄地となった白河城、
仙台藩の支城の谷地小屋城
などがあり、
交代寄合の
溝口家の横田陣屋
その他に代官陣屋もあった
↓↑
明治初期
版籍奉還後の
1869年(明治二年)
の太政官令で
陸奥国南端である
福島県域は
陸奥国から分離し
西側が岩代国(いわしろのくに)
東側が磐城国(いわきのくに)
となった
岩代国は
福島県中通り地方の中北部と会津地方
磐城国は
福島県中通り地方南部と福島県浜通り地方
宮城県南部(亘理郡、伊具郡、刈田郡)
1869年(明治二年)7月20日
福島藩が
重原藩に移封され
幕府領となっていた
伊達郡、信夫郡を管轄するために
福島県(第1次)が設置
1871年(明治四年)
7月(旧暦)
廃藩置県で全国に多数の県
11月(旧暦)
福島県域は
岩代国の会津地方
(旧会津藩領の越後国蒲原郡の一部
東蒲原郡を含む)
が若松県、
岩代国
と
磐城国からなる中通り地方が
二本松県(二本松県・12日間後に
県庁が信夫郡福島町に移転
福島県に改称し機能はしていない)
磐城国はほぼそのまま
磐前県(いわさきけん)
の3つの県として統合
1876年(明治九年)8月21日
福島県(第1次)、若松県、磐前県が合併
現在の福島県(第2次)が成立
磐前県北部(亘理郡、伊具郡、刈田郡)が
宮城県に、
磐前県南部の一部が
茨城県に
移管され、
1886年(明治十九年)
東蒲原郡が新潟県へ移管
↓↑
大和朝廷の勢力圏
福島県域が北限
蝦夷勢力圏との境界に当たる
信夫国(福島盆地)
などの国には防備の任があった
↓↑
関東や近畿地方などから
開拓のための移民
その後、
国は評(こおり)と呼び名が代わり
陸奥国に再編
大和朝廷の勢力圏も
宮城県域、さらに北に拡大し
信夫評(しのぶごおり)
も「北端」ではなくなった
↓↑
701年(大宝元年)
大宝律令の施行
陸奥国となり
評は郡
評司(国造)は郡司になった
718年(養老二年)
石城国
と
石背国
が分置
石城国=菊多郡、石城郡
標葉郡(しねはぐん or しめはぐん)
行方郡(なめかたぐん)、宇太郡
曰理郡(わたりぐん)の6郡
石背国(いわせのくに)=信夫郡、安積郡
石背郡、白河郡
会津郡の5郡
現福島県域は
石城国
or
石背国
に属することとなり
陸奥国の領域ではなくなった
分置後も
蝦夷との戦いが続き
東北全体(陸奥・出羽)での戦いに拡大
724年(神亀元年)
までには
石城国
と
石背国
は再び
陸奥国に合併
後
信夫郡から伊達郡が分割
安積郡からは安達郡などが分割
会津郡も耶麻郡を始め多くの郡に分割
↓↑
会津の由来
記紀の記述
崇神天皇が
北陸道に遣わした
大彦命(おおひこのみこと)
と
東海道に遣わした
建沼河別命(たけぬかわわけのみこと)
が、日本海側と太平洋側から遠征して
出会ったのが
「相津(あいづ)」だった
この「相津」が後に「会津」と表記
会津盆地でいくつかの川が
合流するために舟運の拠点として
会津、
あるいは
日本海側と太平洋側の物産を運ぶ隊商が
会津盆地で取引をすために
会津と呼ばれるようになった・・・などの説
↓↑
大和朝廷の勢力圏は
福島県域が北限で
蝦夷勢力圏との境界に当たる
信夫国(福島盆地)などの国には
国境防備の任もあった
↓↑
移民
国は評(こおり)・・・・評=言+平
と呼び名が代わり
陸奥国に再編
大和朝廷の勢力圏も
宮城県域
北に拡大し
信夫評(しのぶごおり)も
「北端」ではなくなった。
↓↑
701年(大宝元年)
大宝律令の施行時には
陸奥国
評は郡
評司(国造)は郡司になった
拡大した陸奥国から
718年(養老二年)
石城(いわき )国
と
石背(いわしろ・いわせ)国
が分置された
↓↑
石城国=菊多郡
石城郡
標葉郡(しねはぐん or しめはぐん)
行方郡(なめかたぐん)
宇太郡
曰理郡(わたりぐん)の6郡
石背国(いわせのくに)=信夫郡、安積郡、
石背郡、白河郡、
会津郡の5郡
↓↑
現福島県域は
石城国
または
石背国に属し
陸奥国の領域ではなくなった
分置後も
蝦夷(えぞ・えみし・カイ)
との戦いが続き
東北全体(陸奥・出羽)に拡大
724年(神亀元年)までに
石城国
と
石背国
は再び
陸奥国に合併
これらの郡は、その後、人口の増加などにより
さらに再分割
信夫郡から伊達郡が分割され
安積郡からは安達郡などが分割され
会津郡も耶麻郡を始め多くの郡に分割された・・・
ーー↓↑ーー
甲州(こうしゅう)
令制国の一
甲斐国の別称
↓↑
慶応四年三月六日
1868年3月29日
甲州勝沼の戦い
慶応四年三月六日(1868年3月29日)
柏尾の戦い
勝沼・柏尾の戦い
甲州戦争
甲州柏尾戦争
とも
板垣退助の軍勢
と
近藤勇の軍勢が戦った合戦
↓↑
甲斐国
山梨郡
勝沼(甲州市勝沼町)
甲府盆地の東端に位置
信濃国から
甲府(甲府市)を経て
江戸へ向かう
甲州街道の勝沼宿
↓↑
甲州街道
江戸から
郡内地方の
山間部を経て
甲府盆地(国中地方)へ至り
勝沼は盆地へ入った最初の地点
勝沼から
郡内地方を越えれば
武蔵多摩地方
新選組の幹部や隊士を多く輩出した
多摩地方にも近い
↓↑
甲斐国
享保九年(1724年)
幕府直轄領化
甲府城(甲府市)には
甲府勤番が配置
代官支配地
天保七年(1836年)
甲斐一国規模の
天保騒動の際には
勤番士
三百数十人と
各代官手付
手代50余り
↓↑
1867年(慶応三年)
中岡慎太郎
の仲介を経て
五月二十一日
小松清廉邸で
薩摩藩の
西郷隆盛・吉井友実・小松清廉
らと
土佐藩の
乾(板垣)退助・谷干城・毛利恭助・中岡慎太郎
らが会談
薩土討幕の密約(薩土密約)を結ぶ
二十二日
乾(板垣)退助は
薩摩藩と討幕の密約を結んだことを
山内容堂へ報告
乾(板垣)退助が
江戸築地の
土佐藩邸に
勤王派
水戸浪士を
匿っていることを告げられ
これを了承
大坂で
アルミニー銃300挺
の買い付けを命じ
乾(板垣)退助に
土佐藩の軍制近代化改革を命じた
↓↑
薩土密約に基づき
1867年(慶応三年)12月28日
京都にいる
西郷隆盛から
土佐の
乾(板垣)退助あてに
「討幕の開戦近し」との伝令
1868年(慶応四年)一月三日
鳥羽・伏見の戦い
1月6日
京都から
谷干城
が早馬で土佐に到着
京都において
武力討幕戦が開始されたことを
土佐藩庁に報告
↓↑
大政奉還が成って以降
乾(板垣)退助は
武闘派の棟梁と警戒され
藩軍の大司令(陸軍大将)の職を解かれ
その他総ての役職を被免され
失脚していたが
即日、失脚を解かれ
藩軍の大司令に復職
1月6日
乾退助は
谷干城の報告を受けて
薩土討幕の密約を履行すべく
土佐勤王党の流れをくむ隊士や
勤皇の志を持った諸士からなる
迅衝隊を土佐で編成
1月7日
朝廷より
「徳川慶喜追討」の勅が出された
↓↑
1月13日
迅衝隊は
土佐城下致道館前で出陣祈願
土佐藩門閥派の重鎮
寺村左膳らが
止めに入るが出陣
直後
「讃岐高松、
伊予松山両藩
及び
天領川之江征討」
の勅を拝し
「錦の御旗」を授けられ
皇威を畏み、正式に官軍としての命を奉じた
迅衝隊が
高松、松山に到着すると
両藩は朝敵となることを恐れ降伏
京都へ上洛
↓↑
総督
板垣退助
山内容堂は当初
鳥羽・伏見の戦いを私闘と見做し
土佐藩士の参戦を制止したが
「薩土討幕の密約」に基づいて
初戦から参戦した者も多く
追討の勅が下った後は
京都で在京の
土佐藩士と合流した
「迅衝隊」は
部隊を再編し軍事に精通した
「板垣(乾)退助」を
大隊司令兼総督とし
退助はさらに朝廷より
東山道先鋒総督府参謀に任ぜられた
2月14日
京都を出発し東山道を進軍
乾退助の12代前の先祖とされる
板垣信方の320年目の命日で
天領である甲府城の掌握目前の美濃で
武運長久を祈念し
「甲斐源氏の流れを汲む
旧武田家家臣の
板垣氏の末裔であることを示して
甲斐国民衆の支持を得よ」
との岩倉具視等の助言を得て
「乾(いぬい)」を
「板垣」氏に姓を復し
東山道(中山道)を進軍
東山道先鋒総督府軍は
諏訪で本隊と別働隊に分かれ
本隊は
伊地知正治
が率いてそのまま中山道を進み
板垣退助(乾退助)
率いる別働隊は
幕府の天領であった
甲府を目差した
甲府城入城が
決戦の勝敗を決するとし
板垣退助は
「江戸~甲府」と
「大垣~甲府」までの距離から
東山道先鋒総督府軍の
不利を計算し、走って進軍
土佐迅衝隊(12小隊, 約600名)と
因幡鳥取藩兵(8小隊, 約800名)らと共に
1868年(慶応四年)3月5日
甲府城入城
↓↑
断金隊、護国隊の結成
板垣退助が
旧武田遺臣であると知れ
「武田家旧臣の
板垣信方
の末裔が甲府に帰ってきた」
と領民に迎えられた
旧武田家家臣の子孫の
浪人や神官、長百姓らが協力を願い出
甲斐の郷士らで
「断金隊」や、「護国隊」が組織
武田信玄の墓前で結成式
↓↑
板垣退助
らより一日遅れ
大久保大和(近藤勇)
の率いる
甲陽鎮撫隊
は甲府についたが
甲州街道
と
青梅街道
の分岐点近くで布陣
柏尾坂附近で戦闘となったが
洋式兵法にも精通していた
迅衝隊がこれを撃破
戦闘が始まって僅か約2時間で勝敗がつき
甲陽鎮撫隊は山中を隠れながら江戸へ敗走
「板垣」の復姓は
甲斐国民心の懐柔に効果
江戸に進軍する際も
旧武田家臣が多く召抱えられていた
八王子千人同心たちの心を懐柔させた
↓↑
新選組は
京都守護職指揮下で
京都市街の治安維持
慶応四年一月
鳥羽・伏見の戦い
淀千両松の戦いで
新政府軍と戦って敗れ
江戸へ移った
新政府軍は
東海道・東山道・北陸道に別れ
江戸へ向けて進軍
↓↑
新選組局長の
近藤勇は
抗戦派と恭順派が
対立する江戸城において
勝海舟と会い
幕府直轄領である甲府を
新政府軍に先んじて押さえるよう
出陣を命じられた
(江戸開城を控えた勝海舟が
暴発の恐れのある近藤らを
江戸から遠ざけた?)
新選組
と
浅草弾左衛門(矢野内記)配下
の被差別民からなる
混成部隊が編成され
甲陽鎮撫隊と名を改め
近藤勇は大久保剛(後に大和)
土方歳三は内藤隼人
と変名
ミニェー銃をはじめとする
洋式砲が多数配備されたが
近藤らは
剣術の腕を過信し・・・?
隊士らに殆ど
西洋式練兵をさせぬまま
3月1日に江戸を出発し
甲州街道を行軍
↓↑
近藤勇は
「甲府を新政府軍に先んじて押さえるよう」
という
勝海舟の指令を軽んじ
新選組70人と
被差別民200人からなる
混成部隊の不満をやわらげ
士気を高めるため
幕府より支給された
5,000両の軍資金を使って
大名行列のように贅沢に豪遊しながら行軍
飲めや騒げの宴会を連日繰り返し
移動の邪魔となった
大砲6門のうち4門を置き去りにし
2門しか運ばなかった
さらに天候が悪化し行軍が遅くなり
甲府到着への時間を空費
沖田総司は途中で江戸に戻った
↓↑
正月
甲府城へ公家の
高松実村を総帥とした
「官軍鎮撫隊」が入城
高松隊は高松を中心に
伊豆国出身の
宮大工・彫刻師である
小沢一仙らを加えた
草莽諸隊で
甲斐で年貢減免などの
政策を約束しつつ甲府城へ入城したが
官軍東海道総督府から
勅宣を受けていない
高松隊への帰国命令が発せられ
小沢一仙は処刑された(偽勅使事件)
↓↑
3月4日
新政府側
板垣退助の率いる
土佐藩
迅衝隊(12小隊, 約600名)と
因幡鳥取藩兵(8小隊, 約800名)が
東山道総督府先鋒として
甲府城に入城
甲府城内の勤番士は立退きを命じられ
後に官軍は
甲府市中に残った勤番士を場内に戻し
近藤派に属したものは入牢
↓↑
甲陽鎮撫隊は勝沼から前進
甲州街道と青梅街道の分岐点近くで布陣
300名いた兵は次々脱走し121名まで減
近藤は
「会津藩の援軍がこちらへ向かっている」
と騙して脱走を防ごうとした
土方は
神奈川方面へ赴き旗本の間で結成されていた
菜葉隊(隊長:吹田鯛六、以下隊士:500名)
に援助を頼むが黙殺
↓↑
3月6日
山梨郡
一町田中村
歌田(山梨市一町田中・歌田)において
迅衝隊
と
甲陽鎮撫隊
との間で戦闘
迅衝隊が圧倒し
近藤は
勝沼の柏尾坂へ後退
兵は逃亡
甲陽鎮撫隊は
八王子へ退却し、解散
近藤らはその途中で
土方と合流
↓↑
甲府城の迅衝隊は
その後江戸へ向かい
官軍側であった
市ヶ谷の
尾張徳川藩邸(防衛省本部)を本陣とし
新宿方面を警備
江戸城の無血開城と
上野戦争で江戸を確保し
戊辰戦争の戦場は
関東北部の
宇都宮
会津
越後
へと移った
ーーーーー
・・・
↧
November 26, 2017, 4:57 am
・・・ここ2、3日、姿を見せなかった「ハエ(蝿=虫+甲+甩)」さんが出てきて遊んでくれている。どっか行っちまったのかなぁ~、どこかに隠れているのかなぁ~・・・家の中のアッチ、コッチを捜して、最後にはオォ~ィッ、出てきてぉくれョゥォ~、である・・・ワラちゃうけれど、ボクは「彼女(?)」の消息を心配している。雪が積もって温度も零度以下だし、彼女、来年への越冬は無理カモって・・・今日は纏わりついて遊んでくれている。ダレかのお使いなのかな、なぁ~んて。人間の魂魄が離脱して動物や虫に憑依してやってクルってコトがあるらしいけれど、ボクはキミが人間の魂魄の憑依なんかじゃなくてもィイんだ・・・「病原体媒介虫」ですか・・・モチロン、キミは「衛生害虫」なんかジャァない・・・
「銀蝿」でも「金蝿」でもないけれど、「家蝿」って「家族」?・・・やっぱ、蝿やその他の虫には「輪廻」で「転生」したくないなッ・・・「モモエグリイエバエ」って、「桃(腿・股・百々)抉り家蝿」?・・・桃恵、栗畏、重葉得・・・
![]()
ーーーーー
ハエ(蠅・蝿)=ハエ目(双翅目:そうしもく)
ハエ亜目(短角亜目)
環縫短角群(かんぽうたんかくぐん)
ハエ下目(Muscomorpha)属
の総称
日本だけで60ほどの科
属する3,000種近い種が存在
「ハエ(蝿・蠅)」と名のつくもののうち
「アシナガ(足長、脚長、肢長)ハエ科
オドリ(踊)バエ科」
などは「アブ(虻)」の仲間
「アブ(虻)」は
・・・「阿武」は「則天武后」
「煬(あぶ・ヨウ)」は「煬帝(隋王)」
「安武=あぶ=阿倍・焙」
「阿武隈山地」は
宮城県南部から
福島県東部を通り
茨城県北東部へ続く
紡錘形の高原状山地」
通常「ハエ(蝿・蠅)」とは別の
「直縫短角群」
「アブ(虻)」と名のつくもののうち
「ハナ(花)アブ科
アタマ(頭)アブ科」
などは「ハエ(蝿・蠅)」の仲間
ーーーーー
「ハエイロネ」・・・「蠅伊呂泥(はえいろね)=蝿伊呂杼(はえいろど)」って、「百襲姫=倭迹迹日百襲姫命」の母親で、
「意富夜麻登玖邇阿礼比売(おおやまとくにあれひめの)命(古事記)=大海姫命(おおあまひめみこと・勘注系図?)」、
「倭国香媛(やまとのくにかひめ)、
マタの名を
蠅伊呂泥(はえいろね
絚某姉(糸瓦・はえ某姉・日本書紀)」で、
「七代孝霊天皇の
妃となって、
娘
倭途途日百襲媛(やまとととひももそひめ)」
を生んだ女性である・・・
その娘の
「倭途途日百襲媛」は「三輪山の大物主(大物主大神)」との結婚譚があるが、神の正体は「小さな黒蛇=ペニス?・櫛笥の中に小蛇の姿)」で、「百襲媛」にバレて・・・箸(竹者)墓・・・伝説・・・
「母母曽毘売(百襲姫)」
「活玉依比売」が三輪山の神の居所を毛玉の糸でツキとめたって、ギリシャ神話の「ミノタウロス(巨牛頭の怪物)」のラビリンス(迷路)からの脱出の剽窃?・・・「美濃(みの)の蛇有留守(たうろす)or 美濃多雨露州」って「斎藤道三(利政・蝮・まむし)」だろうッ・・・
「倭迹速神浅茅原目妙姫(やまととはやかんあさじはらまくわしひめ)=百襲姫と同一」
↓↑
「然更求爲大后之美人時、大久米命曰、
此間有媛女、是謂神御子、其所以謂神御子者、
三嶋湟咋之女、
↓↑・・・湟=氵+皇=川の名・湟水
濠・堀・城の周囲のほり
三島溝杭姫=玉櫛媛(たまくしひめ)
日本書紀で事代主神の妃
古事記で大物主の妃
神武天皇の皇后である
媛蹈鞴五十鈴媛命の母
別名は
溝咋姫神・三島溝杭姫
三嶋溝樴姫・溝咋玉櫛媛・活玉依姫
↓↑ 勢夜陀多良比売とも
名
勢夜陀多良比賣、
其容姿麗美故、
美和之大物主神
見感而、
其美人
爲
大便之時、・・・「うんこ」?
↓↑ いきむ(りきむ)声「うん」に
接尾語「こ」が付いた?
「阿吽(あうん)」の「吽(うん)」
中国仏教で
大小便を「吽」
大小便の溜まり場を
「吽置(ウンチ)」と云うらしい
「ばば」?・・・江戸時代の幼児語?
猫糞(ねこばば→場場・場張)?
「猫好き婆さんが人から借りたものを
返そうとしなかったという
江戸時代の婆さんに由来」?
婆ァさんのヤルことが「汚い」って?
バッチィ=汚いモノ
ばば=大便
↓↑ ちい=小便
「御虎子=おまる」→「放(ほう)まる」?
「御丸」の形態からだろう
塒を巻く(とぐろをまく)
蛇が渦巻状に巻いて蟠(わだかま)る
とぐろ=塒=蜷局
「ウンコの」
「便」の原義は
「順調、好都合、スラスラ」?
排便が可ってコト
便利ってコト
友好、都の合理性・・・?
「便=すなわち・(助字)
そうすると
~するとすぐに
つまり~である」
詰まり、便秘、でアル?
「便=イ+更(一曳・一由乂)
「糞=米+異(田共)」
「屎=尸+米」
「大便(ダイベン・糞)」って
何時頃からのコトバなんだか?
「スカトロジー(Scatology)」?
↓↑ 「猫糞 (ねこばば)」?
化丹塗矢
自其爲
大便之溝流下、
突其美人之富登、
爾其美人驚而立走
伊須須岐伎、
乃將來其矢置於床邊、
忽成麗壯夫、
即娶其美人生子、
名謂
富登多多良伊須須岐比賣命、
多田良=たたら=踏鞴・蹈鞴・鞴(ふいご)
亦名謂
比賣多多良伊須氣余理比賣、
一寸木・委好(鋤・鉏・耜・犂・耒)
故是以謂神御子也」
ーーーーー
「斌(ヒン)=文(亠乂)+武(止一弋・ト丄一弋)
=うるわしい・あきらか・たけ
ヒン・フン
外見の美しさと
内面の実質が調和しているさま」・・・
文武天皇
(683~707)
第四十二代天皇(在位697~707)
名は珂瑠(かる)
大宝律令を制定
天武・持統天皇の孫
草壁皇子の第一皇子
母は
↓↑
元明天皇
(第四十三代天皇
在位慶雲四年七月十七日
(707年8月18日)
~
和銅八年九月二日
(715年10月3日)
名は阿閇皇女(あへのひめみこ )
阿部皇女
草壁皇子の正妃
文武天皇と元正天皇の母
藤原京から平城京へ遷都
「風土記」編纂の詔勅
「古事記の完成」
「和同開珎の鋳造」
ーーーーー
・・・
↧
↧
November 28, 2017, 12:33 am
↧
November 29, 2017, 5:02 am
・・・「頓珍漢」のツヅキ・・・
ーーーーー
New Orleans(オリンズ→織理務図)
&
Orleans (オルレアン→嗚留例晏)
・・・Joan of Arc・・・ジャンヌ・ダルク
↓↑
「晏=日+宀+女
アン・くれる
おそ・さだ・はる・やす
おそい・日が低く落ちかかるさま
時刻がおそい
晩(夜、おそい)
「何晏也=ナンゾ晏キヤ(論語)」
靖=やすらか・やすし
安堵・安土・・・and・・・按度・・・蛙務説
↓↑
「頓=屯+頁=トン・チュン
たむろ(屯)+ページ(頁)
屯=明治時代、巡査の詰めている所
巡査の「調書」?
駐在所・駐屯地
古代日本における
真綿の質量・取引単位
頓=とみに・ひたすら
頭を地面につけて礼をする
ぬかずく・頓首
その場にとどまる・落ち着く
整頓・停頓
すぐに・即座に・急に・とみに
頓悟・頓才・頓死・頓知
ひたぶる(頓・一向)
いちずなさま・ひたすら
完全にその状態であるさま
向こう見ずなさま
強引で粗暴なさま。
「とにに(頓に)=副詞の「とに」は「頓」の字音「トン」
「とみに」 に同じ
「風波とみにやむべくもあらず(土佐)」
急に・俄(にわか)に
「頓首=ぬかずく・頭を下げて地につける
躓(つまず)く・倒れる
苦しむ・苦しめる
やぶれる(壊れる・失敗 する)」
「嵌頓(カントン)=腸管などの内臓器官が
腹壁の間隙から脱し
もとの位置に戻らなくなった状態
嵌頓ヘルニア(脱腸)」
「頓=一回、一度」
「頓服薬」
「頓首」
「困頓(疲れで動きがとれない)」
「整頓(ととのえる)」
「頓躓=どんと重みをかける・急に動く
とっさに変化する」
「頓足=足を頓す」
「頓仆(トンボク)=たおれる・ふす」
「一頓=腰をおちつける休み所や宿
休憩所で一食するコト」
「頓挫(突然くじける・不意な挫折)」
「頓死(急死)」
「頓知(状況に応じて働く知恵)」
「頓悟(その場で悟ること)」
「頓(とん)とわからない、すぐにはわからない」
「頓服(必要なときに)すぐに服用する」
「頓服薬=腹痛薬・頭痛薬」
↓↑
ジャパン
マルコ・ポーロの
「東方見聞録」の
「黄金の国・ジパング (ZIPANG・ZIPANGU) 」
「にっぽん・じっぽん」・・・日・實・実
・・・本・椪・笨・翻
ほむ=誉む・褒む
本多和気尊(ホムダワケノミコト)
本多和氣尊(ホムダワケノミコト)
品陀和氣尊命(ホ ムダワケノミコト)
品陀和気尊(ホムダワケノミコト)
品陀皇大神(ホンダコウタイジン)
誉田命(ホンダノミコト)
品陀別天皇(ホンダワケテンノウ)
譽田別天皇(ホンダワケテンノウ)
誉田別尊(ほむたわけのみこと)
誉田別命(ほんだわけのみこと)
大鞆和気命(おおともわけのみこと)
↓↑
本多正信=相模国玉縄藩主
本多正純=下野国小山藩主
宇都宮藩主
本多正信の長男
本多忠勝=上総大多喜藩初代藩主
伊勢桑名藩初代藩主
本姓は藤原氏・通称は平八郎
↓↑
垂仁天皇・・・「推認転向・推認典項」?
と
沙本比売・・・・・順和(すな)の比べ売り?
詐本=サホン=差本=作翻?
佐波遅比売・・・・たすけるナミジ(並字)?
名見字
狭穂毘売・・・・・佐俣(サホ)
熊本県下益城郡美里町佐俣
佐保川=大和川水系の支流
の子
本牟智和気御子
誉津別命(ほむつわけのみこと)
誉津別命(日本書紀)
本牟都和気命(古事記)
本牟智和気命(古事記)
品津別皇子(尾張国風土記・逸文)?
中国語で
「日本」を
ズーベン(ziben)
リーベン(liben)
と発音
「日本=rìběn」
と発音
アメリカ合衆国ミズーリ州フランクリン郡
ジャパン(Japan)
↓↑
「ジパング」と「ジャパン」
「ジパング~ジャパン」
「ジャパン」は中国語の
「Jih-pŭn」がマレー語の
「Jăpung, Japang」を経て
ヨーロッパ諸語に取り入れられ
「Chipangu (チパング)」
と語源は同じ
『東方諸国記(ポルトガル語版)』(1514年筆)
「Jampon」
ダミアン・デ・ゴエス
『マヌエル王代記』(1562年筆・1567年刊)
「Japongos」
ジョアン・デ・バロス
『アジア史』第1編(1552年刊)
「Japões」
同第3編(1556年刊)の
「Japam」
16世紀に東アジアに来航した
ポルトガル人が
「日本」の中国音(広東音)
を直接伝え聞いて記録
1554年の
ロポ・オーメンの世界図で
ジャパン(大陸と陸続きになっている)
とは別に
ジパングらしき無名島が描かれている
「ジャパン」と「ジパング」
が同一であることを示した最初の地図は
メルカトルの
1569年版世界地図(en:Mercator 1569 world map)
↓↑
「Japan」以外の使用[編集]
ドイツ語およびポーランド語
「Japan(ヤーパン)/Japonia(ヤポニア)」
「Japanisch(ヤパーニッシュ)/Japoński(ヤポンスキ)」
単略形「Jap.(ヤープ)」が使用
「日本人」を「イルボンサラム」
と云うのは隣国の人
「日本」を「リーベン」or「ルイベン」or「イーベン」
「日本人」は
「リーベンレン」or「ルイベンレン」or「イーベンレン」
「日本」は
「リーベン(イーベン)」
「日本人」は
「リーベンレン(イーベンレン)」
ーー↓↑ーー
発音が似ているのは「?」だが・・・
↓↑
両班(りょうはん、
ヤンバン・韓国語〉
リャンバン・北朝鮮語)
高麗、李氏朝鮮王朝時代の
官僚機構・支配機構を担った
支配階級の身分
士大夫
身分階層と同一
身分制度は
「甲午改革」後に廃止
「乙未事変(いつびじへん)」
=「明成皇后弑害事件」
李氏朝鮮
第26代国王
高宗の王妃であった
「閔妃」が
1895年10月8日
三浦梧楼
らの計画に基づいて・・・?
王宮に乱入した
日本軍守備隊
領事館警察官
日本人壮士(大陸浪人)
朝鮮親衛隊
朝鮮訓練隊
朝鮮警務使
らに暗殺された
↓↑
両班(やんばん・リャンバン)
高麗時代に役人の
文官を文班(ムンバン)
武官を武班(ム バン)
両者をあわせ
官職に就いている人を
両班といった
「班=序列」のことで
朝廷において
南面の国王に向かって
右側に文官
左側に武官
が整列
両 班(南でヤンバン、北でリャンバン)
身分制度
「良民」と「賤民」に二分
「良民=自由民・納税、国役の義務を負い
「両班(文班、武班)」
「中人(下級役人、技術官など)」
「常民(農民、商人、職人)」
に分けられた
↓↑
「賤民」は
「奴隷―奴婢」と
「白丁(ペクチョン)」
「才人(広大・芸人)」
「官妓(役所に所属する酌婦)」
「牽令(キュンエン・牛馬を引く者)」
「砲手(猟師)」
「水尺(スチョク・狩猟民)」
「駅卒(駅の使用人)」
「巫女」
「僧侶」
など・・・
「奴婢」は
「公奴婢―国家に所属するもの」
「私奴婢―個人に所属するもの」
に分けられ
奴婢は
「公奴婢」
「私奴婢」
とも
「入役奴婢」と「納貢奴婢」
とがあった
「入役奴婢」は
国の労役や主人の雑役に従事
「納貢奴婢」は
国や主人から独立の生計を営み
一定の身貢をする義務
「奴婢」は
売買、贈与、相続の対象
父母の一方が奴婢の場合は
子も奴婢となった
↓↑
「両班」が罪を犯し「奴婢」になったり
「奴婢」が軍功などで
「中人・常民」になった
↓↑
晏
アン・くれる
おそ・さだ・はる・やす
おそい・日が低く落ちかかるさま・時刻がおそい
晩(夜・おそい)
↓↑
「何晏也=ナンゾ晏キヤ(論語)」
やすらか・やすい
ーーーーー
1894年3月28日
閔氏政権によって
開化派の中心人物
金玉均
が
閔妃の刺客である
洪鐘宇
の回転式拳銃で暗殺
5月31日
閔氏政権に対し農民が蜂起し
甲午農民戦争勃発
閔氏政権は
宗主国
清に軍の出動を要請
日本も朝鮮へ出兵
1894年7月23日
日本軍は景福宮を占領
日本は
興宣大院君(高宗の父)の復権を行い
開化派の
金弘集政権は
日本の支援のもと
甲午改革を進め
日清戦争は日本が勝利
1895年4月17日
下関条約が締結
政権を追われていた
閔妃の一族は
ロシア公使
カール・イバノビッチ・ヴェーバー
ロシア軍の力を借りて
クーデターを行い
1895年7月6日
政権奪回
日本公使
三浦梧楼
軍事顧問
岡本柳之助
らは
露派の
閔妃を排除するクーデター
1895年10月8日午前三時
日本軍守備隊
領事館警察官
日本人壮士(大陸浪人)
朝鮮親衛隊
朝鮮訓練隊
朝鮮警務使
が
景福宮に突入
騒ぎの中で
閔妃は斬殺
遺体は焼却
興宣大院君
と
閔妃
の権力闘争
10月10日
日本政府は
小村寿太郎
外務省政務局長を京城に派遣
三浦梧楼は
10月24日後任に免官処分
小村が
特派大使として
井上馨
が京城に派遣
軍人8人は
第五師団の軍法会議
三浦ら48名は謀殺罪等で起訴され
広島監獄未決に収監
証拠不十分で免訴、釈放
朝鮮では
閔妃暗殺の2日後(10月10日)
閔妃の死亡が公表される前に
大院君が
閔妃の王后の地位を剥奪し
平民に落とす詔勅公布
小村壽太郎の助言で
11月26日に再び王后閔氏に復位
朝鮮の裁判
「王妃殺害を今回計画したのは、私」
と証言した
李周会(前軍部協弁=次官)
朴銑(日本公使館通訳)
尹錫禹(親衛隊副尉)
3人とその家族を
三浦らの公判中の同年10月19日に処刑
ーーーーー
・・・???・・・フランス国歌に怒るフランス人にあったコトがあるけれど・・・「ダイサンカイキュウ」ってナンなんだか・・・「フランスの平家の平民」・・・?
「第三身分とは何か(だいさんみぶんとはなにか」、フランス語: qu'est-ce que le tiers état )、エマニュエル=ジョゼフ・シエイエスが表したパンフレット。フランス革命の原動力。タイトルは「第三階級とは何か(1789年初版)」とも訳される・・・
・・・アベ(坊主)=シェイエス(総裁政府の5人の総裁のひとり(ルーベルの後任))・・・
↧
November 30, 2017, 5:13 am
・・・なんか「ジャパン」を検索していたら以下のブログを発見・・・勝手に参考させてもらって、勝手に添付してしまったけれど、世の中には面白くて、スゴイ人がいるねッ!・・・原文は・・・
ーー↓↑ーー↓↑ーー↓↑
「アメリカにある地名 Japan の意外な由来
リアルETの英語学習
高校入試&TOEIC/BIGLOBEウェブリブログ」
http://studyenglish.at.webry.info/201706/article_25.html
ーー↓↑ーー↓↑ーー↓↑
ジャパン(Japan)
アメリカ合衆国ミズーリ州フランクリン郡
非法人地域
北緯38度14分21秒
西経91度18分21秒
セントルイスの都市圏内
セントルイスから
南南西へ約120km
カトリックの
セントルイス大司教区管轄下
ジャパン聖殉教者教会が立地
教会の住所は
法人化された市である
サリバン・・・サリバン先生・・・奇蹟の人・ヘレン・ケラー
↓↑
ジャパン(Japan)という名の郵便局
1860年に建てられ
1908年に廃止
ーー↓↑ーー
1860年
干支=庚申・・・更新・後進・行進・亢進・交信・後身・口唇
「庚申信仰」・・・猿田彦
日本(天保暦)
安政六年十二月九日~安政七年三月十七日
万延元年三月十八日~万延元年十一月二十日
皇紀2520年
清王朝
咸豊九年十二月九日~咸豊十年十一月二十日
朝鮮
檀紀4193年
李氏朝鮮
哲宗十一年
↓↑
2月10日
咸臨丸、太平洋横断航行
↓↑ ・・・咸臨丸=江戸幕府の軍艦
木造でバーク式の3本マストの蒸気コルベット
旧名(オランダ語名)は
Japan(ヤパン号・ヤッパン号・ヤーパン号)
「咸臨=君臣が互いに親しみ合うこと(易経)」
軍艦奉行
木村芥舟は咸臨丸の司令官として
遣米副使を命じられ、乗組士官を選考
運用方
佐々倉桐太郎、鈴藤勇次郎、浜口興右衛門
らを任命
測量方
小野友五郎、伴鉄太郎、松岡磐吉
らを任命
蒸気方
肥田浜五郎、山本金次郎
らを選定
従者
福澤諭吉
勝海舟
らを同乗
通訳
中浜万次郎
米国側との連絡に
米海軍大尉ジョン・ブルック
↓↑ ら米国軍人の乗艦を幕府に要請し認可
万延元年
一月十九日
浦賀を発った咸臨丸は
二月二十六日
サンフランシスコに到着
木村芥舟ら一行は
遅れて到着した正使一行と共に
市民の熱烈な歓迎をされ
現地の人々との交流も行った
ワシントンへ向う正使一行と別れ
↓↑ ↓↑
↓↑ 小栗忠順=日米修好通商条約批准のため
咸臨丸と伴走した
米艦ポーハタン号で渡米
新見正興
村垣範正も米艦ポーハタン号で渡米
正使-新見正興
副使-村垣範正
監察-小栗忠順
勘定方組頭-森田清行
外国奉行頭支配組頭-成瀬正典
外国奉行支配両番格調役-塚原昌義
帰路は
ナイアガラ号にて大西洋航路で
南アフリカ・インド経由で帰国
9月27日に江戸へ到着
村垣範正は航海日誌
↓↑ 「村垣淡路守公務日記=遣米使節日記」
↓↑ を残した
37日後の
3月17日
サンフランシスコへ到着
閏三月十九日
サンフランシスコを発って
咸臨丸はホノルル経由で
↓↑ 五月五日に浦賀へ帰還
![]()
2月26日(安政七年二月五日)
午後7~8時頃
横浜の本町通り(中区本町)で
オランダ人船長の
W・デ・フォス(Wessel de Vos)
N・デッケル(Jasper Nanning Dekker)
が攘夷派により斬殺
3月
サルデーニャ王国・・・猿出重似也?
フランスへの
サヴォイア・ニース割譲と引き換えに
中部イタリア諸国
(パルマ・モデナ・トスカーナ・ロマーニャ)
を併合
3月24日(安政七年三月三日)
桜田門外の変
大老「井伊直弼」が暗殺・・・彦根藩主、井伊直弼
「現今判取、云い直す化」?
4月8日(万延元年三月十八日)
元号が
安政~万延
に改元
5月17日
ドイツのサッカークラブ
TSV1860ミュンヘンが設立
7月2日(ユリウス暦6月20日)
ロシア帝国の輸送船
「マンジュール号」が・・・・「饅頭留・万重留」?
金角湾・・・・「金角湾=ロシア語
↓↑ ブーフタ・ザラトーイ・ローク」は
ロシア沿海の
ウラジオストクにある入り江
アムールスキー半島の先端に
角状に細長く切れ込んでいる」
「金角湾(トルコ語 Altın Boynuz
ギリシア語 Χρυσόν Κέρας
金の角の意)
トルコのイスタンブールにある湾
↓↑ トルコ語ハリチュ(Haliç・ハリチ=入り江)」
に到達
湾の北岸に砦の建設を開始
ウラジオストク開基の日
9月7日
ジュゼッペ・ガリバルディ
両シチリア王国の
首都ナポリに入城・・・・名補理
翌10月
両シチリア王国の・・・・「細々里・昔昔里」
「示地理蛙」?
版図である
シチリア・・・・・・・・「史知理亜」
を含む
南イタリアを
サルデーニャ王国・・・・「猿出重似哉」
国王
ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世に献上
11月6日
エイブラハム・リンカーン・・・エイプ・ラ・ハム・リン・カアン
↓↑ 瀛 部 覶 葉務 臨 化案
アブラハム=脂食む ape=類人猿・直立して歩く
尾のないサル
ape=chimpanzee・gorilla
↓↑ orangutan・gibbon・cf.monkey
アメリカ合衆国大統領に当選
12月
アメリカ南部諸州が
合衆国からの離脱を宣言
ーー↓↑ーー
1908年
干支=戊申・・・椄知の重の申(上海・猿・猴・猨・狙)
狙う・狙撃
日本
明治四十一年
皇紀2568年
中国
清王朝
光虬三十三年十一月二十八日~光虬三十四年十二月九日
朝鮮
大韓帝国・隆熙二年
↓↑
2月1日
ポルトガル国王
カルロス1世
皇太子ルイス・フィリペが暗殺
2月18日
移民に関する
日米紳士協約締結
(日本は米国への新規移民を禁止することを約束)
3月5日
時事新報社
シカゴ・トリビューンの世界美人コンクールの
日本予選として日本初の美人コンテストを開催
3月7日夕方~9日夕方
北海道釧路地方で暴風雪
(家屋倒壊により釧路町で19人、昆布森村で18人圧死)
3月8日
ニューヨーク
女性労働者が
パンと婦人参政権を要求するデモ
(国際女性デーの由来)
3月9日
インテルナツィオナーレ・ミラノ創立
3月22日
東京大久保で
出歯亀事件発生
黒板勝美「国史の研究」
4月27日
第4回夏季オリンピック
ロンドンで開幕(〜10月31日)
4月28日
第1回ブラジル移民を乗せた
笠戸丸が神戸港を出港(6月到着)
5月15日
第10回衆議院議員総選挙
5月20日
ジャワ
民族主義的政治結社
プディ・ウトモ結成
6月10日
日新火災海上保険設立
6月22日
赤旗事件(大杉栄、荒畑寒村ら14名を検挙)
6月30日
シベリアでツングースカ大爆発
7月1日
銚子無線電信局(銚子無線電報サービスセンタ)開局
7月4日
第1次西園寺内閣総辞職
7月10日
ヘイケ・カメルリング・オネス
ring・link→平家・亀留吝具・嗚音素
初の「ヘリウムの液化」・・・helium・「縁有無の液果」?
に成功
7月14日
第2次桂内閣成立
7月23日・・・・七月二十三日・・・弘文天皇・大友皇子
オスマン帝国
青年トルコ人革命
7月24日
ロンドンオリンピック
男子マラソンで
ドランド・ピエトリが係員の助けを借りて
最初にゴールに辿り付いたが、失格
2着のジョニー・ヘイズが金メダル
7月25日
池田菊苗
「グルタミン酸を主要成分とせる
調味料製造法(味の素)」が特許登録・・・アジのモト
7月26日
アメリカ連邦捜査局設立
8月7日
ヴィレンドルフの
ヴィーナス発掘
9月16日
ゼネラルモーターズ(GM)創業
(ウィリアム・C・デュラント)
9月19日
グスタフ・マーラー交響曲第7番初演(プラハ)
9月23日
アルバータ大学創立
9月27日
米国でフォード・モデルT完成
9月30日
メーテルリンク童話劇・・・「目(女)重照(出留)吝句」
「青い鳥」初演(モスクワ)
清で
欽定憲法大綱発布(国会開設を公約)
10月1日
フォード・モデルT発売開始
10月3日
新聞プラウダ刊行(ウィーン亡命中のトロツキーら)
10月5日
ブルガリア
オスマン帝国から独立宣言
10月6日
オーストリア=ハンガリー帝国
ボスニアとヘルツェゴヴィナを併合
10月7日
セルビア王国とモンテネグロ公国が
反オーストリア=ハンガリー同盟を結成
10月18日
ベルギーがコンゴ自由国を併合
10月24日
日本統治下の台湾
縦貫線基隆・高雄間が全線開通
10月28日
ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世
と
英軍大佐エドワード・ワートリー
の対談が
デイリー・テレグラフ紙に掲載
(デイリー・テレグラフ事件)
11月3日
米大統領選挙
ウィリアム・タフトが勝利
11月10日
国際ギデオン協会が
最初の聖書をホテルに配布
11月14日
清で光緒帝が崩御
翌日に西太后も崩御
11月13日
アンドリュー・フィッシャー
オーストラリア首相に就任
11月15日
「新フランス評論」創刊
11月22日
第1回日米野球
11月30日
高平・ルート協定締結
(日米両国の太平洋での現状維持や
清の領土保全・機会均等)
波多野精一「基督教の起源」
12月2日
愛新覚羅溥儀が清の皇帝に即位
12月16日
豪華客船「オリンピック」起工
12月21日
オスカー・スレイター事件起こる
12月22日
第25議会召集
12月28日
メッシーナ地震発生
↓↑
「アララギ」創刊(伊藤左千夫ら)
正宗白鳥『何処へ』
語劇の絶頂期
水俣村に日本窒素株式会社創設
中部で農民の抗税デモ
流刑が廃止される
ーーー↓↑ーーー
http://studyenglish.at.webry.info/201706/article_25.html
↓↑ ↓↑
Incidentally, on September 2, 1945, the signing of Japan's Instrument of Surrender was held on the battleship Missouri in Tokyo Bay--the flag that stood in the background had once flown on Perry's flagship Powhatan, and was brought from the United States for the occasion.
ちなみに、昭和20年(1945年)9月2日
東京湾の
戦艦ミズーリ艦上で
日本の降伏文書調印式が行われた際、
この時のペリー艦隊の
旗艦「ポーハタン」号に
掲げられていた米国旗が本国より持ち込まれ、
その旗の前で調印式が行われた。
(Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス)
↓↑
The community established its first post office November 13, 1860 with Absolam R. Dyson the first postmaster. He became a Confederate soldier. The post office closed March 17 to October 5, 1865. It remained open until January 31, 1908.
その地域は
1860年11月3日に初めての郵便局を建て
最初の局長は
ダイソン氏でした。
彼はその後
南部連邦政府の兵士となりこの地を離れました。
その郵便局は
1865年の3月17日~10月5日までは閉鎖されましたが
1908年の1月31日まで営業していました。
↓↑
The present church building was built in 1896
and the cemetery shortly afterward.
現在の教会の建物は
1896年に建てられ
その後すぐに墓地もできました。
↓↑
During the Second World War, the citizens of Japan, who pronounce the name of their town 'Jay-pan' resisted the pressure brought upon them to change their town's name."
第二次世界大戦の間は
ジャパンの住人たちは
自分たちの町の名前を
「ジェイパン」と発音することによって
敵国の名前がついた町の名前を変えろ
という圧力に抵抗しました。
↓↑
ここまでが新聞記事の引用です。
ここからは
これを引用した女性のブログ記事から。
Below is a map of Franklin County, Missouri from about 1920, I believe. It shows the townships, railroads and larger streams. An "x" represents a place that was a post office at one time, but had been closed by 1925, while an "o" represents a place that was still a post office as of 1925.
1920年ころの
ミズーリ州フランクリン郡の地図
郡区名,鉄道,大きな川
「×」印は一時期郵便局が置かれた場所
1925年までには閉鎖
「〇」印は
1925年の時点でまだ郵便局があった場所
![]()
![]()
↓↑
The northern boundary of Franklin County is the Missouri River, and it is one county west of St. Louis County.
フランクリン郡の
北の境界線はミズーリ川で
セントルイス郡から見て西にある郡の一つです。
↓↑
In the lower left area of the map is Boone Township, with the Bourbeuse River running across it. Below the river can be seen Japan, and below that Argo.
地図の左下の地域は
ブーン(Boone)郡区で
Bourbeuse川が流れています。
その川の下に
「ジャパン」
が見つかります。
その下は
「アーゴー(Argo)」です。
↓↑
アァゴォ・・・蛙鴉語嗚・・・嗚呼漁尾(互訖)
訖=言+乞=おえる・おわる=終→尾張
ついに=終に→対に・竟に・遂に
とまる・やむ・いたる・およぶ
コチ・キツ
ーー↓↑ーー↓↑
the Argo=ギリシャ神話のアルゴー号 (Argonaut)
英雄イアソン・・・位-朝臣=朝臣(あそん、あそみ)
684年(天武天皇十三年)制定の
「八色の姓」
をはじめ
黄金の羊の皮を求める
五十余人の冒険者たち
(アルゴナウタイ)・・・「阿留語名唄意(易)」?
を乗せた巨船・・・
ーーーーーー
Argo
アルゴー=南天の大星座
艫とも座(Puppis)・帆座(Vela)
羅針盤座(Pyxis)・竜骨座(Carina)
の4つの別々の星座に分けられる
ーーーーー
映画「アルゴ」
1979年
イラン革命の混乱のなかで起きた
アメリカ大使館人質事件を題材とした
2012年のアメリカ映画
第85回アカデミー賞作品賞を受賞
ーーーーー
「Thunderbirds are go!」・・・are go=出発・出動・発進
ready・準備完了
「オセロー」の旗手「イアーゴー(Iago)」
ーー↓↑ーー
フランクリン郡(Franklin County)は、
アメリカ合衆国ミズーリ州の東部、
ミズーリ川の南岸に位置する郡である。
2010年国勢調査での人口は101,492人であり、
2000年の93,807人から8.2%増加した。
州内では10番目に人口の多い郡である。
郡庁所在地はユニオン市(人口10,204人)であり、
同郡で人口最大の都市は
ワシントン市(人口13,982人[3])である。
フランクリン郡は
セントルイス大都市圏に属しており、
独立市である
セントルイス市と
ミズーリ州、
イリノイ州
にある周辺郡を
合わせると都市圏人口は280万人になる。
セントルイス市西の準郊外地域を構成している。
フランクリン郡は
1818年に組織化され、
建国の父である
ベンジャミン・フランクリン
に因んで名付けられた。
ーーーーー
郡内にはハーマン・ブドウ栽培地域に含まれる
ワイン醸造所があり、
また
ミズーリ川の両岸に跨る
ミズーリ・ラインランドと呼ばれる地域に属している。
田園部では
メタンフェタミンの製造と消費という問題があり、
2005年のA&Eテレビのドキュメンタリー
『Meth: A County in Crisis』
で取り上げられた。
ーーーーー
・・・ジャホン=邪本・蛇本・舎本・写本・・・
↧
↧
December 1, 2017, 5:27 am
・・・一昨日(おととい・イッサクジツ)、十一月二十八日、三笠の従姉が来て泊っていった。彼女、九州の福岡に懇意にしていた友人の「Yさん」が施設にい、札幌の「Kさん」と一緒にお見舞いを兼ねながら旅行してきたコトをハナシてくれた。福岡市は結構、巨大な都市らしい・・・それに「菅原道真の天神様」の本場・・・
![]()
ーーーーー
中世に商人による自治都市が形成され、
戦乱で度々焼き払われながらも
豊かな町人文化を育んだ。
豊臣秀吉の手で復興されたのち、
黒田(如水・孝高・官兵衛・シメオン)
・・・締め音・〆音・市目(女)音(怨)
が福岡城とその城下町を築き
那珂川を境に
西が城下町としての「福岡」
東が商人町としての「博多」
となった
江戸時代から明治時代初頭にかけて
福岡と博多は共存していたが
1876年(明治九年)に福岡と博多は統合され
福博(ふくはく)となり、その後、福岡と改称・・・
ーーーーー
・・・従姉とハナシているうちに「Yさん」の故郷「与論島」、隣接する「徳之島」、「沖縄」のハナシ、「西表島(いりおもてじま・沖縄県八重山郡竹富町に属する八重山列島の島)」のハナシ・・・
「吐噶喇列島(とかられっとう)」、「種子島」、最近の「バリ島アグン山」噴火のハナシが・・・2015(平成27)年5月29日の「瓢箪島の口永良部島(新岳で29日午前10時前に爆発的噴火)」のハナシになり・・・
そして「屋久島」のハナシになって、従姉が読んだ「林芙美子」の小説「浮雲」に跳び、そして、これも従姉が観たらしい「高峰秀子、森雅之」主演の映画「浮雲」まで飛んだ・・・
従姉のハナシでは映画の最期の場面が「屋久島」だったそうだが、ボクは小説もこの映画も観ていない。
記憶にある「浮雲」のタイトルは学校で習った「言文一致」の「二葉亭四迷の小説」、それも「原文」を読んだことはない・・・
従姉がコンピュータで映画「浮雲」を検索して欲しいと云うので、開けたら、作品が「1955年」、映画の舞台が戦前1943~戦後の混乱期・・・
「森雅之(もり まさゆき・1911年1月13日~1973年10月7日)は、北海道札幌郡上白石村(札幌市白石区)生まれ、東京都出身の俳優。父は小説家の有島武郎。本名は有島 行光(ありしま ゆきみつ)」・・・オフクロの本棚には2、3冊、有島武郎の小説がある・・・
映画「浮雲」のコンピュータのモニターには紹介記事で
おせい:岡田茉莉子
伊庭杉夫:山形勲・・・・・・・・観た映画の殆んどが悪役
向井清吉:加東大介・・・・・・・「大判」の名刺の牛ちゃん
仏印の所員・加納:金子信雄・・・日活映画の悪役
米兵・ジョー:ロイ・ジェームス・外人の悪役
信者:谷晃・・・・・・・・・・・岸田今日子の前の夫
などの名前が出てきて、あの役者が悪役でドウのコウの、とかのハナシになってしまった・・・
「森雅之」は
黒沢明の映画「白痴(4時間26分)」の主演者であることはダレかの映画評論で知っていたが・・・1951年(昭和26年)公開、舞台は昭和20年代の札幌ですか・・・
ーーーーー
黒澤 明
1910年(明治四十三年)3月23日~1998年(平成十年)9月6日
生年 庚戌(辛・丁・戊) 没年 戊寅(己・丙・甲)
生月 己卯(甲・ ・乙) 没月 庚申(己・壬・庚)
生日 丁亥(戊・甲・壬) 没日 丙辰(乙・癸・戊)
午未=空亡 5乙卯-6丙辰-7丁巳
ーーーーー
「丹治(にち・タンジ)」・・・?・・・「青空文庫」に「二葉亭四迷の小説・浮雲」が掲載されているが・・・覗いてみると、どうやら「難読漢字」は、この「浮雲」の「漢字に対する仮名振り小文字の発明=ルビ」にあるらしい・・・
↓↑
・・・なんか、今現在の「相撲業界」、「国会の森友、家計」の財務省や、文部省の役人、閣僚の答弁状況を揶揄しているみたいだが・・・
「それは課長の方が或は不条理かも知れぬが、しかし苟(いやし)くも長官たる者に向って抵抗を試みるなぞというなア、馬鹿の骨頂だ。まず考えて見給え、山口は何んだ、属吏じゃアないか。属吏ならば、仮令(たと)い課長の言付を条理と思ったにしろ思わぬにしろ、ハイハイ言ってその通り処弁(しょべん)して往きゃア、職分は尽きてるじゃアないか。然(しか)るに彼奴のように、苟(いやしく)も課長たる者に向ってあんな差図がましい事を……」
「イヤあれは指図じゃアない、注意サ」
「フム乙(おつう)山口を弁護するネ、やっぱり同病相憐(あいあわれ)むのか、アハアハアハ」
高い男は中背の男の顔を尻眼(しりめ)にかけて口を鉗(つぐ)んでしまッたので談話(はなし)がすこし中絶(とぎれ)る。錦町(にしきちょう)へ曲り込んで二ツ目の横町の角まで参った時、中背の男は不図(ふと)立止って、
「ダガ君の免を喰(く)ったのは、弔すべくまた賀すべしだぜ」
「何故」
「何故と言って、君、これからは朝から晩まで情婦(いろ)の側(そば)にへばり付いている事が出来らアネ。アハアハアハ」
「フフフン、馬鹿を言給うな」
ーーーーー
![]()
![]()
↓↑
「日本=ニチホン=丹治本」を同音異字の漢字を羅列していたら「丹治(にチ・タンジ)-本(もと・ホン)」になった・・・その意味を検索していたら・・・登場人物の名前らしいが・・・「丹治=タンジ=単字(単語)=丹次=嘆じ・歎じ」・・・「丹治=にじ=似字・似事」・・・「丹薬」による「治療」ではないのか?
「丹前・丹後・丹波・丹那・丹奈」などの地名と・・・
「丹=硫黄と水銀との化合した赤土・その赤色・埴輪の埴(はに)・丹塗り矢の丹色・辰砂・鉛に硫黄と硝石を加えて焼いて作ったもの・鉛の酸化物・黄色をおびた赤色で絵の具や薬用とする・主成分は四酸化三鉛・鉛丹(エンタン)・薬のこと(仁丹)」・・・
「丹=赤色の土・水銀と硫黄と化合した赤土・丹砂・朱砂・辰砂・ あか・あけ(朱)・あかし・あかく塗る・精鍊した薬の金丹(不老不死の藥)」・・・
「まごころ(誠心)・赤心にして僞なきもの」・・・
「牡丹(花の名)」・・・
「鼠姑(ソコ・わらじムシ)=等脚目ワラジムシ(草鞋虫)科の小型の純陸生甲殻類・甲殻綱等脚目の節足動物・灰褐色の長楕円形で、十数個の節から成り、ダンゴムシ(団子虫)に似るが扁平で、触れても球状にならない」・・・
「丹麥(ヂンマルク・デンマーク・Denmark)は
歐洲の國名=丁抹」・・・
↓↑
「丁(奇数・ひのと・火の弟」を「抹殺・抹消・塗抹」・・・?
・・・「火の弟」の「抹殺」・・・
「ハムレットの叔父(Claudius)」?・・・
「復讐劇」・・・ヤラレタラ、ヤリカエスのが鉄則?・・・
「Hamlet=ハムレット=甸国皇子・班烈多
狂公子・狂皇子」・・・
「Frailty, thy name is woman.
脆きもの、汝の名はオンナ
脆きもの、汝の名は日本」
「To be or not to be, that is the question.」
「沙翁(Shakespeare)=沙吉比亜」・・・
ーーーーー
ウィリアム・シェイクスピア
(William Shakespeare)
1564年4月23日・26日(洗礼日)
(1564年5月3日g)
~
1616年4月23日
↓↑
永禄七年三月十三日
グレゴリオ暦
西暦1564年5月3日 1616年4月23日
生年 甲子 没年 丙辰
生月 戊辰 没月 壬辰
生日 乙卯 没日 戊寅
子丑=空亡
六曜
先負
日曜日
ーーーーー
↓↑
「抹=さっとなする・こすりつける・マツ
一抹
塗り潰す
塗リ消す
抹殺・抹消・塗抹
すりつぶして粉にする
抹香・抹茶
こすりつける・塗りつける
「丹砂を以て面を抹し」
こすってなくす・塗りつぶす
こすって粉にする
「薬ヲこ(抹)スル・(日葡)」
「抹=扌(手)+末」=する・マツ
こする・こすって消す
塗って見えなくする
すって小さな粉末にする
小さいもの
琴の弦をなでて、
音を小さくおさえる」
ーー↓↑ーー
「浮雲」の本文の何処に
「丹治(にチ・タンジ)」が出てくるのやら・・・?
↓↑
日本=ジツホン=字通本・字椄本・実本
=ひホン=比本=比翻=秘本=卑本
=ニチホン=似知本=耳知本=二字補務=似字補務
=丹治本=昵補務
昵(ジツ)=日+尼(尸+七=牝)
↓↑ 尼(あま・ニ)=屍の牝・雌・女
↓↑
顋=思+頁=おとがい・あご
↓↑
拿破崙髭(ナポレオン)
比斯馬克髭(ビスマルク)
髭あり服あり
我また奚(なにを)かもとめんと
済した顔色(がんしょく)で、
火をくれた
木頭(もくず)と
反身(そっくりかえ)ッて
お帰り遊ばす、
イヤお羨(うらやま)しいことだ
盤帯(はちまき)
微塵(みじん)
左而已(さのみ)=それほど
非道(ひどく)
吝(おしま)ず
掙(扌+爭)了(かせぐ)
足掻(あがき)踠(足+宛・もがいて)
↓↑
ちんぷんかん(珍紛漢=珍糞漢=陳奮翰)
言葉や話がまったく通じず
何が何だか、さっぱりわけのわからない・・・
ちんぷんかんぷん
(珍糞漢糞=珍粉漢粉=珍紛漢紛=陳奮翰奮)
江戸時代の儒学者が難しい漢語つ使って
教養をひけらかしているのを聞いた庶民が
儒学者を冷やかすために作った言葉・・・
↓↑
薔薇(ばら)の花は頭(かしら)に咲て
活人は絵となる世の中独り文章而已(のみ)は
黴(かび)の生えた陳奮翰(ちんぷんかん)の
四角張りたるに頬返(ほおがえ)しを附けかね
又は舌足らずの物言(ものいい)を学びて
口に涎(よだれ)を流すは
拙(つたな)しこれはどうでも
言文一途
↓↑
1887年(明治20)第1編刊
1888年第2編刊
1889年第3編
を「都の花」に連載
官制の改革が行われた
1886年の東京を舞台に
内海文三・・・「得通視文簒」?
と従妹の
お勢
の相思相愛の関係が
文三
が役所を免職になったのち
変貌していくありさまを描く
世俗的なお勢の母親はともかく
新時代の教育を
身につけたお勢までが
なぜ
卑しい出世主義者の
「本田昇」・・・ほむたのぼる・・・
に惹(ひ)かれていくのか
文三・・・・・・文+三
にはわからない
異様なものとして現れてきた
世界の姿を問い続けながら
文三
は孤独のうちに
発狂寸前まで追い詰められていく・・・
↓↑
「昵=ジツ・ヂツ・ちかづく・なじむ
近づいて慣れ親しむ
昵近(ジッキン)・昵懇(ジッコン)
ほんとう・真実
まごころ・誠実
中身・内容・実質
成果・実績
なれる・なれしたしむ
昵交
狎昵(コウジツ)・親昵(シンジツ)
昵(ちか)づく」
ーー↓↑ーーー
言文一致=ゲンブンイッチ=原文一致・元文一致
↓↑
宣=宀+一+日+一・・・類字は「宜(よろしく・ギ)」
=のべる・のる・のたまう・セン
宣言・宣告・宣誓
広く行き渡らせる
宣教・宣伝・宣揚
天子や神が意向を述べる
宣旨 (センジ) ・宣命 (センミョウ)
院宣 (インゼン)・託宣(タクセン)
勅宣(チョクセン)・宣下(センゲ)
神や天皇が神聖なる意向を
人々に対し口で言ったりして表明
太祝詞事(ふとのりとごと)・祝詞・六月晦大祓
呪詞や名など
みだりに口にすべきでないことを
はっきりと言う
しめす・すみ・つら・のぶ・のぶる・のり
ひさ・ふさ・むら・よし
あまねく意向をわからせる
街宣・宣言・宣告・宣誓
宣戦・宣布
宣伝・街宣・託宣・不宣
↓↑
本居宣長(もとおりのりなが・ホンイセンチョウ)
ーーー↓↑ーー
宣化(センカ・宣言+変化)
天皇(テンコウ・転向)
同母兄の
安閑天皇に後嗣がなかったので
武小広国押盾尊
が即位して
宣化天皇
となった
武烈天皇
以来の旧臣
大伴-金村(かなむら)
や
物部-麁鹿火(あらかひ)
を
大連(むらじ)
↓↑ ・・・大連市=遼寧省の南部に位置
渤海と黄海に突き出た
遼東半島の南端
北緯38度43分~40度10分
仙台と同緯度
市花はアカシヤ
古名は「三山浦」
旧名=ダルニー市
日露戦争後ロシアに代わり
日本が中国大陸で統治し始めた
初めての都市が大連・・・
日本は古地図に見られる中国語の
地名「大連湾」からとった
これはロシア名の
ダルニ(遠い)と発音が似ている
1905年(明治38年)
ポーツマス条約により
日本の租借地である
関東州の一部
![]()
↓↑ 丹東市(タントンシ)=中国遼寧省南部
北緯40度07分33.32秒
鴨緑江を隔てて北朝鮮と接する国境の街
↓↑ 旧名は安東(アントン・あんどう)
とし
新たに
蘇我稲目を大臣
阿倍大麻呂臣を大夫(まえつきみ)
とした
新羅が任那を侵略したので
大伴金村に詔し
その子
大伴磐(磐は筑紫に留まった)・・・磐(いわい)=石井
と
大伴狭手彦
を遣わし
任那を助け
百済を救った・・・
一度失脚した
大伴金村
が
名誉挽回のために
軍を起こし
南朝鮮経営の失敗を挽回するため・・・?
・・・朝鮮経営は行き詰まっていた・・・
ーーー↓↑ーー
宣化=中国、河北省北西部の県
宣化区=中華人民共和国河北省張家口市の区
宣化県=中華人民共和国河北省張家口市の県
(宣化区とは異なる)宣化府
ーーー↓↑ーー
宣化天皇
↓↑
雄略天皇十一年?(467年?)
~
宣化天皇四年二月十日(539年3月15日?)
第二十八代天皇
(在位、宣化天皇元年12月(536年1月?)
~
宣化天皇四年二月十日(539年3月15日?)
諱 檜隈高田皇子
別称 建小広国押楯命
武小広国押盾天皇
父親 継体天皇
母親 尾張目子媛
皇后 橘仲皇女
子女
石姫皇女
小石姫皇女
倉稚綾姫皇女
上殖葉皇子
火焔(カエン)皇子・・・変えん・替えん・代えん
買えん・飼えん・化円
日影皇女
宅部皇子
他
皇居 檜隈廬入野宮
↓↑
皇后=橘仲皇女(たちばなのなかつひめみこ
仁賢天皇の皇女)
石姫皇女(いしひめのひめみこ
欽明天皇の皇后)
小石姫皇女(おいしひめのひめみこ
欽明天皇の妃)
倉稚綾姫皇女(くらのわかやひめのひめみこ
古事記に倉之若江王で男性
欽明天皇の妃)
上殖葉皇子(かみえはのみこ・恵波王・椀子)
丹比公(多治比真人・偉那公の祖)
某(夭逝、男女不明)
妃=大河内稚子媛(おおしこうちのわくごひめ)
火焔皇子(ほのおのみこ・椎田君・偉那公の祖
母不詳
日影皇女(ひかげのひめみこ
欽明天皇の妃)
宅部皇子(やかべのみこ
扶桑略記・本朝皇胤紹運録には
欽明天皇の皇子)
ーー↓↑ーー
諱は
檜隈高田皇子
(ひのくまのたかたのみこ・日本書紀)
和風諡号は
建小広国押楯命
(たけをひろくにおしたてのみこと・古事記)
武小広国押盾天皇
(たけをひろくにおしたてのすめらみこと・日本書紀)
継体天皇の第二子?
母は
尾張目子媛(おわりのめのこひめ)・・・尾張の目の子
安閑天皇の同母弟
欽明天皇の異母兄
ーー↓↑ーー
第二十八代天皇
名は
タケオヒロクニオシタテノミコト
継体天皇の第三皇子?
母は
尾張-連-草香の娘・・・草香=くさか=久坂・日下・草加・草薙
「目子媛 (めのこひめ)」
大和檜隈廬入野宮
に都
仁賢天皇の娘
橘仲皇女を皇后
在位期間中
蘇我稲目が大臣
↓↑
安閑天皇
が崩御したとき
子供がなかったために
同母弟の
宣化天皇が
満六十九歳で即位・・・69サイ・・・陸拾(足)玖
筑紫の官家の整備
大伴金村に命じて
新羅に攻められている
任那に援軍を送った
即位元年(536年?)
蘇我稲目が大臣
子の
蘇我馬子
以降の礎が築かれた
在位が
三年余
安閑・宣化朝は
父、
継体天皇
死後直ぐに即位した弟の
欽明天皇と
並立していたとの説(辛亥の変仮説)・・・?
宣化天皇の血統は
石姫皇女を通して受け継がれている・・・?
後裔氏族
多治比氏・・・他字比・他似比・丹治比
その末裔に
武蔵七党の
丹党
同じ
武蔵七党の私市党にも
多治比氏の末裔とする・・・
歌人・額田王は
宣化天皇の四世孫(玄孫)・・・
↓↑
「宣化記・古事記」
「弟(いろと)
建小広国押楯(たけをひろくこおしたて)命
檜垌(ひのくま)の
廬入野(いほり)宮に坐しまして
天の下治めらしめしき」
「宣化記」の系譜記事
宣化天皇が
二人の比売(ひめ)を娶って
産まれた御子が
男子三人・女子二人
子孫にあたる氏族の記録
宣化天皇陵
奈良県
橿原市の
畝傍(うね び)山の
南および南東一帯をさす古代地名
宣化天皇陵は
身狭桃花鳥坂上
(むさのつきさかのえ)陵・・・身狭=九州北部の古地名?
身狭=むさし=武蔵
宣化天皇陵
現在治定の
ミサンザイ古墳・・・「鷦鷯=三十三才=ミサンンザイ」
「仁徳天皇(大鷦鷯尊)
武烈天皇(小泊瀬稚鷦鷯尊)」
鷦鷯=ささき=佐々木
(橿原市鳥屋ミサンザイ古墳出土の
鉄剣銘
から
箭羅奈胆加(やらないか)大王
身狹-桃花鳥-坂上陵
(むさのつきさかのえのみささぎ)
桃花鳥=とう・つき・トキ(朱鷺・鴇・鴾・鵇)
コウノトリ目トキ科の鳥
↓↑
第二十八代宣化天皇(せんかてんのう)
異称
檜隈高田皇子
(ひのくまのたかたおうじ
武小広国押盾尊・日本書紀)
建小広国押楯命
(たけをひろくにのおしたてのみこと・古事記)
?~ 宣化天皇四年
73歳
在位期間
安閑二年(宣化天皇元年)
~
宣化天皇四年
父
継体天皇
第二子
安閑天皇の同母弟
↓↑
第二十八代天皇
武小広国押盾尊
(たけおひろくに おしたてのみこと)
漢風諡号
継体天皇の皇子
新羅(しらぎ)軍の
任那(み まな)侵入の際
大伴狭手彦を派遣
撃退
↓↑
「安閑・宣化天皇・欽明天皇」・・・???・・・
ーーーーー
・・・九州の「倭國王朝」は筑紫・・・「阿毎王朝」は肥後・・・
・・・「倭委奴國」は「怡土」・・・「怡土郡(いとぐん)は、福岡県(筑前国)の郡」・・・「伊都」は伊太利亜の「羅馬」or「バチカン=和地関」・・・41度=四拾壱(肆足壱←壹・位置)のタビ
和の地に関係・・・北緯41度54分・・・
函館市=北緯41度46分・・・
松前郡福島町=北緯41度29分・・・
亀田郡七飯町=北緯41度53分・・・
爾志郡乙部町=北緯41度58分・・・
ーーーーー
・・・
↧
December 2, 2017, 5:31 am
・・・「2017年12月01日・金曜日・丁酉年辛亥月壬戌日」ですか・・・六十干支、五十九番目の日・・・雪がドッサリ・・・イヨイヨ「冬」・・・
「壬戌(みずのえいぬ・ジンジュツ)の日
戌(辛・丁・戊)」・・・「印綬・正財・偏官」
明日は
「癸亥(みずのとのい・キイ)の日
亥(戊・甲・壬)」・・・「正官・傷官・劫財」
・・・六十干支、最後の六十番目の日・・・
ダレが考えだしたんだか、「年月日時」の「六十干支の組み合わせ」、「60⁴=3600×3600=12960000」・・・「壱阡貮陌玖拾陸萬」・・・キッと暇で「加減乗除」と「漢字文字弄(いじ)り」しかヤルコトがなかったのカモ・・・
ーーーーーー
・・・
↧
December 3, 2017, 6:41 am
・・・類字會名・・・万磨・・・?・・・ルイジアナ(Louisiana)・mamma・・・・new-嗚林・・・ニューオーリンズ(New Orleans・La Nouvelle-Orléans)・・・
ーーーーー
![]()
井上陽水 ドキュメント
『氷の世界40年』
~日本初ミリオンセラーアルバム
倫敦帰国・1973年9月13日・12月1日発売
https://www.youtube.com/watch?v=7AICHvLAPsk
井上陽水 - 氷の世界(ライブ)
NHKホール 2014/5/22
https://www.youtube.com/watch?v=3Nsl9BvUSbs
ルイジアナ・ママ
ジーン・ピットニー
Gene Pitney - Louisiana Mama
https://www.youtube.com/watch?v=4RwZVV31uG8
ジョーンバエズ/朝日のあたる家
https://www.youtube.com/watch?v=00-C7566LEM
stanton
sallwan
ルイジアナ(Louisiana)
フランス王ルイ14世
(Louis XIV、在位:1643年〜1715年)
に由来する
ロベール=カブリエ・ド・ラ・サールが
ミシシッピ川の流れるこの領域を
フランス領と宣言したときに
ラ・ルイジアーヌ(La Louisiane)
と名付けた
The 接尾辞の-ana(ないし-ane)は
ラテン語の接尾辞で
「特定の個人、対象または場所に関するもの」
を指す
「Louis」+「ana」=「ルイに関するもの」
を意味
フランス領ルイジアナは
フランス植民地帝国の一部として
現在のモービル湾から
カナダとの国境の北にまで延び
カナダ南西部の小部分を含んでいた
ワトソン・ブレイク遺跡
11のマウンドで構成
遺跡は約5,400年前、紀元前3500年頃
に建設
ーーーーー
・・・
↧
December 4, 2017, 11:49 pm
・・・ランダム検索・・・ 「小泉八雲・島根県松江で旧制中学教員となったのち、日本に帰化」・・・「小泉八雲(ラフカディオ・ハーン=パトリック・ラフカディオ・ハーン (Patrick Lafcadio Hearn)・父チャールズはアイルランド出身の軍医、母ローザはギリシャ、キシラ島の出身・明治二十三年(1890)来日・松江中学の英語教師となり小泉節子と結婚・明治二十九年イギリス国籍から日本国籍に帰化」・・・「来日前にニューオーリンズで新聞記者を務めていた」・・・
ーーーーー
小泉 八雲(1850年6月27日~1904年9月26日)
1850生年 庚戌(辛・丁・戊)1904没年 甲辰(乙・癸・戊)
0006生月 壬午(丙・ ・丁)0009没月 癸酉(庚・ ・辛)
0027生日 己酉(庚・ ・辛)0026没日 癸亥(戊・甲・壬)
寅卯=空亡
ギリシャ(当時イギリス領)
レフカダ島で誕生
東京府
豊多摩郡
大久保村
西大久保で死没
ーーーーー
「ニューオーリンズ港と北海道釧路市釧路港は姉妹港」・・・
↓↑
![]()
ミネソタ州
ミシシッピ川(ミシシッピがわ、Mississippi River)は、北アメリカ大陸を流れる河川の1つである。アメリカ合衆国のミネソタ州を源流とし、ミシシッピ川の水源であるイタスカ湖からメキシコ湾へと注いでいる。
「ミシシッピ」の名は、オジブワ族インディアンの言語で「偉大な川」を意味するmisi-ziibiまたは「大きな川」を意味するgichi-ziibiからの転訛
↓↑
アイオワ州
State of Iowa(眠たがり)
ーーーー
ジャパン (ミズーリ州)
ジャパン(Japan)
アメリカ合衆国ミズーリ州フランクリン郡
非法人地域
北緯38度14分21秒
西経91度18分21秒
セントルイスの都市圏内にあり
セントルイスからは南南西へ約120km
集落の中心部は
ハイウェイH
と
ハイウェイAE
との交差点付近
集落の中心部から
西へ約500mには
ジャパン
の名を冠した
カトリックの
セントルイス大司教区管轄下の
ジャパン聖殉教者教会が立地
教会の住所は
ジャパンから最も近い
法人化された市である
サリバン
となっている
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3_(%E3%83%9F%E3%82%BA%E3%83%BC%E3%83%AA%E5%B7%9E)
↓↑
ジャパンという名の郵便局が
1860年に建てられ
1908年に廃止されるまで稼働
日本=Japan
にちなんで名付けられた地名・・・
Holy Martyrs of Japan,
Church of the (Japan).
Archdiocese of St. Louis
ーーーーー
ミズーリ川(Missouri River)
アメリカ合衆国中部を流れる川
ミシシッピ川の最も大きな支流で
本流の西側に位置
全長は4,130km
流域面積は
アメリカ合衆国本土のおよそ
6分の1
「ミズーリ」は
この地に先住した
インディアンのアルゴンキン語で
「泥の河」
という意味
この川は多量の泥を含むので
「Big Muddy・(Muddy=泥の)」
とよばれる
ーーーーー
ミズーリ州(State of Missouri)
ーーーーー
アーカンソー州(State of Arkansas
カンザ族と近縁の
クアポー族 (Quapaw) の言葉で
「下流の人々の土地」を意味する
「アカカズ(akakaze)」
あるいは
スー族の言葉で
「南風の人々」を意味する
「アカカズ(akakaze)」
をフランス語風に発音したのが
「アーカンソー(Arcansas)」
アーカンソーは
1803年
アメリカ合衆国が
ナポレオン・ボナパルト
から買収した
ルイジアナ領土の一部
北はミズーリ州に接し
東はテネシー州とミシシッピ州
西はオクラホマ州とテキサス州
南はルイジアナ州に接している
略称「Ark,AR」
州都は
「リトル-ロック(little-rock・little-lock」市
小-石
小石川診療所=小石川養生所
江戸時代に幕府が江戸に設置した
無料の医療施設
将軍徳川吉宗
と
江戸町奉行
大岡忠相の主導した
「享保の改革」における
下層民対策・・・貧民救済施設
享保七年(1722年)一月二十一日
麹(麦+匊)町(東京都新宿区)
小石川伝通院(三郎兵衛店)の
町医師である
小川笙船・・・笙=竹+生=竹管を十九、十三ならべた
しょうの笛
船=舟+八+口
(赤ひげ先生)・・・山本周五郎・黒沢明
が
将軍への訴願を目的に設置された
目安箱に貧民対策を投書
笙船は翌月に評定所へ呼び出され
吉宗は忠相に養生所設立の検討を命じた
建築費は金210両と銀12匁
経常費は金289両と銀12匁1分8厘
人員は与力2名、同心10名、中間8名
与力は入出病人の改めや
総賄入用費の吟味を行い
同心のうち
年寄同心は
賄所総取締や諸物受払の吟味を行い
平同心は部屋の見回りや
薬膳の立ち会い
「錠前(lock & key)」預かり
などを行った
中間は朝夕の病人食や看病
洗濯や門番などの雑用を担当
女性患者は
女性の中間が担当
享保七年(1722年)十二月二十一日
小石川薬園(小石川植物園)内に開設
建物は
柿葺の長屋で
薬膳所が2カ所設置
収容人数は40名
医師は
本道(内科)のみで
小川ら
七名が担当
はじめは
町奉行所の配下で
寄合医師・小普請医師
などの幕府医師の家柄の者が
治療にあたっていたが
天保十四年(1843年)から
町医者に切り替えられた
町医者のなかには
養生所勤務の年功により
幕府医師に取り立てられるものもいた
ーーーーー
「アーカンザス(kænzəs)・ar-KAN-zəs)」
「アーカンソー(ɑːrkənsɔ)・AR-kən-saw)」
を主張する論争があった
1881年
州議会立法で公式に
「アーカンソー」
と決定
開拓初期に
「クマ=熊」が多く棲息し
「クマの州=Bear State」
という愛称で呼ばれる・・・「クマモン」って?
ーーーーー
ジャパン(Japan)
アメリカ合衆国
ミズーリ州
フランクリン郡
↓↑
フランクリン郡(Franklin County)
アメリカ合衆国
ミズーリ州の東部
ミズーリ川の南岸
に位置する郡
郡庁所在地は
ユニオン市
同郡で
人口最大の都市は
ワシントン市
↓↑
フランクリン郡は
セントルイス大都市圏に属す
独立市
セントルイス市と
ミズーリ州
イリノイ州
にある周辺郡を合わせると
都市圏人口は280万人
セントルイス市の
西の準郊外地域を構成
フランクリン郡は
1818年
建国の父である
ベンジャミン・フランクリン
に因んだ名
↓↑
フランクリン郡
地域の前史時代は
幾つかの
インディアン文化が続き
ヨーロッパ人と遭遇したときは
オーセージ族
インディアン
が住んでいた
スペイン帝国が地域を支配した時代
最初のヨーロッパ人が入植
スペインの
丸太作り砦
サンフアン・デル・ミズリ
(1796年~1803年)
が現在の
ワシントン市に建設
アメリカ独立戦争後
移民が西に動き
探検家で
1799年
地域の開拓を始めた
ダニエル・ブーン
の家族と追随者もいた
その後の20年間
大半の開拓者は
アッパーサウスから来て
土地を耕すために
奴隷を連れてきていた
↓↑
1833年
ドイツ人移民
が地域に入り
奴隷所有者の数を上回るようになった
ドイツ人は奴隷制度に反対
子孫は南北戦争のときに
北軍の強い支持者
南軍の将軍
スターリング・プライス
が戦中にその部隊を率いて
地域を略奪して回った・・・
↓↑
南北戦争前に地域には蒸気船が往来(オウライ)
荷物や旅人の運搬に力を発揮
鉄道が開通すると交通の中心
南北戦争終戦時
製造業が興った
ーーーーー
小都市バーガーの近くの
バイアス・ブドウ園は
1983年に指定された
ハーマン・ブドウ栽培地域の中にある
ニューヘイブンに近い
レブラー・ブドウ園と
ワイン醸造所もその中にある
ミズーリ川両岸にある
ワイン醸造所は
ミズーリ・ラインランド
と呼ばれ
そのブドウ園は19世紀半ばに
ドイツ系移民が始めた
禁酒法時代以前は
ミズーリ州が国内でも
第2のワイン製造州だった
禁酒法時代には
宗教的な目的で許される
ワインを除いて
全て閉鎖
州内のワイン産業の再建は
1960年代
田園部で
違法薬物の
メタンフェタミン
の製造
薬物と戦う郡役人の様子が
2005年
A&Eテレビのドキュメンタリー
『Meth: A County in Crisis』
で取り上げられた
ーーーーー
セントアルバンズ近くの
セントチャールズ郡は
現在ミズーリ川の南岸
フランクリン郡の
オーガスタは
現在北岸にある
郡内を
バービューズ川が流れ
延長は107マイル (171 km)
この川が深く狭い峡谷を作り
大蛇行
ユニオン市の近くで
メラメック川に注ぐ
↓↑
フランクリン郡
オザーク高原に入っており
急峻な丘陵と深い谷、洞穴、泉
また陥没が特徴的な
カルスト地形
↓↑
設立
1818年12月11日
郡名の由来
ベンジャミン・フランクリン
郡庁所在地=ユニオン
ーーーー
非法人地域
北緯38度14分21秒
西経91度18分21秒
セントルイスの都市圏内
セントルイスから
南南西へ約120km
カトリックの
セントルイス大司教区管轄下
ジャパン聖殉教者教会が立地
教会の住所は
法人化された市である
サリバンのジャパン・・・
ーーーーー
フランス領ルイジアナ
最初のヨーロッパ人開拓者
フランス系カナダ人
セントルイスから約1時間南の
セントジェネビーブ
に最初の開拓地を造った
1750年頃
イリノイ・カントリーから移ってきていた
ミシシッピ川東岸にあった開拓村では
土地が痩せてきており
増加する人口を養うに足る平地が無かった
セントジェネビーブは農業中心として繁栄
小麦、トウモロコシおよびタバコを生産
余剰分を下流の
ルイジアナに船で運んだ
農産物は
ルイジアナ
ニューオーリンズ市
重要なものになった
1762年
フォンテーヌブロー条約
ヌエバ・エスパーニャ副王領とされ
1764年
ニューオーリンズ市から来た
フランス人によって
セントルイスの町が設立
1764年~1803年まで
ミシシッピ川西岸の流域は
その北限まで
フランス領ルイジアナと呼ばれた
スペイン人が
セントルイスに現れたのは
1767年9月
セントルイスは
ミズーリ川やミシシッピ川流域に広がる
インディアンとの毛皮交易中心となり
長い間地域経済の支配要素となった
交易会社と提携している者達は
セントルイスから毛皮を船積みして
ニューオーリンズ市まで運び
そこからヨーロッパの市場に送った
その見返りに様々な商品が業者に渡り
それがインディアンとの交易に使われた
毛皮交易とそれに関連する事業で
セントルイスは初期の金融中心となり
それで得た富によって
瀟洒な家を建て、贅沢品を輸入する者もいた
セントルイスは
ミシシッピ川
と
イリノイ川
が合流する地点に近く
農作地域からの産品も取り扱えた
ミシシッピ川による輸送と交易は
地域経済と一体のものとなり
セントルイスは地域最初の主要都市として
特に蒸気船が発明され川の交易が増えた後は
著しい発展を遂げた。
↓↑
ルイジアナ
1800年
ナポレオン・ボナパルトは
サンイルデフォンソ条約によって
スペイン領だった
ルイジアナをフランスに取り戻した
条約は秘密にしておかれた
ルイジアナは
1803年11月30日
にフランスに移管されるまで
名目上スペイン領だった
これはルイジアナが
アメリカ合衆国に移譲される
3週間前のことだった・・・
↓↑
アメリカ合衆国による
1803年のルイジアナ買収地の一部だった
ミズーリ州は
19世紀に西に向かう探検隊や開拓者の出発点で
「西部への玄関」という渾名がついた
セントルイスの西にある
セントチャールズは
1804年
ミシシッピ川から出発し
西部領土を探検し
太平洋に至った
ルイス・クラーク探検隊の
出発点かつ帰還目標地となった
セントルイスはその後長い間
西に向かう開拓者隊の重要な供給点
1812年
ニューマドリード地震
ミズーリ州西部の開拓者の多くが
アッパーサウスから移ってきたので
労働力として
アフリカ人奴隷を連れてきており
その文化と奴隷制度の継続を望んだ
ミズーリ川沿いの17郡に入った者が多く
そこはプランテーションによる
農業を可能にする平地であり
リトル・ディキシー
と呼ばれるようになった。
↓↑
1821年
ミズーリ妥協
奴隷州として州昇格を認められ
暫定州都は
セントチャールズに置かれ
1826年
州都はミズーリ川沿いの
ジェファーソンシティ
に移された
州の西側境界は
コーズマスを通る子午線で
定義されたので直線
コーズマスは
カンザス川が
ミズーリ川に合流する地点だった
この直線は
オーセージ境界線と呼ばれている
1835年
インディアンから土地を買収した
プラット買収によって
州北西隅に領域が付け加えられ
カンザス川より北側にある
ミズーリ川が州境になった
この領土追加によって
バージニア州に代わって
当時の国内最大の州になった
(当時のバージニア州は
ウェストバージニア州を含んでいた)
1830年代初期
モルモン教徒が北部州やカナダから移ってきて
インディペンデンス近くとその北に入植
昔からの開拓者(主に南部出身)と
モルモン教徒(主に北部出身)の間に
宗教と奴隷制度を巡って紛争
1838年
モルモン戦争
1839年
リルバーン・ボッグス知事が
「根絶命令」
昔からの開拓者が
モルモン教徒を
ミズーリ州から追い出し
その土地を没収した・・・
↓↑
ーーーーー
・・・
↧
↧
December 5, 2017, 11:57 pm
・・・音別町・・・音(おと)を別(わ)ける・「化和字理が塞(ふさ)がる」・・・「連」=むらじ・レン=「聯」・・・「大連(おおむらじ・ダイレン)」は「大聯(おおむらじ・ダイレン)」・・・じゃぁ、「蓮華(はす・芙・荷・水草の名・水中に自生・葉は円形で水面に浮く)」=「艹+聯」+「華」、「南無妙法蓮華経=ナンミョウホウレンゲキョウ=南無妙法蓮華経」・・・「南無=南には無い」なら「北に有る=北有」だろう・・・「北に有るモノ」は「妙(女少)」の「法(氵十一ム)」の「艸(艹・サ・草冠)と聯の連結した経」?・・・「オンナがスクナイ」って、「奇妙」である?・・・エスキモーでは「ういご(初子・初児」が女の子ならば「生贄」にしたらしいが・・・
「北極星」は北に有るのは確かだが・・・熊になった母親カリストーと息子アルカス・・・ママの命、危なかったが、中国北方の種族は概ね「大王・汗・種族長」が死ねば、次世代の族長は「父親に関係した女性」や「兄弟姉妹」、その「親族」も粛清した・・・
「genocide」・・・「臥薪嘗胆」の解決策だったカモ・・・「運命共同体、民族主義者」の大陸も半島も、隣国の怨恨は粘ッ濃い・・・
だが、「神(旧約聖書)」も執拗(しつこ)い・・・「カインの復讐は七」、その「アダムの七代目、カインの末裔,メトサエルの子レメクの復讐は七拾七倍」・・・発端は「Gatt or God or Goat・・・got」カモ・・・
「アルクス(円弧・弧(えんこ・こ)のラテン語=アルクス (arcus)・虹のラテン語プルウィウス・アルクス(pluvius arcus)」・・・
「蓮華・蓮根・蓮台・紅蓮 (ぐれん)・白蓮(びゃくれん)」・・・「法華宗」は日本に於ける「プロテスタン(聖書に記録されたコトのみの信仰)」だろう・・・なるほど、「信長」は「法華宗」が論争に負けても「法華経」の信徒だったらしい・・・
お経もヒトが記録したモノだけれど・・・ヤッパ、「本当」もアテにならない人間のやることである・・・念仏解釈や神話口承伝説と同次元かも・・・人間の「証人=ショウニン=承認・上人・聖人」はアテにならないカモ・・・
ーーーーー
「聯=耳+幺+幺+丱」・・・
「蓮」→「艹+聨」→「耳+茲+丱」・・・
「茲(ここに・ここ・ジ・シ)=現在の時点・場所を示す語
この時・この場所で」・・・
「聨」の異体字は、「聨・聫・聮・䏈・联(→朕?)
つらなる・つらねる・つづく・レン」
「聯」は「連」に書きかえられるようになった
「合従聯(連)衡」=「合従=秦に対抗するために
他の6国の連合を蘇秦が説いた」
「連衡=秦が他の6国と個別に
同盟を結ぶことを張儀が説いた」
↓↑
「同音の漢字による書きかえ(報告)」
第32回国語審議会総会(昭和31.7.5)で
文部大臣宛に報告したもの
「文部科学省 用字用語例(平成23.3最新改定)」
で
「聯絡=レンラク=連絡」と書くようになった
聯=耳+幺+幺+丱・・・耳+茲+丱
異体字は、聨・聫・聮・䏈・联
つらなる・つらねる・つづく
「聯」は「連」に書きかえられるようになった
「同音の漢字による書きかえ(報告)」
第32回国語審議会総会(昭和31.7.5)で
文部大臣宛に報告したもの
「文部科学省 用字用語例(平成23.3最新改定)」
で
「聯絡=レンラク=連絡」と書くようになった
「聨合=聯合=レンゴウ=連合」
聯珠・聯綿
対にする・二つならべる
対聯・柱聯
「連」が書きかえ字
対聯(タイレン)・柱聯(チュウレン)
門聯(モンレン)
聯なる
聯句(レンク)・聯繫(レンケイ)・聯亙(レンコウ)
聯合(レンゴウ)・聯珠(レンジュ)・聯想(レンソウ)
聯隊(レンタイ)・聯袂辞職(レンベイジショク)
聯邦(レンポウ)・聯盟(レンメイ)・聯綿(レンメン)
聯絡(レンラク)・聯立(レンリツ)
聯珠・聯綿
対にする・二つならべる
対聯・柱聯
「連」が書きかえ字
対聯(タイレン)・柱聯(チュウレン)
門聯(モンレン)
聯なる
聯句(レンク)・聯繫(レンケイ)・聯亙(レンコウ)
聯合(レンゴウ)・聯珠(レンジュ)・聯想(レンソウ)
聯隊(レンタイ)・聯袂辞職(レンベイジショク)
聯邦(レンポウ)・聯盟(レンメイ)・聯綿(レンメン)
聯絡(レンラク)・聯立(レンリツ)
音別町・・・音(おと)を別(わ)ける
音(おと)の分別
↓↑ ↓↑ ↓↑
北海道
釧路支庁管内
白糠郡・・・白糠(しろぬか)・・・ 庶路(しょろ)
シライカラ=シラリカ・sirar-ika
アイヌ語の意味
「潮越す・満潮時、川に潮が入ったため」?
「シララ=潮」
「岩=シラリカ(shirar-ka)は
潮が・岩礁に・溢れる」・・・
「シラリカㇷ゚=shirar-ika-p
(白い潮が?)岩を・越える・処」
「シラ」が「岩・磐・石」・・・
「ウカウ(u-ka-u・互いに・上に・ある
重なりあう)」・・・浮こう・宇高?
に存在した町
北緯42度53分
東経143度55分
アイヌ語の
「オム-ペッ=川尻・塞(ふさ)がる・川」
かわじりが塞がる・・・降雪での水止めのダム?
に由来
ニレ(楡)の・・・似れ・煮れ・仁連・仁禮・仁礼・・・似例
皮を浸した・・・・化話(掛倭)にヒタシタ(比他史多)?
「オン-ペッ(発酵する・川)」
に由来
↓↑
函館市・・・室町時代の1454年(享徳三年)
津軽の豪族、河野政通が函館山の
北斜面にあたる
宇須岸(ウスケシ=アイヌ語「湾の端」)
に館を築き、形が箱に似ていることから
「箱館」と呼ばれるようになった
アイヌ語の「ハクチャシ(浅い・砦)」
に由来する説も・・・
北緯41度46分
東経140度43分
ーー↓↑ーー
ゴールド-カントリー(Gold Country)、
or
マザーロード・カントリー、ロード(lode)
は鉱脈を意味する
アメリカ合衆国
カリフォルニア州の
中央部から北東部に
掛けての地域の呼称
1849年
カリフォルニア・ゴールドラッシュ時代
フォーティナイナーズ(49)・・・四拾九・肆足玖
と呼ばれた
移民の波を引き寄せた
鉱物資源
金鉱脈があることで
名前がつけられた
↓↑
エルドラド郡コロマ・・・ころま・虚賂瞞(万・萬)
サッターズミル・・・・・索椄蛙事・見る
コロマ、エルドラド郡
北緯38度4分
西経120度8分
↓↑
松江市・・・・・出雲神話
北緯35度28分
東経133度2分
↓↑
松江市位置
北緯35度27分
東経133度03分
↓↑
福島市・・・・・附句揣摩
北緯37度45分
東経140度28分
↓↑
宮城県・・・何故、「宮城(キュウジョウ)」なのか?
「M天皇」が居た場所?・・・
明治天皇=諱は睦仁(むつひと)→六=陸
御称号は祐宮(さちのみや)
宮城郡は奈良時代から国府が置かれてきた
「宮宅(みやけ)」が「宮城」?・・・
仙台市
北緯38度16分
東経140度52分
↓↑
多賀山地
茨城県北東部
阿武隈高地の南部
北緯36度37分
東経140度35分
阿武隈高地
↓↑
茨城県
水戸市・・・常陸・常盤・日達・日立・・・比建(達)
北緯36度21分
東経140度28分
↓↑
東京
北緯35度41分
東経139度41分
↓↑
京都府
北緯35度1分
東経135度45分
↓↑
阿蘇
北緯32度53分
東経131度6分
↓↑
鹿児島
北緯31度33分
東経130度33分
↓↑
紹興市(会稽)
浙江省
北緯30度00分
東経120度35分
↓↑
上海・・・・・申=さる=猿
北緯31度10分
東経121度29分
↓↑
ロサンゼルス・・・Los Angeles=羅府
Los Angeles・・・天使
北緯34度3分0秒
西経118度15分0秒
↓↑
ニューオリンズ・・・ニューオーリンズ
英語 New Orleans
仏語 La Nouvelle-Orléans
北緯29度57分
西経90度4分
↓↑
ミズーリ・・・・・・水雨里(利)
ジャパン(Japan)
アメリカ合衆国
ミズーリ州
フランクリン郡
サリバン・・・・・・Sullivan・・・「作理判・猿番」?
サリバン(Sullivan)は
英語圏の姓、地名
アイルランド語由来で
「小さくて黒い目」の意味
北緯38度14分21秒
西経91度18分21秒
↓↑
アレクサンドリア・・・Alexandria・亜歴山
北緯31度11分
東経29度55分
↓↑
ローマ・・・・・・・・Rome・羅馬
北緯41度53分
東経12度28分
↓↑
ロンドン
London
倫敦
北緯51度30分
西経0度07分
↓↑
聖パトリック (Saint Patrick) とも・・・
パトリキイとも・・・「葉録理奇異(規意)」?
アイルランド語では・・・Ireland・愛蘭・・・阿蘭?
↓↑ 王竜(ワンロン)は貧農
豪族黄家の奴隷
阿蘭(アーラン)を妻にもらう
「大地(The Good Earth)」
パール・S・バックの長編小説
(1931年)
「息子たち(1932年)」
「分裂せる家(1935年)」
三部作 "The House of Earth"
↓↑ エドガー・アラン・ポー(Edgar Allan Poe)
「江戸賀蛙・鴉(蛙)乱・報」?
1809年1月19日 ~1849年10月7日
↓↑ ↓↑
1809生年戊辰(乙・癸・戊) 己酉(庚・ ・辛)
0001生月乙丑(癸・辛・己) 癸酉(庚・ ・辛)
0019生日乙未(丁・乙・己) 丙戌(辛・丁・戊)
辰巳=空亡
↓↑ ↓↑
アメリカ合衆国の小説家、詩人、評論家
マサチューセッツ州ボストンに生まれ
両親は旅役者
両親は
イングランドからの移民
両親を若くに失い
商人
アラン家に引き取られ育った
「アッシャー家の崩壊」
「黒猫」
「モルグ街の殺人」
「黄金虫」
などの短編作品を発表
1845年
詩
「大鴉」でも評判
1833年
13歳だった従妹
ヴァージニア・クレムと結婚
1847年
結核によって彼女を失い
1849年
↓↑ ポーも死亡
Pádraigと綴り
ポーリク
などと発音・・・
↓↑
ラフカディオが
一般的に
ファーストネームとして知られているが
実際は
ミドルネーム・・・
アイルランドの守護聖人
聖パトリック
にちなんだファーストネームは
「ハーン」自身
キリスト教の教義に懐疑的で
この名をあえて使用しなかった・・・
↓↑
ファミリーネームは来日当初
「ヘルン」とも呼ばれていた
松江の島根県立中学校への
赴任を命ずる辞令に
「Hearn」を「ヘルン」と表記し
当人もそのように呼ばれることを気に入って定着
妻の節子には
「ハーン」と読むことを教えた
Hearn
O'Hearn
は
アイルランド南部では多い姓・・・
↓↑
日本
東京府
豊多摩郡・・・とよたま
大久保村・・・おおくぼ
西大久保・・・にしおおくぼ
↓↑
レフカダ島
(ギリシア語 Λευκάδα
Lefkada、ギリシア語発音: [le̞fˈkaða])
イオニア海(地中海の一部)に位置する
ギリシャ領の島
地理的・行政的な
イオニア諸島地方に属する
最大の都市は
レフカダ (Lefkada (city))
↓↑
北緯38度43分
東経20度39分
諸島イオニア諸島
↓↑
古名は
レウカス島
(古代ギリシア語: Λευκάς / Leukás)
この地名は
ギリシャ語で
「白」を意味する
「レフコス」
あるいは
「白い岩」を意味する
「レフカタス」
に由来する・・・
↓↑
中世には
アヤ・マウラ島(Αγία Μαύρα)
の名でも呼ばれた
この島は長らく
ヴェネツィア共和国
と
オスマン帝国
の統治下にあり
イタリア人たちは
サンタマウラ(イタリア語: Santa Maura)
トルコ人たちは
アヤマウラ(トルコ語: Ayamavra)
の名で呼んだ・・・
↓↑
島には
青銅器時代(紀元前3000年~紀元前1000年)
の遺跡があり遺物が発見
↓↑
古代ローマの地理学者
「ストラボン」によれば
アカルナニア (Acarnania) の
海岸部は
古い時代に
「レウカス(Leucas)」
と呼ばれていたという
レウカスは
紀元前7世紀に
コリントス人
によって植民が行われ
水路が開鑿されて
本土と切り離された
ペロポネソス戦争中
レウカスは
スパルタを盟主とする
ペロポネソス同盟に参加
↓↑
紀元前338年
マケドニア王国の
ピリッポス2世
による支配下に置かれ
その後
古代ローマの領域に入る
紀元前2世紀に
ローマに反乱
↓↑
1204年
イピロス専制公国
第4回十字軍後の混乱の中で自立
レフカダ島もその領域に含まれた
1294年
ニケフォロス1世が
娘の
マリア
を
ケファロニア宮廷伯
ジョヴァンニ1世
オルシーニ
と結婚させた際
レフカダ島は娘の所領として贈られた
オルシーニ伯によって建設された
サンタマウラ要塞は
当時の島の中心地であった
後、
島の領主は
アンジュー家
や
トッツィ家
に代わった
↓↑
1479年
オスマン帝国が島を占領
1502年~1503年
ヴェネツィア共和国が一時的に支配
1503年
オスマン帝国が奪回
1684年
ヴェネツィア共和国が島を占領
アマクシヒ(現在のレフカダ市街)
に首府が移された
↓↑
1797年
ナポレオン1世によって
ヴェネツィア共和国は終焉
レフカダ島を含むイオニア諸島は
フランス領イオニア諸島となった
1799年
ロシア海軍が諸島を占領
1800年
ロシアとオスマン帝国が設立した
共同保護国
七島連合共和国(イオニア七島連邦国)
の一部となった
1807年
ティルジット条約
イオニア諸島は
フランス帝国の支配下に戻されたが
1809年以降イギリスの攻勢にさらされた
レフカダ島は
1810年
イギリスによって占領
1815年
第二次パリ条約
イギリスの保護国として
イオニア諸島合衆国
(United States of the Ionian Islands,
Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων)
が樹立
レフカダ島
もその一部となった
1864年6月2日
イオニア諸島は
ギリシャ王国に引き渡された
レフカダ島
Λευκάδα=Lefkada
↓↑ ↓↑ ↓↑
ラフカディオ・ハーン
(小泉八雲)
は
この島の出身
「ラフカディオ」の名は
この島の名から採られている・・・
ーーーーー
ーーーーー
ダブリン
(Dublin・Baile Átha Cliath・Dubh linn)
北緯53度20分
西経6度15分
アイルランド島東部の都市
アイルランドの首都
リフィー川河口に位置し
その南北に町が広がる
2世紀のアレクサンドリアの
地理学者
プトレマイオスの文献に
エブラナとしるされている
住民である
ケルト人は
291年
レンスター軍との戦いで勝利
ダブリンの
アイルランド語の名称
ブラー・クリー
は、この勝利のあとにつけられた名称
↓↑
450年ごろ
パトリキウスによって
キリスト教に改宗
9世紀半ば頃
リフィー川から攻め上がってきた
ノルマン人ヴァイキングが
ケルト人の町を破壊し城砦を築き
これをゲール語で
「黒い水たまり」=「ドゥヴ・リン(Dubh Linn)」
と呼んだ・・・
↓↑
3世紀の間
アイルランドの住民は
デーン人からたびたび
ダブリンを奪回
1171年
デーン人はイングランドの
ヘンリー2世
にひきいられた
アングロ・ノルマン人
によって追放
ヘンリー2世は
1172年に
ダブリンに宮廷をおき
イングランドの都市
ブリストルの属領とした
ダブリンは
イングランドの
アイルランド支配の拠点となった
1534年
反乱
アイルランドの
愛国者
フィッツジェラルド
が一時支配
↓↑
17世紀
イギリスの
ピューリタン革命の間
ダブリンは
クロムウェルの
議会派勢力に包囲
1798年
アイルランド民族主義組織
ユナイテッド・アイリッシュメン
の蜂起に
ダブリン攻略の試みは失敗
1803年、1847年、1867年
蜂起がくりかえされ
1916年と1919年から1921年の
アイルランド蜂起
ダブリンは戦場となった
↓↑
17世紀末頃
大陸から来た
ユグノー
フランドル人
によって各種工業が発展
18世紀には
大英帝国第二の都市
ヨーロッパでも
5番目に大きい都市となった
↓↑
イギリス植民地時代
1800年
合同法が
アイルランド議会にて可決、成立
グレートブリテン王国との合同が成され
アイルランド議会は解散
アイルランドは
連合王国の他の地域と比較して
ベルファスト(造船とリンネル工業)
などの一部の地域を除いて
産業革命が進展しなかった
1916年
復活祭蜂起
独立戦争
内戦
↓↑
英愛条約に基づき
1921年以降
ダブリンはイギリスの
自治領
「アイルランド自由国」
の首都となった
自由国は
破壊されたダブリンを再建し
立法機関である
ウラクタスを設置
1937年
新憲法施行により
「独立した民主的な国家」
エールが成立
1949年
アイルランドは英連邦より離脱
共和制国家
「アイルランド」
の首都となった
↓↑
ダブリン
Baile Átha Cliath
Dublin
ーーーーー
・・・白石・・・鍾乳石、石灰・・・
石灰(せっかい)=生石灰(酸化カルシウム、CaO)
または
消石灰(水酸化カルシウム=Ca(OH)2)
炭酸カルシウム(CaCO3)
や
カルシウム(Ca)を指す・・・「いしばい」とも・・・
↓↑
酸化カルシウム(生石灰) CaO
水酸化カルシウム(消石灰) Ca(OH)₂
石灰岩(岩石名)
石灰石(鉱石名)
方解石・霰石(鉱物名) CaCO₃
炭酸カルシウム CaCO₃
土壌改良
ラインパウダー
乾燥剤
↓↑
ライムライト(Limelight)・・・チャプリンの無トーキ映画
照明器具の一種
舞台照明に用いられた
別称は
カルシウムライト
石灰灯・灰光灯
↓↑
「耳のある者は
御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。
わたしは勝利を得る者に
隠れた
「マナ=真名?・眞魚」・・・弘法大師・空海・・・佐伯眞魚
を与える。
また、彼に
「白い石」を与える。
その石には、
それを受ける者のほかは
だれも知らない、
新しい名が書かれている。
(新約聖書 黙示録 2:17)」・・・???・・・
↓↑
白石市・・・宮城県南部、蔵王連峰の ふもとに位置
↓↑
宮城県
白石市
北緯38度0分
東経140度37分
不忘山(蔵王連峰の南端の峰)
・・・林-不忘(はやし-ふぼう)
長谷川 海太郎(はせがわ かいたろう)
1900年1月17日 - 1935年6月29日
日本の 小説家、翻訳家。
1900生年 己亥(戊・甲・壬)1935年 乙亥(戊・甲・壬)
0001生月 丁丑(癸・辛・己)0006月 壬午(丙・ ・丁)
0017生日 庚寅(己・丙・甲)0029日 丙子(壬・ ・癸)
午未=空亡
↓↑林不忘(はやし ふぼう)
↓↑牧逸馬(まき いつま)
谷譲次(たに じょうじ)
の3つのペンネームを使い分けて活躍
林不忘は時代小説「丹下左膳」
牧逸馬は犯罪実録小説、家庭小説、翻訳
谷譲次は米国体験記
「めりけんじゃっぷ」で知られる
↓↑ ↓↑
函館中学で5年生一同が
運動部長排斥からストライキを起こし
首謀者とされた海太郎が卒業試験で落第処分
退校して
明治大学専門部法科に入学
専門部卒業後
1920年に太平洋航路の
「香取丸」で渡米
オハイオ州のオベリン大学に入学
退学、様々な職種を転々としながら
全米を放浪
IWW(世界産業労働組合)で組合活動
1924年には貨物船の船員として
南米からオーストラリア
香港を経て、大連に寄港、
下船して朝鮮経由で帰国
↓↑ ↓↑
「丹下左膳・こけ猿の巻」
↓↑ 東京日日新聞・大阪毎日新聞・1933年6~11月連載
↓↑
鉢森山・雨塚山・大萩山・二ッ森山(716.1m)
白石川、その支流が流れる・・・
「あらいはくせき(新井白石)」・・・
↓↑
七ヶ宿町(しちかしゅくまち)
宮城県南西部
刈田郡に位置
宮城県刈田郡七ヶ宿町字関
北緯37度59分
東経140度26分
↓↑
・・・黒石・・・黒曜石・・・
黒石市・・・
北緯40度38分
東経140度35分
青森県
十和田
八幡平
国立公園北西に位置
市域の東部は
八甲田山に続く山地
ウェナッチ市
(アメリカ合衆国ワシントン州)
1971年(昭和46年)10月5日に
姉妹都市
・・・
↧
December 7, 2017, 12:30 am
・・・隣の街の病院へ行きは鉄道、帰りはバスで・・・雪の降る中、バスは定刻通りには来ず、だった・・・乗り物の窓の外にはリンゴ売りは居なかったが、猛吹雪のホワイト・アウト(white out)・・・先週TVで観た南極基での事件に巻き込まれていく女FBI(ケイト・ベッキンセール)の映画だったが、「ホワイトアウト(whiteout)は、雪や雲などによって視界が白一色となり、方向・高度・地形の起伏が識別不能となる現象。 ホワイトアウトの状態に陥ると、錯覚を起こしてしまい、雪原と雲が一続きに見える。太陽がどこにあるのか判別できなくなり、天地の 識別が困難になる」・・・それ以前にボクの眼自体が霞んで視えなくなってきているが・・・
兎に角、家を出た朝はヨロケながらナントか駅を目指し、帰りはバス停を降りて、やっとコサッ、橋の上まで歩いて来たが、雪の飛礫(つぶて)が前進を拒む・・・折角、病院を出たのにコンなところで雪に埋もれてオダブツするわけにはいかないか、と家を目指したが・・・やっと帰宅した家は一階半分は雪没・・・腰痛、足の筋肉痛は覚悟の上の除雪作業・・・
冒険家の「N・U」氏がどんな気持ちで北極や、マッキンリー冬期単独登頂をしたのかは知らないが・・・人間も色々・・・
山岳映画や冒険映画を観るのはスキだけれど・・・生きるとなれば、ボクのセンタクは「オハラショウスケさん」だろうな・・・
ーーーーー
1984年2月12日
43歳の誕生日
世界初の
マッキンリー
冬期単独登頂
2月13日
以降、交信不能、消息不明・・・
後、明治大学山岳部が
2度の捜索
登頂成功の山頂に立てた日の丸の旗竿
雪洞に残された植村の装備が発見
現在に至るまで遺体は未発見
最後の交信の
1984年2月13日
を命日・・・享年43
↓↑
植村 直己
1941年(昭和16年)2月12日~1984年(昭和59年)2月13日
1941年 辛巳(戊・庚・丙) 甲子(壬・ ・癸)
0002月 庚寅(己・丙・甲) 丙寅(己・丙・甲)
↓↑ ↓↑ ↓↑
0012日 辛卯(甲・ ・乙)13丁丑(癸・辛・己)
↓↑ ↓↑ ↓↑
0011日 庚寅(己・丙・甲)14戊寅(己・丙・甲)
午未=空亡 大運=丙戌(辛・丁・戊)
ーーーーー
・・・???・・・「保倭怡土(意図・伊都・糸・緯度)逢渡」・・・
↧
December 8, 2017, 12:52 am
・・・「マッキンリー山」・・・「デナリ=出名理」・・・デ(カイ)ナリ・・・デ(カ)ナリ・・・デ(ル)ナリ・・・で(アル)なり・・・
ーーーーー
デ+か デ+さ デ+た デ+な デ+は デ+ま デ+や
デ+き デ+し デ+ち デ+に デ+ひ デ+み デ+い
デ+く デ+す デ+つ デ+ぬ デ+ふ デ+む デ+ゆ
デ+け デ+せ デ+て デ+ね デ+へ デ+め デ+え
デ+こ デ+そ デ+と デ+の デ+ほ デ+も デ+よ
デ+ら デ+わ
デ+り デ+ゐ
デ+る デ+う
デ+れ デ+ゑ
デ+ろ デ+を
ーーーーー
マッキンリー(McKinly)
マッキンレー(McKinley)
マッケンリー(McKenley)
マッキンリー山
アメリカ合衆国
アラスカ州にある
北米最高峰の山
「デナリ」の旧名
北緯63度4分10秒
西経151度0分26秒
↓![]()
マッキンリー郡
(ニューメキシコ州)
アメリカ
ニューメキシコ州の郡
↓↑
ウィリアム・マッキンリー
第25代アメリカ合衆国大統領
1843.1.29
オハイオ・ナイルズ・・・呵海呵(オハイオ)
~
1901.9.14
ニューヨーク・バッファロー
アメリカ
第25代大統領 (在任 1897~1901)
南北戦争に参加
戦後法律家
オハイオ州政界に進出
1877~83、85~90年
共和党連邦下院議員
高率関税主義者として
90年
マッキンレー関税法を成立
91年
クリーブランドの実業家
M.ハナの援助で・・・・・・・「M・ハナ」?
オハイオ州知事に当選
1893年再選
1896年
ハナの助力で・・・・・・・・「花図鑑」を見よ?
共和党大統領候補
金本位制の綱領下に・・・・・「金の本の位=金王朝」?
民主党候補
W.ブライアン・・・・・・・・「Bryan=ブライアン=無頼案」?
を破って当選
就任後
ディングリー関税法・・・・・「出音(寅・陰)具理」
虎・山陰・松蔭
を成立させた
1898年2月15日
キューバ独立運動・・・・・・「玖馬・古巴」
に同情する世論を背景に
メーン号事件・・・アメリカとスペインの戦争の発端
アメリカの最新鋭艦のメイン号が
爆発、沈没
ワシントンの自作自演の米戦艦爆破事件
「スペインの機雷による仕業」と発表
スペインに宣戦布告
スローガンは
「メイン号を忘れるな」⇔「真珠湾を忘れるな」
米西戦争はスペイン(西班牙)の敗北
を契機に
アメリカ=スペイン戦争に突入
戦争に勝ったアメリカは
フィリピン
プエルトリコ
ハワイ
などを獲得
彼は領土獲得に反対する勢力を押えて
海外膨張を支持
1900年
金本位制確立
パナマ運河建設交渉開始・・・「巴奈馬」
軍組織の改革
01年
プラット修正法
門戸開放宣言・・・・「文訳解法宣言」?
などが事績
1900年
再選されたが
翌年9月6日
バッファローで・・・「buffalo・野牛→柳生・八柳」
無政府主義者・・・・「anarchist・鴉(蛙)名記素訳」
によって
狙撃
8日後に死亡
↓↑
アメリカ合衆国
アラスカ州・・・・阿拉斯加(アラスカ)
の南半を占める
弧状山脈
アリューシャン山脈・・・「亜拉西安・阿留申→蛙留猿?」
から
カナダのユーコン准州の境界まで
約650kmにわたって弧状に延び
北側に
ユーコン川
と
クスコクウィム川
が流れ
三つの山系に分かれている
山系には氷河
多くの活火山があり
北アメリカ最高峰の
デナリ(マッキンレー山・6190m)
フォラカー山(5304m)
ハンター山
ヘーズ山
を含む
↓↑
デナリ(Denali)=マッキンリー山(Mount McKinley)
アメリカ合衆国アラスカにある山
北アメリカ最高峰
標高は6,190m(2012年の測量前は6,194m)
マッキンリー山(Mount McKinley)
と呼称 されていたが
2015年8月31日
アメリカ合衆国連邦政府は
「デナリ」を正式な呼称と告示
「デナリ」=先住民デナッイア族の言語
デナッイア語で
「偉大なもの」を意味
1980年
アラスカ州法に基づき
山を含む周囲に
デナリ国立公園が設置
ーーーーー
2014年6月7日
デナリ(Denali)=マッキンリー山(Mount McKinley)
最速登頂者
キリアン・ジョルネ
標高2000mのベースキャンプから
頂上を11時間48分で往復
下りにはスキーを使用
登頂には9時間43分かけ
それから2時間程度で滑り降りた
ーーーーー
2015年6月21日
イモトアヤコ登頂・・・井本 絢子(いもと あやこ)
珍獣ハンター・イモト
鳥取県西伯郡岸本町(伯耆町)出身
1986生年乙丑(癸・辛・己)2015年乙未(丁・乙・己)
0001生月己丑(癸・辛・己)0006月壬午(丙・ ・丁)
0012生日丙辰(乙・癸・戊)0021日戊辰(乙・癸・戊)
子丑=空亡
日本テレビ撮影隊
ーーーーー
↓↑
キリアン
アイルランドなどの男性名
聖キリアン (Killian, Kilian, Cillian)
中世初期の
アイルランド出身の
キリスト教宣教師
カトリック教会の聖人
640年
アイルランドの貴族に生まれ
聖職者の道を歩む
司教に任命され
ヨーロッパ大陸へ伝道活動
ガリアを経て
フランク族への伝道のため
ヴュルツブルクで
司祭のコールマン
助祭トトナン
と共に
フランケン地方
テューリンゲン地方
を中心に布教活動
ヴュルツブルク領主
ゴツベルト公爵
を改宗させた
↓↑
キリアンが
公爵が兄の未亡人と結婚していること
(レビラト婚)を
教会法に反するとしたため
夫人が公爵不在中に
キリアン
と
コールマン
トトナン
を暗殺
遺体をミサの道具や聖書と共に
その場に埋めた(689年7月8日)
752年7月8日
遺体は正式に埋葬
その上に大聖堂が建てられ
ノイミュンスター教会
となる
聖キリアンの遺品にあった
新約聖書も
1803年まで大聖堂に保管されていたが
後、大学図書館の管轄となった。
↓↑
バイエルン、ワイン製造業者
痛風、リューマチ
の守護聖人
聖キリアン祭
聖キリアンを守護聖人とする
ヴュルツブルクでは
7月に
「聖キリアン(キリアニ)祭」
が、ワイン祭りとして行われ
ワインの女王を先頭に
野菜や果物の籠を手にした
民族衣装姿の子供たち
リボンで飾った柱や
常緑樹で作った飾りを持った人々
楽隊が町を練り歩く・・・
↓↑
ワイン祭り
7月の第1土曜より17日間続く
聖キリアンが
ブドウの栽培を奨励した・・・
ーーーーー
・・・
以下は
「McKinley
マッキンリー(スコットランド,アイルランド)」
に関するブログ記事検索から
ーーーーー
苗字苑
世界の姓語源・意味・ルーツ・由来辞典
http://www.malpicos.sakura.ne.jp/HomePage/Surnames/Surnames.html
を参考に勝手に抜粋添付したものです・・・
研究しているヒトってスゴイナァ~って・・・
少々改作してあるけれど、原文は上記のモノです・・・ゴメン
ーーーーー
↓↑
姓は
スコットランド=ゲール語に由来の
「Mac Fhionnlaoich」
を
「マッキンリー」
の様に発音
M(a)cKinleyという表記は
英語式綴りによる
音転写
原義は
「Fionn-laochの息子」
「Fionn-laoch」=男名
スコットランド=ゲール語
「fionn」=「白い、美しい、蒼白な、明るい、
誠実な、賢明な、確かな、知られた、小さい」
↓↑
McKinley
マッキンリー(スコットランド,アイルランド)
父称姓で
「Fionn-laochの息子」
「Fionn-laoch」は
「美しき戦士
白き英雄」の意
「Leagha(という渾名の人物の)息子」の意
渾名は
アイルランド
スコットランド=ゲール語の
leagh=溶ける、溶かす
に由来・・・
↓↑
父称姓
スコットランドの
ストラスクライド
(Strathclyde)州
に多い姓
1881年当時の集計で
イングランド北部の
大都市
マンチェスター(Manchester)・・・「萬知恵素多蛙」?
の
衛星都市
ストックポート(Stockport)
にも集住
この時点で同市に最も
「McKinley」姓が多く分布
異綴の
「MacKinley」姓は
スコットランドとイングランドの間ほどにある
ノーサンバーランド州
クリーヴランド
に多い・・・
↓↑
この姓は
スコットランド=ゲール語に由来
この言語での表記は
「Mac Fhionn-laoich」
と綴り
「マッキンリー」
の様に発音
「M(a)cKinley」
という表記は
英語式綴りによる
音転写
原義は
「Fionn-laochの息子」
↓↑
「Fionn-laoch」
という男名は
スコットランド=ゲール語
fionn=「白い、美しい、 蒼白な、明るい
誠実な、賢明な、確かな、知られた
小さい」
アイルランド
「fi(o)nn」=「白い」
スコットランド=ゲール
アイルランド
「laoch」=「英雄、戦士」
「美しき戦士、白き英雄」
の意味
↓↑
「Fionn-laoch」という名前が
スコットランド=ゲール
「mac」=「息子」
に後続した事で
緩音化(lenition)が生じ
語頭子音[f]が対応する
有声音[v]で発音される様になり
これが更に弱化して
語頭子音が消失し
「McKinley」
は完全に発音に倣ったもので
「Kinley」の
語頭「K-」はその前にある
↓↑
スコットランド=ゲール語の
「mac」=「息子」
の語末子音「k」の残音・・・
↓↑
「Fionn-laoch」というゲール語の男子名は
中世スコットランドの領主の名にもあり
シェイクスピアの四大悲劇の1つ
『マクベス (Macbeth)』
は
スコットランド
王国マリ朝(1040~1058年)
の実在の王
マクベス(在位:1040~1057年)
を題材にした
「マクベス」の父親である
「マリ(Moray)」領主が
同じ語源の
「フィンリー(Find-láech)」
という名前・・・
「マクベス」の名は
中世のスコットランド=ゲール語で
「Mac Bethad mac Findlaích」
と綴り、後半に
父フィンリーの名前が含まれている
ーーーーー
・・・そうですか、子供の頃に観た「マクベス=蜘蛛の巣城(黒沢明・1957年(昭和32年)1月15日公開)」は藪の中を走りながらナニかを喋っている白髪の老婆・・・怖い、恐ろしい・・・だけで、理解出来なかった・・・が、ボクの年齢が増すと共に2、3、4度と幾度も観て、そのスゴサが判って来た・・・兎に角、「三船敏郎」と「山田 五十鈴」の演技は凄く、「圧巻=アッカン=悪漢・悪感」だった・・・
↓↑
マッキントッシュ
(Macintosh, McIntosh, Mackintosh)
スコットランドの姓
林檎の品種=マッキントッシュ (McIntosh)
マッキントッシュ
(macintosh・mackintosh)
レインコートの一種
↓↑ ・・・雨合羽・・・渡世人(ヤクザ)のアマガッパ
・・・天(海人・海女・海部・贏・尼・阿万)合葉
↓↑ 合羽=マント・マンソ・coat
overcoat(オーバー コート)
ポルトガル語の
「capa(宣教師が着ていた外套)」
木綿製の「道中合羽」
旅人の防寒用外套
和紙に柿渋をしみ込ませた
防水性の外套
渋紙で合羽を仕立てたものが
「雨合羽」
「道中合羽」は風塵を避ける外套
砂ぼこり(埃・塵)避け
↓↑ 三度笠=竹の皮や菅を編ん笠
深く顔を覆う形状
三度の笠
江戸、京都、大坂の
三ヶ所を毎月三度ずつ
往復してい た
飛脚(定飛脚)=三度飛脚
彼らが身に着けていた
女性用として
寛延、宝暦頃まで用いられ
初めは貞享年間
↓↑ 俗に「大深」と云われた女笠
また、
それに使用される布地
(マッキントッシュ・クロス)
織物の裏にゴムを引き
綿布を貼り合わせてある
↓↑
Macintosh=マッキントッシュ=真っ金訳通取
↓↑
「外套(ガイトウ・Шинель・Shinel)
ニコライ・ゴーゴリの短編小説
1842年出版
小役人
アカーキー・アカーキエビッチ
が外套を新調
その新調祝いに
飲み会に引っ張り出され
酒を飲まされ
帰途、強盗に襲われて
外套を盗まれてしまう
警察に訴えるが相手にされず
ある高級官僚にも訴えるが相手にされず
そのショック(shock)で・・・書椄苦・書通句?
病気になり
死んでいく
彼の死後
夜な夜な
往来する
官吏から
外套を引き剥がす幽霊が出
幽霊は最後に
アカーキーの訴えを無視した
「無下」にした・・・無碍(無礙・ムゲ)?」
「高級官僚」の馬車を襲って消えた
↓↑
「まっきんる=末金鏤」
奈良時代の漆工芸の技法の一
器物に漆を塗った上に
金・銀のやすり粉を蒔 (ま) いて文様を表し
さらに漆を塗って研ぎ出す
のちの研ぎ出し蒔絵にあたる
正倉院の
「金銀鈿荘唐大刀
(きんぎんでんそうのからたち)」
がある。
ーーーーー
・・・・
↧
December 9, 2017, 12:55 am
・・・「外套=ガイトウ=該当・街頭・街灯・街燈・画意等・我意等」・・・「礙当=石+疑+当=石(いし・セキ)を疑(うたが・ギ)う」って?・・・「碍当=石+㝵+当=石を得(う・エ)る」って?・・・ナニ?・・・
天下布武=織田信長の戦略
↓↑
沢彦宗恩(タクゲンソウオン)の進言
択 諺 総 音
↓↑
沢彦宗恩=臨済宗妙心寺派の僧
妙心寺東海派の
「泰秀宗韓」から印可を受け
妙心寺第三十九世住持
辞した後は
美濃の
大宝寺の住持
瑞龍寺に居住
天正十五年(1587年)十月二日示寂
貞享三年(1686年)
「円通無礙禅師」の号が下賜
円通(エンツウ)無礙(ムガイ)?
ーーーーー
礙=碍=さまたげる・ガイ・ゲ
進行を邪魔して止める
障礙・阻礙・妨礙・無礙
「害」を代用字とすることがある
「碍」は俗字
「碍子(ガイシ)」は
もっぱら「碍」を用いる
↓↑
礙=石+疑・・・石を疑(うたが・ギ)うって?
碍=石+㝵・・・石を得(う・エ)るって?
異体字は「石得・硋」
↓↑ 㝵=得の古字(古文)
石の得って?・・・石の効用・有効
碍子=電線とその支持物との間を
電流を絶縁するために用いる器具
電柱・鉄塔などに装着される電力用
電信用のものを指す
点火プラグや電熱器などにおいて
電線を絶縁する器具を指す
碍子=緻密な硬質磁器に釉薬を施した
固形絶縁体
電線その他の導体を絶縁して
固定するのに使われ
用途によっては
ガラス、プラスチック
他の材質のものもあるが
絶縁性の磁器碍子が一般的
↓↑ 電流障碍(ショウガイ)
碍=石+日+一+寸
↓↑碍は礙の俗字
碍=石+日+一+寸
得=彳+日+一+寸
彳(テキ・チャク)=ノ+イ
彳=少しずつ歩く
人の脚の3つの部分が
連なる様子に象る(説文解字)
甲骨文では
十字路の象形・・・辻道・交差路
「行=彳+亍」・・〒=郵便マーク←飛脚
郵便屋さんの郵便物の配達
=少し歩いては止まること
たたずむこと
「彳=左足」
「亍=右足」
↓↑「石得」=石の得用(効用・有効・利用価値)
↓↑「石疑」=石の疑問
(石井・岩井・・磐井の乱
↓↑ いわい=祝い=磐余=神武)の疑問?
↓↑
無礙・無碍=ムゲ・・・有礙・有碍=ウゲ・妨げ有り
仏教用語
無障礙とも
障りや妨げが無く
自由自在であること
融通無礙
阿弥陀仏がもつ十二の
光の功徳(十二光)の無礙光
諸仏の
智 慧を無礙智
理解力を無礙解
弁舌力を無礙弁
法・義・辞・楽説
の四つに細分する
法=無礙智
義=無礙智
辞=無礙智・・・辞=言語・ことば
↓↑↓↑ 漢文の一体
楚辞の系統をひく様式で
押韻して
朗誦に適した文
↓↑ 辞=辭・・・覶(ラ・ラン)・亂
ことば・ジ
文章
辞書・辞令・訓辞・言辞・謝辞
修辞・助辞・措辞・題辞・遁辞
美辞・名辞
やめる・ことわる
辞職・辞退・辞任・辞表・固辞
別れを告げる
辞去・辞世
漢文の文体の一
辞賦
↓↑↓↑ ↓↑
単語を文法上の性質から
二つに分類したものの一
名詞に対する他の品詞
常に詞(自立語)に伴って
文節を構成する語
↓↑ 助動詞・助詞
↓↑↓↑ 他に接続詞・感動詞など
↓↑楽説=無礙智
の如く
これらを
四無礙智という
↓↑
礙=碍=進行を邪魔して止める
さまたげる
↓↑ 障礙・阻礙・妨礙・無礙
闊達無礙
度量が広く、小さなことに拘(こだわ)らないコト
思いのままにのびのびとしているさま
闊達=心が広く物事に拘らないさま
↓↑ 闊達無碍・豁達無礙とも書く
豁=「谷+害」の左右逆の漢字もあるが・・・
豁=害+谷
「害」と「谷」を合わせた字で
開けていて「ひろい」という意味?
ひろい・開けている・心が広い
?・・・広いならば、谷の象形「V」だが、
「害」は「そこなわれた・妨害」、「谷」である
人間が谷沢の渓流に流されたか、
谷そのものの水を塞き止めたか、の
「害+谷=豁」で、
谷の機能(流れ)が失われた、
「害(そこなわれた)」だろう・・・
だが、「豁」の字は
「宀+丰+口+谷(ハ𠆢口)」
「宀+土+古+谷(ハ𠆢口)」で
「丰」が
「土(十一)+丄」
「士(十一)+丄」
とは異なる・・・
「丰=三+丨」=丰=豐
「草の穂が三角形に茂るさま
夆(とがった、峰 、鋒、蜂)
「邦、豐」の音符(ホウ)
「豊=曲+豆→禮=礼=レイ」
と
「豐=丰+丰+山+一+口+䒑=ホウ」
は元々別字
「豐=ゆたか・とよ
フ・ホウ(ホゥ)・ブ」
「豐=富む・みちる・実る
語の上につけて
ゆたかなことをほめたたえる語」
「豆の豐滿なる者なり」
「豐侯という盃の台」
「高坏の食器(豆)に
穀物をたくさん盛った象形」
↓↑
「豊(レイ)=禮(示豊)儀
は
豆(たかつき)にモノ(曲)を
供えた字」
・・・豆(たかつき)の添えモノと
曲芸(豊=乚(イン)=イン=隠・隱)
乚=乙(おつ・おと・イツ)?
乙=Z(ゼット)・・・乙=7+ム?
「豐葦原(とよあしわら)」?
「豊葦原(とよあしわら)」?
「豐國=豐前(ブゼン)+豐後(ぶんゴ)」
「豊國=豊前(レイゼン)+豊後(レイゴ)」
天平七年(735年)
国司
陽候史真身が任官・・・ヤゴ(水蠆)は
蜻蛉の幼虫・トンボの宙返り
穐津(秋津・安芸津)島
↓↑
豊国(豐國)=律令制以前の国
『国造本紀』では
成務朝に
伊甚国造と同祖の
宇那足尼が豊国造に任じられた
↓↑
伊甚国造(いじみのくにのみやつこ
↓↑ いじみコクゾウ)
「伊甚=イジン=異人・偉人・伊神」
↓↑ の「國造=コクゾウ=穀蔵」?
令制国の上総国埴生郡(千葉県茂原市の
一部と
長生郡長南町
睦沢町の一部を
支配した国造
伊甚屯倉設置以前は
夷灊郡も支配していた
夷=蝦夷・外人・異邦人
尊王攘夷
灊=セン=氵+鬵()=潛・潜
異体字は「𤄵・𤅬・潛・𨽨・潜」
潛(ひそむ)→夷が灊(ひそむ)
灊=氵+兂+兂+鬲(一口冂儿丅)
↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑
鬲(レキ)
中空構造の三足を持った沸騰機
空間に水を入れ
その上に甑(こしき・ソウ)を載せ
火にかけ、水を沸騰させ
粟や稲などを蒸した
鬲と甑のセットは
甗(ゲン)
夏・殷・周で甗は
一般的な調理器具として定着した
鬲部(レキブ)
「鬲」字は中国古代の三脚炊具
「鼎(かなえ)」に似る
字形は側面から見た形で
腹部分に紋様
三本の足がある象形
偏旁の意符としては
炊具や煮炊き・飲食に関することを示す
中国で広く使用され
甑(ソウ) と組合せて穀類を蒸す器具
↓↑ ↓↑ ↓↑
灊(セン)=氵(サンズイ・纂、簒の隋)
兂兂(二列のカンざし・かみさし・シン)
口(くち・コウ)
冂(まえがまえ・まきがまえ)
儿(ニン・ジン・ひげ)
丅(した・げ・カ・下)
↓↑ ↓↑
神指し(上注し)の
口述
巻きが前
人参の下
↓↑
豊國(とよのくに・とよくに)
豊後(とよくにのみちのしり)
ブンゴ=文語
豊前(とよくにのみちのくに
とよのさきのくに)
ブゼン=分全・武前(全)
伏膳
布前・憮然
天下布武=織田信長の戦略
↓↑
沢彦宗恩(タクゲンソウオン)の進言?
択 諺 総 音
↓↑
沢彦宗恩=臨済宗妙心寺派の僧
妙心寺第三十九世住持
辞した後は
瑞龍寺に居住
天正十五年(1587年)十月二日示寂
貞享三年(1686年)
「円通無礙禅師」の号が下賜
円通(エンツウ)無礙(ムガイ)?
↓↑
「豊→豐=たかつき=高坏・高杯」
↓↑
高坏=たかつき=高杯
高い台のついた坏形の食器
高坏形の土器は縄文時代晩期に一般化し
弥生時代になると不可欠な
食器の器形として定着
木製のものも使用
古墳時代
土師器 (はじき) や須恵器の
高坏が使用
須恵器のそれにはふた付きもある
中国の豆 (トウ)
ギリシアのキュリクス
にあたる。
食物を盛るのに用いた
長い脚の付いた器(うつわ)
1本の脚の上面に
円形または方形の皿が付いたもの
高坏を逆さにして
底(土居(つちい))の上に
火皿を置き灯台の代用にしていた・・・
↓↑
「豆(トウ・ズ)」という漢字は
古代中国で使われていた
高杯(たかつき)という脚がついた
食器・礼器を表す象形文字
「まめ(主にダイズ=大豆)」は
「菽」と書かれていた
食器「豆(高杯)」に盛られた
ダイズ(大豆)を「豆」と表現するようになり
中国・日本とも「豆」といえば
食物の「豆(まめ)」を意味する
「豊作」の「豊(ホウ)=曲がったマメ」だが
↓↑
「豐≠豊」は
「礼(禮・レイ・示+豊)の古字」
「豐=丰+丰+山+豆」は
「草の盛んにしげれる貌=丰茸」
みめよし(美好)
おもぶくら(豐頰)
顏がまろく肥えてうつくし
風に通用す
「丰裁・丰標」
「熟語は丰采・丰姿・丰容」
「土(十一)+丄」
「士(十一)+丄」
とは異なる・・・
「害+谷」の合体の「豁」が「広い」とは思われない
そこなわれる谷(たに・コク
渓谷=ケイコク=警告・経国・傾国)
「拾意(比呂意・ひろい)」?・・・
豁達・開豁
ゆるす・大目に見る
豁免・・・寛(?)・寛大
カチ(クヮチ)・カツ(クヮツ)
ひらける・ひろい
豁達・開豁
広々と開けているさま
あけっぴろげ
豁然=視野が大きく開けるさま
心の迷いや疑いが消えるさま
豁然大悟=疑い迷っていたことが
からっと開け解けて真理を悟ること
一旦豁然=ふとした時にいきなり
迷いがなくなり、悟りが開けること
豁達=闊達=濶達=度量が広く
小事にこだわらないさま
闊達自在=細かなことにこだわらず
心のままにふるまうこ
↓↑ 豁=ひらく・ひろ・ひろし
「禮=礼」
「礼」は
「禮=示」+「豊・豐」の略体ではなく
「元来からの文字」の会意形声文字「ネ+乚」
「禮(レイ)」のつくりは・・・・類字は「禯」
新字体の「示+豊(ホウ)」ではなく
旧字体の「示+豐(レイ)」の漢字
↓↑
「禯(ジョウ)=示+農」・・・豊饒・豊穣・豊作
「聖王(554)」=朝鮮、百済の第二十六代の王
(在位 523~554)
武寧王の子
諱は
明禯(メイジョウ)
「まつり=禯・禫・祊・茉莉
祭・禡・禘・祻・礿
末利・禴・肜・奉り・祼・禓」
政(まつりごと)
↓↑
「豊=豆(たかつき)」
に供え物をならべた様
整えられた祭礼の供え物
形よく整えられた行儀作法
儒教の徳目の一
整えられた形式、儀式
婚礼、祭礼
社会習慣、慣習
相手を尊重する取り扱いや挨拶
礼遇、敬礼
埃=ちり=塵・塕・坱・坌・坺
鏤・笭塵
地理・地利・散・千里
↓↑
Egypt(エジプト・埃及)・首都 Cairo
Chile(チリ・智利)・・・首都 Santiago
chill=冷え・冷たさ・寒け・寒さ
冷え込み
Just chilling=ダラダラと
chill out=落ち着いて
チリソース(chili sauce)
チリ(chili)=中南米原産の
唐辛子(チリペッパー)
無碍自在=無礙自在
妨げるものなく自由であること
あらゆる事物に捉われることなく
自由自在
行動や考えが何の障害もなく
自由で伸び伸びしていること
融通=滞りなく通ること
無礙=妨げのないこと
↓↑ 礙=碍
碍=石+得・・・?
得=彳+貝(財貨)+寸・・・?
手で財貨を拾いに行くこと?
↓↑
礙=石+疑
疑=子+止+矣・・・?
矣は人が振り返って
立ち止まる様を描いたもの・・・?
子に気をつけて
立ち止まっている様子で
ためらって足をとめる意となる・・・?
「礙」は
石がじゃまをして
足をとめるという意・・・?
↓↑
漢字構成の漢字が違う
疑=匕(牝)+矢(ノ一一人)+マ+疋(一ト人)
ーーーーー
・・・
↧
↧
December 12, 2017, 1:57 am
・・・十二月九日、十日・・・12月11日になってしまった・・・ボクジシンの「石」に関する知識や、「石」の漢字自体の熟語の意味の不理解、非理解の無知加減と、その無恥のどうしょうもないコトには・・・「石尤風」も「頑石点頭」も、「射石飲羽」も「木人石心」も今現在、初めて調べて知った「四文字熟語」・・・それに、字形から漢字をなんとなく理解出来そうなのだが、調べた「辞典・辞書」の意味内容は違っていた・・・「漢字の熟語の意味」は「その古典文章の前後の物語や、出来事の説明」を知らないと、一文字の漢字の形象を理解出来たとしても、「熟語漢字の由来」をしらなきゃぁ、どうにもならない、か・・・
「イシ」への妄想は尽きないけれど・・・冷たい石像よりも、温かい実像(肉像・宍像)がイイ・・・
「モウソウ」じゃぁ、ネッ・・・よっぽどの「同類・同輩」じゃなくちゃぁ、付き合いきれないのはハナからだけれど・・・
肉感のある「AIロボット」なら、お付き合いしてくれるカモだが・・・「アナタは人類にとってヤクたたずデアル」って・・・
ーーーーー
石=厂(一ノ)+口=いし・いわ・セキ・ジャク・コク
厂(がけ・カン・ガン)
「山石なり・厂(崖)の下に在り
口⇔○の象形(説文解字・巻九)」?
口が○の象形であることは判るが、
「一+ノ+口」=「厂(崖)+口」とは
「一(初め)」に
「ノ(ヘツ・ヘチ・傾斜)」から
転がり落ちた角(□・◆)のある
「岩(磐・嵒)」が
「小さく丸く球形」になったモノ・・・だろう・・・
↓↑
石
鉱石・岩
石鍼=いしばり・セキシン=石針・砭(ヘン)
↓↑ 鍼灸術で用いる石製の針
焼いて瀉血などで病気を治療
骨身にこたえること・身にしみること
「八寒八風人の肌骨に石鍼し
(浄瑠璃・関八州繫馬・・・
平将門の子供、相馬良門・小蝶の兄妹と
源頼光の弟、頼信・頼平の抗争)」
↓↑ ↓↑
八寒地獄
頞部陀(あぶだ)地獄 Arbuda
八寒地獄の第一
寒さのあまり鳥肌が立ち
身体にあばたを生じる
尼剌部陀(にらぶだ)地獄 Nirarbuda
八寒地獄の第二
鳥肌が潰れ、全身にあかぎれが生じる
頞哳吒(あたた)地獄 Atata
八寒地獄の第三
寒さによって「あたた」という
悲鳴を生じる
「虎虎婆」まで共通
臛臛婆(かかば)地獄 Hahava
八寒地獄の第四
寒さのあまり舌がもつれて動かず
「ははば」という声しか出ない
虎虎婆(ここば)地獄 Huhuva
八寒地獄の第五
寒さのあまり口が開かず
「ふふば」という声しか出ない
嗢鉢羅(うばら)地獄 Utpala
八寒地獄の第六
全身が凍傷のためにひび割れ
青い蓮のようにめくれ上がる事から
「青蓮地獄」とも呼ばれる
鉢特摩(はどま)地獄 Padma
「紅蓮地獄」
八寒地獄の第七
鉢特摩(はどま)=蓮華の音写
落ちた者は酷い寒さにより
皮膚が裂けて流血し
紅色の蓮の花に似る
摩訶鉢特摩(まかはどま)地獄 Mahapadma
意訳で
「大紅蓮地獄」
八寒地獄の第八
八寒地獄で最も広大
摩訶(まか)=大の音写
ここに落ちた者は
紅蓮地獄を超える寒さにより
体が折れ裂けて流血し
紅色の蓮の花に似る
↓↑ ↓↑
八風(はっぷう)
仏教で修行を妨げる
8つの出来事
人間が求める4つの出来事
四順(シジュン)
利い(うるおい)=目先の利益
誉れ(ほまれ)=名誉をうける
称え(たたえ)=称賛される
楽しみ(たのしみ)=様々な楽しみ
人間が避ける4つの出来事
四違(シイ)
衰え(おとろえ)=肉体的な衰え、金銭・物の損失
毀れ(やぶれ)=不名誉をうける
譏り(そしり)=誹謗中傷される
↓↑ 苦しみ(くるしみ)=様々な苦しみ
↓↑ ・・・八寒地獄は現世の現実とお変わりなし・・・
石製のもの
石碑・石器
堅い
値打ちがないモノ
重さ
↓↑大きさ(碩と通じて)・・・碩=石+頁・・・大石内蔵助
↓↑
石(いし・いわ・セキ)
岩石が細かく砕けたもの
細かいものが小石、砂
石(こく)=尺貫法の体積の単位・斛
石(いし)=トランジスタ
石(いし)=隕石
石(いし)=CPU・GPU
石(いし)=結石・胆
石(いし)=碁石
石見国・石州
石=八音の一つ・石製の楽器
石(いし)=人名・日本にも石姓がある
茨城県高萩市に集中分布
茨城県
日立市・・・常陸・常盤・日達
十王町
伊師発祥
伊師=いし=石・・・伊都の師匠?
「イシ」って、バテレン?
に転訛・・・
↓↑
厂+二+口=古文(集韻)
一+𠆢+口=䂖=異体字
石印・石英・石火・石化・石灰・石棺・石橋
石窟・石経・石工・石人・石像・石苔・石帯
石炭・石柱・石馬・石碑・石筆・石仏・石友
石路
石和(いさわ)・・・石和温泉(山梨県笛吹市
の旧東八代郡石和町地域の温泉)
ーーーーー
石尤風=逆風・傳說古代、有商人尤某娶石氏女、情好甚篤
「石尤風(セキユウフウ)」=南朝宋の故事
夫の尤(ユウ)の帰国を
待ちあぐねた妻の石(セキ)氏は
思いつめた揚句に病死
臨終に、
自分は大風になって
天下の旅人のゆくてを阻(はば)んで
婦人を悲しませてやると誓った・・・
「逆風」のことを「石尤風」と云う・・・
「イシ(イワ)はカゼをウラム」じゃぁナイ?・・・
神風・・・風魔神・・・
↓↑
・・・「尤=理にかなっている・もっともである」、「尤=とが、もっとも、ことなる、はなはだ・ユウ」・・・「尤(もっとも・ユウ)=過ち、禍、災い、異なる、怪しい、恨む、特に」という意味?・・・「最(もっと)も」ではない・・・
「声符
尤を声符とする漢字
忧・犹・沋・𣧗・肬・訧・𩑣」
語彙
尤異・尤禍・尤悔・尤最・尤度・尤物
異体字
怣=失+心(集韻の古文)
𡯊=(字彙補)にある異体字(漢隸・楊君頌)・・・
「尤」は「犬」の漢字に似ているけれど・・・
「蚩尤(シユウ・ Chīyóu)」は中国神話の神、戦の神・・・
「蚩尤は兵(兵器)を発明した元祖」
「路史」では姓は「羌」
「炎帝神農氏の子孫」
「獣身で銅の頭に鉄の額を持つ」
「四目六臂」で
「人の身体に牛の頭と鳥の蹄を持ち、頭に角
石や鉄を食べて鴟義(シギ)とも呼ばれた」・・・
「黄帝と戦い、濃霧(毒ガス?)で苦しめたが
指南車を作って方位を測定した黄帝に
涿鹿(タクロク)で敗北、捕らえられ殺され」
「蚩尤は苗(なえ・ミョウ)族の始祖」・・・猫・描・錨
↓↑
石破天驚=石が破れ、天が驚くほど「詩文・文章・音楽」が
巧妙であるという意・・・
ーーーーー
・・・知らない四文字熟語が結構ワンサカ・・・
↓↑
石部金吉(イシベキンキチ)
一石二鳥(イッセキニチョウ)
頑石点頭(ガンセキテントウ)
道生が石に説法すると、石はうなずいた
金石糸竹(キンセキシチク)
楽器の総称
「金=鐘・石=打楽器の磬
糸=琴・竹=細い竹の簫(笛)
金石之交(キンセキノまじわり)
変わることの無い、かたい友情
玉石混淆(ギョクセキコンコウ)
宝石と只の石が入り混じっている
玉石混交(ギョクセキコンコウ)
玉石同匱(ギョクセキドウキ)
木箱に宝石と石が一緒
玉石同砕(ギョクセキドウサイ)
宝石も石も一緒に砕けてなくなる
魚目燕石(ギョモクエンセキ)
本物にそっくりな偽物で無価値
敲金撃石(コウキンゲキセキ)
金を敲き石を撃つ
詩文の響きや韻律が美しいこと
「敲金=鐘などの金属の打楽器を敲くこと
撃石=磬などの石の打楽器を打つこと
張籍の詩を
金石のような美しい音色だと
韓愈が評した」
剛腸石心(ゴウチョウセキシン)
意志が固く、度胸があること
山霤穿石(サンリュウセンセキ)
山溜、石を穿つ
山溜穿石(サンリュウセンセキ)
射石飲羽(シャセキインウ)
矢の羽までも深く突き刺さる意
焦熬投石(シュウゴウトウセキ)
ひどく壊れやすいことのたとえ
匠石運斤(ショウセキウンキン)
匠石の優れた斧使い
心堅石穿(シンケンセキセン)
樹下石上(ジュカセキジョウ)
出家して行脚している人の境遇
水滴石穿(スイテキセキセン)
水落石出(スイラクセキシュツ)
隠れていた実体が現れる
石心鉄腸(セキシンテッチョウ)
石上樹下(セキジョウジュゲ)
石破天驚(セキハテンキョウ)
石画之臣(セッカクのシン)
リスクの少ない計画を立てる臣下
or
壮大な計画を立てる臣下
石画=石のように堅い計画
石火電光(セッカデンコウ)
泉石煙霞(センセキエンカ)
泉石膏肓(センセキコウコウ)
漱石枕流(ソウセキチンリュウ)・・・夏目漱石
孫楚漱石(ソンソソウセキ)
他山之石(タザンのいし)
枕石嗽流(チンセキソウリュウ)
枕石漱流(チンセキソウリュウ)
枕流漱石(チンリュウソウセキ)
隠者の生活
鼎鐺玉石(テイソウギョクセキ)
鼎鐺玉石(テイトウギョクセキ)
特上の贅沢をすること
鉄心石腸(セッシンセキチョウ)
鉄腸石心(テッチョウセキシン)
点滴穿石(テンテキセンセキ)
電光石火(デンコウセッカ)
磐石之固(バンジャクのかため)
盤石之固(バンジャクのかため)
匪石之心(ヒセキのこころ)
石のように転がることがない心
浮石沈木(フセキチンボク)
石を浮かべ木を沈む
道理に合わない権力、権威
仏足石歌(ブッソクセキカ)
短歌に七音の一句を加え
五・七・五・七・七・七
の六句、三十八音の形式の歌
砲刃矢石(ホウジンシセキ)
木人石心(ボクジンセキシン)
薄情で冷酷な人
or
意思が固く、頑固な人
薬石之言(ヤクセキのゲン)
欠点を正すのに役立つ忠告(薬石)
薬石無効(ヤクセキムコウ)
落穽下石(ラクセイカセキ)
他人の弱みや窮地を狙って
追い討ちをかけること
流金鑠石(リュウキンシャクセキ)
「鑠=熔かす=熱さや火力」
十個の太陽が同時に昇って
金属や石を全て熔かしたという
中国の伝説
ーーーーー
↓↑
石上宅嗣=729(天平一)~781(天応一)
日本最古の公開図書館
「芸亭」の設立者
(中納言
石上
乙麻呂=弟麻呂の子
乙麻呂は
左大臣
石上麻呂の三男
官位は従三位・中納言)
物部朝臣石上宅嗣
757(天平宝字一)年
相模守
その後地方官を歴任し
761(天平宝字五)年
遣唐副使に任ぜられるが
直後に罷免
宝亀六年(775年)十二月二十五日
石上朝臣から物部朝臣に改姓?
宝亀十年(779年)十一月十八日
物部朝臣から石上大朝臣に改姓?
↓↑
石川五右衛門の児・・・「碍子・礙子」
↓↑
石田三成の児・・・・・「碍子・礙子」
いわた=磐田・岩田・岩多・岩太・祝田
↓↑
石(岩)見重太郎
石水=いわみ=岩水・・・
下石=おろじ
↓↑
石川県=金沢県・・・「石川郡」に由来
「石の多い川」
「手取川」が
上流から石を多く流すことから
通称「石川」と呼ばれる
北緯36度33分
東経136度46分
金沢市の地名の由来は
小立野(こだつの)台地で
砂金採掘を行った
「金洗沢(かなあらいのさわ)」による・・・
ーーーーー
孫悟空=石猿=齊天大聖
仙石から生れた神通力をもつ猿
天界を騒がせ五行山下に閉じ込められたが
天竺に取経に行く
三蔵法師に助けられ
従者となり
猪八戒 (チョハッカイ)・・・豚=猪悟能==豬哥神
天蓬元帥
沙悟浄 (シャゴジョウ)・・・河童=捲簾大将=沙和尚
とともに三蔵を危難から守る
ーーーーー
石申(BC4世紀)
中国の天文学者
甘徳と同時代の人
魏で生まれた
石申先生(石申夫)
保存されている本
121個の星の位置を決めた
最も早く太陽の黒点を観測
石申
石申夫
公元前4世紀
魏國人
戰國天文學家
占星家
著有
「天文・八卷」
「史記・天官書」
戰國時期的著名天文學家
「在齊、甘公」
「楚、唐昧・趙、尹皋・魏、石申」
「晉書・天文志上・則進一步」
「シ・シェン(石申・シーズーシェン)」
紀元前4世紀
中国の天文学者
甘徳で生まれ、魏の国の人物
「Shi」
121個の星を位置づけた
黒点観測をした
8巻の天文学
1巻の天体地図
1巻の星カタログ
占星術に関する論文に保存
Shi Shen
「石申天文、Shi Shen Tianwen」
579年頃
Ma Xian(馬顯)によって編集された
Masters Gan and Shi
(甘石星經、Gan Shi Xingjing)
のStar Manual
月の上の火口
Shi Shenは
彼にちなんで命名
ーー↓↑ーー
「子」は「孑=一+了=孑孒・孑孑・孑孒・孑孑=ぼうふら」に類字で類似・・・「カの幼虫・水たまりに棲む・体長は約五(ミリメートル)・棒状でくねくねと動きながら上下する・ぼうふり、季夏、由来体の動きが棒を振るのに似ていることから棒振とも書く・参考「孑孑=ケツケツ」・・・
↓↑
「子(ね・シ)=一+了=名詞」
「十二支(じふにし)」の第一
時刻の午前零時。また、それを中心とする二時間。
方角の北
↓↑
「子=こ=児(ジ)=名詞」
幼い子・子供
人を親しんでいう語・男女にも使用
男が女性に対して用いる場合が多い
↓↑
万葉集~
鳥などの卵・鳥の子
↓↑
子(シ)
接尾語
姓の下に付けて、尊敬の意
「孔子・孟子・孫子」・・・
男性の名の下に付けて
親愛、尊敬を表す
手紙などで自分の名の下に付けて
謙譲の意を表す
「以上・・・子」
↓↑
子(シ)
代名詞
あなた・きみ
対称の人称代名詞
↓↑
子=こ=児
接尾語
その仕事をする人の意を表す
「舟(ふな)こ」
人に対して親しみをこめて呼ぶ
「背(せ)こ・吾妹(わぎも)こ」
親しみの気持ちをこめて、人の名に付ける
女性の名の下に付けて
用いる
音読(シ)が普通
「小野妹子(をののいもこ)」
「蘇我馬子(そがのうまこ)」
など男性にも使用
ーー↓↑ーー
以上・・・モノにつく「扇子」や「礙子=碍子=硋(石亥)子」の説明がなかったが、「ムゲ=無下」にしたわけではないが・・・「無下」は「捨てて顧みないでいる・すげなくする・だいなしにする・むだにする」、「冷淡なさま・すげなく・そっけなく・相手の懇願を無下に拒む・度外れなさま・むやみに・やたらに・まったく・すっかり」、「あまりにひどい・非常によくない」・・・
「無碍=妨げること(もの)無し」と、「無下=最低・それ以下は無し・問題外」には困った・・・
前回、書き込んだが・・・
↓↑
・・・「ガイシ=礙子=碍子
=硋(石亥)子=𣝅(木疑)子」・・・
・・・「ムゲ=無礙=無碍
=無硋(石亥)=無𣝅(木疑)」・・・・
↓↑
高圧電線を鉄塔で支え、張って(吊るして)いる
懸垂碍子=懸垂碍子・・懸かって
垂れる
仁(イニ・人二)=垂仁天皇
(イジン)の
石が㝵(得)る子
懸垂礙子=懸垂礙子・・懸かり垂れる
仁
の
石(ペテロ・Petros・Peter
シモン・ペテロ=Simon Peter
バルヨナ・シモン
漁師(fisherman
pêcheur・pecheur
ペスカトーレ=pescatore)
ペトロ(ペテロ)=経訳賂?
シモン=シメオン=閉め音?
ペトル・Petrus
Stone
「イエスにより
ケファ(Kêpâ)=岩の
断片、破片=石と呼ばれた」
が
疑う子
↓↑ 山頂の垂訓・・・イエス・キリストの「最初の弟子」
↓↑ イエスの受難時ペトロは逃走、鶏が鳴く夜明け前までに
↓↑ イエスを3度否認した・・・
↓↑ ドミネ・クォ・ヴァディス(Domine, quo vadis?)
高圧電気の高圧電流だから・・・
![]()
![]()
↓↑
電線を鉄塔などから
懸垂して支える碍子
超高圧の送電線に用い
使用電圧に応じて適当な個数を連結
↓↑
ガイシ
礙(石疑)子=碍(石㝵)子=硋(石亥)子
↓↑
礙の漢字構成
礙=石+疑
=丆+口+疑
=一+丿+口+疑
=一+丿+口+匕+矢(ノ一一人)
+龴+疋(了ト人)
碍の漢字構成
碍=石+㝵
硋の漢字構成
硋=石+亥・・・石は亥の子・イシは猪子
猪=獣は
子=一了=始終=鼠・・・移鼠=基督
イシ=「医師・李氏・遺子」は「亥=北西の子」・・・
高句麗・高麗(人参)・満州?
ーーーーー
・・・???・・・「ペテロ(岩)の人」は「基督(キリスト・クリスト・ハリスト)」の「弟子(乙子)」・・・
ニワトリ(鷄・鶏・雞)が鳴く夜明け前の3度のウソ・・・
↧
December 13, 2017, 2:36 am
12月=子月=10番目の月=December
・・・「子」の椄(つ)く漢字熟語だが・・・「α+子」、「~子」・・・「馬子・鳥子・妹子」・・・「子=ねずみ=鼠(ソ・ショ)」・・・「鼠小僧次郎吉」・・・
ーーーーー
1797?~1832(?年~天保三年)
盗賊
大名屋敷を中心に盗みに入り
義賊として鼠小僧と呼ばれた
平戸藩主
松浦氏など大名にも人気があった
上野小幡藩松平家に入って捕縛
鈴ヶ森で
磔(はりつけ)
ここは
松平定信が
1793年(寛政五)に建てた
水子塚
江戸相撲の
発祥地を記念の
力塚
猫塚
等があり
国学者、加藤千蔭
戯作者、山東京伝
浄瑠璃語り、竹本義太夫
など有名人の墓もあり
鼠小僧次郎吉の墓は
墓石を欠いて持っていると
勝負運がつくと評判になり
見世物の興行場書となり
多数の参詣人で賑わった
↓↑
尾張藩では武家長屋に忍び入って
刀、衣類を盗んだ藩士
同役などの鼻紙袋から
金子(きんす)を盗んだ藩士
寺の賽銭(さいせん)を盗もうとした藩士
など
武士による盗犯の事例が多
盗賊鼠小僧次郎吉は
諸大名を中心に延べ
100余軒の武家屋敷から
計3000余両を盗み
1832年(天保三)に獄門
ーーーーー
で、「~子」・・・
↓↑
草子=古本用語・さくし(冊子)の転
綴(と)じてある本
字などを書いたものも書いてないものもいう
仮名書きの物語・日記・歌などの総称
「古今の草子を御前におかせ給ひて(枕草子)」
書き散らした原稿・したがき
「絵草紙・草双紙」などの略
字の練習用に紙を綴じたもの」
↓↑
・・・「草紙(シ)・草双紙(シ)」だから「草子(シ)」の「子」は「音」を重ねて「紙(糸+氏)~子(了+一)」へと文字の意味を拡げた・・・「いと」の「氏(うじ)」から「おわり」の「一(はじまり)」と・・・しかも「草双紙(かみ)」は「草双子(ふたご)・双鼠=ソウソ=相曾)」・・・「鼠=ソ・ショ」だが、「改竄(カイザン)」の「竄=穴(宀八)+鼠(ソ・ショ)」は「サン・ザン」である・・・景教(唐に伝来したキリスト教の一派・シリア人、ネストリウス(Nestorius・386~451)の教義・781年(建中二年)に伊斯が建立した大秦景教流行中国碑文は景浄の撰文)で「移鼠(イソ)」は「イエス・キリスト=耶蘇・基督」であった・・・「マリア=未艷」・・・字面からは「未艷=未だ艷ならず」だが「処女=乙女」ではなかった・・・キリストを「人の子」として産んだ・・・
「改竄(カイザン)=原文、原本を勝手に書き変えること」・・・「聖書の改竄」である?・・・「改竄=他言語へ翻訳」と云うことなのか?・・・「飜(番+飛・ひるがえす)譯(言+睪・わけ・ヤク・エキ)」・・・
「約束・契約」の書なのか?、「翻訳」の書なのか?・・・「約=ヤク=訳・薬・厄・役・焼く・妬く」・・・「≒(やく・凡そ・大体・概ね・近似)」、「疫(病)・扼(殺)・躍(動)・(跳)躍」・・・
↓↑
大秦
景教・・・景行・景保
流行
中国
碑文
32(参拾弐・参拾貮)行・・・十=拾=足=たり・垂り
毎行
62(六拾弐・陸拾貮)字・・・十=拾=足=たり・垂り
計約1900(壱阡玖陌)字
景浄の撰
書は
呂秀巌
漢字の外に
エストランゲロ(古体のシリア文字)・・・叙(敍)利亜
(恵諏訳等務解路?・得蘇訳覶夢解路?)
が刻され
この文字は景教に関係ある
僧侶約
七十人の名を記したもの
大部分には相当する
漢名を添えてある
碑文概要
キリスト教の教義
阿羅本が景教を伝えた時
唐の
太宗が感激して
宰相の
房玄齢
に出迎えさせ
貞観十二年七月
詔勅を賜った
玄宗・・・阿倍仲麻呂(朝衡=晁衡)の仕えた皇帝
文武二年(698年~770年)宝亀元年
(685~762・唐王朝第六代皇帝
在位712年~756年・姓は李・名は隆基)
や
唐の武将
郭子儀・・・「郭の子の儀」?
が
景教を保護したことなどを記録
景浄
円照が編纂した仏典目録
『貞元新定釈教目録』巻第17
に
インド僧
般若三蔵が
胡本(ソグド語版)の
『大乗理趣六波羅蜜多経』
を翻訳する際
「波斯僧景淨」
の協力を仰いだと記録
碑文を撰した
景浄は
ペルシャ(波斯)人であり
般若三蔵
と交流があった
804年末
長安に入った
空海
が
サンスクリット語を
学んだのが
般若三蔵
であり
空海の長安での住居
西明寺
や
般若三蔵
の
醴泉寺は大秦寺に近いことから
空海が景教に触れた・・・
『貞元録』は
800年に
徳宗へ上進された
空海の師、
恵果
を
「大秦景教流行中国碑」に登場する
「佶和」・・・佶(イ十一口)=健やか・たくましい
と同一人物とする説も・・・
↓↑
「竄」
「のがれる・かくれる・もぐる・逃げ隠れる」は「隠れ切支丹」の宿命であるが、「独裁的な権力者が弾圧する者は甲乙を問わず」である・・・「竄入=攙入=逃げ込むこと・誤って 紛れ込むこと・原(元)文中に不要な字句などが紛れ込むこと」・・・「流竄=遠隔地へ追放すること」・・・
「文章を都合良く書き改める」のは「政治屋・役人屋」・・・その場でウソをツキさえすれば殺されずにスムのは双方同じ心情だろう・・・「嘘も方便」は殉教者には通用しなかった・・・
↓↑
竄=のがれる・にげる・にげかくれる
竄入・竄伏
はな(放)す・追放する
竄流
あらためる・書きかえる
改竄
竄=穴(宀八)+鼠=鼠(ねずみ)が穴にかくれる意
改竄(カイザン)・貶竄(ヘンザン)
奔竄(ホンザン)・流竄(ルザン)
竄(かく)れる
竄定(ザンテイ)
竄匿(ザントク)・竄入(ザンニュウ)
竄伏(ザンプク)・竄流(ザンリュウ)
竄(のが)れる
↓↑
草子(そうし)・・・「天草子」→「アマクサの子」?
1591年~1597年
「伊曾保物語・平家物語―天草本」
(The Jesuit Mission Press in Japan)
物の本に対して
より通俗的・娯楽的で廉価な、安っぽい書物類
これの出版を手がける「草子屋」は
物の本屋より一段格下の本屋・・・
そうし(草紙=草子=双紙=冊子)
「さくし(冊子)」の音変化
漢籍・和本などで
紙を綴 (と) じ合わせた形式の書物
綴じ本
物語・日記・歌書など
和文で記された書物の総称
御伽 (おとぎ) 草紙・草 (くさ) 双紙など
絵入りの通俗的な読み物の総称
習字用の帳面・手習い草紙
書き散らしたままの原稿
↓↑
類語
折り本(おりほん)
綴本(とじほん)
巻子本(かんすぼん)
冊子(さっし)
↓↑
そうしあわせ(草紙合わせ)
平安時代の物合わせの一
↓↑
ソウシ
草紙
宗師
奏詞
相思
草紙
荘子
桑梓
掃司
↓↑
御伽草子(おとぎぞうし)
鎌倉時代末~江戸時代にかけて成立し
新規な主題を取り上げた短編の絵入り物語
「お伽草子・おとぎ草子」とも表記
広義に室町時代を中心とした
中世小説全般を指し
室町物語とも呼ばれる
御伽草子
↓↑
浮世草子(うきよぞうし)
江戸時代に生まれた
前期近世文学の主要な文芸形式の一
浮世草紙
井原西鶴の
「好色一代男(1682年刊行)」
以降の一連の作品を
それまでの
仮名草子とは一線を画するものとし
今日では
浮世草子
と呼ぶ
(当時は
「草双紙」と呼ばれ
「仮名草子」
「浮世草子」
はのちになって区別された)
↓↑
元禄期
大坂を中心に流行し
民衆生活の幅広い主題を扱って
多くの作品が書かれた
(浮世には世間一般という意味と
色事、好色といった意味がある)
京都の八文字屋自笑から ...
↓↑
仮名草子
仮名草子(かなぞうし)
江戸時代初期に
仮名
もしくは
仮名交じり文で書かれた
近世文学における物語・散文作品の総称
↓↑
井原西鶴の
「好色一代男」
が出版された
天和二年(1682)頃を区切りとする
仮名を用いた
庶民向けの読み物として出版
雑多な分野を含む
中世文学と近世文学の
過渡期の散文を一括りにした呼称
↓↑
御伽草子(おとぎぞうし)
室町時代から江戸時代初期
に・・・・・似
かけて・・・掛け・縣け・書け・賭け・加計
欠け・駈け・駆け・描け・掻け
・・・カケ・・・
つくられた=造られた・創られた・作られた
ツクラレタ=通句等例多
(タ=拿・妥・太=タイ=他意)
短編の物語草子の総称
狭義には江戸時代中期に
大坂の
書肆が
「御伽文庫」
として刊行した
「文正草子・鉢かづき・唐糸草子・木幡狐
物くさ太郎・梵天国・猫のさうし・一寸法師
さいき・浦島太郎・酒呑童子」
など23編
広義の御伽草子は
約500編伝わる
鎌倉時代の物語の流れをひく
公家の
恋愛物
(忍音物語・若草物語)
継子物
(岩屋の草子・鉢かづき)
僧侶に関する
児物語
(秋の夜の長物語)
破戒僧の失敗談
(ささやき竹)
遁世・懺悔物の
(三人法師)
本地物
(熊野の本地)
武家の英雄伝説、怪物退治談
(義経関係の
御曹子島渡・浄瑠璃物語
頼光関係の
酒呑童子)
地方伝説、復讐談
(明石の三郎・あきみち)
庶民の立身成功談
(文正草子・物くさ太郎)
異国物
(楊貴妃物語・類至長者)
異類物
(鼠の草子・雀の発心
木幡狐・鴉鷺合戦物語)
など内容は多種多様
物語の衰退を受けて登場し
近世の小説のさきがけとなった・・・
↓↑
「草紙・草子・双紙・冊子(ソウシ)」
「さくし(冊子)」の音変化か・・・
漢籍・和本などで
紙を綴(と)じ合わせた形式の書物
綴じ本
物語・日記・歌書など
和文で記された書物の総称
御伽(おとぎ)草紙
草(くさ)双紙
など
絵入りの通俗的な読み物の総称
↓↑
ーーーーー
おとぎ‐ぞうし
ザウシ
御伽 草 子
↓↑
室町時代から江戸初期にかけて作られた
短編物語の総称
平安時代の
物語文学
から
仮名草子
に続くもので
空想的・教訓的な童話風の作品・・・
江戸中期
享保(1716~1736)ころ
大坂
渋川清右衛門
がそのうちの
23編を
「御伽文庫」と名づけて刊行・・・
「蘆刈説話・恨の介・熊野の本地・住吉物語
七夕伝説・奈良絵本・二十四孝
判官物・本地物・巡り物語」
↓↑ ↓↑
「読み書きそろばん(読み書き算盤)」より
…戦国時代に日本にきて
主として都市部で布教活動をした
キリシタン宣教師も
日本における児童の
読み書きの能力を高く評価している
またこの時代
町人層に広く読まれた
《御伽草子》には
九九を使った表現が多くみられ
九九の計算能力が普及していた
当時の計算は
一般的には
九九のような暗算が広く行われ
むずかしい計算には
算木や
十露盤(算盤・そろばん)
が使用されていた・・・
↓↑
ーーーーー
長=異体字は「镸・兏(厂上儿・厂ト兀)
・仧(上人・ト一人)」
長=匚+二+レ(丄・礀ノ・乚)+乂
簡体字は「长」
兀=はげる(禿げる)・たかい
コツ・ゴチ・ゲツ
一+丿(ヘツ・ヘチ)+乚(乙・Z)
初めの捌(経通・経訳)の乙(音)?
↓↑
髠=髪の毛を剃り落とす刑罰
正面から見た象形が而
兀=刖(ゲツ)・同音で足きりの刑
↓↑
傲兀(ゴウゴツ)
突兀(トッコツ)
↓↑
兀子(ゴシ・ゴッシ)=四角い四脚の腰掛け
宮廷の儀式用の椅子
腰掛
↓↑
兀兀(コツコツ)
兀然=コツゼン=忽然
兀立(コツリツ)
㐳・扤・阢・杌
髠=镸+彡+几(兀・一儿)
長=三+衣
長=镸=巨+ム
長=镸=厂+二+一+ム
↓↑ 「+三+ム
一+l+三+ム
=丄+三+ム
上+二+ム
镹=镸+久=镹(キュウ・ク)
肆=镸+聿=肆(シ・つらなる)
镾=镸+爾=镾(ビ・ミ・わ)
碭=金+長=碭(チョウ・するどい)
↓↑
八百長(やおちょう・ハピャクチョウ)
明治時代の八百屋の店主の
長兵衛は通称
「八百長」で
相撲の年寄
伊勢海五太夫
と碁仲間で
碁の実力は長兵衛が勝っていたが
商売上の打算で
ワザと負けたりし
勝敗を調整し
伊勢海五太夫
のご機嫌をとっていたが
発覚し
ワザと負けるコトを
相撲界では
「八百長」・・・と言う・・・
「八百長=人情相撲=インチキ」・・・
「インチキ(瞞着)・いんつく(福井弁)」
「こんちくしょう=此畜生」
「此畜生=こんこんちき=コンコン鳴く畜生狐
こんこんちきしょうめ
狐音畜生女」
「狐=きつね・コ
犭+瓜
異体字
瓠・瓡・葫」
声符「瓜」・瓜・呱・泒・觚・弧・柧・苽
孤・窊
声符「狐」
「いかさま=如何様」って?・・・
「詐欺的賭博」・・・
「相撲は
Entertainerのentertainmentだろう?
芸能人・人を喜ばせたり笑わせたりする人
(a person who tries to please or amuse)
エンターテイナー
エンターテナー
エンターテーナー」
「無気力相撲」と「人情相撲」とはチガウのッ?
勝負事で、前もって勝敗を打ち合わせ
うわべだけの真剣勝負すること
なれあいの勝負=八百長試合
なれあいで事を運ぶこと
「八百長=いんちき」
事前に示し合わせた通りに勝負をつけること
↓↑
長子=チョウシ=調子=チョウシ=銚子
養子=ヨウシ=陽子・・・単子・端子・分子
中間子
猪子(いのこ)
虎子(コシ)
獅子(シシ)
狼子(ロウシ)野心
豚児(トンジ)犬子(ケンシ)
王子
太子
銅鈸子
土拍子
孔子
孟子
荘子
朱子
旻子(アンシ)
瓶子(ビンシ)
緞子(ドンス)
格子(コウシ)
杓子(シャクシ)
光子
九子(くし)
公子
孝子
量子
孫子
天子
遺子
火子(カコ)
黒子(ほくろ・くろこ)
茄子(ナス)
胞子
菓子(カシ)
酉子(とりこ)
玉子(たまご)
加子=水主(加子=水夫)
遺伝子(イデンシ)
精子
卵子
愛子(まなこ)
石子(いしなご)
金子(キンス)
童子
弟子
案山子(かかし)
数の子(鯑)
数子(スウシ)
粒子
整流子
電子
太子
烏帽子(えぼし)
螺子(ねじ・捩子・捻子・螺旋・錑)
妻子
才子
楽羊啜子
蚊子咬牛
麟子鳳雛
矮子看戯
君子
仏子
千子
尼子(あシ)
帽子
ーーーーー
着=羊+ノ+目
ジャク・チャク
きせる・きる・つく・つける
䒑+十+一+ノ+目
䒑+十+丆+目
⺶+目
ーーーーー
疑=匕+矢+マ+乛+ト+人・・・擬音・擬態
↓↑
丆失矢午攵牛毎缶
↓↑
万=丆+フ
↓↑
不=丆+ト・・・丆
石=丆+口
↓↑
疋=ヒツ・ヒチ・ソ・ショ・ひき
乛+⺊+人・乛+ノ+上・乛+龰
両方の足の太腿から爪先までの部分
動物を数える言葉・匹(ひき)
正統な・由緒正しい・雅(優雅)
ひき・ひきへん
古くは「正」
𤴔=疋=𤴔
「乛」=「一」=「ワン」
「一・乙(L・弟=嗚訳得訳・音)」・・・龍宮(寓)城
「﹂・ノ▬(かみさし)」・・・「毎=﹂+毋」の上の漢字
了=おわる・さとる・レウ・リョウ
了=乛+亅・・・ア
↓↑
乙・乚・乛
乜・九・乞・也・习・乡・乢・乣・乤・乥
书・乧・乨・乩・乪・乫・乬・乭・乮・乯
买・乱・乲・乳・乴・乵・乶・乷・乸・乹
乺・乻・乼・乽・乾・乿・亀・亁・亂・亃
亄・亅・了・亇・予・争・亊・事・二・亍
于・亏・亐・云・互・亓・五・井・亖・亗
亘・亙・亚・些・亜・亝・亞・亟・亠・亡
亣・交・亥・亦・产・
ーーーーー
・・・亇=竹=チク・たけ
亇+亇
「𠄌」=ケツ=レ・𠄌
「亅」とは逆の「𠄌」字状
先端を曲げた鉤形
了=フ(乛)+亅=了
完結・終わる・終わり
はっきりしている
はっきりと分かる
明らかなさま
明瞭
全く、すっかり
漢字林(非部首部別)
「𠄎」=「乃(すなわち)」-「ノ(ヘツ)」
「乃=すなわち・これ・そこで・しかるに・かえって
さきに・もし」・・・???・・・
・・・声符
乃を声符とする漢字
仍、扔、艿、㭁、礽、䚮、鼐
草書体が平仮名の「の」
最初の払いが片仮名の「ノ」
乃往・乃翁・乃公・乃今
乃至・乃者・乃父・乃祖
ーーーーー
・・・???・・・
↧
December 16, 2017, 5:51 am
・・・12月15日・・・取り敢えず要塞(チャシ=砦・castle)のgorgeousなsinglebetのroomから「帰還」してきた・・・昨日の窓から眺望したピンネシリは雪の冠を載せて雄大・・・
![]()
![]()
![]()
fortressa stronghold
fortress
stronghold
fortifications
fortressa stronghold
forta fortressa strongholda
《mountain》 fastness
↓↑
隠し砦の三悪人
1958年(昭和33年)12月28日公開
黒澤明監督映画
↓↑
『スター・ウォーズ』
(1977=新版では
『エピソードIV/新たなる希望』)
のアイディアは、この映画を元にした・・・
ジョージ・ルーカス監督自らが回想・・・
↓↑
北海道(蝦夷地)に
526カ所の砦・・・砦=止+牝+石
石=一の口
(○・磐の欠片)
チャシコツ(チャシ跡)が確認
シャクシャインらが
和人と戦う中で多くの
チャシが築かれた
チャシ=砦
↓↑
1670年記録の
『寛文拾年狄蜂起集書』・・・
に
「シヤクシヤ在所を明け
チャシに
籠居申候て不参候」
↓↑
シャクシャインの在所が
明らかになり
茶志(チャシ)・・・・茶=艹+𠆢+十+八
に 志=十+一+心
籠(こ)もり居る・・・籠=竹+立+月+丂+匕+匕
龍=龙(簡体字)
竜(新字体・古字)
申しそうろうて
フサンそうろう・・・?
↓↑
ユーカラでは
チャシは英雄の住居、牢獄
チャシ
基本的には高い場所に築かれ
壕や崖などで周囲と切り離された施設
チャシへの登り口はチャシルと呼ばれ
チャシルは非常に傾斜がきつい
梯子を使わなければ入れないような
チャシコツも・・・
↓↑
1643年
オランダの商船
カストリクム号
が残した記録中の
チャシは
山の上に
人間の身長の1.5倍ほどの
柵を張り巡らしたもので
チャシルは
急峻な小径となっており
柵の内部には
2,3軒の住居が存在
↓↑
チャシの形状
分類
孤島式
平坦地
湖の中に孤立した
丘や
島を利用したもの
丘頂式
山や尾根の頂の部分を利用したもの
丘先式
突出した丘や岬の先端を利用したもの
面崖式
崖地の上に半円形の壕を築き
その内部をチャシとするもの
↓↑
341箇所のチャシ跡が確認
現在では500箇所以上のチャシ跡
北海道(日高支庁)
沙流郡の
平取町にある
二風谷遺跡のように
大規模な発掘や調査が行われた
チャシもある
↓↑
チャシには
北方ユーラシアの
ゴロディシチェ
や
カムチャツカ半島の
オストローフィ
との構造における
類似点がいくつか見出され
ゴロディシチェは
ユーラシア北部に広く分布する
砦の一種で
同様のものが
ラテン語では
oppidum
ドイツ語では
burg
英語では
borough、
hillfort
と呼ばれる
構造上チャシに最も近いのは
ブリテン島の
ヒルフォート
である・・・
チャシの関係は不詳
↓↑
茶志内(ちゃしない)
アイヌ語で「チャシ=砦」
↓↑
松浦武四郎
「丁巳日誌」に
「チヤシナイ
右の方小川。
此処にむかし
夷人の貴人有し処にて
チヤシは城の事也。
むかし
城の有しと云事」
「夷人の貴人有し処」を教示した
アイヌは
トックアイヌ
の
乙名(首長)
らである・・・
住んでいた時期、場所は不明
↓↑
茶志内(ちゃしない)駅
北海道
美唄市
茶志内町
北海道旅客鉄道(JR 北海道)
日本貨物鉄道(JR貨物)
函館本線の駅
JR北海道の
駅番号はA17
駅名の由来
アイヌ語の
「チャシ・ナイ(砦・川)」
だが
周囲に砦があった痕跡は不明
↓↑
サル
アイヌ語で湿原や泥炭地・葦原
サルの地名
沙流・斜里・猿払・サロベツ・佐呂間
長流川・サルキ
サルキ=アイヌ語で湿原に生えている葦
↓↑
ピンネ・シリ=賓根知・賓根山・・・賓音尻・敏音知
「ピンネ・シリ」=「男である・山」
マツネ・シリ=待根尻
「マツネ・シリ」=女である・山」
「月形」に
地勢根尻(チセ・ネ・シリ)山
賓根(ぴんね)山
が併記
「チセ・ネ・シリ=家・のような・山」
の意味
↓↑
ピンネシリ
北海道
樺戸郡
新十津川町
と
石狩郡
当別町
の境にある標高1,100.4mの山
北緯43度29分30.3秒
東経141度42分24.1秒
↓↑
周麿川=アイヌ語のシュマルプネプ
シュマ・ルプネ・プ
(石・ごろごろある・もの)
シュう・マル・プネ・プ
周 ○ 浮根=舟
プ=歩(赴・附・賦・夫・婦)
周麿川→周磨駅跡
天北線の駅の名標は
周磨(麻+石)
地名は
周麿(麻+呂)
北海道枝幸郡中頓別町字中頓別172-6
北海道
枝幸郡・・・枝(えだ・シ)の幸(さち・コウ)
中頓別町・・・中の頓(屯+頁)の別
↓↑ 屯=一+屮・匕+H・一乚H
トン・チュン
屯する(たむろする)・群れる
幼児の束ねた髪
巡査(警察官)が
とどまっている場所
駐在所・駐屯所
なやむ(悩)・苦しむ
易の六十四卦の一
険しくて行き悩む形
↓↑ ↓↑
1000kg(メートル法)
1016.1kg(ヤード・ポンド法)
907kg(米・ヤード・ポンド法)」
船舶の容積・軍艦の排水量の単位
約100立方フィート(約2831ℓ)
貨物の容積の単位
約40立方フィート(約1132ℓ)
↓↑
屯蹇(チュンケン)
屯営(トンエイ)
屯所(トンショ)
屯田兵(トンデンヘイ)
屯田(みた)
↓↑ 屯家=屯倉=みやけ
字
中頓別172-6
↓↑
中頓別(なか・とん・べつ)町
北海道の宗谷地方南部に位置する町
↓↑
頓別=アイヌ語トウンペッ(湖に入る川)
↓↑
「トー・ウン・ペッ=湖から・出る・川」
・・・「ウン」は「入る」か?「出る」か?・・・
↓↑
頓別川の中流に位置し
「中」が冠してある
↓↑
敏音知岳(ピンネシリ岳、703m)
中頓別町のシンボル
町の中央部に位置
アイヌ語「男山」
↓↑
北海道北部
宗谷支庁
枝幸(えさし)郡の町
北見山地北部の
ポロヌプリ山(839m)
敏音知(ぴんねしり)山(703m)
に囲まれ
中央を
頓別川が北流
市街地は
頓別川
支流の
兵知安(ぺいちあん)川
の合流付近
明治30年代の初めに
頓別川の上流に
砂金が発見され
砂金採りが多数入地したが
定住した者はほとんどいなかった
1913年
浜頓別からの開墾道路が伸び
人口が急増
↓↑
ピリカ ヌプリ
メナシ ヌプリ
アサト ヌプリ
ニセイアンヌプリ
ヌプリ=アイヌ語「山」
「場所・そこ・大地=シリ」
ピンネシリ
マツネシリ
ポロ シリ
アイヌ語「シリ(sir)」
地、大地、土地、島、所
山
水際のけわしい山
目に見えるかぎりの空間
昼夜
天候
気温
なぎ・・・
状況の感知、関知、観知、寒地、換地・・・?
seri-o-us
・・・「シリ-オ-ウス」です・・・Sirius
シリウス(Sirius)=大犬座の最も明るい恒星
地球上から見える最も明るい恒星
「おおいぬ座のα星
α-CMa=α Canis Majoris
セイリオス(Σείριος・Seirios)」
「天狼(ろう)星」
実視連星で、
伴星 シリウスBは
「子犬」ともいわれる
シリウスBは地球の3倍程度の大きさ
質量は太陽と同じくらいで
密度は太陽の10倍
古代エジプトで
「ナイルの星」
エジプト神話の
「ソティス」
シリウス星=太陽神ラーの妹
「ソティスはわが妹にして
明けの明星はわが子なり」
・・・・「ソティス」?
↓↑
・・・「蘇帝(綴)素」?
蘇定方(592年~667年)
隋-唐の軍人
660年(顕慶五)高宗
左武衛大将軍として新羅派遣
661年七月の
平壌討伐が失敗
662年二月撤退
名は烈
字は定方
諡は荘
本貫は「冀州武邑県」
紀州武勇懸?
↓↑
「ソティス」は
ナイルの洪水のはじまりを告げる星
太陽が昇る直前にあらわれる頃
ナイルの氾濫がはじまる
イシスの化身で
夏至のはじめの雨は
「イシスの涙雨」
「イシスの星」・・・石州?=イシス=医師国?
オリオン座のベテルギウス・・・
嗚理音 経照義宇蘇
うす=臼・碓・有珠・宇津・宇受=猿女)
こいぬ座のプロキオン・・・譜賂記音?
ともに、冬の大三角を形成
↓↑
ピンネシリ=賓根尻=賓根山
賓=宀+一+少(亅八ノ)+貝(目八)
ヒン・まろうど
大切に扱われる客
賓客・貴賓・迎賓・国賓・主賓・来賓
北海道
樺戸郡
月形町
北部
樺戸山地に位置
神居尻山・・・北海道石狩郡当別町
隈根尻山・・・北海道樺戸郡
月形町
浦臼町
石狩郡
当別町・・・・当てて別(捌・わけ)る
との境
樺戸三山の一
山頂から
待根山
神居尻山
を望むことができる
↓↑
砂川
アイヌ語の
オタウシナイ(砂の多い川)
空知
アイヌ語
ソーラップチ
ソー=滝
ラップチ=くだる
↓↑
奈井江
アイヌ語
ナヱ=砂多き川
北海道
空知郡
奈井江町
字
奈井江
11番地
北緯43度25分31.1秒
↓↑
太=「ブト」
アイヌ語
put(プトゥ)=河口
↓↑
1870年(明治二年)
伊達邦直
ナヱイ川
と
ナヱ川
両川口に標杭を立てる
↓↑
「ナエイ(naei・nae)=谷川
西岸高き川を
ナエイ
今、奈井江と云ふは誤る・・・「奈江井」が正解?
江の井戸(出戸・緯度・伊土)とは
奈何(如何・いかん)?
移管・医官・遺憾・偉観・異観
上川土人は
谷をナエと云ひ
川をナイと云ふ」
naye=その川
nay-e=川(沢・小川・谷川)-その
↓↑
吉田東伍
「大日本地名辞書」に
「奈井江(ないえ)」ではなく
「奈江井(なえい)」・・・?
と記録・・・?
・・・奈=一+人+二+亅+八
異体字=柰(正字)=十八示
㮈(俗字)=十八大示
十の八は一の人
二(ふたつ)の亅(かぎ)の八(やつ)
㮈の類字は捺・・・
捺印
押捺・・・手形・足形
![]()
![]()
![]()
↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑↓ ↑
「手形・足形」は縄文土器
北海道豊原4遺跡 土坑出土品
垣ノ島遺跡(かきのしまいせき)
北海道函館市に所在
縄文時代の遺跡
縄文時代早期前半(約9000年前)
の墓制
駒ヶ岳噴火による集落断絶
後期初頭の
盛土遺構~後期後半(約3500年前)
に至るまでの
縄文集落
北海道・北東北の
縄文遺跡群の一つ
精製土器の
漆塗りの注口土器
足形付土版
装飾品など20万点以上発掘
幼子の足形や手形をつけて焼いた
約6500年前の土版が
坑底から17枚出土
足形付土版は
東北地方~北海道
にかけて出土
↓↑
石川県かほく市・人面付土製品
沖中遺跡
縄文晩期・青森県三戸町
だっこする土偶(複製)宮田遺跡
縄文中期
八王子市・手形・足形土版
大石平遺跡
縄文 後期
青森県六ヶ所村
↓↑
奈=いかん・いかんせん
いかんぞ・なんぞ
疑問・反語の助字
奈辺=那辺
梵語・外国語の音訳に使用
奈落(ナラク)
加奈陀(カナダ)
片仮名の「ナ」
草書体の平仮名の「な」
ーーーーー
・・・???・・・
↧
December 17, 2017, 8:09 am
・・・2017-12-17・・・「デセンバー=十二月・De-cember・Dec=十番目の月」・・・「de-・・・=打ち消し・否定・逆・除去などを意味する動詞」・・・ラテン語「de-」 ・・・「DE=off(離れる)・down(下)」・・・「離れる」ことから「否定(デナイ=deny)」は知っているが・・・「デ=de」は「出=山+山」であるカナ・・・電話にデル(∂=出る・偏導函数)???・・・デかける・・・ダスって・・・
「拒絶(デクリン=de-cline)」、「強意(a great de-al)・デール=de-al=分配する・分ける・配る・処理する・扱う」・・・
「詳細(de-tails)・デティール」・・・
「旅立ち(デパァチャー・de-parture)」・・・
「de-vice=装置・考案物・からくり・意匠・工夫・手段・方法・a safety device=安全装置」・・・
「デヴィス=出葉意素・出羽夷州」って?・・・
「旨い(デリシャス=de-licious)」・・・唾が出るか?
「De-cember=デセンバァ=出船場吾(五+口)」
「出船場阿(阝+可)」
「出戦場拳(𠔉+手)」・・・
「あげる・あがる(上・揚・挙・騰)」・・・
「拳(𠔉+手)=あげる・かかげる・こぶし・ケン= fist(フィスト)・knuckle up」・・・
「拳大の石=a stone the size of one's fist(フィスト)」・・・
「アゲル」は「与える」でもあるけれど・・・
「ヤる」って?・・・「何をクレるの?」
「フィスト=附意素訳」・・・???
↓↑
De-termining(~を決心する、決意する・決める)
de-cide
de-vices(装置・手段・方法)
detective(探偵)
de-tect(に…を見つける、看破する・発見する・検出する
de-tect hypocrisy(偽善を見破る)
ーーーーー
三月=March・Mar
四月=April・Apr
五月=May・
六月=June・Jun
七月=July・Jul
八月=August・Aug
九月=September・Sept
十月=October・Oct
十一月=November・Nov
十二月=December・Dec・・・十番目の月
↓↑
一月=January・Jan・・・・ 十一番目の月
二月=February・Feb・・・・十二番目の月
ーーーーー
・・・「獻(虍+鬲+犬)=ケン=献(南+犬)」・・・
「獻=物を煮る意と音とを示す鬳(ケン)と犬(ケン)から成り、 もと「羮(あつもの)」にして「神に捧げる犬」の意を表わし、「たてまつる」の意になった・・・「鬳=南=あつい」・・・
会意兼形声文字「獻(鬳+犬)」
「頭部が虎の形をした甑(こしき)」の象形
「耳を立てた犬」の象形
(「甑(こしき)に血を塗るためのいけにえの犬」)
(「虎の模様がある煮炊きの用具=甑(こしき)」)
「鬲(かなえ・レキ)=古代中国で用いられた三足の器
足は中空、煮炊きに用いた」
「融=鬲+虫=とける・ユウ」・・・「融合・核融合」
ーーーーー
2017年 丁酉(庚・ ・辛)
0012月 壬子(壬・ ・癸)
0017日 戊寅(己・丙・甲)
ーーーーー
宇宙サテライト(satellite)戦争(war)
衛星間戦争・・・
↓↑
衛星(natural satellite)
惑星や準惑星・小惑星の周りを
公転する天然の天体
↓↑
satellite(サテライト)
衛星・人工衛星
大規模な空港の主ターミナルから
通路を伸ばして設けた補助ターミナル
↓↑
サテライトウイルス
(satellite virus)
増殖するために
他のウイルスの存在を必要とするウイルス
D型肝炎ウイルスなど
衛星ウイルス・欠損ウイルス
サテライトオフィス(satellite office)
都市周辺部に設置され
都市部にある本社と連携
↓↑
本体から離れて存在するもの
の比喩
衛星・人工衛星・衛星国・衛星雄
サテライトDNA
ゲノムDNAの中にある反復配列の一種
他のウイルスと共存することで
感染・増殖する
(ウイルスに寄生する)
性質を持つウイルス(サテライトウイルス)
または
核酸(サテライト核酸)のこと
↓↑
衛星、惑星の周りを公転する天体
人工衛星、放送衛星、通信衛星
「本体から離れて存在するもの」の比喩
ーーーーー
シリ ヲ ウス・・・尻を刺し貫いた「倭男具那」→日本建
『日本書紀』
『先代旧事本紀』
本の名は「小碓尊(おうすのみこと)
小碓王(おうすのみこ)」
亦の名は「日本童男(やまとおぐな)
後の名は「日本武尊(やまとたけるのみこと)
日本武皇子(やまとたけるのみこ)」
『古事記』
本の名は「小碓命(おうすのみこと)」
亦の名は「倭男具那命(やまとおぐなのみこと)
倭男具那王(やまとおぐなのみこ)」
後の名は「倭建命(やまとたけるのみこと)
倭建御子(やまとたけるのみこ)」
「ヲウス(小碓)」
『日本書紀』
双子(大碓命・小碓尊)として生まれた
景行天皇が怪しんで
「臼(キュウ)=うす=碓(タイ)」
に向かって叫んだことによる
「ヲグナ(童男=男具那)」=未婚の男子
「ヤマトタケル」の名称は
↓↑
↓↑
ヤマトタケル(?~景行天皇四十三年)
日本武尊(日本書紀)
倭建命(古事記)
第十二代
景行天皇の皇子
第十四代
仲哀天皇の父
熊襲征討
東国征討
オウスノミコト (小碓命)
西方の熊襲征伐で
童女に扮して
川上梟帥 (かわかみの たける)
を討つ
そのとき
梟帥が、
日本建の名を献上
↓↑
天皇詔小碓命
「何汝兄於朝夕之大御食不參出來、
專汝泥疑教覺。(泥疑二字以音)、下效此」
如此詔以後、至于五日、猶不參出。
爾
天皇問賜小碓命
「何汝兄久不參出。
若有未誨乎」
答白
「既爲泥疑也。」
又詔
「如何泥疑之。」
答白
「朝署入廁之時、
待捕、搤批而、
引闕其枝、
裹薦投棄」
↓↑
爾
臨其樂日、
如
童女之髮、
梳垂其結御髮、
服其姨之御衣御裳、
既成
童女之姿、
交立女人之中、入坐其室內。
爾
熊曾建兄弟二人、
見感其孃子、
坐於己中而盛樂。
故臨其酣時、
自懷出劒、
取
熊曾之衣衿、
以劒
自其
胸刺通之時、
其弟
建、
見畏逃出。
乃追、
至其室之椅本、
取其背皮、
劒
自
尻刺通。・・・尻(しり)を
刺(さ)し
通(とう)す
↓↑
爾其
熊曾建
白言
「莫動其刀、
僕有白言」
爾暫許、押伏。
於是白言
「汝命者誰」
爾詔
「吾者
坐
纒向之日代宮、
所知大八嶋國、
大帶日子淤斯呂和氣天皇之御子、
名
倭男具那王者也。
意禮
熊曾建二人、
不伏
無禮聞看而、
取殺意禮詔而遣」
爾其
熊曾建白
「信、然也。
於西方、
除
吾二人
無
建強人。・・・・建強の人→腱弱の人=アキレス
然於
大倭國、
?
吾二人而、
建男者坐祁理。
是以、
吾
獻御名。・・・ 獻御名=献御名
獻(虍鬲犬)=献(南犬)
鬳=南
会意兼形声文字です(鬳+犬)
「頭部が虎の形をした、甑(こしき)」の象形
「耳 を立てた犬」の象形
「甑(こしき)に血を塗るためのいけにえの犬」
「神聖化された甑(こしき)を意味=神に物を捧げる」
自今以後、
應稱
倭建御子」・・・倭(やまと)
建(たける)
御子(みこ・オンシ)
是事白訖、
卽
如
熟苽・・・・・・・熟苽
振折・・・・・・・振折(ふりわる)
而殺也。
故、
自其時稱御名、
謂
倭建命。
然而還上之時、
山藭・河藭
及
穴戸藭、
皆言向和而參上。
ーーーーー
↓↑
「川上梟帥(熊曾建)」・・・川上「梟帥」
↓↑ 熊襲(くまそ)=古事記に「熊曾」
筑前国風土記に「球磨囎唹」
梟=母鳥を食らう不孝の鳥
夏至に梟のあつものを
百官に賜う儀式があった
梟(キョウ・ふくろう)=鳥+木
梟を木に磔る意
鳥の頭が木の上にある
フクロウは
餌を木の枝に刺す
↓↑ Minerva(ミネルバ)=アテネの聖なる鳥
から捧げられた名・・・?
「尊」は皇位継承者・・・
『日本書紀』で表記
乎訳得訳(弟)の「小碓」は阿仁(兄)の「大碓」を本当に殺したのか?
何故、父親の「景行天皇」は「小碓」を怖れていたのか?
何故、子供の
仲哀天皇は
神功皇后
と
武内宿禰
に殺されたのか・・・?
ーー↓↑ーー
仲哀天皇
成務天皇十八年?~仲哀天皇九年二月六日
第十四代天皇
在位
仲哀天皇元年一月十一日~同九年二月六日
父親は
日本武尊(命)の次男
皇后は
三韓征伐の
神功皇后
子供は
応神天皇
熊襲を討とうとしたが
橿日宮で
崩御
和風諡号は
足仲彦天皇
(たらしなかつひこのすめらみこと)
帯中日子天皇(古事記)
日本武尊(やまとたけるのみこと)の
第二王子
皇后は
気長足姫(おきながたらしひめ)
神功(じんぐう)皇后
↓↑
日本武尊の
第二王子
母はフタジイリヒメノミコト
皇后はオキナガタラシヒメノミコト
神功皇后
熊襲を討つため
皇后とともに筑紫に行幸し
死没
足仲彦尊
(たらしなかつひこのみこと)
成務天皇七年 ~ 仲哀天皇九年
52歳
↓↑
母=両道入姫(ふたじのいりひめ
垂仁天皇 皇女)
皇后=気長足姫尊
(おきながたらしひめのみこと・神功皇后)
皇子皇女
誉田別 皇子(ほむたわけのおうじ・応神天皇)
籠坂(かごさか)皇子
誉屋別(ほむやわけ)皇子
宮=角鹿笥飯宮
(つぬげのけひのみや・敦賀)
→ 徳勒津宮(ところつのみや・南海道)
→ 穴戸
↓↑
足仲彦天皇(たらしなかつひこのすめらみこと)
帯中日子天皇(古事記)
「タラシヒコ」
の称号は
12代景行
13代成務
14代仲哀
7世紀 前半に在位した
34代舒明
35代皇極
両天皇が同じ称号
↓↑
叔父の
成務天皇に嗣子が無く即位
日本武尊の第二子
母は垂仁天皇の皇女・両道入姫命
皇后は神功皇后
仲哀天皇(148年~200年3月8日)
第14代天皇
日本武尊の実子
在位=192年2月11日~200年3月8日
ーー↓↑ーー
seri-o-us
・・・「シリ-オ-ウス」・・・Sirius
シリウス(Sirius)=大犬座の最も明るい恒星
地球上から見える最も明るい恒星
「おおいぬ座のα星
α-CMa=α Canis Majoris
セイリオス(Σείριος・Seirios)」
「天狼(ろう)星」
実視連星で、
伴星 シリウスBは
「子犬」ともいわれる
シリウスBは地球の3倍程度の大きさ
質量は太陽と同じくらいで
密度は太陽の10倍
古代エジプトで
「ナイルの星」
エジプト神話の
「ソティス」
シリウス星=太陽神ラーの妹
「ソティスはわが妹にして
明けの明星はわが子なり」
↓↑
・・・・「サティス・シティス・スティス・セティス」
査定 数・指定 素・州綴 素・施渟 州
「子弟=師弟=姉弟=私邸=支弟=視程」
・・・・「ソティス」?
↓↑
・・・「蘇帝(綴)素」?
↓↑
蘇定方(592年~667年)
隋-唐の軍人
660年(顕慶五)高宗
左武衛大将軍として新羅派遣
661年七月の
平壌討伐が失敗
662年二月撤退
名は烈
字は定方
諡は荘
本貫は「冀州武邑県」
紀州武勇懸?
656年
程知節に従って前軍総管
阿史那賀魯を攻撃
鷹娑川で
阿史那賀魯が2万騎で対陣
定方は総管の
蘇海政
とともに連戦したが
決着つかず
突厥の別部の
鼠尼施らが2万騎を率いて
敵方に来援
定方は騎兵の精鋭500を率い
山嶺を越えて敵陣に討ち入り戦勝
657年
伊麗道行軍大総管
再度、
阿史那賀魯を攻撃
阿史那賀魯と
処木昆の
屈律啜の数百騎は西方に逃走
阿史那賀魯が油断し狩猟の最中に
定方は襲撃して破った
阿史那賀魯はさらに
石国に逃れた
阿史那弥射の子の
阿史那元爽が
蕭嗣業と合流し
阿史那賀魯を捕縛
定方は
左驍衛大将軍に任ぜられ
邢国公に封ぜられた
子の
蘇慶節も
武邑県公に封ぜられた
↓↑
659年
思結闕俟斤都曼が
疏勒・朱倶波・渇槃陀
の三カ国を煽って唐に叛乱
定方は安撫大使となって討伐
葉葉水にいたり
都曼
が馬頭川を守ると
定方は歩兵の精鋭1万と騎兵3000を選抜し
昼夜分かたず
三百里を駆け抜け
都曼の陣の前に現れ
都曼は驚いて戦うこともなく城に逃げ込んだ
唐軍がこれを攻めたて
都曼は窮迫し
自らを縛って降伏
定方が捕虜を
乾陽殿に献上
邢州
鉅鹿の
三百戸の
食邑を加えられ
左武衛大将軍
↓↑
660年
熊津道大総管
軍を率いて百済の征討
城山から海をわたって
熊津口に上陸
沿岸の百済軍を撃破
真都城に進軍
百済の主力と決戦勝利
百済王
義慈
太子の
隆は北方に逃走
定方が
泗沘城を包囲
義慈の子の
泰が自立して王を称し
泰は抗戦を続けようとしたが
義慈は開門して
降伏
百済の将軍の
禰植
と
義慈は唐軍に降り
泰も捕らえられ
百済は平定
百済王
義慈
隆
泰
らは
東都洛陽に送られた
↓↑
定方は三カ国を滅ぼし
子の
蘇慶節は
尚輦奉御の位を加えられ
定方は
遼東道行軍大総管
平壌道行軍大総管に転じた
高句麗の軍を
浿江で破り
馬邑山の敵営を落とし
平壌包囲
大雪に遭って
包囲を解いて帰還
涼州安集大使に任ぜられ
吐蕃
や
吐谷渾とも戦った
667年
76歳で死去
左驍衛大将軍・幽州都督の位を追贈
諡を荘
ーーーーー
↓↑
「ソティス」は
ナイルの洪水のはじまりを告げる星
太陽が昇る直前にあらわれる頃
ナイルの氾濫がはじまる
イシスの化身で
夏至のはじめの雨は
「イシスの涙雨」
「イシスの星」・・・石州?=イシス=医師国?
オリオン座のベテルギウス・・・
嗚理音 経照義宇蘇
うす=臼・碓・有珠・宇津・宇受=猿女
こいぬ座のプロキオン・・・譜賂記音?
ともに、冬の大三角を形成
ーーーーー
屯蹇(チュンケン)=なやむ・なやみ苦しむ
↓↑=あしなえ
足が悪く、自由に動かないこと
なえぐ
蹇歩(ケンポ)
おごる・たかぶる・おごり高ぶるさま
かたい・強い・正直
蹇諤(ケンガク)
まがる・くねくねと曲がるさま
かたくな・素直でない・とどこおる
とどまる・とまる・ゆきなやむ
蹇滞(ケンタイ)
まがる・くねくね曲がるさま
易(エキ)の六十四卦の一
あしなえ・足が自由に動かないこと・なえぐ
「蹇歩=ヤマトタケル=倭武・日本健
↓↑ ↓↑
西園八校尉(サイエンハッコウイ)
中国の後漢末期
中平五年(188年)
に置かれた官職の総称
また
西園三軍
皇帝直属の部隊
「西園軍」を創設し
「西園軍」を率いる人物として
霊帝に寵愛された
蹇碩
(『三国志演義』では十常侍の一人)
袁紹
鮑鴻
の3名を中心にすえた
↓↑
8月
「西園軍」が設置された
10月
平楽観(宮殿の西側、西園にある演場)
で閲兵式
霊帝
自らが出席し
甲冑を身に纏って騎乗
自らを
「無上将軍」と称した
その横に
何進
が控え
「西園八校尉」が任命
↓↑
『後漢書
(何進伝)』
上軍校尉 ― 蹇碩(小黄門)
中軍校尉 ― 袁紹(虎賁中郎将)
下軍校尉 ― 鮑鴻(屯騎都尉)
典軍校尉 ― 曹操(議郎)
助軍校尉 ― 趙融
佐軍校尉 ― 淳于瓊
その他、左右校尉があった
↓↑
『山陽公載記』
上軍校尉 ― 蹇碩(小黄門)
中軍校尉 ― 袁紹(虎賁中郎将)
下軍校尉 ― 鮑鴻(屯騎校尉)
典軍校尉 ― 曹操(議郎)
助軍左校尉 ― 趙融
助軍右校尉 ― 馮芳
左校尉 ― 夏牟(諫議大夫)
右校尉 ― 淳于瓊
↓↑
中平(チュウヘイ)
後漢の
霊帝
劉宏の治世に行われた
四番目の元号
184年~189年
中平六年四月
少帝劉弁が即位し
改元されて
光熹元年とされたが
八月
昭寧と改められ
九月
献帝
劉協が即位し
永漢に改められた
十二月
光熹・昭寧・永漢
の三号は除かれ
再び
中平六年に戻された
↓↑
元年二月・黄巾の乱
元年三月・党人の禁錮を解く
盧植・皇甫嵩を
黄巾賊討伐に派遣
元年十一月・黄巾の乱を一旦鎮圧
元年十二月・光和七年を中平元年と改元
六年四月・霊帝崩御
少帝
劉弁が即位
何太后が朝に臨む
六年八月・大将軍何進が宦官に殺される
袁紹が
兵を率いて宮中の宦官を誅殺
并州牧の
董卓が兵を率いて洛陽に入る
六年九月・董卓
少帝を廃し
献帝
劉協を立て
何太后を毒殺
六年十一月・董卓
相国となる
↓↑
中平 元年 2年 3年 4年 5年 6年
西暦184年 185年 186年 187年 188年 189年
干支 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳
↓↑
2月節分前は
183年
癸亥年
001月
甲子
001日
丁丑日
ーーーーー
・・・???・・・「出る」の「考察=コウサツ=絞殺・高察・高札」・・・
↧
↧
December 18, 2017, 8:39 am
・・・十二月18日=on the 18th of December・・・デ、デデデデッ・・・ディォ~、イデ、デ、ィデテ、ィデデォィォ~・・・「バナナ・ボート」・・・?・・・「オンミサタリマンタリリバナナ」・・・「ハリー・ベラホンテ」・・・「バナナ・ボート・ソング(Banana Boat Song)・デイ・オー(Day-O)・ジャマイカの民謡」・・・・「banana boat,water sled」・・・
ベラホンテ
https://www.youtube.com/watch?v=c1PkhHnr5dQ
浜村美智子
Michiko Hamamura (浜村美智子)
The banana boat song (バナナボート) - 1957
https://www.youtube.com/watch?v=p6SDhDYvoQQ
美空ひばり
バナナ・ボート Hibari Misora Banana Boat Song
https://www.youtube.com/watch?v=sQIpfPqunNg
ーーーーー
on December 18th=on 18 December
=on the 18th of December
12月18日に
十二月18日=on the 18th of December
十番目の月の十八の日
ディッセンバー=December・Dec
ディセンバー
「師走=しわす・しはす=師馳
史話蘇・詩話素・志和守
臘数
極月(きわまりづき
ゴクゲつ=語句解通
ゴクづき)
神(かみ)
「古代ギリシア語=Θεός・テオス
ラテン 語=deus・Deus・デウス
英 語=多神教の神々は小文字の
god・gods
or
deity・deities
デミウルゴス(デーミウールゴス
古希:Δημιουργός
英語:Demiurge
プラトンの著書のタイトル
「ティマイオス(Timaeus)は
人物名
ロクリスの哲学者」
「自然」が副題
これに記録された
世界の創造者
「デミウルゴス(δημιουργός)の
原義は工匠、建築家で
イデアを見て、模倣しながら
現実界(物質世界)を作る存在として
デミウルゴスの名を挙げて
善なる存在と捉えられている
現実界は
デミウルゴスが創造した
イデアの似姿(エイコーン)・・・?
↓↑
「春秋左氏伝・荘公三十二年」
漢字の「神」の初出
「神」=天文をコントロールし
耕地を与える技術を持ってい
聡明で正直な呪術師
神=人間で農業指導者として
農事暦に天文や気象の周期と
作物の関係を記録し
種まきの時期を選び
食物を計画的に
収穫・備蓄し
人を動員し
興亡を左右した人間のこと・・・
↓↑ ↓↑
神=示+申・・・モウゼ=申命記
↓↑
邪馬台国
女王
卑彌呼(?~247 or 248年)
・・・彌=弥・・・弥栄(いやさか)
爾=尓=ノ一+亅+八
なんじ・しかり
238年
魏の皇帝
曹叡から
「親魏倭王」
「銅鏡」
を賜う
↓↑
入り込む・要り込む・炒り込む
イリ混む・・・
イリ川(Ile, Ili,
ウイグル語:カザフ語
Іле, İle,
ロシア語
Или
モンゴル語
Ил,
シベ語
Ili bira)
は、中華人民共和国の
新疆ウイグル自治区の
北部の
イリ・カザフ自治州から
カザフスタン南西部の
アルマトイ州にかけて流れる川
イリ地方=中央アジアの中央部
イリ川畔の地域
イリ渓谷・イリ河谷・イリ盆地
などとも
新疆ウイグル自治区の北部の
イリ・カザフ自治州から
カザフスタン南西部の
アルマトイ州にかけて流れる川
天山山脈が源
西に流れ
バルハシ湖に注ぐ
河口には巨大な三角州
流域のイリ地方では
烏孫
チャガタイ・ハン国
ジュンガル
など遊牧国家が興亡
![]()
ーーーーー
イル=ハン国
モンゴル帝国(1206~1634)
初代皇帝チンギス=ハン(1162~1227)
の孫
チンギスの四男
トゥルイ(1192~1232)の
五番目の子
フラグ(フレグ・1218~1265)
第4代モンゴル皇帝
モンケ=ハン(憲宗・帝位1251~1259・
トゥルイの長男で
フラグの長兄)
西アジア一帯の征服(1253)
バトゥ(1207~1255)
のヨーロッパ遠征(1236~1242)に続く
遠征を実行
イル・ハン国
イランのモンゴル王朝(1256~1353)
代々の王が
「イル・ハン(トルコ語・国の王)」
の称号をとった
1253年
モンケ・ハンの命により
その弟
フラグ(旭烈兀)
在位1256~1265)
は遠征軍を率いてイランに遠征
↓↑
「イル=イリ=王」・・・?
「イル (il)=中東神話の神
イル川 (フランス・Ill)
イル川 (オーストリア・Ill)
ラ・イル (La Hire・フランス語の姓
「イル(il)」=イタリア語
男性名詞につく定冠詞(the)
「イル(ill)」=病
「イル(île,ile)」=フランス語の島・区・領域
ーーーーー
和風諡号で「イリ」「ネコ」「ワケ」の三種類
↓↑
第10代崇神~第19代允恭
天皇の和風諡号
↓↑
(第10代)ミマキ-イリ-ヒコイニエ
御間城-入 -彦五十瓊殖
御肇国天皇
( みくにしらずてんのう)
(第11代)イクメ-イリ-ヒコイサチ
活 目-入 -彦五十狭茅
(第12代)オオ-タラシ-ヒコオシロ-ワケ
大 -足 -彦 忍代 -別
(第13代)ワカ-タラシ-ヒコ
稚 -足 -彦
(第14代)タラシ-ナカツヒコ
足 -仲 彦
(第15代)ホムダ-ワケ
誉 田-分
(第16代)オオサザキ
大 鷦鷯
(第17代)オオエノイザホ-ワケ
大 兄 去来穂-分
(第18代)タジヒノミズハ-ワケ
多遅比 瑞 歯-分
(第19代)オアサツマ-ワク-ゴノスクネ
押朝 津間-稚 -子 宿 禰
ネコ1世(Necho I、? - 紀元前664年)はエジプト第26王朝の祖となったサイスの王ないし統治者(在位: 紀元前672年 - 前664年)
ネコ2世(Necho II)はエジプト第26王朝のファラオ(在位: 紀元前610年 - 前595年)
ネコというのは古代ギリシャ読みで、
正確には
ネカウ(Nekau)
別の読みに
ネクタネボ。プサムテク1世の子
紀元前609年、滅亡寸前のアッシリアの残存政権を支援遠征
古代エジプト語で「猫=マウ」・・・
ーーーーー
第一代
神武天皇
(じんむてんのう)
神 大和 磐 余彦 尊
(かむやまといわれひこのみこと)
始馭天下之 天 皇
(はつくにしらすてんのう)
第二代
綏靖天皇
(すいぜいてんのう)
神 渟名川 耳 尊
(かむぬなかわみみのみこと)
第三代
安寧天皇
(あんねいてんのう)
磯城津彦 玉 手看 尊
(しきつひこたまでみのみこと)
第四代
懿徳天皇
(いとくてんのう)
大 日本 彦 耜 友 尊
(おおやまとひこすきとものみこと)
第五代
孝昭天皇
(こうしょうてんのう)
観松 彦 香殖 稲 尊
(みまつひこかえしねのみこと)
第六代
孝安天皇
(こうあんてんのう)
日本 足 彦国 押 人 尊
(やまとたらしひこくにおしひとのみこと)
第七代
孝霊天皇
(こうれいてんのう)
大 日本 根子彦 太 瓊 尊
(おおやまとねこひこふとにのみこと)・・・ネコ1
第八代
孝元天皇
(こうげんてんのう)
大 日本 根子彦 国 牽 尊
(おおやまとねこひこくにくるのみこと)・・・ネコ2
第九代
開化天皇
(かいかてんのう)
稚 日本 根子彦 大 日日 尊
(わかやまとねこひこおおひひのみこと)・・・ネコ3
第十代
崇神天皇
(すじんてんのう)
御間城入 彦 五十瓊殖尊
(みまきいりびこいにえのみこと)
御肇国天皇
(みくにしらずてんのう)
第十一代
垂仁天皇
(すいにんてんのう)
活 目入 彦 五十狭茅尊
(いくめいりひこいさちのみこと)
第十二代
景行天皇
(けいこうてんのう)
大 足 彦 忍代 別 尊
(おおたらしひこおしろわけのみこと)
第十三代
成務天皇
(せいむてんのう)
稚 足 彦 尊
(わかたらしひこのみこと)
第十四代
仲哀天皇
(ちゅうあいてんのう)
足 仲 彦 尊
(たらしなかつひこのみこと)
第十五代
応神天皇
(おうじんてんのう)
誉 田分 尊
(ほんだわけのみこと)
胎 中 天 皇
(だいなかつてんのう)
第十六代
仁徳天皇
(にんとくてんのう)
大 鷦鷯 尊
(おおさざきのみこと)
難 波天 皇
(なんばてんのう)
第十七代
履中天皇
(りちゅうてんのう)
大 兄 去来穂分 尊
(おおえのいざほわけのみこと)
第十八代
反正天皇
(はんぜいてんのう)
多遅比 瑞 歯分 尊
(たじひのみずはわけのみこと)
第十九代
允恭天皇
(いんきょうてんのう)
押朝 津間稚 子 宿 禰 尊
(おあさずまわくごのすくねのみこと)
第二十代
安康天皇
(あんこうてんのう)
穴 穂 尊
(あなほのみこと)
第廿一代
雄略天皇
(ゆうりゃくてんのう)
大 泊 瀬幼 武 尊
(おおはっせわかたけるのみこと)
第廿二代
清寧天皇
(せいねいてんのう)
白 髪武 廣 國 推 稚 日本 根子 尊
(しらがたけひろくにおしわかやまとねこのみこと)・・・ネコ4
第廿三代
顕宗天皇
(けんそうてんのう)
弘計 尊
(おけのみこと)
第廿四代
仁賢天皇
(にんけんてんのう)
億計 尊
(おけのみこと)
第廿五代
武烈天皇
(ぶれつてんのう)
小泊 瀬稚 鷦鷯 尊
(おはっせわかさざきのみこと)
第廿六代
継体天皇
(けいたいてんのう)
男大迹 王
(おおどののおおきみ)
第廿七代
安閑天皇
(あんかんてんのう)
勾 大兄 廣 國 押 武 金 日 尊
(まがりのおおひねひろくにおしたけかなひのみこと)
第廿八代
宣化天皇
(せんかてんのう)
武 小廣 國 押 盾 尊
(たけおひろくにおしたてのみこと)
檜 前天皇
(ひのくまてんのう)
第廿九代
欽明天皇
(きんめいてんのう)
天 國 排 開 廣 庭 尊
(あめくにおしはるきひろにわのみこと)
志帰島 天 皇
(しきしまてんのう)
第三十代
敏達天皇
(びだつてんのう)
訳語田 渟中倉 太 珠 敷 尊
(おさだのぬなくらふとたましきのみこと)
他田天皇
(ただてんのう)
第卅一代
用明天皇
(ようめいてんのう)
大兄(おおえ)
橘 豊 日 尊
(たちばなのとよひのみこと)
池辺天皇
(いけべてんのう)
第卅二代
崇峻天皇
(すしゅんてんのう)
泊 瀬部
(はつせべ)
長 谷部 若 雀 尊
(はつせべのわかさざぎのみこと)
倉橋天皇
(くらはしてんのう)
第卅三代
推古天皇
(すいこてんのう)
額田部(ぬかたべ)
豊 御食炊 屋姫 尊
(とよみけかしぎやひめのみこと)
小治田天皇
(こじたてんのう)
第卅四代
舒明天皇
(じょめいてんのう)
田村
(たむら)
息 長 足 日廣 額 尊
(おきながたらしひひろぬかのみこと)
高市天皇
(たかいちてんのう)
岡本天皇
(おかもとてんのう)
第卅五代
皇極天皇
(こうぎょくてんのう)
寶
(たから)
天 豊 財 重 日足 姫 尊
(あまとよたからいかしひたらしひめのみこと)
飛鳥天皇
(あすかてんのう)
後岡本天皇
(ごおかもとてんのう)
第卅六代
孝徳天皇
(こうとくてんのう)
軽(かる)
天 萬 豊 日 尊
(あまよろずとよひのみこと)
第卅七代
斉明天皇
(さいめいてんのう)
皇極天皇に同じ(重祚)
第卅八代
天智天皇
(てんぢてんのう)
葛城(かつらぎ)
中 大 兄
(なかのおおえ)
天 命 開 別 尊
(あめみことはるわけのみこと)
近江天皇
(おうみてんの)
第卅九代
弘文天皇
(こうぶんてんのう)
大友(おおとも)
伊賀(いが)
第四十代
天武天皇
(てんむてんのう)
大 海 人
(おおあまと)
天 渟中 原 瀛 真人 尊
(あまのなかはらおきのまひとのみこと)
浄 御原 天 皇
(じょうおはらてんのう)
第四十一代
持統天皇
(じとうてんのう)
鸕野讃 良
(うのささら)
大 倭 根子天 之廣 野目女 尊
(おおやまとねこあめのひろのひめのみこと)
藤 原 宮 御宇天 皇
(ふじわらのみやおうてんのう)
岡 宮 天 皇
(おかみやてんのう)
草 壁 皇子
(くさかべのみこ)
長 岡 天 皇
(ながおかてんのう)
岡宮天皇に同じ
第四十二代
文武天皇
(もんむてんのう)
珂瑠
(かる)
倭 根子豊 祖父 天 皇
(やまとねことよおおじてんのう)・・・ネコ5
後藤 原 宮 御宇天 皇
(ごふじわらのみやおうてんのう)
第四十三代
元 明 天 皇
(げんめいてんのう)
阿閇
(あべ)
崇道 尽 敬 天 皇
崇道 尽 敬 皇 帝
(すどうじんけいてんのう)
舎人親王
(とねりのみこ)
日本 根子天 津御代 豊 國 成 姫 天 皇
(やまとねこあまつみしろとよくになりひめてんのう)・・・ネコ6
第四十四代
元 正 天 皇
(げんしょうてんのう)
氷高
(ひだか)
日本 根子高 瑞 浄 足 姫 天 皇
(やまとねこたかみずきよたらしひめてんのう)・・・ネコ7
第四十五代
聖武天皇
(しょうむてんのう)
首
(おびと)
天 璽 國 押 開 豊 桜 彦 尊
(あめしるしくにおしはるきとよさくらひこのみこと)
勝 寶 感 神 聖 武 皇 帝
(しょうほうかんしんしょうむのこうてい)
第四十六代
孝 謙 天 皇
(こうけんてんのう)
阿部
(あべ)
高 野 姫
(こうやのひめ)
法号
法 基 尼
(ほうきのあまぎみ)
寶 子 称 徳 孝 謙 天 皇
寶 子 称 徳 孝 謙 皇 帝
(ほうしのしょうとくこうけんてんのう)
第四十七代
淳 仁 天 皇
(じゅんにんてんのう)
大 炊
(おおい)
淡 路帝
淡 路廃帝
(あわじてい)
第四十八代
称 徳 天 皇
(しょうとくてんのう)
孝謙天皇に同じ(重祚)
春 日 宮 天 皇
(かすがのみやてんのう)
施基 皇 子
(しきのおうじ)
田原 天 皇
(たはらてんのう)
第四十九代
光 仁 天 皇
(こうにんてんのう)
白 壁
(しらかべ)
天 宗 高 紹 天 皇
(あまむねたかつぎてんのう)
後田原 天 皇
(ごたはらてんのう)
崇道 天 皇
(すどうてんのう)
早 良親 王
(さわらしんのう)
第五十代
桓武天皇
(かんむてんのう)
山部
(やまべ・サンブ)・・・「サン=纂・簒」部・・・
日本 根子皇 統 弥 照 尊
(やまとねこあまつひつぎいやてらすのみこと)・・・ネコ8
柏 原 天 皇
(かしわばらてんのう)
第五十一代
平 城 天 皇
(へいぜいてんのう)
安殿日本 根子天 推 國 高 彦 尊
(あてやまとねこあめおしくにたかひこのみこと)・・・ネコ9
奈良天皇
奈良帝
(ならてんのう)
第五十二代
嵯峨天 皇
(さがてんのう)
神 野
(かみの)
第五十三代
淳 名天 皇
(じゅんなてんのう)
大 伴
(おおとも)
日本 根子天 高 譲 弥 遠 尊
(やまとねこあめたかゆずるいやとおのみこと)・・・ネコ10
西 院 天 皇
西 院 帝
(さいいんてんのう)
第五十四代
仁 明 天 皇
(にんみょうてんのう)
正 良
(まさら)
日本 根子天 璽 豊 聡慧 尊
(やまとねこあめしるしとよさとのみこと)
深 草 天 皇
深 草 帝
(ふかぐさてんのう)
ーーーーー
イリ・カザフ(香佐富)自治州
↓↑
イリ=伊犁
中国北西部の
シンチヤン (新疆)
ウイグル (維吾爾) 自治区
カザフスタン(香佐富斯坦)
アルマ・アタ(Алма-Ата)
ロシア語
アルマ・アタ(Alma-Ata)
カザフ語で
アルマ(алма)=リンゴ
アタ(ата)=父
「リンゴの父」
↓↑
アルマトゥ(Алматы)
アルマトイ(アルマトゥイ)
北緯43度16分39秒
東経76度53分45秒
アスタナ(Astana)
カザフスタン(香佐富斯坦)共和国
の首都
1997年にアルマトイから遷都
旧称
アクモリンスク (Akmolinsk)
ツェリノグラード (Tselinograd)
アクモラ (Aqmola)
「アスタナ」はカザフ語で「首都」
カザフスタン(香佐富斯坦)の
中部に位置
イシム川が流れる
北緯51度10分0秒
東経71度26分0秒
↓↑
「亾=乚+人」
ボウ・モウ
ほろびる・なくなる
亡兦・乚人・亾
それまであったものが
減ったり衰えたりし
最後には無くなってしまう、滅びる
そこにいた人が死ぬ
そこにいた人が姿を消す、逃げる
亿=イ+乙
ヨク・オク・イツ・オツ・オチ
亿=人+乙
同繁「億」
工尺譜(コウセキフ)
↓↑
邑=口+巴=阝の音読=ユウ・オウ
「阝旁(おおざとボウ)」右・・・邑(むら・くに)
阜=阝の音読=フ・フウ・ブ
「阝偏(こざとヘン) 」左・・・阜(おか)
阜=𠂤+十=ノ+㠯+十
追=辶+𠂤=辶+ノ+㠯
佀=イ+㠯(イ)
㠯(イ)=異体字は「以・已」
巳と通じて「やむ」
已と通じて「すでに・はなはだ
のみ・ゆえに」
以・㠯・似・佀・姒・娰・㚶
泤・䎣・耜・䬮・飴・苡・苢・笖
以=もって・おもう・ともに
ひきいる・ゆえ・イ
以上、以下
苢=チサ(chisa)
レタスの別称
佀=是は「巳(シ)」的谐音字
似が本字、又は姓
㚶=姒・・・兄弟の妻
启=チィー=啓(ケイ・うやまう・敬う)
戶+口=户+口=戸+口=厂+コ+口・・・后
中国語の启(啟=啓)
短い手紙=谢启礼状
開く・開ける
指導する・教える
始める・開始する
出発する
申し述べる・敬启=拝啓
𠂤=ノ++㠯=ノ+l+コ+コ
呂(背骨)=口+ノ+口
耜(すき・シ)=耒(ライ・レイ)+㠯(シ)
↓↑
偏微分(へんびぶん、partial derivative)
「偏導関数」とは - 二つ以上の独立変数を持つ関数を、ある一つの変数に関して偏微分 した関数
derivative
(本源から)引き出した; 派生的な.2〈考えなど〉 独創性のない,新しさの欠けた.【名詞】【可算名詞】1派生物.2【言語学】 派生語.3【化学】 誘導体.4【数学】 導函数
derivative
商品先物用語・金融派生商品
金融派生商品
金利・為替・株式・債券などを
先物・オプション・スワップ取引の形で
組み合わせた高レベルな金融商品
引き出された(derived)
derivative
「派生的、副次的」
デリバティブ(Derivatives)
金融派生商品
既存の金融 商品(株式、債券、為替)から
派生してできた取引に付けられた総称
先物取引
オプション、スワップ等の総称
取引に大きな元手を必要とせず
決済も差金部分のやり取りのみ
少ない資金で大きな取引ができる
物質微分
material derivative
流れに乗って移動する流体粒子の
物理量(温度や運動量)の時間変化率
連続体力学の概念の一つ
固定された場所での
物理量の時間変化でなく
流れに乗って動く
仮想的な
「観測者」が観た物理量の時間変化
delivery
手紙・品物などの配達
express delivery
home delivery
宅配便・出前
Delivery
配達や配信
「出産」や「 話し方」
の意味を有す
話す技術のことを
「デリバリースキル」
delivery
ーーーーー
で・デ・出・弟・・・乙・・・音・・・音・・・寅=とら=虎・彪・・・
↧
December 19, 2017, 9:04 am
・・・しはす=師走・師駆・臘数=シワス=史倭州(素・数・諏・蘇)・・・「詩話・紫波・史話・四話・皺」の「素(子=鼠・蘇=耶蘇・蘇我)」・・・「牛・羊、山羊、馬、兎」の草食動物の「草の反芻」での消化(ショウカ・背負うか)・・・「鼠(ねずみ)・栗鼠(りす・スクイラル・スクァーレル・スクゥォァーラル・ squirrel)」は草食動物か?・・・「ネズミ(鼠または鼡)は、哺乳類ネズミ目(齧歯目)の数科の総称」・・・「丸い耳、とがった鼻先、長い尻尾」・・・「草食性」・・・「なまこ」の漢字は「海の鼠」だけれど・・・アリストテネスはネズミは塩を舐めているだけで受胎すると考えていたらしい?・・・「ネズミはゾウの天敵」・・・「ネズミはゾウの長い鼻に潜り込んで窒息死させる」と信じられていたらしい・・・
![]()
「ハムスター (hamster) は、キヌゲネズミ亜科に属し、雑食性」で「風邪」に罹(かか)る・・・モルモット(marmot)?・・・
「guinea pig(ギニア-ピッグ)=モルモット=家畜化されたテンジク(天竺)ネズミ (cavy)」 で、「ペット・実験動物のmarmot とは別もの」・・・「実験材料・試験台・モルモット(学名:Cavia porcellus、英語: guinea pig」・・・
「ギニア(幾内亜)共和国・首都はコナクリ」
「ギニア-ビサウ(幾内亜-美須)共和国」・・・
「guinea pig=ギニアの豚
=テンジク(天竺)ネズミ属の一種
温和で比較的飼いやすいため
愛玩用、実験動物として養殖
齧歯(ゲッシ)類」・・・
「guinea pigを
モルモットと呼ぶのは、
山に生息する他の齧歯(ゲツし)動物、
リス科マーモット属
山鼠
ウッドチャック
英名マーモット=marmot に由来」・・・
↓↑
「齧歯=ゲツシ=月支=月氏」です・・・
↓↑
「ハムスター (hamster) 」は匂(臭・におい)と音には敏感だが、夜行性で「色盲」らしく、「自分の糞を食べることがある。これは、一度では消化しきれなかった養分を再度吸収するため」らしい・・・「反芻」?・・・
「ハムスターは穴掘りの能力に優れており、複数の入口に、寝床、食料の貯蔵庫などの様々な部屋が繋っている巣穴を掘る」・・・
名前が
ゴールデンハムスター
(金食素太蛙?
語嗚留伝葉務素多蛙?)
=
シリアンハムスター(施理案葉務素多蛙?)
・・・「星(スター・star)=日+生(牛一)→(丑一)」?
兎に角、ネズミは
「齧歯(ゲッシ)」類、属・・・「十二支のネズミ(子)」
↓↑
十二月=子支月=ネズミ(鼠・鼡・ねずみ)月・・・極めツキ(月)・・・「シハス」・・・「支端(葉・歯・頗)数のツキ」だろう・・・
ーーーーー
臘(しはす・くれ・ロウ)=臈
臈=月+葛(艹曷)
臘(しはす・くれ・ロウ)=月+巤(巛鼠)
臘=くれ・年のくれ
まつり
臈=僧侶が得度してからの年数
↓↑
臘数(しわす・しはす)
地名 川上 町 臘 数
読み方 かわかみちょうしわす
市区町村 高梁市(高梁市の地名)
都道府県 岡山県(岡山県の市区町村名)
岡山県
高梁市
川上町
臘数(しはす)
↓↑
師走
師匠の僧がお経をあげるために
東西を馳せる月=師馳す(し はす)
平安末期の
「色葉字類抄(いろはじるいしょう)」の註
↓↑
師=𠂤+一+巾=し=子=支=示=施
𠂤=つちくれ・タイ・シ
丿+㠯=イ・異体字は以、已
簡体字は以
声符=佀耜允苢㭒台
𠂤=異体字は「堆(十一隹)」
=タイ=台・臺
・・・タイ=碓(石隹)・・・小碓命
声 符は「𠂤=シ・帥・歸・追
師=二千五百人を師と為す
帀に従ひ
𠂤に従ふ
𠂤の四帀なるは、
「衆」の意
𠂤+帀=𠂤=ひもろぎ(膰・脤・胙)の肉
神籬(ひもろぎ)
「ひ=霊」
「もろぎ=籬 (まがき)」
で神を守る意
神霊が憑依している
山、森、老木などの周囲に
常磐木を植え
玉垣を結んで
神座としたもの
後に
室内、庭上に
榊(さかき)
常磐木(ときわぎ)を
立てたモノの場所(神坐)
=生贄の肉・生or燻製の肉?
帀=軍人の曲刀・・・佩(は)く
㞢の反字「帀」・めぐる・ソウ
「帀」の異体字は「迊・匝」
満ちる=密匝匝=びっしり詰まった・匝地
「あたり一面にある白雪=匝地一面の雪」
↓↑
佩=イ+几+帀(一巾)
・・・頭巾=冃(ボウ)≠月
「布=ナ+巾」
ひれ=領巾・肩巾=ひれ=比礼
=薄く細長い布
害虫・毒虫などの害を避ける
呪力があると信じられたもの
奈良時代~平安時代
盛装した婦人が肩にかけ
左右に長くたらした薄い布
=ヒレは風にひらめくものの意
振ると波を起こしたり
害虫・毒蛇などを
祓(はら)う呪力があると
信じられていた布
女性が首にかけ
左右に長く垂らしたりし
別れを惜しむ時に
振ったりした・・・ハンカチ
鏡を拭(ふく・ぬぐ)う
のに用い、後代の手拭
布巾・・・雑巾
鰭(ひれ)=魚+老+日
↓↑fillet=止め・溶接の締め具
ヒレ=最上肉
フィレ=魚肉切り身
フィレオ=細長いひも
髪紐・リボン
=知覚神経繊維の束
網膜の毛帯
↓↑ lemniscus
幣=敝+巾・・・紙幣・貨幣
佩=おびる・はく・ハイ
身に帯びる
佩剣・佩刀・佩用・帯佩
腰につける飾り
玉佩
心にとどめて忘れない
感佩 (カンパイ)
佩刀 (はかし・はかせ)
↓↑
師=ひもろぎの肉を扱う
儀礼を取り仕切る人
「𠂤」は積み重ねること
「帀」はあまねく行動すること
多くの人を集めた集団
それを率いる人
「𠂤」は生贄の肉
「帀」は刀
官(カン・つかさ)
官=宀(やね)+𠂤(軍が奉じる祭肉)」
𠂤(タイ)=軍隊が行動するときに
携えて祭る肉のかたまり
建物(宀)で祭っているさま
=官は軍の聖所
㠯(イ)=異体字は「以・已」
巳と通じて「やむ」
已と通じて「すでに・はなはだ
のみ・ゆえに」
以・㠯・似・佀・姒・娰・㚶
泤・䎣・耜・䬮・飴・苡・苢・笖
以=もって・おもう・ともに
ひきいる・ゆえ・イ
以上、以下
苢=チサ(chisa)
レタスの別称
佀=是は「巳(シ)」的谐音字
似が本字、又は姓
㚶=姒・・・兄弟の妻
追=辶+𠂤=辶+ノ+㠯
ーーーーー
・・・
↧
December 20, 2017, 11:25 am
・・・「月氏という名の語源は戦国時代にいた和氏、禺氏、牛氏などの転写・・・イラン系言語からきたとする説、月氏は玉(ぎょく・翡翠=ヒスイ)の産地(タリム盆地)を占めていたので玉(ギョク)氏が訛って月(ゲッシ)氏になった」・・・???・・・
ーーーーー
漢字の字形、象形には色々な説があるけれど、単純な部首構成の文字の意味は具体的なモノとして理解出来るとしても、抽象化された文字は本当のところ、ナニの「意味」なのかは「?」である・・・
「楷書漢字」は原則的に
横線・・・・・「-」
縦線・・・・・「丨」
左右上からの
斜線・・・・・「\・乀」「/・丿」
かぎ線・・・・「乚・亅・レ」
チョン・・・・「ゝ・丶」
点・・・・・・「・」「::・¦¦」
丸・・・・・・「。」
の「一画部首」漢字の合体に尽きる。
しかも
「甲骨文字・金文・篆文」
を前提にして。形状は
「□枠内」に納まる
「楷書」として漢字の統一化をはかった。
甲骨文字は殷、夏
金文は周末
戦国時代は篆文、小篆
として整理された書体で
これらを前提として
楷書は秦代に整理統一された
で、出来あがった「楷書文字」を前提に
現在日本で使用している漢字の意味を
考察したい・・・との「妄想願望」である・・・
音声だけの日本語は「片仮名・平仮名」で
表示出来るが、漢字の表示がなければ、
それらの意味内容を理解するのは無理である。
日本語は日本人にとっても
「漢字の象形」を得て理解可能である。
ハッキリと自明なのは
具体的な「部首」としての形象文字であるが
漢字分解は「一画部首」に帰し、
その漢字構成は
「一画部首漢字の個々の合体の意味」である・・・
熟語文字は「物語の説明」が必要である・・・
ーーーーー
「帀=一+冂+丨
「帀」が「刀・刃物・庖(广包)丁」の形象とは
思えない?・・・横棒(一)に
布巾、手拭を吊るしている形象
↓↑
「帀=㞢の反字」・・・「㞢」の形象は
物干し竿を
横に支える
三叉の銛
Ψ(プシー)+一
の「U」字を
角ばった「凵」にした
合字の
設置台だが
㞢=山+丄(上・ジョウ)
「帀=めぐる・ソウ」
は風にひらめいている布で「そよぐモノ」?
or
「靡(なび)くモノ」、「揺れ動くモノ」
「めぐる(巡る・廻る)」は
池を回遊する魚?のイメージだが・・・
「㞢=屮+一」=異体字は「之(これ・シ・の)」
声符は「㞢=寺・蚩・臺
音韻は「之・cji・tjio」
之・支・止・㞢
之(ゆく・行く)
乏(とぼしい)=ノ+之→貧乏
ノ(挙手)
丿(曳く・ひく
ヘツ・ヘチ・ヒツ)?
丿=書法の左払いの筆画
掠=左払いの運筆
=字形を
右上から左下へ引く形
撆(ヘツ)=敝+手=別・撃つ=撇
撆缺・彯撆・排撆・点撆
掠=手+亠+口+亅+八
かする かすめる・リャク・リョウ
奪い取る・かすめる
掠取・掠奪
寇掠(コウリャク)
侵掠
掠笞(リョウチ)・・・ムチで叩く
「臺=吉+冖+至(一ム十一)
発音 タイ
簡体字 台
異体字 坮・㙵・䑓・台
声符「㞢」 㞢・寺・蚩
声符「臺」 嬯(女+臺)・擡(手+臺)
薹(艹+臺)
ーーーーー
𠂤=つちくれ・タイ・シ
丿+㠯
㠯=イ・異体字は以、已
簡体字は以
声符=佀耜允苢㭒台
𠂤=異体字は「堆(十一隹)」
=タイ=台・臺
・・・タイ=碓(石隹)・・・小碓命
声符は「𠂤=シ・帥・歸・追」
𠂤≠自(おのずから・みずから・ジ)
(自-丨)=𠂤
or
(𠂤+丨)=自
↓↑
師=𠂤+帀
↓↑ 帀=一+巾
幣=敝+巾・・・・紙幣・貨幣
↓↑
敝=やぶれる・おおう・ヘイ
↓↑㡀+攵
通仮字=蔽・幣
異体字=弊
幣=㡀+攵+巾
↓↑ ↓↑
声 符=㡀・敝・嫳・斃・蔽・鼈・彆
獘・鐅・幣・暼・蹩・撆・瞥
鷩・弊・潎・鄨
↓↑
説文解字
帗(フツ)なり、敗衣なり
攴に従ひ、㡀に従ふ 、㡀の亦聲
「瞥=みる(見)・ちらりと見る
一瞥
ちらつく
見えたり消えたりする
雪などがちらちらまばらに降る
かすむ(目がかすむ
ぼんやりとして見えない)
敝+目
破れた衣服の象形とボク音
右手の象形
↓↑ (破れると人の目の象形)
敝=破れた・ぼろぼろの
謙譲の接頭辞
敝宅拙宅
↓↑
敝帚自珍
ちびた箒でも自分には大切な宝
敝帚千金
↓↑
敝=ヘイ・ベイ・やぶれる
痛みやすい縫い飾りのある
礼装用のひざ掛けの形
それを殴って(攵・攴)
やぶる、やぶれる
みてぐら・贈り物・たから・かね
ヘイ
しでぬさ
神に供える「ぬさ・たいせつなもの」
巫女が着衣する装束の用の
「きぬ・帛」
のちに
「貨幣・紙幣」と用いられる
幣は本字
幤は俗字
獘(ヘイ・ベイ
たおれる・たおす
やぶれる・やぶる
つかれる
↓↑ とまる・つきる
敝=やぶれる・やぶる
おとろえる・つかれる
ヘイ
ぼろぼろになる
敝衣
つかれる・よわる
↓↑
自分のことにつける謙称
衰敝(スイヘイ)
敝衣(ヘイイ)
敝衣蓬髪(ヘイイホウハツ)
敝履(ヘイリ)
敝れる(やぶれる)
弊(ヘイ・ついえる)
物が破れてぼろぼろになる
弊衣・弊履
からだがぐったりとなる
疲弊
たるんで生じた害
弊害・弊風・悪弊・旧弊
語弊・時弊
宿弊・積弊・通弊・病弊
自分に関することに添えて謙遜を示す
弊屋・弊誌・弊社・弊店
「敝(ヘイ)」と通用
弊=悪い習慣・いけないこと・害
・・・
ーーーーー
石=いし・いわ・ライ
=丆+口=一+丿+口
面=つら・おもて・メン
=丆+囬=一+ノ+囬=一+ノ+[+目+]
囬(俗字)・囘(古字)
廻(代用字)・迴(繁体字)
↓↑
丆=朝鮮語を漢字だけで書くとき
「면」の代わりに使った文字
仮定の~したなら
~たら
~するなら
~すれば
~やれば
~やるならば
~でなければ
丆=면(ミョン)・・・面の省略文字?
顔ぶれ(가면・カミョン)
仮面(화면・ファミョン)
画面 (면허・ミョンホ)
ーーーーー
面=丆+囬
=一+ノ+囬
=一+ノ+[+目+]
=一+ノ+[+丨+二+丨+]
=一+ノ+月+凵
=一+ノ+且+冂
(冂+_・凵+-・匚+丨・乚+丨)
↓↑
月・朋・冃・目・日・旦・亘・曰・且・自砠
ーーーーー
月読命=ツクヨミ・ツキヨミ
夜を統べる神
「夜の食国」
「滄海原の潮の八百重」の支配
イザナギ
(伊弉諾・伊邪那岐・伊耶那岐)
の右目から生まれた
日本書紀・第五段第十一の一書
穀物の起源の神
第一の一書
伊弉諾尊が
左の手に
白銅鏡を持って
大日孁尊(天照大神)を生み
右の手に
白銅鏡を持って
月弓尊(月読命・月夜見尊)を生んだ・・・
「月弓尊」・・・月の弓の形のミコト(ソン)
とうとい
「月読命」・・・月を読むミコト(メイ)
いのち
「月夜見尊」・・月の夜を見るミコト(ソン)
とうとい
「月余美=月餘美命(万葉集)」
↓↑
日本書紀
月夜見尊が降って
保食(うけもち)神のもとに赴き
保食神は饗応として口から飯を出したので
月夜見尊は「けがらわしい」と
保食(うけもち)神を剣で刺し殺し
保食神の死体からは
牛馬や蚕、稲などが生れ
穀物の起源となった
天照大神は
月夜見尊の凶行を
「汝悪しき神なり」
と怒り
以来、日と月とは
一日一夜隔て離れて住むようになった
↓↑
古事記
食物の神、
大気都比売神(おほげつひめ)
が
須佐之男命に殺される
↓↑
「書紀・巻十五・顕宗紀」
任那へ派遣された
阿閉臣
事代に
月神が憑いて
高皇産霊をわが祖と称し
「我が月神に奉れ
さすれば喜びがあろう」
と宣い
山背国の葛野郡に社を建て
壱岐県主の祖
押見宿禰(おしみのすくね)に祭らせた
山背国
月詠神社由来
宣託された壱岐には月詠神社が存在
山背国の月読神社の元宮・・・
現在では
橘三喜の誤りで
宣託された本来の
式内社月読神社は男岳にあった
月読神社とされる
今は遷座され
箱崎八幡神社に鎮座
↓↑
六国史の第二
「続日本紀・光仁天皇」
暴風雨
卜したところ
伊勢の月読神が祟った
毎年九月に
荒祭(あらまつり)神にならって
馬を奉るようになった・・・
↓↑
「山城国風土記」
逸文の「桂里」で
「月読尊」が
天照大神の勅を受け
豊葦原の中つ国に下り
保食神のもとに至ったとき
湯津桂に寄って立ったという伝説
「桂里」という地名が起こった
月と桂を結びつける伝承は
インドから古代中国を経て
日本に伝えられた・・・ギリシャだろう・・・
万葉集にも
月人と桂を結びつけた歌
日本神話において
桂と関わる神は複数おり
古事記で
天神から
天若日子のもとに使わされた
雉の鳴女
兄の鉤をなくして
海神の宮に至った
山幸彦
↓↑
出雲国風土記
千酌(ちくみ)の
驛家(うまや)
郡家(こおりのみやけ)の
東北のかた
一十七里一百八十歩なり
伊佐奈枳命(いざなきのみこと)の御子
「都久豆美命(つくつみのみこと)」
此處に坐す。然れば則ち
都久豆美と謂ふべきを
今の人
猶、千酌(ちくみ)と號くるのみ
ただし
都久豆美命は
渡津の守護の
月神で
古くから千酌を守る土着神
朝廷の支配が強まったため
土地の人々が
伊佐奈枳の子とした
ツクヨミとは関係ない・・・
ーーーーー
大月氏
匈奴に追われ
アム・ダリア流域に退却し
後
西方に動き
クシャン(クシャーン=クシャーナ)王朝
↓↑
月氏
↓↑
玉(翡翠)の産地
西域ホータンの
崑崙山
交易を担っていた
月氏にちなんで
「禺氏の玉」
「和氏の璧」
と呼んでいた
西方世界では
月氏のことを
「セレス(絹)」
と呼んでいた
↓↑
何故「月氏」なのか?・・・絹=蛾=月媛
月氏(ゲッシ)
紀元前3世紀~1世紀ごろ
東アジア、中央 アジア
に存在した
遊牧民族、国家名
紀元前2世紀
匈奴に敗れてからは
中央アジアに移動
大月氏
と呼ばれ
大月氏時代は東西交易で栄えた
ーーーー
秦の始皇帝(在位:前246年~前210年)
中国の北方で
東胡
と
月氏
が強盛
匈奴は
陰山の北からオルドス地方を領する小国
大国である
東胡や月氏の間接支配
匈奴の
単于頭曼は
太子である
冒頓を廃し
その弟を太子にしようと
冒頓を月氏へ人質として送った
頭曼は冒頓がいるにもかかわらず
月氏を急襲し
これに怒った
月氏は冒頓を殺そうとしたが
逃げられてしまう
匈奴に逃げ帰った
冒頓は
父の頭曼を殺して
自ら単于となり
東の東胡に攻め入ってこれを滅ぼし
西へ転じて
月氏を敗走させ
次いで
南の
楼煩
白羊河南王を併合
漢楚内戦中の中国にも侵入
瞬く間に大帝国を築いた
その後も依然として
敦煌付近に月氏はいた
漢の
孝文帝(在位:前180年~前157年)
時代に
匈奴
老上単于
配下の
右賢王の征討に遭い
月氏王が殺され
その頭蓋骨は盃(髑髏杯)にされた
王が殺された月氏は二手に分かれ
ひとつが
イシク湖周辺へ逃れて大月氏
もうひとつが
南山羌(青海省)に留まって
小月氏
となった
ーーーーー
大月氏
イシク湖周辺に逃れた
月氏の残党(大月氏)は
そこにいた
塞族の王を駆逐し
その地に居座った
老上単于(在位:前174年~前161年)
の命により
烏孫の
昆莫が攻めてきたため
大月氏は
西へ逃れ
最終的に
中央アジアの
ソグディアナ(粟特)に落ち着いた
大月氏は
アム川の南にある
トハリスタン(大夏)を征服し
その地に
和墨城の
休密翕侯(きゅうびつきゅうこう)、
雙靡城の
雙靡翕侯(そうびきゅうこう)、
護澡城の
貴霜翕侯(きしょうきゅうこう)、
薄茅城の
肸頓翕侯(きつとんきゅうこう)、
高附城の
高附翕侯(こうふきゅうこう)の
五翕侯]を置いた
一方、前漢では匈奴の侵入に悩まされ
西方の月氏と共同で
匈奴を撃つべく
武帝(在位:前141年~前87年)の時代
張騫を使者とした使節団を西域に派遣
張騫は匈奴に捕われ
10年以上かけ
西域の
大宛・康居
を経て、
大月氏国
に到着
この時の
大月氏王は
匈奴に殺された先代王の夫人で
女王であった
大月氏女王は
張騫の要件を聞いたが
復讐心は無く
国家は安泰し
漢が遠い国であるため
同盟を組むことはなかった
ーーーーー
クシャーナ朝
護澡城の
貴霜(クシャン)翕侯である
丘就卻(きゅうしゅうきゃく)が
他の四翕侯を滅ぼし
自立して王となり
貴霜王と号した
丘就卻は
安息(パルティア)に侵入し
高附(カーブル)の地を取った
濮達国・罽賓国を滅ぼし
その支配下に置いた
丘就卻は80余歳で死ぬと
その子の
閻膏珍(えんこうちん)
が王となり
閻膏珍は
天竺(インド)を滅ぼし
将一人を置いてこれを
監領した
この政権は
クシャーナ朝を指し
丘就卻は
クジュラ・カドフィセス
閻膏珍は
ヴィマ・タクト
に比定
中国では
大月氏と呼び続けた
ーーーーー
キダーラ朝
『魏書』列伝第九十
「大月氏国、
北は蠕蠕(柔然)と接し
(柔然から)たびたび侵入を受けたので
遂に西の薄羅城(バルフ)へ遷都
その王寄多羅(キダーラ)は勇武で
遂に兵を起こして
大山(ヒンドゥークシュ山脈)を越え
南の北天竺(インド)を侵し
乾陀羅(ガンダーラ)以北の
五国をことごとく役属した」
とあり
この頃の大月氏は
クシャーナ朝の
後継王朝である
キダーラ朝を指し
中国ではキダーラ朝までを
大月氏と呼んでいた
その後
キダーラ朝は
匈奴(エフタル、フーナ)の侵攻を受けた
ーーーーー
小月氏
「羯族」および「羯・羯」を参照
月氏から分かれて
南山羌(青海省)に留まった小月氏は
その後も生き長らえ
三国時代の記録に
「敦煌西域の南山中(チベット高原)
婼羌の西から葱嶺(パミール高原)までの
数千里にわたって
月氏の余種である
葱茈羌・白馬羌・黄牛羌がおり
それぞれに酋豪がいた」
とある
『魏書』にある
小月氏国は
上記の小月氏ではなく
クシャーナ朝の後継王朝である
キダーラ朝の君主
キダーラの子が治める分国で
都は富楼沙城(ペシャーワル)
にあった
ーーーーー
昭武九姓
『北史』・『隋書』・『新唐書』
に見える
昭武九姓はいずれも
月氏の子孫で
月氏が
敦煌・祁連にいた時代
張掖祁連山北の
昭武城に拠っていたことから
中央アジアに
西遷後
自分たちの故地を忘れぬよう
昭武氏を国姓とした
↓↑
月氏という名の語源
戦国時代にいた
和氏、禺氏、牛氏
などの転写・・・
イラン系言語からきたとする説
月氏は
玉(ぎょく:ヒスイ)の
産地(タリム盆地)を占めていたので
玉氏が訛って月氏になった・・・
月氏の子孫である
クシャーナ朝の彫像に
月のシンボルが多く見出される
月氏が
月を崇拝のシンボル(トーテム)
としてい
中国側がその意訳として
月氏にした・・・
ーーーーー
釈適之『金壺字考』(宋代)に
「月氏…月音肉。支如字。亦作氏」
とあり
中国の
張西曼は
「大月氏は大肉氏の誤写であり
タジーク民族の対音である」
と主張し(1947年)
それが中国やアメリカで支持され
「月氏(Yuezhi)」を
「肉氏(Rouzhi)」
と表記・発音する研究者が生まれた
ーーーーー
19世紀以来
テュルク系、イラン系、チベット系、
モンゴル系、カッシート
と、定説は無かった
月氏はイラン系であるという説
1957年に発見された
スルフ・コタル碑文
1993年に発見された
ラバータク碑文
などによって
クシャーナ朝が
イラン系言語である
バクトリア語を使用していた
その祖先と思われる
大月氏
および
月氏
もイラン系言語を用いていた・・・
これは月氏の子孫がそのまま
クシャーナ朝になったとする場合であり
クシャーナ朝の起源には
土着民説
大月氏説
がある・・・
最近の研究
新たに
新疆で出土した
ウイグル語訳の『慈恩伝』の中に
焉耆・亀茲を
大月氏の遺留部族と記した箇所が見つかった
敦煌文書の『西天路竟』で
焉耆が月氏と記されていた
1980年代以降の言語学の研究と併せ
月氏は
トカラ語を使用していた可能性が高い
ーーーーー
『史記』大宛列伝や
『漢書』西域伝などで
月氏の故地は
敦煌と祁連の間とされている
ーーーーー
大月氏のいた場所
『史記』や『漢書』に
「大月氏国の都は
媯水の北に在り
その川の南にある
大夏を役属させていた」
という記述があることから
媯水
すなわち
アム川の北(ソグディアナ)に在った
その周辺国として
北に康居
東に大宛
南に大夏
西に安息(パルティア)
があった。
大月氏の都は
『漢書』では監氏城
『後漢書』では藍氏城
『魏書』では盧監氏城から薄羅城
ーーーーー
五翕侯
大月氏は
ソグディアナに西遷後
トハリスタンを征服し
そこに5人の
翕侯(きゅうこう:諸侯)を置いた
『漢書』での
高附翕侯が
『後漢書』では
都密翕侯となっている
『後漢書』西域列伝高附国の条に
「『漢書』は(高附を)五翕侯に数えたが
それは事実ではない
(正しくは)
安息に属した後
月氏が安息を破るにおよび
高附を得た」
とあり
大月氏の
トハリスタン征服直後に
高附翕侯を置いたのではなく
クシャン朝時代に
丘就卻(クジュラ・カドフィセス)の
安息(パルティア)侵攻によって
高附(カーブル)の地を得た
事実は不明だが
『魏書』および『北史』では
『漢書』の高附翕侯を踏襲している
ーーーーー
仏教伝来
中国への仏教伝来
哀帝の
元寿元年(前2年)に
大月氏国王の使者
「伊存(いそん)」が
『浮屠教』と言う経典を
景蘆に口伝した(『釈老志』)
これが諸説の中でもっとも早い
ーーーーー
広義の遊牧スキタイ
中央アジア西部の北方から
天山の南麓、アルタイ地方、
モンゴル高原の西端、
甘粛の祁連山脈
まで拡大していた・・・
月氏もその一支と見る・・・
ーーーー
月氏
中央アジアで活躍した古代民族
人種的帰属は不明
チベット人,トルコ人
などさまざまの説
中国の春秋時代 (前8~5世紀) 頃から
モンゴル高原の西半を支配し
中国の史料には
「禺氏 (ぐうし) 」
「和氏 (かし) 」
などという名で記されている
秦末、漢初の頃から次第に勢力を増した
ーーーーー
前3世紀の末
冒頓単于率いる匈奴に
敗れた
月氏の主力は西方に逃れ
天山山脈の
北の
イリ地方に移動
それを
大月氏と言う
大月氏はさらに
烏孫に追われ
パミールを超えて
アム川上流の
ソグディアナから
バクトリアに入った
バクトリア王国を滅ぼし
この地を支配していた
トハラ(トカラ)
月氏と匈奴
紀元前5世紀ごろ(日本は縄文時代)
現在の
河西回廊地方で活躍
中国から
『月氏』
(げっし・禺氏・ぐうし・和氏・かし)
と呼ばれた民族
ーーーーー
・・・
↧