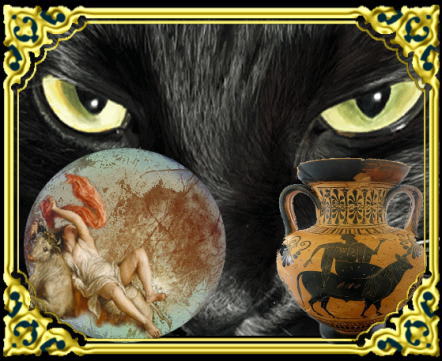シジミぃ~や、シジミィ~・・・二枚貝綱異歯亜綱シジミ科?
↓↑
桶=木+甬
十+八+マ+用
=おけ=槽=木+曹
=置・於・措
=織け・尾毛・尾下・尾家・・・尾張藩
↓↑
・・・飼葉桶・・・?
億計(おけ)
弘計(をけ)
播磨国の
縮見屯倉首(しじみのみやけのおびと)![]()
忍海(おしぬみ)部細目の
馬飼牛飼として仕えた二人の兄弟皇子
↓↑
・・・海馬おけ=記憶の貯蔵装置・・・?
↓↑
桶狭間(永禄三年五月十九日
の戦(ユリウス 暦1560年6月12日
グレゴリオ暦1590年6月22日)
永禄三年五月十九日
西暦1560年6月22日(グレゴリオ暦)
西暦1560年6月12日(ユリウス暦)
1560年6月12日12時19分
庚申年
辛巳月
甲申日
大安日
水曜日
↓↑ ↓↑
西暦1560年6月22日(グレゴリオ暦) 信長
西暦1560年6月12日(ユリウス暦)
信長生日 戊 寅 or 甲 午
↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑
庚申(戊壬庚)⇔食神(冲)・偏官
辛巳(戊庚丙)⇔傷官(害)・正官
甲申(戊壬庚)⇔偏官(冲)・比肩
庚午(丙 丁)⇔食神(合)・偏官(自刑)
↓↑ ↓↑
・・・織田信長・織田家・・・カラオケ(唐・加羅・韓-緒家)?
↓↑ ↓↑
天文三年五月十二日(1534年6月23日)
~天正十年六月二日(1582年6月21日)
甲午(丙 丁)偏官・印綬 帝旺⇔壬午
干合
己巳(戊庚丙)劫財・偏印 建禄⇔乙巳
害 比肩建禄格
戊寅(戊丙甲) ・偏官 長生⇔戊子
申酉空亡 大運甲戌偏官
戊午(丙 丁)比肩・印綬 帝旺⇔戊午
あるいは
天文3年5月28日(1534年7月 9日)
~天正十年六月二日(1582年6月21日)
甲午(丙 丁)比肩・食神 死⇔壬午
自刑午
庚午(丙 丁)偏官・食神 死⇔乙巳
自刑午
甲午(丙 丁) ・食神 死⇔戊子
辰巳空亡 大運乙亥劫財
自刑午
庚午(丙 丁)偏官・食神 死⇔戊午
↓↑ ↓↑
自刑 午-午-午-午・・・???
寅(虎)⇔冲己⇔申(猿)
巳(蛇)⇔冲己⇔亥(猪)
ーーーーー
双子の兄弟
『創世記』25章~36章
ヤコブ(Jacob) 旧約聖書中の族長の一
イサクの子
双子の兄
エサウをだまして長子権をうばう
天使と格闘して敗れたが
神の祝福を受けイスラエルと改名
エサウ(Esau) 兄・・・・重差得・餌得?
ヤコブ(Jacob)弟・・・・耶鼓舞・爺瘤・椰混布?
祖父はアブラハム
父 はイサク(Isaac・意味は笑う)60歳
母 はリベカ(Rebekah・カルデア人)・・・珂瑠出蛙?
長子相続権の祝福譚・親族抗争
↓↑
双子の兄弟
大碓(おほうす)・兄・・・姉・老・伯父・伯母
小碓(を うす)・弟・・・妹・若・叔父・叔母(倭姫命)
倭姫=第十一代垂仁天皇の第四皇女
↓↑ ↓↑
日本武(倭建命・倭男具那・日本童男)VS伊吹山の白猪
↓↑
兄弟(異母兄弟・異父兄弟)
大津皇子=父は天武(大海人皇子)・母は大田皇女
草壁皇子=父は天武(大海人皇子)・母は持統(鸕野讃良)
天武天皇の叔母は「倭姫王」
「古人大兄皇子」の娘
中大兄皇子(天智天皇)の皇后
古人大市皇子
古人皇子・吉野太子
・・・吉野に隠ったのは
天武(大海人皇子)⇔古人大市皇子?
とも呼ばれる
舒明天皇の第一皇子
母は蘇我馬子の娘
蘇我法提郎女(ほほてのいらつめ)
で
蘇我入鹿とは従兄弟
古人大兄皇子の兄弟姉妹
天智天皇(中大兄皇子)
間人皇女(孝徳天皇皇后)
天武天皇(大海人皇子)
蚊屋皇子(母は吉備国の蚊屋采女(かやのうねめ))
・・・ナゼ、「蚊屋」 なのか・・・
「蚊=中の厶の文」の「屋=屍に至(一厶十一)る」?
虻=阿武・あぶ=則天武后
蚊=?・・・中のヨコシマな亠(音)の乂(かり)?
↓↑
億計(おけ)
弘計(をけ)
↓↑
父、磐坂市辺押磐皇子と
母、葛城蟻臣
(かつらぎのありのおみ)
の女(むすめ)
荑媛(はえひめ)
の子
億計(おけ)=第24代仁賢天皇
↓↑ 意祁(億計・おけ)
億計天皇・・・憶測
大石尊
(おほしのみこと)
意祁命
意富祁王
(おほけのみこ)
大脚
(おほし)
大為
(おほす)
字は
嶋郎(しまのいらつこ)
漢風諡号は
↓↑ 仁賢天皇
皇后は
春日大娘皇女
子女
高橋大娘皇女・・・高橋の大の娘
高木郎女(古事記)?
高木神
高木 兼寛(たかき かねひろ)?
嘉永二年九月十五日
(1849年10月30日)
~
大正九年(1920年4月13日)
日本海軍軍人
海軍軍医総監(少将相当)
医学博士
男爵
東京慈恵会医科大学の創設者
脚気の撲滅に尽力
「ビタミンの父」
朝嬬皇女
手白香皇女・・・・継体天皇皇后
手白髪郎女(古事記)
子に欽明天皇
樟氷皇女
橘仲皇女
武烈天皇・・・小泊 瀬稚鷦鷯
(おばつせわかさざき)
真稚皇女
春日山田皇女
皇居は
石上広高宮
↓↑ ↓↑
弘計(をけ)=第23代顕宗天皇
袁祁(弘計・をけ)
来目稚子
(くめのわくご)
袁祁石巣別命
(をけいわすわけのみこと)
弘計(をけ)天皇
袁奚(をけ)天皇・・・奚?
渓谷
・・・鶏・鷄・雞
二和鳥
奚=爪+糸=鳥を糸で繋ぐ意?
奚=なんぞ・なに・ケイ
異体字「貕」
声符「奚・㜎・谿・騱・螇・雞
鼷・徯・豯・鷄・謑・鞵
膎・蹊・𪓷」
蹊=こみち・ケイ
𧾷+奚
・・・鼠蹊=もものつけね
同訓異義「なんぞ・なに
何曷胡盍那庸奚詎」
↓↑ ↓↑
奚=爪+幺+一+人
雞=爪+幺+一+人+隹
鷄=かけ=ニワトリの古名?
「庭つ鳥
鷄(かけ)の
垂尾(たりお)の
乱れ尾の
長き心も・・・・のんびりした心持
安堵した気持ち
思ほえぬかも・・になんかにはなれない
万葉集(1413)」
「かけろ」と鳴く声から・・・懸卦賂?
家鶏(カケイ)・・・
鶏冠(とさか・ケイカン)
父の
市辺皇子が
雄略天皇に殺され
二王は逃亡し
播磨の
縮見屯倉に奴として潜伏した
山部連小楯が
播磨国宰(みこともち)として赴任し
志自牟なる人物の新室の宴席で
両皇子を見いだした
ーーーーー
![]()
・・・???・・・シジミぃ~や、シジミィ~・・・
史事見・詞字見・市児見・指示見・・・?
蜆(中+厶+見・basket clams・ クラム)・・・私事観・・・
↓↑
corbicula(コービキュラ)
Cyrenidae(サイレニダエ?)・・・淡水域や汽水域に生息する小型の二枚貝・・・
カイ=歌意=貝=甲斐=蝦夷・・・貝=Shellfish・・・?
↓↑ ↓↑
アメフラシ=雨虎=sea hare(シー ヘア)
アワビ =鮑=abalone(アバロウニ) ・・・阿波(安房・泡・粟)の美(備)
ウニ =海胆・雲丹
=sea urchin(シー アーチン)
ウミウシ =海牛=sea slug(シー スラグ)
エビ =海老・蝦=shrimp(シュリンプ)
カキ =牡蠣=oyster(オイスター)
カニ =蟹=crab(クラブ)
クラゲ =海月・水母
=jellyfish(ジェリーフィッシュ)
ゴカイ =沙蚕=lugworm(ラグワーム)
サザエ =栄螺
=turban shell(ターバン シェル)
ナマコ =海鼠
=sea cucumber(シー キューカンバ)
ハマグリ =蛤=clam(クラム)
ヒトデ =海星=starfish(スターフィッシュ)
フジツボ =富士壺=barnacle(バーナクル)
ホラガイ =法螺貝=conch(カンチ)
ヤドカリ =宿借り
=hermit crab(ハーミット クラブ)
巻き貝 =univalve shell (ユニバルブ シェル)・・・ユニ・バルブ
結合制御弁・弁膜・調節弁
二枚貝 =bivalve shell (バイバルブ シェル)・・・バイバル⇔聖書?
ーーーーー
・・・???・・・
土佐に流刑になった「葛城一言主神」の権威の凋落・・・???
・・・「坂本大臣(龍馬)」の失墜・・・
根使主(ね の おみ・470年(雄略天皇十四年四月)
坂本臣(おみ)の祖
根臣・姓は臣(使主)
「建内宿禰
の子は九人
次に
木角宿禰は
木臣、都奴臣、坂本臣の祖」・・・
「坂本臣」
「紀朝臣同祖、彦太忍信命
武内宿禰命之後也(古事記・孝元天皇)」
「坂本朝臣」
「紀朝臣同祖、建内宿禰男 紀角宿祢之後也
男白城宿禰三世孫 建日臣。
因レ居賜二姓坂本臣一(和泉国皇別)」
「坂本朝臣」
「紀朝臣同祖、紀角宿禰男
白城宿禰之後也(左京皇別)」
↓↑
坂本糠手(丁未の乱)
坂本財(壬申の乱)
↓↑
安康天皇は
坂本臣の祖先
根使主を
大草香(大日下)皇子の所に
派遣し
若日下王の
結納品
「押木玉縵(おしきのたまかずら)」
を天皇に差し出さずに着服
嘘を言って
大草香皇子を死に追いやった
十六年後
呉の使節の宴会接待時
根使主の玉縵の隠匿とウソがばれ
根使主は逃亡
日根で稲城をつくって防戦したが
敗北し殺害された
天皇は
根使主の子孫を2つに分け
一つを皇后のための名代大草香部の部民とし
一つを茅渟県主(ちぬ の あがたぬし)に与え
「負嚢者(ふくろかつぎのもの)」とされた
大草香皇子に殉死した
難波吉士日香蚊に
カバネを与え
大草香皇子の名
「大草香部吉士」と名乗らせた・・・
↓↑
根使主の遺児
小根使主(おね の おみ)は、
「天皇の城は堅からず、我が父の城は堅し」
という自慢をしたので
天皇は
小根使主を殺した
↓↑
684年(天武天皇十三年)
八色の姓で
坂本臣一族は
朝臣を賜姓された・・・???
・・・ハナシは「幕末~明治」の「坂本龍馬」の顛末だろ・・・?
次のハナシも・・・バクマツ・・・?
↓↑
磐城皇子(いわき の みこ)・・・磐の城
「石木王=磐城王=磐城皇子」
雄略天皇
と
吉備上道臣氏出身の
稚媛との間の子
↓↑
星川稚宮皇子
(ほしかわのわかみやのみこ)
の
同父兄
異父兄に
吉備上道兄君
吉備上道弟君
がいる
磐城皇子の弟が
白髪皇子(清寧天皇)
↓↑
星川皇子
雄略天皇の皇子
母は吉備上道臣の娘
稚媛
雄略天皇の死
清寧天皇即位に際し
母の稚媛の教唆で反乱を起こし
大蔵を抑え
吉備上道臣(名は不詳)の
皇子支援水軍の到着以前に
大伴室屋
東漢掬(やまとのあやのつか)
の軍に鎮圧焼き殺された
↓↑
雄略朝に百済から貢上した
今来才伎(いまきのてひと)
の
陶部(すえつくり)
鞍部(くらつくり)
画部(えかき)
錦部(にしごり)
訳語(おさ)などの管理を命ぜられた
雄略天皇の臨終に
大連(おおむらじ)の
大伴室屋
と
東漢掬(やまとのあやのつか)
とに遺言し
白髪皇子(清寧)を
後継天皇に立てることを託した
天皇が死ぬと
星川皇子が
母の吉備稚媛(きびのわかひめ)の
教唆で
大蔵を占拠し
室屋と掬は兵を発して
大蔵を囲み
火を放って皇子らを焼き殺した
東漢氏(やまとのあやうじ)
は発展して数十の氏に分かれ
多数の帰化系の
小氏や部民を指揮・管理するようになった
ーーーーー
・・・???・・・すげェ~ッ!!・・・
ニュージーランド・・・カナダに63-0で快勝・・・
新西蘭 牛西蘭 新西蘭土 新設蘭杜 紐斯蘭 新地伊蘭土 新刖蘭・・・
↓↑
桶=木+甬
十+八+マ+用
=おけ=槽=木+曹
=置・於・措
=織け・尾毛・尾下・尾家・・・尾張藩
↓↑
・・・飼葉桶・・・?
億計(おけ)
弘計(をけ)
播磨国の
縮見屯倉首(しじみのみやけのおびと)

忍海(おしぬみ)部細目の
馬飼牛飼として仕えた二人の兄弟皇子
↓↑
・・・海馬おけ=記憶の貯蔵装置・・・?
↓↑
桶狭間(永禄三年五月十九日
の戦(ユリウス 暦1560年6月12日
グレゴリオ暦1590年6月22日)
永禄三年五月十九日
西暦1560年6月22日(グレゴリオ暦)
西暦1560年6月12日(ユリウス暦)
1560年6月12日12時19分
庚申年
辛巳月
甲申日
大安日
水曜日
↓↑ ↓↑
西暦1560年6月22日(グレゴリオ暦) 信長
西暦1560年6月12日(ユリウス暦)
信長生日 戊 寅 or 甲 午
↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑
庚申(戊壬庚)⇔食神(冲)・偏官
辛巳(戊庚丙)⇔傷官(害)・正官
甲申(戊壬庚)⇔偏官(冲)・比肩
庚午(丙 丁)⇔食神(合)・偏官(自刑)
↓↑ ↓↑
・・・織田信長・織田家・・・カラオケ(唐・加羅・韓-緒家)?
↓↑ ↓↑
天文三年五月十二日(1534年6月23日)
~天正十年六月二日(1582年6月21日)
甲午(丙 丁)偏官・印綬 帝旺⇔壬午
干合
己巳(戊庚丙)劫財・偏印 建禄⇔乙巳
害 比肩建禄格
戊寅(戊丙甲) ・偏官 長生⇔戊子
申酉空亡 大運甲戌偏官
戊午(丙 丁)比肩・印綬 帝旺⇔戊午
あるいは
天文3年5月28日(1534年7月 9日)
~天正十年六月二日(1582年6月21日)
甲午(丙 丁)比肩・食神 死⇔壬午
自刑午
庚午(丙 丁)偏官・食神 死⇔乙巳
自刑午
甲午(丙 丁) ・食神 死⇔戊子
辰巳空亡 大運乙亥劫財
自刑午
庚午(丙 丁)偏官・食神 死⇔戊午
↓↑ ↓↑
自刑 午-午-午-午・・・???
寅(虎)⇔冲己⇔申(猿)
巳(蛇)⇔冲己⇔亥(猪)
ーーーーー
双子の兄弟
『創世記』25章~36章
ヤコブ(Jacob) 旧約聖書中の族長の一
イサクの子
双子の兄
エサウをだまして長子権をうばう
天使と格闘して敗れたが
神の祝福を受けイスラエルと改名
エサウ(Esau) 兄・・・・重差得・餌得?
ヤコブ(Jacob)弟・・・・耶鼓舞・爺瘤・椰混布?
祖父はアブラハム
父 はイサク(Isaac・意味は笑う)60歳
母 はリベカ(Rebekah・カルデア人)・・・珂瑠出蛙?
長子相続権の祝福譚・親族抗争
↓↑
双子の兄弟
大碓(おほうす)・兄・・・姉・老・伯父・伯母
小碓(を うす)・弟・・・妹・若・叔父・叔母(倭姫命)
倭姫=第十一代垂仁天皇の第四皇女
↓↑ ↓↑
日本武(倭建命・倭男具那・日本童男)VS伊吹山の白猪
↓↑
兄弟(異母兄弟・異父兄弟)
大津皇子=父は天武(大海人皇子)・母は大田皇女
草壁皇子=父は天武(大海人皇子)・母は持統(鸕野讃良)
天武天皇の叔母は「倭姫王」
「古人大兄皇子」の娘
中大兄皇子(天智天皇)の皇后
古人大市皇子
古人皇子・吉野太子
・・・吉野に隠ったのは
天武(大海人皇子)⇔古人大市皇子?
とも呼ばれる
舒明天皇の第一皇子
母は蘇我馬子の娘
蘇我法提郎女(ほほてのいらつめ)
で
蘇我入鹿とは従兄弟
古人大兄皇子の兄弟姉妹
天智天皇(中大兄皇子)
間人皇女(孝徳天皇皇后)
天武天皇(大海人皇子)
蚊屋皇子(母は吉備国の蚊屋采女(かやのうねめ))
・・・ナゼ、「蚊屋」 なのか・・・
「蚊=中の厶の文」の「屋=屍に至(一厶十一)る」?
虻=阿武・あぶ=則天武后
蚊=?・・・中のヨコシマな亠(音)の乂(かり)?
↓↑
億計(おけ)
弘計(をけ)
↓↑
父、磐坂市辺押磐皇子と
母、葛城蟻臣
(かつらぎのありのおみ)
の女(むすめ)
荑媛(はえひめ)
の子
億計(おけ)=第24代仁賢天皇
↓↑ 意祁(億計・おけ)
億計天皇・・・憶測
大石尊
(おほしのみこと)
意祁命
意富祁王
(おほけのみこ)
大脚
(おほし)
大為
(おほす)
字は
嶋郎(しまのいらつこ)
漢風諡号は
↓↑ 仁賢天皇
皇后は
春日大娘皇女
子女
高橋大娘皇女・・・高橋の大の娘
高木郎女(古事記)?
高木神
高木 兼寛(たかき かねひろ)?
嘉永二年九月十五日
(1849年10月30日)
~
大正九年(1920年4月13日)
日本海軍軍人
海軍軍医総監(少将相当)
医学博士
男爵
東京慈恵会医科大学の創設者
脚気の撲滅に尽力
「ビタミンの父」
朝嬬皇女
手白香皇女・・・・継体天皇皇后
手白髪郎女(古事記)
子に欽明天皇
樟氷皇女
橘仲皇女
武烈天皇・・・小泊 瀬稚鷦鷯
(おばつせわかさざき)
真稚皇女
春日山田皇女
皇居は
石上広高宮
↓↑ ↓↑
弘計(をけ)=第23代顕宗天皇
袁祁(弘計・をけ)
来目稚子
(くめのわくご)
袁祁石巣別命
(をけいわすわけのみこと)
弘計(をけ)天皇
袁奚(をけ)天皇・・・奚?
渓谷
・・・鶏・鷄・雞
二和鳥
奚=爪+糸=鳥を糸で繋ぐ意?
奚=なんぞ・なに・ケイ
異体字「貕」
声符「奚・㜎・谿・騱・螇・雞
鼷・徯・豯・鷄・謑・鞵
膎・蹊・𪓷」
蹊=こみち・ケイ
𧾷+奚
・・・鼠蹊=もものつけね
同訓異義「なんぞ・なに
何曷胡盍那庸奚詎」
↓↑ ↓↑
奚=爪+幺+一+人
雞=爪+幺+一+人+隹
鷄=かけ=ニワトリの古名?
「庭つ鳥
鷄(かけ)の
垂尾(たりお)の
乱れ尾の
長き心も・・・・のんびりした心持
安堵した気持ち
思ほえぬかも・・になんかにはなれない
万葉集(1413)」
「かけろ」と鳴く声から・・・懸卦賂?
家鶏(カケイ)・・・
鶏冠(とさか・ケイカン)
父の
市辺皇子が
雄略天皇に殺され
二王は逃亡し
播磨の
縮見屯倉に奴として潜伏した
山部連小楯が
播磨国宰(みこともち)として赴任し
志自牟なる人物の新室の宴席で
両皇子を見いだした
ーーーーー

・・・???・・・シジミぃ~や、シジミィ~・・・
史事見・詞字見・市児見・指示見・・・?
蜆(中+厶+見・basket clams・ クラム)・・・私事観・・・
↓↑
corbicula(コービキュラ)
Cyrenidae(サイレニダエ?)・・・淡水域や汽水域に生息する小型の二枚貝・・・
カイ=歌意=貝=甲斐=蝦夷・・・貝=Shellfish・・・?
↓↑ ↓↑
アメフラシ=雨虎=sea hare(シー ヘア)
アワビ =鮑=abalone(アバロウニ) ・・・阿波(安房・泡・粟)の美(備)
ウニ =海胆・雲丹
=sea urchin(シー アーチン)
ウミウシ =海牛=sea slug(シー スラグ)
エビ =海老・蝦=shrimp(シュリンプ)
カキ =牡蠣=oyster(オイスター)
カニ =蟹=crab(クラブ)
クラゲ =海月・水母
=jellyfish(ジェリーフィッシュ)
ゴカイ =沙蚕=lugworm(ラグワーム)
サザエ =栄螺
=turban shell(ターバン シェル)
ナマコ =海鼠
=sea cucumber(シー キューカンバ)
ハマグリ =蛤=clam(クラム)
ヒトデ =海星=starfish(スターフィッシュ)
フジツボ =富士壺=barnacle(バーナクル)
ホラガイ =法螺貝=conch(カンチ)
ヤドカリ =宿借り
=hermit crab(ハーミット クラブ)
巻き貝 =univalve shell (ユニバルブ シェル)・・・ユニ・バルブ
結合制御弁・弁膜・調節弁
二枚貝 =bivalve shell (バイバルブ シェル)・・・バイバル⇔聖書?
ーーーーー
・・・???・・・
土佐に流刑になった「葛城一言主神」の権威の凋落・・・???
・・・「坂本大臣(龍馬)」の失墜・・・
根使主(ね の おみ・470年(雄略天皇十四年四月)
坂本臣(おみ)の祖
根臣・姓は臣(使主)
「建内宿禰
の子は九人
次に
木角宿禰は
木臣、都奴臣、坂本臣の祖」・・・
「坂本臣」
「紀朝臣同祖、彦太忍信命
武内宿禰命之後也(古事記・孝元天皇)」
「坂本朝臣」
「紀朝臣同祖、建内宿禰男 紀角宿祢之後也
男白城宿禰三世孫 建日臣。
因レ居賜二姓坂本臣一(和泉国皇別)」
「坂本朝臣」
「紀朝臣同祖、紀角宿禰男
白城宿禰之後也(左京皇別)」
↓↑
坂本糠手(丁未の乱)
坂本財(壬申の乱)
↓↑
安康天皇は
坂本臣の祖先
根使主を
大草香(大日下)皇子の所に
派遣し
若日下王の
結納品
「押木玉縵(おしきのたまかずら)」
を天皇に差し出さずに着服
嘘を言って
大草香皇子を死に追いやった
十六年後
呉の使節の宴会接待時
根使主の玉縵の隠匿とウソがばれ
根使主は逃亡
日根で稲城をつくって防戦したが
敗北し殺害された
天皇は
根使主の子孫を2つに分け
一つを皇后のための名代大草香部の部民とし
一つを茅渟県主(ちぬ の あがたぬし)に与え
「負嚢者(ふくろかつぎのもの)」とされた
大草香皇子に殉死した
難波吉士日香蚊に
カバネを与え
大草香皇子の名
「大草香部吉士」と名乗らせた・・・
↓↑
根使主の遺児
小根使主(おね の おみ)は、
「天皇の城は堅からず、我が父の城は堅し」
という自慢をしたので
天皇は
小根使主を殺した
↓↑
684年(天武天皇十三年)
八色の姓で
坂本臣一族は
朝臣を賜姓された・・・???
・・・ハナシは「幕末~明治」の「坂本龍馬」の顛末だろ・・・?
次のハナシも・・・バクマツ・・・?
↓↑
磐城皇子(いわき の みこ)・・・磐の城
「石木王=磐城王=磐城皇子」
雄略天皇
と
吉備上道臣氏出身の
稚媛との間の子
↓↑
星川稚宮皇子
(ほしかわのわかみやのみこ)
の
同父兄
異父兄に
吉備上道兄君
吉備上道弟君
がいる
磐城皇子の弟が
白髪皇子(清寧天皇)
↓↑
星川皇子
雄略天皇の皇子
母は吉備上道臣の娘
稚媛
雄略天皇の死
清寧天皇即位に際し
母の稚媛の教唆で反乱を起こし
大蔵を抑え
吉備上道臣(名は不詳)の
皇子支援水軍の到着以前に
大伴室屋
東漢掬(やまとのあやのつか)
の軍に鎮圧焼き殺された
↓↑
雄略朝に百済から貢上した
今来才伎(いまきのてひと)
の
陶部(すえつくり)
鞍部(くらつくり)
画部(えかき)
錦部(にしごり)
訳語(おさ)などの管理を命ぜられた
雄略天皇の臨終に
大連(おおむらじ)の
大伴室屋
と
東漢掬(やまとのあやのつか)
とに遺言し
白髪皇子(清寧)を
後継天皇に立てることを託した
天皇が死ぬと
星川皇子が
母の吉備稚媛(きびのわかひめ)の
教唆で
大蔵を占拠し
室屋と掬は兵を発して
大蔵を囲み
火を放って皇子らを焼き殺した
東漢氏(やまとのあやうじ)
は発展して数十の氏に分かれ
多数の帰化系の
小氏や部民を指揮・管理するようになった
ーーーーー
・・・???・・・すげェ~ッ!!・・・
ニュージーランド・・・カナダに63-0で快勝・・・
新西蘭 牛西蘭 新西蘭土 新設蘭杜 紐斯蘭 新地伊蘭土 新刖蘭・・・



































 羊・・・・邪馬台国には存在しなかった・・・
羊・・・・邪馬台国には存在しなかった・・・